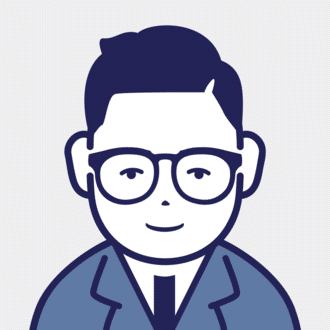段取り力は生まれ育った環境で決まる?中国で気づいた働き方の違い
中国で10年ほど暮らしてみて「段取り力」とか言われる能力は、後天的に身につけるものではなく、言語のように生まれ育った環境が大きく関係するのではないかと思うようになりました。
わたしの身の回りには、超高学歴のエリートから中学すらまともに出ていない人まで、さまざまな背景を持つ中国人がいます。
そしてどんな背景を持っているか関係なく、多くの人が行き当たりばったりで仕事をしたり、生活したりしています。
約束をすっぽかしたり、時間に遅れたりするのは日常茶飯事。
頼んでいた仕事がまったく進んでいなかったり、明確な指示を出したにもかかわらず、自分のやり方のほうが絶対に良いという確信のもと、期待とはまったく違う結果が返ってくることもよくあります。
とにかく、段取りよく物事を進めたり、現実的な計画を立てたり、それに従って行動することが苦手な人が多いのです。
実は、わたしも段取りが悪くて効率よく仕事をこなすのが得意ではありません。
それでも、中国の企業で仕事をしていると、なぜか自分が効率の良いエリートになったような気分を味わえるのです。
これは恐らく、日本が人々に規律正しく行動することを求めるだけではなく、効率良く無駄を省いてタスクをこなすことを当たり前とする社会だからだと思います。
日本では、予定通りに進めることが前提で、計画に沿って行動することが信頼の基準になっているように感じます。
一方、中国では、計画すること自体が大きな意味を持たないことがあります。
突然の方向転換や予想外の出来事が起きることが前提となっているので、最初から「計画通りにはいかないもの」として動いているのです。
また中国人は基本的に目先の利益や案件に振り回される傾向があるので、自分だけ長期的な視点を持って段取りを組んでもうまく機能しないってこともあります。
ここでは、計画を立てることが重要なのではなく、突然の変化にも柔軟に対応できることが重視されているように思います。
そんなわけで、「段取り力」というのは個人的なスキルというよりも、むしろ社会全体の価値観や文化が育むものなのではないか、と考えています。
もし段取りが得意な人も苦手な人も、それが「能力の差」ではなく、自分が属する社会や環境の影響を受けているのであれば、、自分の段取りの悪さを責めるのは意味がなさそうです。
段取りが悪くても仕事が上手く転がっていれば問題ないわけですし、もし段取り力が必要だとしても、それを補うなにかを取り入れれば万事オッケーです。
自分の得意不得意を環境のせいにするわけではありませんが、社会や文化が与える影響を理解することで、少し肩の力が抜けた気がします。
こういった考え方が正しいのかは知らんけど・・・
とはいえ、わたしは効率下げないことに全力を傾ける、所謂効率界隈の陰キャです。
これからも、地味で渋い対策をしつつ仕事をこなしていこうと思っています。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございます。
また明日〜
いいなと思ったら応援しよう!