
「優れた授業」の事例に選出:村井まや子先生担当「Research and Presentation Ⅱ」
神奈川大学外国語学部英語英文学科です。2023年度後学期の神奈川大学全体の学生による授業アンケートの結果、村井まや子先生の「Research and Presentation Ⅱ」が、「文系学部専攻科目(履修者35名未満)」の「優れた授業」の事例に選出されました!
<2023年度前学期「優れた授業」事例集>から村井先生のページを転載します。村井先生は現在、おとぎ話文化研究所所長と神奈川大学外国語学部の非常勤講師として活躍されています。
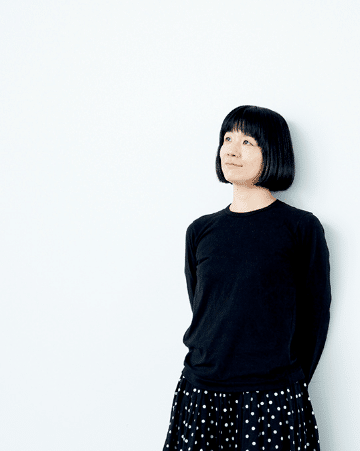
写真:神奈川大学
到達目標
英語の物語の読解・分析・批評の方法を学び、自分の考えを論理的に伝える技能を身に付けます。また、作品の分析を通じ、異文化理解・人と動物や自然との関係・女性等のマイノリティの問題への理解・考察を深めます。
授業内容
英米のおとぎ話とメディアでの動物表象を通じ、「美女と野獣」などの異類婚姻譚から人と動物の関係を考察。民話研究とエコクリティシズムを基に、おとぎ話とそのアダプテーションを分析する。
評価方法
Worksheets: 30%
Reflection Papers: 30%
課題論文:20% 口頭発表:20%
授業を4回以上欠席した場合は不可とし、2回の遅刻は1回の欠席とみなします。
授業実践ポイント
研究の基礎を丁寧に伝え、その「楽しさ」に気づいてもらいます。
問題設定の方法、分析の視点、思考の深め方、論理的な伝え方など研究の基礎となる方法をいったん身に付けると、研究がどんどん楽しくなります。
研究を”楽しむためのスキル”をプロの研究者の立場から一歩ずつ丁寧に伝えます。
Point 1
活発なディスカッションは、毎回の授業の中での地道な種まきが重要
グループディスカッションのルールを初回の授業で説明しますが、初めのうちは盛り上がらないことがほとんど。そんな時は、私自身もルールに則りディスカッションに参加します。学生の意見をひろい、「○○さんはどう思う?」などと別の学生に繋げていくことを地道に繰り返し、ディスカッションの方法を実演を通して示すようにしています。
+αのポイント
ディスカッション前に与える情報や解釈は必要最低限に留め、学生から重要な解釈のポイントや時代背景に関する誤解などが出た場合に補足説明をすることで、学生の記憶に残りやすくしています。
Point 2
論文の基本構成を伝えるため、様々な方法でアプローチ
研究の中でも山場にあたる論文作成は、1番苦しい部分だからこそ、テーマ決定、仮主張および本論の構成の設定までを1授業分を使ってより丁寧に指導します。その際、研究内容については学生の意見を尊重し、あくまでも論文作成のルールを教えることに努めています。
論文提出の前に行う口頭発表では、履修者全員に発表評価シートを配布し、他の学生の発表に対して「論理に矛盾はないか」「序論・本論・結論の3部構成になっているか」などを評価してもらい発信力の養成に役立てるようにしています。
履修学生インタビュー
毎授業の予習✕ディスカッションで分析力が高まった!
次回授業のディスカッションテーマに関わる予習課題が毎週2問程度課されたことで、全員が自分の意見を持った状態でディスカッションに参加できました。おかげで履修者同士の活発な意見交換が生まれ、相乗的に分析力が高まりました。
リフレクションペーパーへのフィードバックでやる気がUP!
ディスカッションテーマに対する自分の意見や感想を記載するリフレクションペーパーを毎授業後に提出し、翌授業に先生からのフィードバックが追記された状態で返却されました。先生からのアドバイスは、後学期最後の口頭発表と課題論文の作成に非常に役立つので、授業へのやる気がどんどん上がっていったと思います。
私たちの意見を尊重しながら的確にサポートしてくれました!
最後のプレゼンに向けて、テーマ探しから構成の組み立て方まで丁寧にフォローしてくれました。学生の疑問に対して正解を示すのではなく、解決の糸口になる文献を勧めるなど考えるヒントを提供してくれたので、思考力が養われたと感じています。また、Teamsに問合わせ先を設けてもらえたため、気軽に質問・相談ができました。
教育支援センターより
村井先生の「”研究は楽しいから一生続けてほしい”を裏テーマに授業に取り組んでいる」というお言葉が印象的でした。インタビューした履修学生たちは、まるで1つの研究チームのような結束感があり、この授業がプレゼミナールとしてアカデミックスキルの向上に繋がっていることがうかがえました。
元記事はこちらから!
村井まや子先生についてはこちらから!
ヤスダ先生の「優れた授業」についてはこちらから!
