
第二京しみず 介護機器と腰痛
介護機器のデモ?
こんにちは、♪今日もどこかで経営企画室♪です💖
グループ内の介護老人保健施設『第二京しみず』で介護機器のデモを行いましたので、その様子をお伝えします。
ところで、介護機器のデモとは何でしょうか?
実は介護施設では(意外と知られておりませんが)日常的に介護機器(福祉用具等々)のデモを実施しているんですよ😊
日頃何気なく使っている介護機器ですが、それはそれは本当に日進月歩で新しい物が日々誕生しています。ない物がないんじゃないかと言うぐらい・・・機器類ながら多士済々とでも言いましょうか、そんな感じです😀
ちなみに介護機器とは馴染みのある介護ベッドや車椅子に始まり、特殊な入浴ができるお風呂や見守りセンサー、ロボット関連等々、無数の素敵な機器が存在しております。これら様々な介護機器は介護保険制度の対象となり、在宅ではご利用者さんが1割負担〜使うことが可能であり、施設ではリースや買取などで介護機器を導入しております。一昔前の介護環境では考えられないぐらいのラインナップが介護保険を使用してご自宅で利用出来る時代です。
介護保険法整備
一昔前の介護・・・少しだけ保険制度について歴史を振り返りましょう。

時代は遡って、1963年の老人福祉法制定により、老人福祉・老人医療政策がスタートしました。たまに入所待機者が多くてなかなか入れないという話でお聞きするかもしれない特別養護老人ホーム、いわゆる特養もこの制度を元に創設されました。
その後、高齢者の増加、寝たきり老人の増加、行き場所がなく病院で社会的入院をする高齢者の増加等々、社会問題の急激な増加により老人福祉・老人医療制度での対応にも限界が生じました。そういった背景もあり、1990年代に入って介護保険の制度準備がなされました。そして2000年に現在の介護保険制度制定により、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みが誕生したわけです。

さて、当然の事ですが介護は人間がしますよね。工場のロボットは人間のように疲労せずに24時間働くことは可能ですが、人間には労力を提供すれば、疲労と言うものが蓄積されます。。。人間である介護スタッフの疲労がどこに蓄積されるかというと、物理的にまず一番多いのが『腰』への疲労の蓄積ではないでしょうか?

制度整備の動き
介護職の方が離職される時に介護職を続けたいけど『・・・腰が限界』と言う話を聞くことがあります。介護保険制度は整備されましたが、今度は介護職の健康を守る必要性が生じてきました。
並行して介護機器に関しては、『介護機器(福祉用具)振興、生活支援ロボットの実用化、新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)』が提言されました。「健康大国戦略」
そして、平成25年には『職場における腰痛予防対策の推進について』が厚生労働省より通達が出されました。これにより平成6年以来の改定が為され、腰痛予防への取り組みが本格化してきました。
厚生労働省通知内の一文を拝借して見ますと、『事業者は、労働者の健康を確保する責務を有しており、トップとして腰痛予防対策に取り組む方針を表明した上で、安全衛生担当者の役割、責任及び権限を明確にしつつ、本指針を踏まえ、各事業場の作業の実態に即した対策を講ずる必要がある。』とあります。
さらに読み込みますと・・・
Ⅳ 福祉・医療分野等における介護・看護作業
3『 リスクの回避』低減措置の検討及び実施
(2) 福祉用具の利用
福祉用具(機器・道具)を積極的に使用すること。
とありますように、厚生労働省通知には福祉用具・介護機器の積極的な使用が明記されました。
制度的にも介護機器と腰痛予防への取り組みがリンクしたターニングポイントではないでしょうか。
介護離職
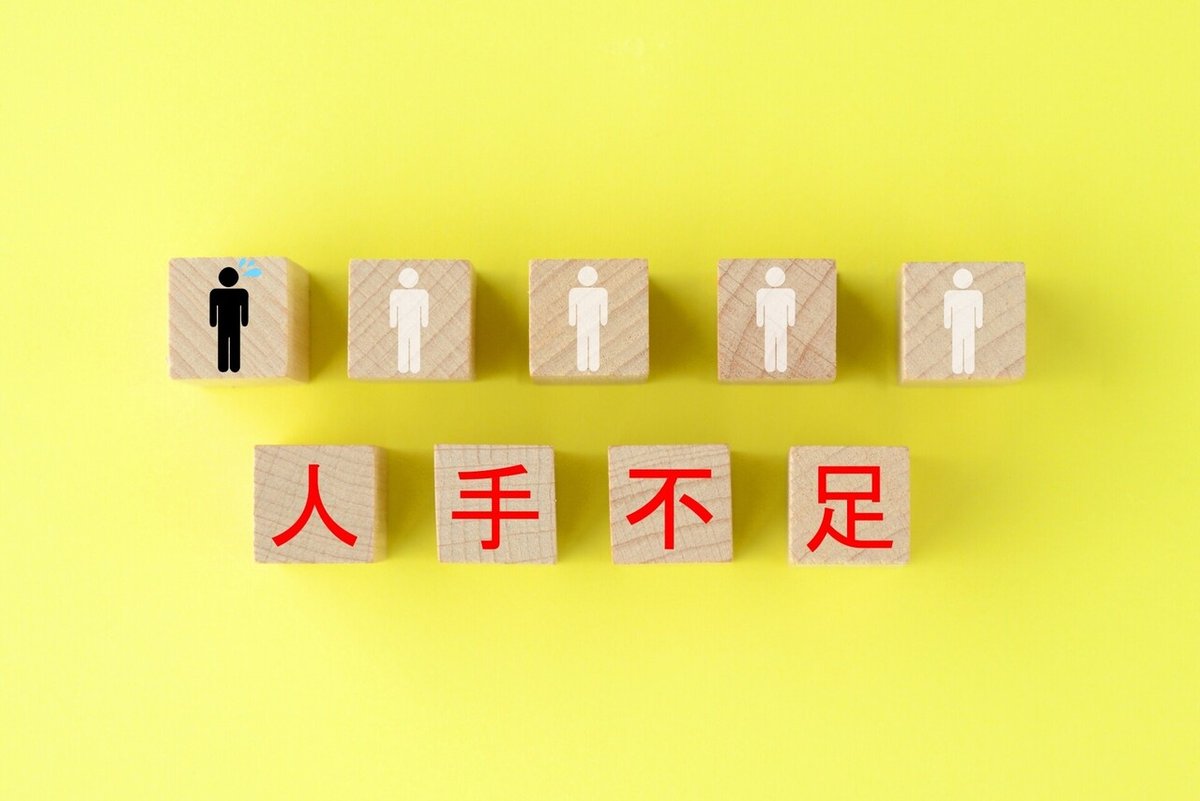
ちなみに、介護業界の全体離職率は若干減少傾向であり概ね年間16%前後を推移。労働条件・仕事に関する悩みの上位項目は『人材不足』が最も高く54.2% 『人手が足りない』と言う不満感が給与や重労働より上位にきていますね。
介護職の離職が最も高い時期には特徴があり1年未満で退職が32.3% 1年以上3年未満が27.8%、おおよそ入職3年以内に60%近くの退職が発生していることになります。
入職したものの・・・と言う、実際の業務と入職者の考えのマッチアップが上手くいかなかったという原因も考えられますが、回答では身体的負担が大きい(腰や体力に不安がある)が30.2%あり、こういった身体的疲弊感も一因ではないでしょうか。
そして慢性的な人手不足の要因に『採用が困難』が8割を占めています。せっかくの人財が腰痛などで辞めてしまうという事を防ぐ努力をしないと・・・その必要性がデータからも理解できますよね。
(全て介護労働安全センターより※H30データ)
介護機器デモの意義
なぜに我々グループ各施設では、介護機器などのデモが日常的に行われているのか?もうお分かりですね??😊
介護機器類をしっかりセレクトし導入することで、職員の負担を軽減し職員の健康を守る事に繋がります。そして職員の健康管理と併せて、有用な介護機器はご利用者さんの負担を減らし安心・安全確保にも繋がります。
介護機器は、どんどん便利な機器類が登場しますが、各現場で本当に使える物を入れないと意味がないですよね。せっかく購入したのに、使われず物置の隅っこで埃をかぶっている・・・なんて事になればもったいないだけでなく、結果誰も得をしません。
私の祖母宅にも、そんなんホンマにすんの??と、いった健康器具が部屋に各種配置されていますが、埃をかぶったまま放置・・・多分一回も使っていない、まぁいわゆる極美品状態で存在します笑
健康器具を買うだけで健康になった気がするんですよね( ^ω^ ) それでも95歳で小規模多機能を利用しながら元気にやっていますので、こういう場合は決して使っていなくても精神の満足度が高まるという効果で個人では十分健康なんでしょうか笑。
ちなみに1947年に採択されたWHO憲章では、「健康」を次のように定義しています。「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること(日本WHO協会訳)」と言っております。
病気をしているから、弱っているから、健康ではない・・・ではないんですね。病気であっても身体が弱っていても、満たされていれば健康である。我々医療、介護業界で働く人間には大事な考え方です。
有用な介護機器を見極め、職員とご利用者さんの健康に貢献すべく、今日もグループ内のどこかでデモが行われております。(ご協力いただいている業者の皆様、いつも有難うございます😊)
経営企画室もデモを体験しました💖
腕をダラーんと前にしておくだけです
(力が入らない状態と仮定します)

徐々にお尻が浮き上がってきましたよ

おー全自動!!
そしてこのまま方向転換して車椅子などに着席できます

こんな感じですね
このように様々な機器類を第二京しみずの事務長が主に提案しながら、現場の皆様が『これは価値がある』と考えられる物が仲間入りしていくわけです。
事務長『これはいいと思うで!』
現場『うーん・・・』
事務長『え!?あかんかなぁ・・・いいと思うんやけど』
現場『うーん・・・』
事務長『 _| ̄|○ 』
現場生え抜きの事務長!現場の気持ちが痛いほど分かっておられますので、頑張って提案するものの・・・w
こんなやり取りが日々繰り返されている、めっちゃアットホームな老健、第二京しみずよりご報告でした😊
