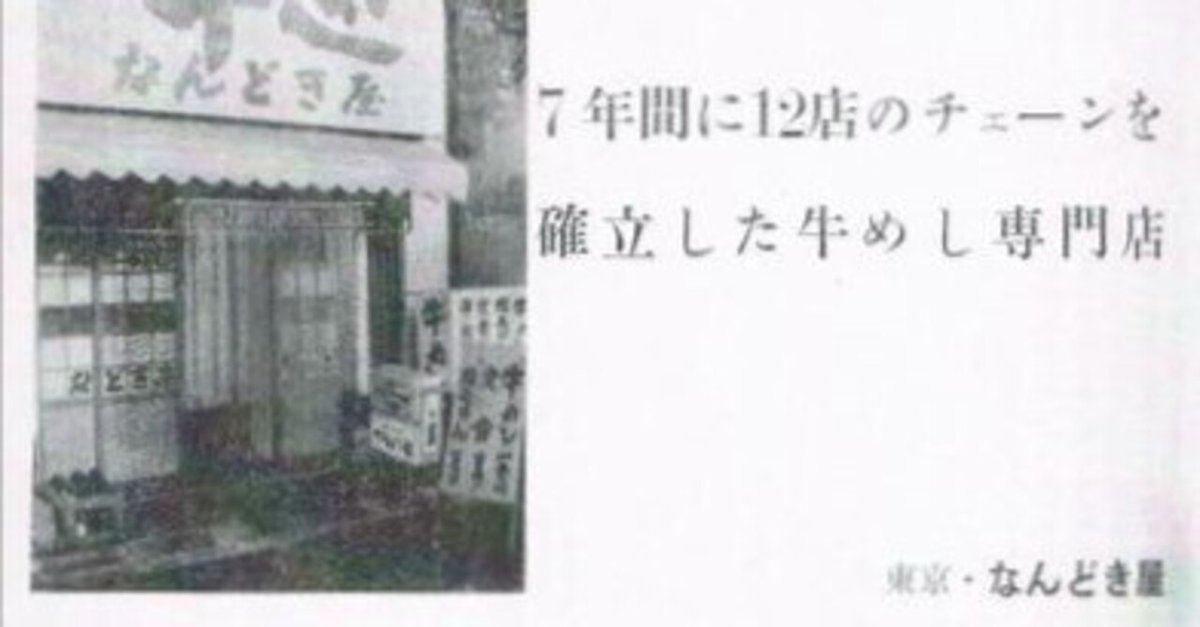
無料公開『牛丼の戦前史』第一章「ミスター牛丼、窮地に立たされる」その6「吉野家はなんどき屋の何を模倣したのか」
『牛丼の戦前史』の第一章「ミスター牛丼、窮地に立たされる」を無料公開いたします。
noteにおける近代食文化研究会の著作・無料公開一覧はこちらから。
それでは『牛丼の戦前史』の第一章「ミスター牛丼、窮地に立たされる」をお楽しみください。
6.吉野家はなんどき屋の何を模倣したのか
さて、吉野家がなんどき屋から模倣したのは24時間営業だけではない。
なんどき屋のチェーン化ノウハウは昭和42年の『月刊食堂 11月号』の記事「7年間に12店のチェーンを確立した牛めし専門店」において公開されている。

おそらく松田瑞穂も熟読したであろうこの記事から、吉野家がなんどき屋からまねたと思われる点をあげていこう
まず、メニューである。
年商1億を目指して効率化を進めていた築地吉野家では、天ぷらなどのメニューを削ぎ落とし、牛丼だけを提供するようになっていた。かつては酒類も販売していたが、これも回転率の低下に結びつくとして販売を取りやめた。
なんどき屋には築地吉野家にはない、牛皿というメニューがあった。24時間営業という性質上、夜には酒を飲む客もいる。そんな客に、おつまみとして牛丼の具のみを、牛皿として提供したのである。
もともとこの、酒のツマミとして牛皿を出す習慣は、戦前の牛丼の屋台から受け継がれてきた習慣だ。昭和6年の『裸一貫金儲市場』(佐伯平造)には、牛丼屋台の経営指南として”夜分のお客はお酒も飲むし、お酒の肴に牛皿を突く”と、牛皿をメニューに加えることを進言している。
ご飯やお新香、生卵、味噌汁も、築地吉野家にはなかったメニューだ。なんどき屋では牛丼に生卵をかけて食べることもできたし、焼いた鮭や納豆にご飯、お新香、生卵、味噌汁をつけた定食も提供していた。
吉野家の社史である『吉野家創業100年』によると、牛丼のみを販売していた築地吉野家は、昭和41年に大きく方針転換する。
それまでの効率化一辺倒のメニューに、牛皿、ご飯、生卵、お新香を追加し、メニューの多様化=効率化の見直しに舵を切ったのである。将来のチェーン化、24時間営業化をにらんで、なんどき屋のメニューを模倣し始めたのであろう。
そして昭和57年には、朝定食という形でなんどき屋の焼魚定食、納豆定食も模倣するのである。
次に、価格戦略である。
先に述べたとおり、昭和44年時点の吉野家は近江牛を使っていた。値段も牛丼並が200円、現在に換算すると1000円をこえる高級牛丼であった。
現在の吉野家のキャッチフレーズは「うまい、やすい、はやい」だが、当時は「うまい、はやい」だけで「やすい」はなかったのである。
安部修仁によると、ちょうど安部が入社した昭和47年ごろから原料をアメリカの牛肉に切り替え、吉野家は「やすい」を標榜するようになったという。
”僕が入社したときはまだ五店目を作っている段階でしたが、ちょうど国産牛とUSビーフが交じり合った時期でした。その頃、初めて「安い」ということを価値の新しいファクターに置いたんですね。”
”チェーン化を目指して「築地の外に出る」となると、日常的なポピュラー・プライスにしないといけないということで。”
吉野家に先んじて日常的なポピュラー・プライスを実現していたのが、なんどき屋であった。なんどき屋の牛丼並は昭和42年時点で120円。してみると、吉野家はなんどき屋のポピュラー・プライス戦略も模倣したのかもしれない。
もっとも、供給量が限られる和牛ではチェーン店を拡大する時に調達が限界に達するので、なんどき屋を模倣しようがしまいが、最終的には数量を確保できる輸入牛を使った安い牛丼にならざるをえなかったのかもしれない。
模倣の三点目が、出店戦略である。
なんどき屋がチェーン店展開を迅速に進めることができたのは、出店戦略を繁華街の小規模店舗に絞っていたからだという。
”その理由のひとつに、同社の出店政策が、投下資本を極力抑えた小坪出店だということだ。確かに、同社の場合すべて保証金、権利金を払っての借り店舗であるが、小スペースの場合、いくら繁華街でもそう高額の資本がかからない。そこをうまく利用したわけだ。”
”だから、土地を買っての出店や大きな規模店の出店と違って、出店場所が繁華街でありながらも店数は、より早く、より多くできるわけだ。なお、繁華街に出店してきたのは、 「一年先、二年先に軌道に乗るというのでは、多店化はできない。その点繁華街は、開店したその日から軌道に乗る」からである。”
この出店戦略を吉野家が模倣したことはいうまでもない。現在はロードサイドの大規模店もあるが、一昔前まで、吉野家といえば駅前の小規模店ばかりだったのである。
模倣の四点目が人事教育政策だ。
吉野家と同じく、なんどき屋も最初は人材の確保に苦労した。ところが、塚越社長が次の文言を各店舗の店頭に貼り出したところ、優秀な人材が集まってきたという。
”『学歴、資金がなくても人生に成功を勝とる道は、環境を選び、確実な商売を身につけて、貯蓄をして、人の信用を得て将来当店のチェーン店として独立及び、健全な結婚を目標に努力することです』”
学歴無視、実力とやる気重視の方針が、応募者の心に響いたらしい。こうして集めた人材に対し、なんどき屋は会社負担で外部教育の機会を与えた。
”「人材育成が多店化のポイントを握っている」と塚越社長がいうように、同社では管理者育成を短期間でやるようにしている。管理者の短期育成は社内教育だけではむずかしいと考えた同社は、従業員の余暇を利用して各人が勉強するように、珠算、簿記などの教育費用を会社で負担している。このような教育体制は、短期育成に効果があるという。”
一方、築地時代の吉野家の従業員は、ほとんどが女性だった。
”『吉野家』一号店の三軒隣りに店を構える龍寿司主人の椎名龍太郎が当時をふり返る。「(中略)店員は多いときで五~六名。全員、女子でした。自宅の同じ敷地内に女子寮を建て、そこに住まわせていたようです。以前の勤めでは労働組合か何か、その関係の仕事にも携ったことがあるらしく、従業員とのイザコザを極端に恐れているような印象を受けました。だから、女子従業員しか雇わなかったんじゃないでしょうか」
高卒の安部修仁がアルバイトから社員にリクルートされ、会社の費用で外部教育をふんだんに施されたことは既に述べた。
学歴無視の実力重視、外部教育の充実。チェーン店化にあたって人事教育政策を改めるさいに、松田瑞穂が「なんどき屋流」をヒントにしたことは間違いないだろう。
ここまで吉野家がなんどき屋から模倣した部分を列挙してきたが、むしろ模倣していない部分をあげたほうが早いのではないかと思う。模倣していないのは、なんどき屋で出していたうどんを吉野家では出さなかった、ぐらいのものではなかろうか。
次の記事 その7「ミスター牛丼、窮地に立たされる」
