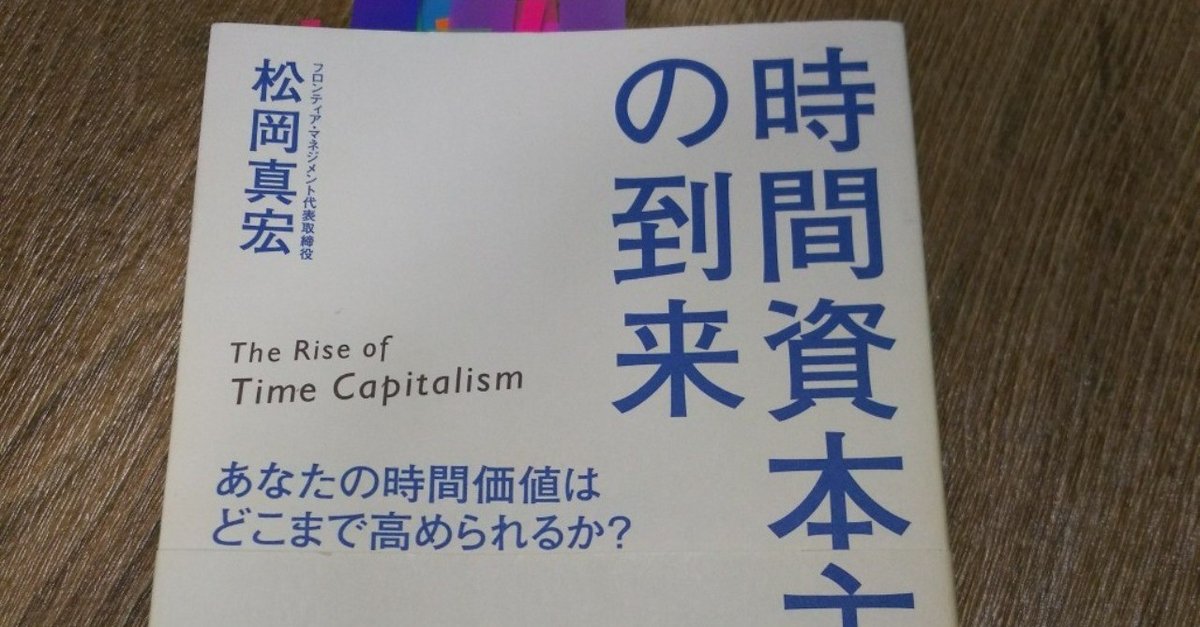
時間資本主義の到来
時間資本主義の到来スマホの登場により、すき間時間が活用できるようになり、価値が生まれた。あるいは、お金を払って人にやってもらうサービスも増えた。
こま切れの時間を活用できるようになった。
すき間時間を有意義に使うためのモノやサービスが登場してきている。
Aさんの持つ1000円と、Bさんの持つ1000円は同じ。
しかし
Aさんの1時間と、Bさんの一時間は同じ価値とは限らない。
時間価値は2種類ある。
①そのモノやサービスを使うことによって、時間が短縮できる。→時間の効率化
②そのモノやサービスを使うことによって、有意義な時間が過ごせる。→時間の快適化
空いた時間を活用するビジネス例・・ウーバー、タイムチケット
空いた時間を活用するには、基本的に共有、交換、使用するための空間が必要。その空間とは現実だけでなくオンラインの場合もある。
時間の価値が高まると、その時間にお金を払ってもいいと思う人が増えていく。
情報収集においても時間の効率、短縮、要約サービスに需要がある。
お金がある人は、お金で時間を買う、例えば移動に時間がかかるなら、特急や新幹線、飛行機を使うかもしれないし、不得意なことは外注するかもしれない。そうすると得意なことに集中してますます格差が生まれる可能性がある。
時間のムダ
選択の失敗をしたくない現代人、
レビューや評判からはずれじゃないことを確認してからでないと試さない、買わない。
時間の快適化は、多様なニーズに対して提供可能なのに対し、時間の効率化は、大企業の寡占が起こりやすい。例)Amazon
仕事の効率化のジレンマ
仕事を効率化しても競争によってみんながそのレベルになるだけで、売上も給料も上がらない。
効率化して空いた時間をさらに仕事に回すと、ますますみなが頑張り、負のスパイラルに陥る。
効率化ではなく付加価値を生み出さなければいけない。
付加価値を見つけるには、人にあわなければいけない。
ネットに転がっているような情報ではなく、一対一で直接話す内容にこそ価値がある。
P.148
電話ができる前は、連絡できる人の数には限界があった。せいぜい10人としよう。それが、電話ができて、すぐに連絡できる人の数は100人に増えた。こうなるとその10分の1の10人には直接会わないと特別な関係にはなれない。ネット時代、1000人につながれるようになったのなら、100人に会わなければいけないのだ。情報通信技術が広がれば広がるほど、会わなければいけない人の数は増える。
重要な情報交換は直接会って行われる。
もうすぐこの本のアップグレード版が出るようだ。
また個人の活動に関しては堀江さんの『時間革命』も参考になる。
