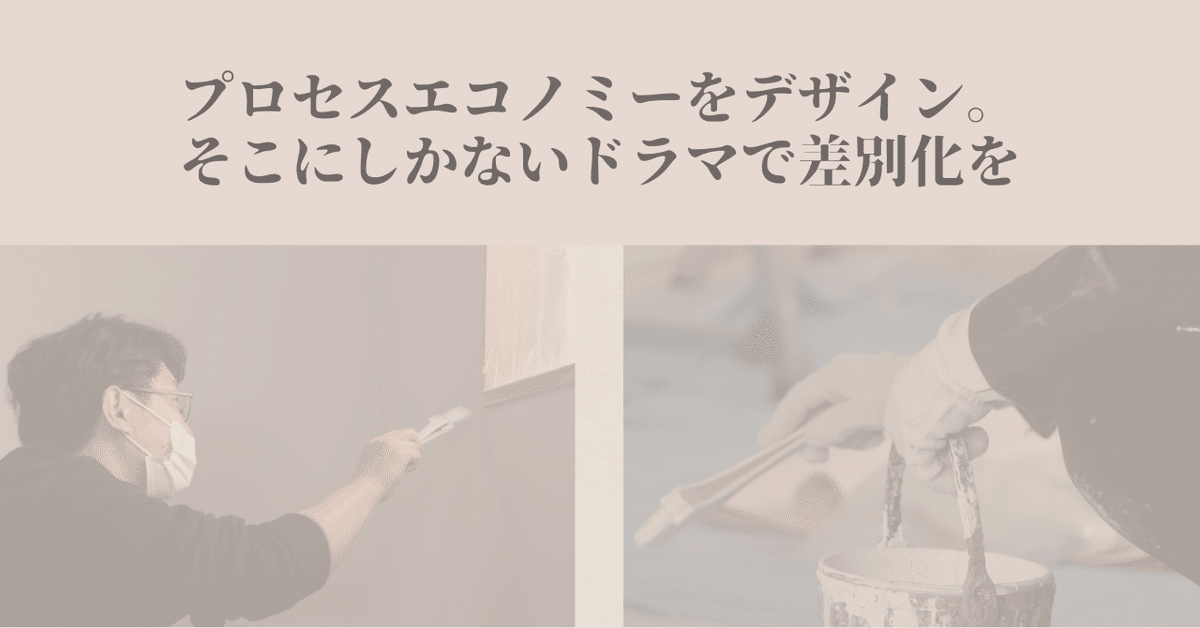
【AMINARI】ファンが増えていく店舗づくりのポイント.Pinoができるまで
株式会社新潟家守舎 代表 小林紘大さん。自身の法人以外にも多数の事業を手掛けており、携わっている事業は30以上にも及ぶパラレルワーカーとして活動している。
新潟家守舎の事業のひとつである「AMINARI(アミナリ)」。
これは「建築プロデュースに、キャスティングの力。」をコンセプトとした遊休不動産(空き家、空き店舗など)建築プロデュースサービスだ。
22年4月にオープンしたフレンチカレーとお菓子のお店「Pino」も、このプロデュースによって形になった。(聞き手・小野寺 美咲)

フレンチカレーとお菓子の店「Pino」
ここは新潟市北区、新井郷川沿いのお店。22年の4月にオープンしたばかりの店内は、思わず写真を撮りたくなる、洗練された空間だ。

Pinoのある松浜は落ち着いた住宅街で、正直、若者が集う町ではない。しかし店内には、若い女性を中心に写真を取りながら食事やお茶を楽しむお客様の姿が多くみられる。
紘大 オープンして半年以上経ちましたが、改めてPinoに携われて良かったなぁと思います。
お店自体が素晴らしいのはもちろんのこと、これからの店舗づくりに有効なポイントがいくつも詰まっていた気がします。その上、プロセスメイキングがカチッとハマった。
コロナ禍にオープンした飲食店にも関わらず、Pinoのファンは着実に増えていき、経営も安定してきている。
今回は店舗づくりに有効なポイントと、プロセスメイキングについて、紘大さんにお話を伺った。
長く愛されるお店にするためのクオリティ追求

■お洒落なだけではない「滞在したくなる設計」
Pinoは、空き家をリノベーションしてつくられている。ご夫妻から相談を受けた紘大さんは、はるさんが新潟市北区松浜出身ということを知り、元々賃貸住宅として貸し出されていた物件に着目した。


川の向こうからも目に留まるような外装のアイデアは、1回目の現地調査の段階からすでに生まれていた。

出来上がったのがこちら。温かみがありつつも、洗練されている。
紘大さんたちのこだわりは、店内にも溢れていた。

店内にはカウンターと、メインの大きなセンターテーブル。
いくつもテーブルとイスをセッティングするのではなく、メインテーブルをどんと構える。そうすると自然に、お客様の相席が発生。自然と交流が生まれていく。
紘大 この場所に来たことを思わず自慢したくなっちゃうような、心が明るくなる空間づくりを意識しました。
このご時世にカフェに足を運んでくれるお客様は、少なからず、住宅とは違った空間や人との関わりを求めている。それを叶えるのがこのメインテーブルです。
幅もあるので、将来的にテーブルを活用してお料理など開くこともできそうですよね。
ひとりの時間をゆっくりと楽しみたい方には、川が望めるカウンターがおすすめ。テイクアウトにも対応しています。

さらに、ファーストフード店のように、注文と精算を同タイミングで行うシステムにした。そうすることで、キッチンに1人、レジ兼フロアに1人の2人体制での運営が可能になる。
■新潟素材も豊富に使った「ここだけ感」のあるメニュー

もちろん大事なのが味のクオリティ。
Pinoの看板、フレンチカレーは昔どこかで食べたような懐かしい味でありつつ、家庭では作れない深みのある味わい。カレー好きにはたまらない!
焼き菓子やケーキのラインナップは、季節によって入れ替わる。どれにしようかと悩むのも楽しい。見た目も美しく、ひとくちづつ、大事に大事に食べたくなるものばかりだ。
食材は近隣の農家から仕入れるものも。他ではなかなか味わえない「ここだけ感」のあるメニューだからこそ、リピートされる方も多い。
ファンの心を掴むプロセスメイキング

紘大 どの業界でも言われていますが、これからはプロセスエコノミー(商品を生み出すまでのプロセスを発信し、収益につなげる考え方)が大事。それは店舗づくりにも当てはまります。
だから、オープンしてからではなく、それ以前からファンになってもらうための動きを意識しました。
■濃いファン=協力してくれる関係者を増やす
まず行なったのは、この物件のオーナーへのプレゼンだ。賃貸物件において、大規模なリノベーションを嫌がるオーナーも少なくない。

斎藤夫妻の持っている熱量をきちんとオーナーに伝えるべく、プレゼンの機会を設け、カレーを実食してもらった。

熱量が伝わるプレゼンができるよう、資料づくりや話し方まで、紘大さんが前面サポート。
結果的にオーナーは「ハード面もソフト面も大丈夫そうだから」と、リノベーションを快諾。オーナーが前向きになってくれるのは、一層心強かった。
そして、外装・内装ともに工事が始まった。

工程は進み、内装工事終盤、22年3月。設計・建築に関わった方が6名ほど集合して、みんなで壁塗りを行なった。

自分たちが参加できるところは参加することで、より店舗に愛着が湧く。
オープン前から人との繋がりを作っておくことで、よりたくさんの人に愛されるお店にする、というのが狙いだ。
一緒に作業することで、関係者の仲が深まるのもいい。
さらにはこの様子を、新潟のライフスタイルメディアセナポンさんに記事にしてもらった。
まだオープンしていない店舗を知ってもらうために、WEBメディアは効果的だ。ご夫妻の思いも含めて取材してもらうことで、未来のお客様にリーチできる。
関係者は、Pinoに愛着を持ってくれる。オープン前に知ってくれた方もまた、興味を持ってくれる。そういった方達がいずれ濃いファンになる。
慌しくも、準備は着々と進んでいった。
■一人でも多くの方に知ってもらえれば、刺さる

外壁工事中、窓には、Pinoのロゴとオープン情報を知らせるチラシを貼り付けた。近隣住民の方に少しでも認知してもらい、「この場所に何ができるんだろう?」とワクワクしながら待っていて欲しかったからだ。
Pinoのロゴは、早々に作成を進めていた。

紘大 10代〜20代は基本的にInstagramを利用して飲食店を調べるので、早々にアカウントも開設しました。ロゴがあれば、オープン前でも発信がしやすいです。
新潟のデザイナーとご夫妻をお繋ぎして打ち合わせを実施して。お店にぴったりの、素敵なロゴが出来上がりました。
このほかにも、オープン前に一人でも多くの方に知っていただけるようポップアップショップに出店するなどして、ついに22年4月。Pinoがオープンした。

地域性×物語で、ファンが根付く場所づくりができる

紘大 建築に携わる身として、こだわった部分もたくさんあります。
Pinoはエコハウス(気候風土や敷地の条件、使い方に応じて自然エネルギーが最大限に活かすなどして、環境に負担をかけない方法で建てられる物件)です。その上で、光熱費も削減できる仕様にするためのノウハウを駆使しました。
建築ノウハウと、プロセスエコノミーを形にする力。紘大さんの技術と夫妻の努力、関係者各位の熱意で、Pinoはオープンから半年で、早くも軌道に乗っている。
紘大 Pinoのランチの価格は1000円を超えます。デザート付きのセットにして、お土産用の焼き菓子を買えば、2000円にもなる。
オープン前、この街の相場と比べて「そんなに高い店、集客できるわけがない」という方もいました。
でも、この価格帯には意味がある。指摘を受けて安易に価格を下げるのではなく、シンプルにメニューの魅力や、フードロス解消の課題解決になるといったポイントを周りに伝えていくことで、少しづつファンが増えていきました。
「相場に見合っていないから」「この場所でそんなメニューは好まれないから」……飲食店を開くにあたっての課題の中には、プロセスエコノミー でファンを獲得すれば解決できるものもあると考えています。
ファンの方がいればいるほど、これまでの常識にとらわれない、自由な店舗づくりができそうですよね。

どんな店舗も、準備の過程(プロセス)で壁や課題にぶつかる。それを乗り越えていく必要がある。そこに地域性が加わると「ここでしか味わえないドラマ」が生まれ、他の飲食店にはない魅力が見えてくる。
メニューやサービスだけでなく、ドラマでも差別化ができるのだ。
紘大 Pinoのプロデュースは、依頼を受けたというより「一緒の船に乗った」感覚すらありました。今後利益を出し続けなければならない「店舗」という性質上、リスクも責任も大きい。でも、それ以上にやりがいがあるんです。この場所にしか生まれない素晴らしいドラマも。
これからも、AMINARIでのプロデュース業にどんどん取り組んでいきます!
店舗づくりにご興味がある方は、こちらからお気軽にご連絡ください。

見ているだけで心躍るメニューの数々。
Pinoの最新情報は公式Instagramで。
https://www.instagram.com/pino__matsu/
試作中のメニューがいち早くチェックできるかも?
のぶさんのTwitterはこちら。
フレンチカレーとお菓子の店Pino
新潟市北区松浜本町1-13-6
営業時間 lunch 11:00-14:30
cafe 14:30-17:00
定休日 木曜日+不定休
駐車場 あり(店舗横に6台)
いいなと思ったら応援しよう!

