
ケア実践講座第4回/ミュージアムアクセシビリティから学ぶ①理論編
ケア実践講座 第4回|ミュージアムアクセシビリティから学ぶ①理論編
日時|2024年10月19日(土)13:00〜15:00
会場|川崎市役所本庁舎304,305会議室
講師|鈴木智香子(国立アートリサーチセンター研究員)
伊東俊祐(国立アートリサーチセンター客員研究員/
國學院大學 文学部博物館学研究室助手)
内容|
・情報保障とは
・合理的配慮とは
ユマニチュードの講座に引き続き、午後はアクセシビリティについての講座になります。
アクセシビリティとは「利用のしやすさ」や「便利さ」といった意味で訳されます。今回と次回の講座ではミュージアムにおけるアクセシビリティを学ぶことで、こと!こと?かわさきの活動に応用できるよう考えを広げていきます。
今回の講師として国立アートリサーチセンター(通称NCAR)から鈴木智香子さん、伊東俊祐さんにお越しいただきました。お二人は今年の春にミュージアムアクセシビリティについて、「ミュージアムの事例(ケース)から知る!学ぶ!合理的配慮のハンドブック」の作成、eラーニング講座「ミュージアム・アクセシビリティ講座 ふかふかTV」の企画・制作を行っています。講座の中でもこの「ふかふかTV」の動画を視聴していきます。
「ふかふかTV」はあらゆる人がミュージアムにアクセスできる機会を充実させることを目的としており、アクセシビリティを進めるうえで重要なキーワード「合理的配慮」と「情報保障」を中心に、国内の美術館の事例から学び、実践するための基礎的な知識が身につく講座となっています。
ことラーの活動は美術館などの施設に限らず、川崎市内の様々な文化芸術資源を活用し行っていきますが、こういった美術館の事例はことラーの活動にも共通する部分が多くあります。そのためNCARにご協力いただき、今回の講座を進めていきます。
講師のお二人についてですが、鈴木さんは現在NCARの研究員としてアクセシビリティの研究を行っています。前職では「とびらプロジェクト」や「Museum Start あいうえの」といったアートコミュニケーション事業にも携わっていました。
伊東さんは先天性の全ろうで、博物館学を専門とし、障害者の生涯学習や文化芸術に関わる研究を進めています。

今回、ことラーが見て、学んでいくのは理論編となる「ミュージアムにおける合理的配慮とは」、「ミュージアムにおける情報保障とは」の2本の動画になります。
合理的配慮、情報保障と聞くと難しい印象を受けますが、アクセシビリティを考えていくには基礎的な考え方です。
動画内ではこの二つの基礎的な知識や具体的な事例を交えながら、わかりやすく解説がされていました。

ことラーには動画のなかで気になったワードや講師の二人に聞いてみたいことなどを付箋に書いていき、貼ってもらいました。
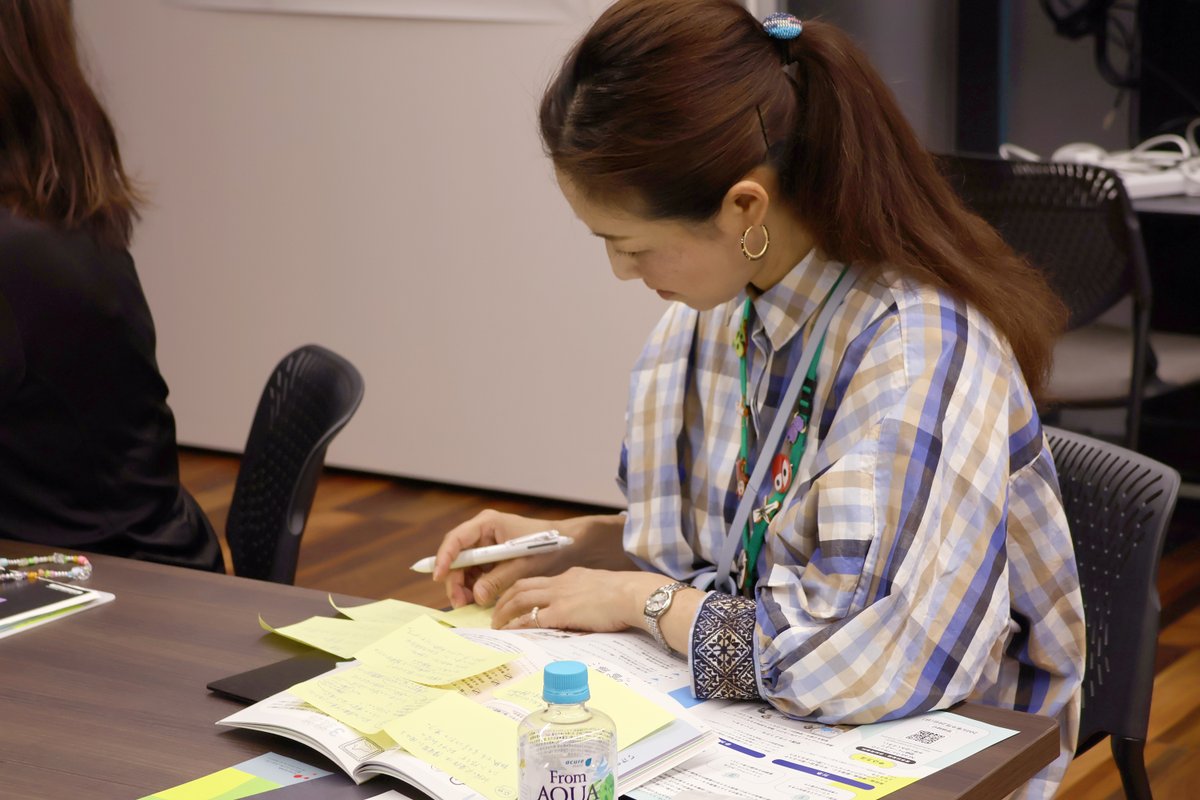

動画視聴後は、鈴木さんと伊東さんに動画作成やアクセシビリティを研究するきっかけや、動画内で出てきた話題や言葉についてことラーが気になったポイントを聞いていき、深掘りをしていきました。

最後にはお二人からことラーへのエールとして一言ずつ期待することをお聞きしました。
鈴木さんからは「ことラー一人ひとりの行動や意識が変わっていくことで社会が変わっていくというポジティブな意識を持って活動してほしい」、伊東さんからは「いかに社会に繋げていくか、自分になにが出来るかということを考えながら一つひとつ積み上げていってほしい」という言葉をいただき、この回は終了しました。
今回はアクセシビリティの基本となる「合理的配慮」と「情報保障」について学びました。この二つはここ最近でよく耳にするようになってきましたが、改めてどういったものかと考えるとわからない部分もあるかもしれません。そういった意味でもことラーにとっても基礎的な内容を認識できる機会となったはずです。
この二つを理解して今後の活動を行うのとそうでないのとでは行動が大きく変わってくるでしょう。この考え方を根底において活動することを心がけてもらいたいと思います。
次回は美術館でのアクセシビリティの実例を見ていきます。美術館に来館される方の状況に応じた迎え入れ方や鑑賞のあり方を知ることで、こと!こと?かわさきの活動へも応用していけるようにアートコミュニケータの視点を持って次回の講座にも参加してほしいです。
(こと!こと?かわさきプロジェクトマネージャー 財田翔悟)
