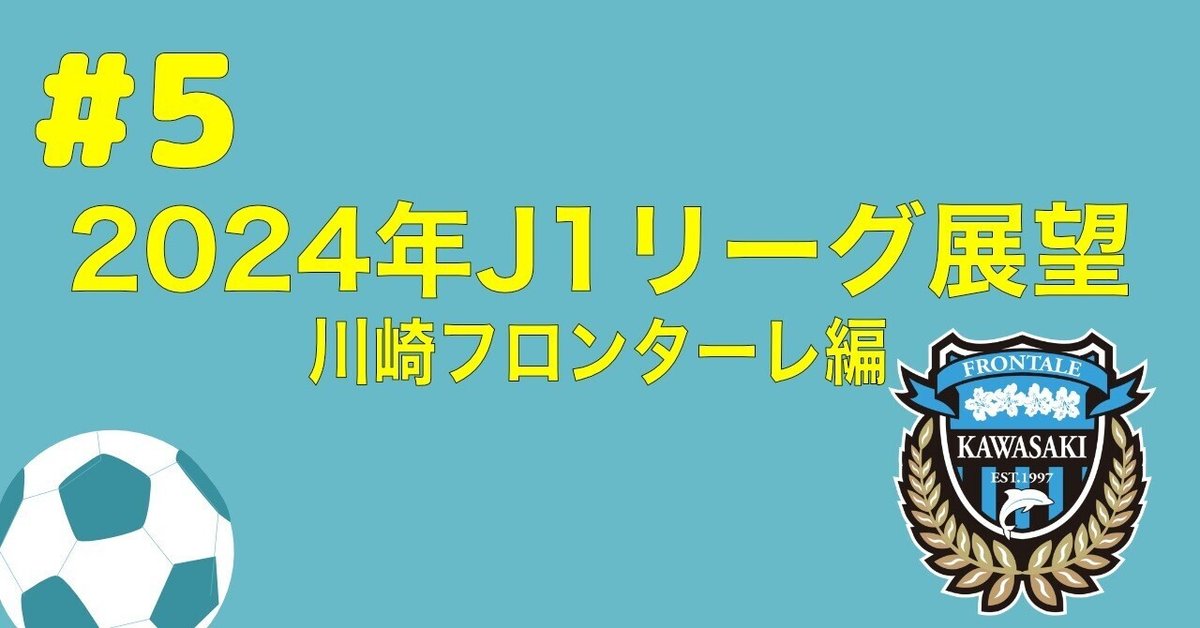
2024年J1リーグ展望 川崎フロンターレ編
ぼやぼやしているとACLがはじまってしまいそうなので、今回は川崎フロンターレの2024年の展望を見てみたいと思います。
まずは前年度までの流れから、
2023年度の総括
監督

川崎はJリーグ史上でも最強クラスといっていい2021年シーズンのスカッドがピークであり、この2年間は成績を落とし続けています。
一方でカップ戦の好成績を見ればまだまだ覇権をうかがえる強豪チームであることは間違いありません。
鬼木達監督は2024年で8年目のシーズンに入りました。
J1の長期政権といえばガンバ大阪の西野朗監督(10シーズン)ですが、もしその記録を狙うのであれば今年の内容と成績はかなり重要となってくるはずです。
「内容」と言ったのは、鬼木監督は去年の段階からチームの戦術を大きく変えようとしていて、理想と現実の狭間で葛藤しているように見受けられるからです。
その葛藤の深さは選手の動向からもうかがえます。
選手

これは、それぞれの選手がシーズンをまたいでどれだけリーグ戦の出場時間を増減させたかを表にしたものです。
(※基本的に増減が500分以上の選手のみを抜粋)
(※オレンジ色の枠は、シーズン中を含めたその年の新加入選手)
(※紫色の枠は、前シーズン中を含めた退団選手)
2021年のシーズン途中で田中碧と三苫薫、さらに冬のオフには旗手怜央と代表級の選手が3人もクラブを去り、ジェジエウなど主力選手の怪我も相次いで、2022年は成績を落とすのもやむなしというシーズンでした。
王座奪還を狙うはずの2023年は、クラブの大黒柱だった谷口彰悟の海外移籍というショックな出来事が起こります。
成績としては前半からつまずき、後半は巻き返して天皇杯を取るなど明るいニュースもありましたが、久しぶりにリーグの優勝争いに絡まないモヤモヤとしたシーズンを過ごすことになりました。
上の表で注目してもらいたいのは佐々木旭とチャナティップです。
2022年に加入してチームの主力になったはずの2人ですが、どちらも次の年には大きく出場時間を減らしています。橘田健人など他の既存選手も同様に出場時間が減っています。
つまり2022年シーズンはチームとしての上積みがなかったということになります。ここにも鬼木監督の葛藤がうかがえます。
では、2023年には川崎にどんな変化が起こっていたのか、今度はチームのスタッツを見てみましょう。
スタッツ

これは2022年と2023年のスタッツの中からネガティブな数字の変化を抜粋したものです。(クセの強い項目名ですみません)
まず左から、
「BOX内G(ペナルティボックス内でのシュートによるゴール)」が減り、
その中でも特に「頭G(ヘッドによるゴール)」が大きく減っているのがわかります。
「クロス数」「空中戦」などは総数は増えているものの成功率の低下によって成功数が減ってしまっています。選手の移籍にともなう連携の問題もあるし、個人の質の問題もあるでしょう。
「大ミス」は相手のシュートやゴールに直接繋がるようなミスの数です。
(たとえば「ビルドアップの時に横パスが引っ掛かってキーパーと一対一」のような例の頭を抱えてしまうシーンです)
この数字はリーグ全体で増加していて、DFに対するプレス技術が上がっている影響がうかがえます。ただし川崎はその中でも上位の増加数でした。また「ファウル数」「与えたPK」の数も増加しています。
個人スタッツ
さて、この辺りで今回の記事のメインテーマを明かしておきたいと思います。
それは「谷口彰悟の移籍で川崎フロンターレの何が失われたのか」です。
現役代表CBでもある谷口の影響力は当然大きなものです。
キャプテンシーなど形として見えない部分もそうですが、数字として見える部分については押さえておくことが川崎の復権に向けて重要なことではないかと思っています。
では、CBの個人スタッツを見てみましょう。

谷口は2022年の数字、それ以外は2023年の数字です。「CBリーグ平均」はJ1レギュラークラスのCBの平均を集計したものになります。
「タッチ数」を見ると、2022年までは谷口がビルドアップの中核だったことがわかります。現在は車屋紳太郎がその役を引き継いでいるようです。
「ロングボール」では「成功率」の高さに谷口のパスの質が見て取れます。プレス回避の苦し紛れではなく意図を持って前線にボールを届けていたことがわかります。
「空中戦」も谷口は優秀です。この空中戦を含めたデュエルに関してはジェジエウも大きな役割を果たしていたのですが、怪我の影響なのか昨年の数字は振るわないものでした。
さて、この「高さ」に関わる事象は守備だけでなく得点力にも影響しているようです。
詳細を見てみましょう。
失われつつある山脈

右:FootballLABを参考に独自にデータを加工して作成
ヘッドによるゴール数の減少もそうですがゴールを決めた人数も大幅に減っているのが気になるところです。
また、右の表はセットプレーによる得失点を表にしたものですが、2022年までは得点の方が上回り川崎のストロングポイントだったセットプレーが、2023年には失点の方が先行してしまっています。谷口や知念慶の移籍だけではなく川崎の「高さ」を担っていたベテラン勢が軒並み調子を落としているのが影響していそうです。
ここまでで「谷口彰悟の移籍で何が失われたのか」。その実態が見えてきたのではないかと思います。
最初の方で言ったように、おそらく鬼木監督はチームの再興に向けて新たな戦術を練っていて、このオフもそのための戦力を集めたのだと思います。
(僕の浅い見識では細かな戦術論については語れないので触れません。このさき良い記事を見つけられたら紹介していくつもりです)
ただ、たとえば「高さ」の数字に関しては選手個人の根本的な質に関わる問題なので、戦術変更で補えるものなのかは疑問です。「大ミス」や「与PK」の数字も悪化していたので、この冬の移籍市場ではCBやGKの補強をするのだろうと見ていましたがあまり積極的な動きは見られませんでした。
2024年の川崎フロンターレは、特にいま挙げてきた数字が改善されていくのかを注目していきたいと思っています。
2024年度シーズンの展望
今年の川崎フロンターレはJ1リーグ未経験の選手が多く加入したため未知数な部分が多いです。
ただ一つテーマを挙げるなら、それは「怪我からの完全復活」かもしれません。
丸山祐市は、J屈指の実績を持ったCBですが、度重なる怪我の影響か昨年のスタッツは奮いませんでした。彼が本来の調子を取り戻せれば、川崎にとって今年最大の補強になると個人的には思っています。
エリソンは、2022年のプレーを見ると第二のダミアンやフッキになれるポテンシャルを持った選手であることがわかります。ただこちらも昨年は怪我で大きく調子を落としています。
ファン・ウェルメスケルケン・際も、21/22のシーズンに怪我をして以降は武器の一つだったドリブルの数字が上がっていません。また、守備のスタッツではタックルの数が多くドリブル突破される数字もやや多いところから積極的に相手に突っ込んでいくタイプの可能性があります。いずれにせよ川崎ではどのようなプレーを見せるかが楽しみです。
以上のように今年の川崎は「怪我をして調子を落としている」選手が多く加入したため、フィジカルやメディカルのスタッフ陣が本当の意味でチームの浮沈を握っているのかもしれません。
その他で言うと、
山本悠樹は活躍が約束されたプレーヤーであり、鬼木監督が彼を中盤のどこに配置するかは開幕戦の注目ポイントになります。
代表入りした三浦颯太も新天地でのレギュラー定着は間違いないでしょう。ドリブルやクロスなどの攻撃面ももちろんですが、前任者の登里享平と比べた時に、ここまで指摘してきたパワー不足を補える存在としても大きな戦力です。
ゼヒカルドは昨年のスタッツを見るとなかなかクセの強い選手のようです。ポジションはCHでいわゆるボックストゥボックスと呼ばれるタイプの選手なのですが、この位置の選手にしてはドリブルを多用していて得意としているのが特徴的です。また、ファウルも被ファウルもイエローカードの数も多いのでなかなかの暴れん坊かもしれません。
(パトリッキはほとんど新人と変わらない実績なので割愛します)
新戦力評価は以上です。
川崎は未知数な部分が多いため成績が上がることも下がることも予想されます。ただ僕の実感で言うと、今のところは分の悪いギャンブルをしているように見えます。CBやGKの選考について根本的な質の部分を求めていかないと、いくら戦術が洗練されていってもつまらない失点で成績を落としていくのではないかと危惧しています。
その意味で今年の最大のキーマンとしてあげるのが高井幸大です。
将来的には谷口を越えるポテンシャルを持った選手だと思っています。まだ若いので無理はさせられませんが、彼の成長が川崎の未来につながっているはずです。
川崎フロンターレ編は以上になります。
続いて同じくACL参加組の横浜Fマリノスの分析と行きたいのですが、その前にまたリーグ全体の話をしておく必要を感じたので次の記事はまた寄り道をすることになりそうです。
応援してくださる方はフォロー、高評価をよろしくお願いします。
