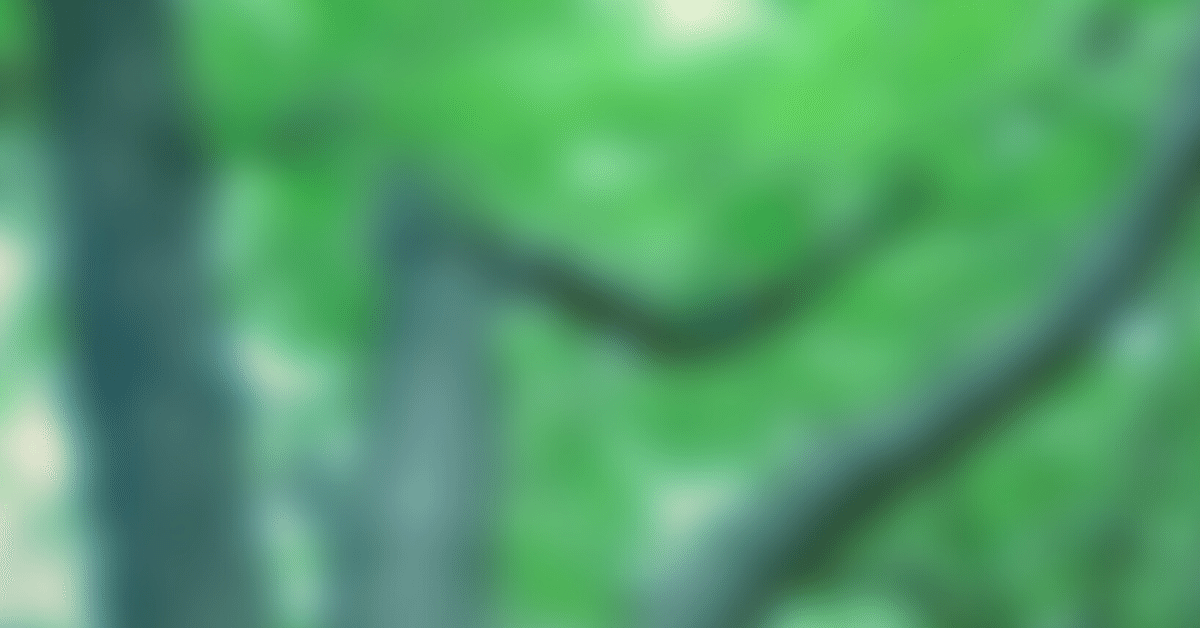
作曲家の自分に、言いたいこと
僕は約10年の作曲家・音楽プロデューサーとしてのキャリアを経て、
シンガーソングライター「leift(レフト)」として活動し始めた。
この一年、僕はいくつもの側面から自分を掘りに掘り下げてきた。
その度に「従来の自分」「新しい自分」を比較してきた。
今日は、僕にとって「従来の自分」の代表格である、作曲家としての自分に向けて、今思うことを正直に書いていく。
本題に入る前に
先日(と言ってももう1ヶ月前だけど)、
力を入れて臨んだ大切な仕事が、公開された。
自分にとって初めての劇伴担当作品、アニメ『ユーレイデコ』だ。
これまでCM音楽の世界で作曲家として活動してきた自分にとって、アニメ作品の劇伴制作に関わらせていただくのは転機そのもの。
クラムボンのミトさんを中心に、Yebisu303さんと僕の3人体制で音楽制作した今作。毎週、テレビで自分が担当した作品を観られることがこんなに嬉しいなんて、思ってもいなかった。毎週の放送を、とても楽しく観ている。
劇伴に関する話は是非、音楽ナタリーのこのページを見てほしい。
今回のnoteには、この『ユーレイデコ』が深く関わることを、
最初に知っておいてもらえると嬉しい。
--
立ち止まってしまった「作曲家の自分」
話は1年前に遡る。
この作品の納品を済ませた頃から、僕はずっと、インストでの音楽表現のあり方に疑問を抱き続けることになる。
インスト表現の、自己記録更新作
『ユーレイデコ』の劇伴制作は、僕のインストアルバム『STELLAR』の完成直後から本格的に制作が始まった。
『ユーレイデコ』の劇伴は、ありがたいことに僕に求められる世界観が非常に当時の自分らしいものだった。描きたい世界がハッキリしていた分、『STELLAR』の気持ちの延長でフルスロットルにギアを踏み、心に対して超高純度な音楽を作ることができた。
じゃあ、自分主導のオリジナル作品はどうか。
僕は『STELLAR』の制作を通じて、
インストで自分自身のムードを具現化するのを、完全にやりきった。
ゆえに、限界を感じ始めていた。
インストは、気持ちを具現化するのに向かない
僕にとって、インストはそういうものだと気づいた。
今思えば、僕は自分のインスト音楽作品に乗せようとした想いが、
重すぎたんじゃないかと思う。
インスト音楽は、当然ながら言語を持たない。
ゆえに印象や空気感で届けていくことになる。
時に、楽曲に込めた想いは語れば語るほど、陳腐に取られることもある。せっかく言語を持たない音楽を作っているのに、言語で楽曲を解説してしまっては、想像に制限をかけてしまうからだ。
「空気」じゃ嫌だ
僕は「空気」の先に「実像」を求め始めた。
その頃から、noteの書き味も一気に変化した。
「告知・宣伝」と、
自らが思うような投稿を避けるようになった。
より自身の内面をえぐるような文体、弱さを晒すことで自分を再発見していくような、自問自答型の構成が増えていった。
音楽のテーマが、「空気」「BGM」「ムード」から「想い」に移行していく。ゆえに表現の中心が、作詞と歌唱だという結論に行き着いた。
そこから先は、同じ音楽でも
目指すべき道が従来とまるで違う、
異世界が待っていた。
主役と脇役の「育ち方」は違う
完膚なきまでに思い知らされた。
映像音楽も、シンガーに歌ってもらうトラックも、どこまで行っても「脇役」でしかない。主役は映像やボーカル。僕はそのことに、とても誇りを持って作曲家を名乗っている。
だからこそ、僕は思えばインスト音楽での表現を追求していた限り、
「脇役としての成長プラン」しか持っていなかったのだと思う。
歌詞そのものがストーリーを帯び、かつダイレクトに聴き手に伝わる、歌。伝えたいことが、粗も含めて直接伝わる表現。ゆえに、インスト以上に「好き」「嫌い」が明確に分かれやすい。
何より、メッセージの主役が自分であるシンガーソングライターとしての活動は、歌を主役に立てれば立てるほど、聴くシチュエーションが限定されていく。言葉を聞き取れれば聞き取れるほど、BGMになりづらく、歌に込められた感情で聞き手は聴く場所を選ぶようになる。
これらは、歌をやってから初めて気がついたものばかりだ。
それほどまでに、僕は無知のまま歌の世界に飛び込んだなと思うし、相応に、深く自分に落胆し、傷つき、自信を見失った。
これだけ自信を失ったのだから
歌が形になればなるほど、
作曲家の自分は古い自分で、歌こそが新しい自分だ。
と、信じきってしまっていた節があった。
これは今となってはそう思える話であって、当時は知らず知らずのうちに「作曲家の自分は、脇役に甘んじている」と思い込んでいた。
それほどに、どれだけ努力した気になっても一向に前に進んだ気がしない歌が、苦しくてたまらなかった。無論言うまでもなく、歌っているだなんて周りには言えなかった。自尊心が許せなかった。
音楽に自信があったはずの自分が、
音楽で自信を、完全に無くした。本当に、完全にだ。
無論
「音楽家として自信に満ちて会っていた」人たちには、
連絡できなかった。
変化の岐路

ふたつあった。
leiftという新名義
当初、僕はKOTARO SAITO名義で歌おうとしていた。
インスト音楽を中心に作曲家・トラックメイカーとして楽曲リリースをしてきた自分の名義に、歌という切り口を「追加」「更新」しようとした。
でもそれだと、
どうしても自分の中で
「歌う以前は古い自分、歌以降が新しい自分」みたいな、
従来の自分を否定しているようなキャリアを踏む気がした。
ずっとモヤモヤしていた。それでいいのか?と。
キャリア形成に大きく関わる決断だと直感して、
「実名より本心を歌える別の人格」を形にしようと決めた。
それが、シンガーソングライターleiftだ。
アルバム『βeige』の前段階
ちょうど去年の今頃、
僕は次のアルバムのタイトルを『βeige』にするって決めた。
自分にとって新しい自分になる。それが世の中から見て新しくなくても、自分のアップデートを大事にしようと決め、何の変哲もない、けど自分にとって新鮮な色であるベージュという言葉に想いを宛てた。
そうは言ったものの、簡単に新しい自分、特に歌い手として僕が満足いく楽曲を作り出すことは容易ではなかった。そしてせっかくleiftという新名義も作ったから、ゼロから新しくアーティストになるべく「黎明期から発展期」的プロセスを、楽曲で描くことにした。
僕はその推移に「α期」「β期」と名前をつけた。
「α期」は後に振り返ったとき、楽曲も歌もより稚拙に感じる可能性がある。アーティストとして自身のあり方を模索し、扱う内容、使う言葉も重くネガティブかもしれない。
でも「α期」を経ずして、本来僕が向かおうとしたleift像にたどり着けないと思えたし、leiftは僕の弱さや本質を晒すプロジェクトだからこそ、モヤッとしている時期を曲にしようと決めた
こうして生まれたのが、楽曲『bleach』だ。
リリースしたこと自体に価値があった「α期」
正直この曲は、僕にとって王道ではないソングライティングを用いた。自分の新しい一面を、自身で発破をかける気持ちで書いた曲。ゆえにメロディもアレンジも、あえてクセをつけて作っている。
それくらい、当時の僕は歌にも自分の楽曲にも、
何より自分という存在そのものにも、
意義を模索しながら生きていた。
おそらく、未来の自分が聴けば『bleach』は不安定な曲だ。
けど、この1曲をマスタリングし終えた時に確かに感じた
これで、ようやく、夜が明けた。
俺は踏み出せる。
って感覚は、今もしっかりと覚えている。
自分に自信を得た。以前と比較にならないほど、
他の楽曲はスムーズにレコーディングは進んでいった。
そして、月日は更に経ち、
6月にシンガーデビューできたことで
歌おうとする自分に、
しがみつかなくていいんだ。
と思えるようになった。
この話は、このnoteの後半で語ろう。
『ユーレイデコ』との掛け算的オファー
話は、僕が『bleach』を作り終えてすぐの頃に始まった。
当時まだ、片手で数える程度の人にしか歌うと話していなかった僕が、『ユーレイデコ』の件で連絡を取り合っていた音楽プロデューサーの佐藤純之介さんに、勇気を出して『bleach』を聴いていただいた。
歌のスキルには思うこと多々あっただろうけど、僕が歌うに至ったこと、歌詞に寄せた僕の想いを、前向きに捉えた言葉を佐藤さんはくれた。
佐藤さんとは『ユーレイデコ』の各話にコラボレーションソングを制作するという話を進めていて、僕も作曲家としてオファーいただき、シンガーを誰にしようかと思案している段階だった。自由度をいただいていたから、この機会にご一緒したいシンガー候補を、思い描いていた時期だった。
そんな時、ふと佐藤さんが僕に言ってくれた。
齊藤さんが歌うのも、アリだと思いますよ!
僕は、そんなふうに言ってもらえるなんて思っていなかった。初めての劇伴担当作品である『ユーレイデコ』の別企画でコラボソングを作らせてもらえるだけで充分ありがたいと感じていた。
え。俺、歌ってもいいの?
ちゃんと、その責務を全うできるのか。そして、leiftという極めて個人的な感情を歌うと決めたアーティストが、アニメ作品が主となるコンテンツに寄り添って音楽を作ることができるのか?
全集中で臨んできたleiftの、デビュー2作目でアニメのタイアップをつけてもらえるなんて、願っても叶わないだろうお話。
凄く凄く嬉しかったのが本音な一方、作曲家として関わるべきか、歌まで歌わせていただくか、返答するのに時間を要してしまった。やり取りの最中、業界未経験の素人みたいなleiftのエゴを佐藤さんにぶつけてしまったこと、今でも申し訳なく思っている。
改めて、作品を見返した日々
色々考えても、当時の状況でleiftを知ってもらえる願ってもないチャンスだと直感的に分かっていた。だからどうしても自分で歌わせてもらいたいと思ったし、だとすれば何を描くのかを、自らの感情とアニメ作品とで完璧な形で融合させたかった。
結果的には、「融合させた」わけではない。
僕自身の感情起伏のタイミングと重なって
自然と「融合した」のが、
僕にとってこのプロジェクトの尊さだ。
アニメ『ユーレイデコ』は、SNS社会で生きる人たちの心情と、プラットフォームと人間の関係性に触れる作品だ。僕はまさに当時、SNSとの向き合いにめちゃくちゃ悩んでいた。
SNSのフォロワーが少ない
見られること、リアクションされること、その先に、ファンという形で応援してもらうこと。現代の表現・発信活動において、SNSは避けて通れない入り口で、収益化の出口さえもある。
はっきり言って、僕はSNSのフォロワーが少ない。
noteはその中でも多い方だけど、他のSNSは本当に弱小規模で、特にYouTubeはこれまでほぼ機能していなかった。フォロワーを増やすための努力を、全然できずにいた。
毎回、楽曲のリリースのたびに、配信先に向けてSNSのフォロワー数を書かなければいけない欄がある。その度に「SNSちゃんとやらなくちゃいけないんだな」「フォロワー数がピックアップに影響するんだ」と、現実を突きつけられた気持ちになった。
楽曲を作っていた4月の中旬はまさに、
その悩みがボディブローのようにのしかかってきていた。
仕事柄、SNSのフォロワーを増やす方法や、人が情報に触れ、人が誰かのファンになるまでのプロセスを知れる機会を、沢山いただく。
だからこそ投稿を継続できかったり、「人が反応しやすい表現」を追求しきれない自分のことを、他人と比較しながら情けない存在だと思っていた。
新しい自分と、これまでの自分
SNSの中で、活動を新たに羽ばたこうとする自分。それは僕にとってleiftだった。一方で、とにかく愚直に曲作りで自分らしさを追求してきた「従来の自分」が、作曲家である自分だ。
leiftになったら、SNSを頑張ろうと思っていた。(結果的に、やっぱり頑張れていないのだけど)心機一転、違う自分になって、心の奥底に凝り固まっている弱さを、本心を磨いて形にしていこうと考えていた。
そう考えた時、これまで培ってきた自分がどうしても、
「古く、おじさんっぽい」と思えて仕方がなかった。
ここでいう「おじさん」とは、
あくまで僕の自己評価として読んでもらえたら嬉しい。
アンチ・オジサニング
僕は今年36歳になるのだけど、こうして自らの年齢を文字で打っても、未だに数字だけ見て、凹む。心の底から、僕は老けたくないと思っている。10代、20代の頃は早く大人になりたかったのに、いざ年齢だけなってみたら、何一つ当時思い描いていた理想郷は存在しなかった。
数字上老けたくないうえに、心が「おじさん化する」ことへの恐怖心が、とにかく強い。ここ数年、僕の心は限りなく子どもに戻っていっている節がある。人生の純度を追い求めて自己分析を繰り返した結果、自分に「それ妥協じゃない?」「時代に合ってないから変えようよ」「事情論とか要らんから」と疑いの目を向け、不躾なほど口に出すようになった。
だからこそ、SNSを使いこなせていない自分に
自分のやり方で数的成果を出せない自分に、
なんだかんだで他人との比較で落ち込んでしまう自分に、
ものすごく腹が立つ。
変われない自分への責任を、「音楽の本質はサウンドだ」と信じて疑わなかった作曲家としての「古い自分」に向けていた。
名義を分けたのに、実際自分はシンガーとして何の実績もないleiftにばかり興味が向いていて、これまで積み上げてきた作曲家としての技術やキャリアなんて、何の意味も為さないと、本気で思っていた。
どこにも属せない自分の「ダサさ」
作曲家としての自分だけじゃない。
学生時代・社会人・そして音楽のプロになった今も、自分が身を置く場所がシーンや業界に存在しない感覚。人からの評価を気にするクセに、人の輪の中で生きていくのが本当に苦手な自分が、嫌いだ。
新しい挑戦をするたびに、今度こそ何処かに居場所が欲しいと願い、開拓しようとする。同じくして、馴染めず、居場所を手に入れられなかった1つ前の自分のことを「ダサい」と思いがちだった。
大衆に混ざることを、
自分のやるべきことだと思っている節が、
実は今もかなりある。
自分を大事にすればするほど、時代や集団のルールに合わせられない、いい流れが来ても乗り切れず、対外的な好機を逃す。僕の普遍的な弱さであり、毎回苦しくなるポイントだなって思う。
葉っぱと、根っこ
話を、楽曲に戻す。
僕は新しい自分を「葉っぱ」と喩え、古くから変わらない自分を「根っこ」と喩えて曲を書くことにした。
この先もきっと、
僕はやりたい方向に葉っぱを伸ばす人生を歩んでいきたい。
都度、フレッシュな自分でいたい。
だけどいくら葉っぱを生え替わらせても、
葉っぱに水を送る大部分は根っこ。
生きる以上、根っこを変えることはできない。
嫌な自分を放置したって、言い訳したって、ただ自分の本質を見失うだけで解決なんて出来っこない。そこまで分かっているのに、古い自分を認めたがらない自分がいる。そんな自分が、ダサいし嫌い。
本質的な自分を変えられないなら、積み上がっていく「古い」と自覚した自分を、ちゃんと受け入れる必要があった。周りの優しい友人、家族は「別に本質から変わらなくていい」と言ってくれる。
でも、僕自身が納得していない。
そんな状態が、長らく
齊藤耕太郎という人間を支配してきた。
--

アニメ『ユーレイデコ』を観ながら、不安に駆られていた僕が気付かされた「変わるたびに放置してきた"従来の自分"への処理」の必要性。
別のインタビューでも話したばかりだけど、コラボソングの声をかけてもらったタイミングと自分の心情の状況が、偶然重なったことは奇跡だと思う。
本質に向き合うことから
逃げちゃダメだ、と思えた。
否定しているのは自分だ
これが、向き合ってみて分かったこと。
根っこの部分に対して、少なくとも僕が仲良くしている人たちは、間違っているだなんて誰も言わない。むしろ外側に見えている自分と内側の自分が違った時、周りは内側の部分を見て付き合ってくれているんだと知った。
逆を言えば、僕の感じている僕の嫌なところは、
「僕だけが」嫌なことだったりする。
結局、極めて自分の問題。
実はそれが一番厄介で、
他人の肯定が全く届かない領域が
つい存在してしまいがちなところだ。
自己分析の功罪
歌うと決めて、
自分の言葉を探しに探した僕にとって、
自分とは何か?を自ら再定義する行為は
絶対に避けられないプロセスだった。
でも結局それゆえに、
僕は自らの純度100%以外のものを、
ことごとく拒絶することになる。
根本的な自分と結びついていないものはダメ。
そう思うと、自分を縦に掘れたとしても
価値観が横に広がっていくことはない。
僕は思い知った。自分がどれだけ、
外的な刺激を受けるたびに
引き出しを増やせてこれたかを。
人格が形成され、かつ社会経験も人並みに積んだ状態で、自分の本質を再度深く掘り直すことは、諸刃の剣だ。否定しうる年月が長ければ長いほど、バランスを崩した時、回復が難しいからだ。
掘ることが、自分に光を差してくれると勘違いしてはいけない。掘るのは、自分が自分の魅力を見つけて内側から光るために必要な工程であって、掘ったからといって他人が自分に光を当ててくれるわけではないんだ。
他人が介在する世界で自分の魅力を輝かせたいなら、自己分析や自分像の定義は、自分らしくいるために必要なコトの、半分程度だろう。もう半分は、他人相手に自分が動き、自分が光だと思う自分を魅せていくことだ。
至極、当たり前な話をしているのは分かってる。
でも、僕は自分が作った檻にハマり、抜け出せないでいた。
真面目に向かえば向かうほど光を失う感覚を、
僕以外の人には味わってほしくない。
僕にとって「古く」見えてた「大人の自分」
社会人として生きてきた僕は、自分の信念を抵触しない程度に、興味のない話題の中に自分の興味を探せる。他人発信のアイデアにも、共感を見つけられる。少し苛立っても、自分は相手に真摯でいるよう努力はできる。
他人主導で動く自分を「嘘じゃん」って切り捨ててしまうのは、
自分を苦しめることになるんだと僕は感じた。
自分以外を完全に排除する人生は、人への依存度が大きい僕にとって、
かえって純度100%の自分を深く傷つける。
だからこそ。100%で居られる人格と、
「あそび」がある人格を、分けて考えることにした。
『bleach』をリリースした直後に、明確にそう思えた。
とても、気持ちが楽になれたし、作曲家としてのクライアントワークを
もっともっとやってみたい、ってハッキリと思った。
他人の目標を一緒に叶え、喜んでくれる顔を見る自分だって、僕が好きな自分だ。他人発信のアイデアやプロジェクトに参加して、学びの機会や新しい価値観をもらう。そうやって、僕は育ってきたじゃないか。
僕はここ数年、他人主導で生きることは「自分への負け」だと思っていた。自分のメッセージで生きる。自分の価値観で生きる。それが絶対神のように思えていた。
でも僕の場合、
「今は」そう言い切れないと確信した。
僕は他人を無視しきれない。
僕は自己評価だけでは、
自分の幸福を満たしきれない。
とりあえず今は、そう結論づけることができた。
それが変化してもしなくても、
大事なのは自分が自分であることだ。
CM音楽を作ってクライアント試写を迎えた時、クライアントが大喜びしてくれる顔を見るのが僕は好きだ。アニメ『ユーレイデコ』についてSNSで「好きだ」「続きが気になる」って誰かが書いてくれていたら、僕の手柄でなくたって、チームの一員として心から嬉しい。
そんな自分をもし「お前のメッセージじゃないだろ、それ」
って自分で言ってしまったら、
それは冷めてるなって思うし、素直になれてない。
僕が求めていた「自分主導、自分本位100%の自分」は、もしかしたら今の段階では、他人に影響を受けて生まれた、憧れの類だったのかもしれない。0か100かで生きられない自分を否定するのは、本当に勿体無い。
今は、自分にそう言い聞かせるだけの「あそび」を作れている。だから、僕は自分100%で臨むleiftの制作を、より先に進められているのだろう。
作曲家の自分へ
よくぞ、シンガーleiftを産むまでの、
音楽家としての基礎力を磨いてくれたと思う。
いきなり歌い出してたら、きっと僕は自分の満足いく音楽なんて作れていない。自分の歌を、自分の作品を俯瞰してプロデュースできるのは、KOTARO SAITOのおかげだって思えてる。感謝しても、しきれない。
そして、leiftの楽曲をKOTARO SAITOがプロデュースするようになって、
明らかに編曲やミキシングもより洗練されたと実感できる。
leiftとして世の中に自分の想いを発信していくためには、作曲家KOTARO SAITOもleiftに負けない速度でトラックメイクの腕を磨かなくちゃいけないし、leiftのおかげで作曲家としての粗が幾つも見えてくることを、冷静に受け止めて欲しい。
--
葉っぱをより、
光が集まる場所に伸ばす覚悟が、leiftにはある。
だから根っこはもっと強くなくちゃいけないし、
根っこを強くして、
leiftだけでなく他の沢山の人が光に近づいていくために、
全力を尽くして欲しい。
--
作曲家としての、次なる目標を探し始めた僕は、
抑圧から自分を解き放ち、少しずつ前を向き始めた。
今までよりずっとしなやかな自信があるし、
表現力も、表現の選択肢も、去年の比じゃないって自負できる。
僕が苦しみ抜いて作りたかった「β期」は、
張り詰めた緊張感じゃなく、肩の力が抜けた軽さだった。
と、いうわけで。
改めて『ユーレイデコ』の世界に寄せて、
leiftとして純度100%で書いた僕の歌を紹介したい。
leaves (with leift)
必要なのは 他人に好かれるコツ
出会い頭 次が見たいタイトル
理想だけ切り取った写真に
まぶたの裏 しまい込んだ卑屈な日々
毎秒こぼす ため息なんか秘密
大衆に混ざる ギミック
性懲りもなく 擬似
葉脈に通う血に 目を背け語る美辞
ミシン目の向こうに 嫌な自分だけ放置
「しょうがない」と呟きながら 手を振る間に
霞む空に溶ける 帰路を導くベル
「君に好かれるために捨てた僕」
核心のない 修飾語は嘘っぽく 自己嫌悪の毒
言葉にして 引かれる怒り
隠す表情は顔こわばり なおさら怖い
不安を口にし 伝った涙
(鳴り響いた)空の先 ベルの音が小さく
葉脈に通う血に 目を向け知った意味
新芽を辿れば やけに太い根が
無知から育み 巣立つまでを見送り
くすぶる「嫌い」も 誰かが好きな魅力
必要なのは 自分主導の自信
こうして、leift名義で歌った僕の作品、2作目は無事に送り出された。『leαves』は1作目の『bleαch』、そして先日リリースされたばかりの3作目『drαw』を橋渡しする楽曲なので、次回は3作目『drαw』についての話。
いいなと思ったら応援しよう!

