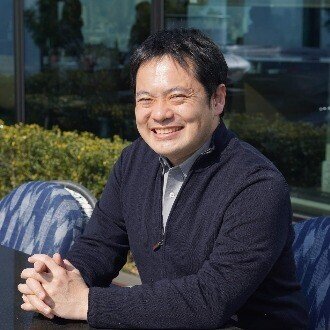ETIC/NEC社会起業塾・一次審査突破後の学びのツボ(生ワードだけ有料)
出身のETIC/NEC社会起業塾が公募中で、おススメだからこそ、ちょっと過去を振り返ってみながら、紹介していきます。一次審査突破した後の研修で実施したことを書いていきます。
一次審査突破して、自分が挑戦していく、社会課題に対して各々様々な社会課題に真剣に挑戦している試行錯誤・創意工夫をしている人々からの質疑応答は、贅沢なゆたかな時間でした。一次審査突破しただけで、そこを感じられたので、絶対に合格したい!と気合をいれたことを今でも思い出します。
ETIC/NEC社会起業塾公募中:6/22正午〆切
今までの合宿スタイルからオンラインスタイルに生まれ変わったとのこと
— 😊つぼた☺️喜業家😀+エンジェル投資 (@KosukeTsubota) May 27, 2020
絶対おススメの社会起業塾!
応募前の相談も受け付けます♪#ETIC https://t.co/GwAlO4J3AL
顧客の特定とニーズ・課題の掘り下げ
誰のために?
無医地区の住民
(全国136,272名、高齢者率約40%)
~~町~~地区住民(1st case)
・人口数5000名
・2011年院長の高齢による閉院から無医地区になる。
・職業割合は、農業40%、工業30%
・高齢者率は21%
~~町
人口数約24000名 内科医6名・精神科医1名
眼科医・耳鼻科医等の特定診療科目が不足しているため定義上は准無医地区。高齢者率21%
解決課題
療に容易にかかることが出来ないために、無医地区住民の外来医療費が低く、入院医療費が高い(初期症状の際に医療にかかることが少なく、重症化してからしか医療に罹っていない。)
初期医療にかかる人が少ないために、糖尿病や高脂血症など生活習慣病を含む慢性期疾患に関して重症化し医療費が増えている。また、そのために医療費が増えるリスクを抱えている。(治らない糖尿病などの疾患は、糖尿病にさせないことで年間500~600万円/人の医療費削減になると医療経済として言われている。)
また、医師がいる無医地区でも、診療専門科目に偏りがうまれている。益子町では、眼科医がいないため、近隣に眼鏡屋もなく、町外から来るメガネの巡業に対して眼科医がいないために保険で作成することができず、高額なメガネ代金を支払っていたり、適正でないメガネを使用していたりする。
事業を通して生み出す顧客の変化
無医地区住民の集まる場所、公民館や集会所、旧診療所などで移動型クリニックを定期的に開設し、住民に対して、医療アクセスをよくすることで、医療に容易にかかれるようにして、プライマリー医療の提供、生活習慣病を筆頭とする自覚症状のない慢性期疾患の疾患コントロールを通して健康寿命の延伸、長期的な医療費用の削減という変化を提供する。
また、眼科や耳鼻科などの特定診療科目にかかることが出来ない人々に対して、診療の機会を提供する。特に、眼科疾患に関しては、緑内障や白内障の早期発見から失明を防いだり、処方箋を利用してのメガネの購入の機会を提供する。
もたらされる社会の変化
人口減少、少子高齢化、限界集落化してきている地方の医療の課題・問題に対して、医療を提供する新しい仕組みができる。
また、診療科目毎に医療を提供する仕組みを作成することにより、今まで特定診療科目の専門医による受診の機会がなかったものに対して
将来的には、無医地区・准無医地区での移動型の医療機関の実証から、ビジネス街やベッドタウン等への要望の対応が可能になり、日本全国に自覚症状がないために仕事を休むことができず、医療に容易にかかれなかった、かからなかった人に対してプライマリケアを提供し、医療費削減・健康寿命延伸につながっていく。
先行事例の調査
地域医療振興協会・徳洲会病院
医療機関は固定で、医師をローテーションさせることで地域に医療を提供する仕組みを作成。
自治体病院
医療保険スタート時から巡回診療を実施している病院が複数ある。保健師などの地域リソースとの連携不足、眼鏡などの健康商材提供サービスが出来ていない。また、医療従事者不足と資金不足の問題から全国的に事業は縮小傾向。
米国:オレゴン大学・ハーバード大学
モバイルクリニックを使用したプライマリケアの提供の実践を2013年より開始。
WHO・NPO法人ロシナンテ
モバイルクリニックを活用した発展途上国の医療サービスの提供を実施している。日本の医療制度と異なっているために、法律的課題解決としては参考にならないが、運営モデルとしては大変参考になる。WHOの仕組みは、看護師がモバイルクリニックにのり、中央部にいる医師に情報を伝達し、判断・指示をしてもらう形式。
最期
ステークホルダーマップやコメント・補足等が書かれた生のワード資料は、有料にします。
過去note
#1:学んだこと
#2:白書のたたき台
#3:同期たち
#4:エントリーシート
ワークシート
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?