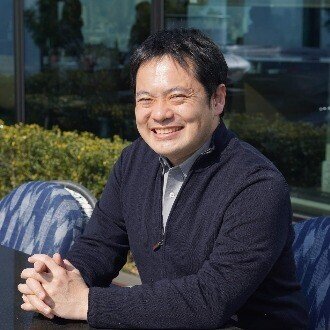ETIC社会起業塾2013エントリーシート共有(生ワードだけ有料)
社会起業塾の自慢をしているだけだと、ただの嫌な奴なので(笑)自分が一次審査を通った際のエントリーシートを共有します。ちなみに提出した時は、写真のように疲れ果てていました。参考にして頂いて、本業に専念しながら応募を検討して頂ければと思います。生ワードだけ有料にしますが、後は公開。
〆切6/22 正午
今までの合宿スタイルからオンラインスタイルに生まれ変わったとのこと
— 😊つぼた☺️喜業家😀+エンジェル投資 (@KosukeTsubota) May 27, 2020
絶対おススメの社会起業塾!
応募前の相談も受け付けます♪#ETIC https://t.co/GwAlO4J3AL
#1学んだこと
#2 :白書の創り方
#3MBAより役だったETIC /NEC社会起業塾のこと
#4エントリーシート
応募者自己紹介と目的
慶應義塾大学看護医療学部一期生卒、Canisius大学経営学修士課程卒。大学時代より、地域医療活動サークルに入り僻地医療に関わる。その傍ら、他大学で同様の地域医療系、社会医学系の活動をするサークルに興味が出来、サークル間のネットワークを構築し、最大1000名が所属するインカレサークルの設立及び300名規模で学生団体が活動報告をするイベントを創ってきた。卒後は、専門学校の教師から米国留学、コーチングファームに就職。2011年東日本大震災時の移動型眼科医療機関ミッションビジョンバンの活動をきっかけに移動型医療機関構想を考え、弁護士・医師・歯科医師・医療事務と私の5人で厚生労働省に質問書などで活動を開始。2012年10月に厚生労働省医政局局長通知により公的病院以外でも移動型医療機関の活動が可能になったことから、11月に一般社団法人医療振興会を当時自治医科大学病院に所属する医師と協同設立。2013年4月より当活動に専従し、栃木県の無医地区にて活動が可能になった。
自覚症状が無い病気などから医療費の増大が問題化してきている日本で、医療の方から人々の生活に距離を縮めていく必要が出てきている。また、人口減少及び高齢化してきている中、医師の高齢化・人口減少などから無医地区・無医村の増加傾向がみられてきている。移動型の医療機関などで、重篤ではない自覚症状が無い慢性期疾患などに医療を提供していかないと日本の医療費の増大が抑えられないと考えています。
未来のビジョン/解決したい社会的課題、背景
日本全国に無医地区(半径4キロメートル以内に50人以上の人口があり、医師がいない地域)が705地区、計136,272名の人口がある。無歯科医地区(半計4キロメートル以内に50人以上の人口があり、歯科医がいない地域)が930地区、計236,527名の人口がある。ここに住む方々は、皆保険制度のために医療費及び介護費を支払っているが、医療機関サービスがないために、医療費の活用が抑制されている方々である。そのために、自覚症状が悪化しないと医療になかなかかからない。実際に、青森県では僻地医療に関して、外来医療費が安い代わりに入院医療費が高いというデータがある。また、都内での救急医療にかかって入院する率は7%に対し、僻地医療では50%以上という調査結果が出ている。重症化することによって日本国内の医療費が増大化するために重症化する前の医療、予防医療が重要だと言われ、具体的には初期の糖尿病患者さんを一人発見し治療することで、医療費用が年間500から600万円コスト削減ができると言われている昨今、医療機関が無い地域への医療サービスの提供が重要である。また、地域の医療従事者の高齢化による引退で、医療機関の閉鎖により無医地区化してきていることが問題視されている。2013年7月より医療振興会で活動を開始する予定である栃木県では、半径8キロメートル以内に7000名の人口がある地域が2011年医師の高齢化による休止により、実質無医地区化した。
そのような地域への医療サービスを提供するためには、医療機関の設立が必要で、医療機関を設立するためには、慣習的に監督医が週に3日以上その場で外来を開かないと保健所より医療機関登録が許されない現状である。医師不足・看護師不足が言われている昨今、一つの地域に医療従事者を止めていくことが難しい。一人の医師で複数の地域が見られるモデルが必要であった。移動型の医療機関が医政局の通知により実施可能になったことで、午前中はA地区(人口300名)、午後はB地区(人口1000名)など多様な地域に医療サービスを提供することが可能になった。また、地区への巡回は、週3日以内と規定されているために、都内の大病院に務める医師などが月に1回地域医療に従事するなどの協力体制が可能になった。これにより、地域に対して第一月曜日は、眼科であると事前告知するなどしておくことで、眼科専門医など一つの臓器に特化した医師も、地域医療に従事することが可能になった。(地域医療では、総合診療医の知識が必要になるために、総合診療などの項目以外を選ばれた医師にとって、従事することにハードルがあった。)
日本全国に医学部は80大学ある。その全ての大学で、地域医療(国際医療含む)に関する学内学生団体が必ずある。そのサークルの卒業生たちは、地域医療に関心はあるが、自分のキャリアの関係で各科専門医になった場合関心があるのに従事することができなかった。そこに対して従事する機会を提供していくようにしていこうと考えている。7月にスタートするのに辺り、協力賛同医は現在10名程度であるが、モデルを構築し、この移動型医療機関モデルを全国展開していきたい。同時に眼科医がいない地域には、メガネ屋がない地域が多い。高齢化によりメガネの需要は伸びてきているので、移動型の医療機関を通し、移動型の健康商材などの提供をし、地域に住む住民の応援をしていきたい。
実現に向けた事業モデル・戦略
地域の保健師の協力を得て、公民館などの集会所に住民に集まって頂き、そこに移動型クリニックをつけて巡回診療を実施する。また、地域に常時滞在するわけではないので、テレビ電話などのITを使用して医療相談・健康相談が可能なようにしていく。同時に全国の無医地区に医療情報健康情報を提供するフリーペーパーを設置し、健康や医療に関する啓蒙活動を実施していくことと同時にそちらのフリーペーパーからメガネなどの健康・医療商材の購入ができるようにインフラを整えていく。
2013年は、移動型医療機関どこでもクリニックの栃木県内におけるモデルケースの作成と無医地区のネットワーク化に尽力し、2014年以降に伝播していくように心がけていく。
在宅にて医療サービスを提供する在宅医療が増加してきているが、在宅医療は在宅から出ることが出来ない高齢者や終末期患者さんが対象であり、在宅から出ることが出来ない人に対しての医療サービスは提供できない。そのために医療機関にかかっていなかった方々に対して、新たに医療機関にかかることが難しいことからその地域で人が集まる場所である集会所などで集まった際に医療を提供させて頂く。
医療サービスは、基本的に慢性期疾患(高血圧・高脂血症・糖尿病など)及び高齢疾患(老眼・白内障など)を対象に実施していく。
エントリーシート
個人情報が入っているので、ワードファイルダウンロードする際は、ちょっと有料にします。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?