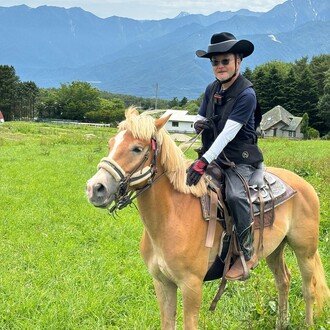#13 高齢者が乗馬を始めるために必要なこと
前期高齢者の乗馬事始
前回は馬と「ウマが合う」ようにするためのアプローチについて書きましたが、いかがでしょうか。
今回は自分の初心者時代の経験をもとに、高齢者が乗馬を始めるために必要な条件を考えてみました。
乗馬に体格体型は関係無い?
あたりまえですが、乗馬するためには、先ず「馬の上に乗れる」必要があります。
馬に「跨る」ことができないと安定して乗れないからです。
この馬に跨るために必要な体型や体格など身体的な条件はあるのでしょうか?
体格は問題ない?
結論から言えば、体格はあまり問題ありません。
3歳くらいの小さな子供でも馬具を調整すれば、馬に乗って引き馬を経験できます。
勘の良い子なら単独で馬に乗り、馬をコントロールできるので、身体が小さいことは乗馬の障害にはならないと言えるでしょう。
馬の乗り手の最高峰である競馬のジョッキーでさえも体重の関係で身体が小さい方が有利だと考えられてますしね。
身体機能の問題は?
さて、身体の大きさはクリアできたとしても、四肢に欠損や機能障害、あるいは麻痺があれば、難しい面があります。
鐙を踏むことができなかったり、手綱のコントロールが難しいかもしれないからです。
このような場合には、乗馬は難しいだろうと思うのですが、全く不可能ということではないようです。
脊髄損傷を受けて車椅子生活をしているような方でも、鞍を改良したり馬装を調整することで馬に乗る事は可能になるようです。努力すれば身体に障がいを抱えている方でも乗馬は可能だと言えます。
ある映画のワンシーンですが、事故の為に脊椎損傷を負い下半身不随となり車椅子生活になってしまった主人公が、再び乗馬に挑戦する物語の映画を見たことがあります。この映画では、主人公は他人のチカラを借りずに自力で馬に跨っていました。
どのようにして馬に跨るのでしょうか?
車椅子生活のライダーは馬乗り場の電動ウインチとハーネスを使って、自力で馬の上に身体を引き上げて鞍の上に乗ったのでした。
ドラマ上の演出だったのかもしれないけど、きっと実例があるのだろうと思いました。
そうなると、(上達できるかどうかを考えずに)乗馬を体験することだけを目標にするならば、体型体格、更に言えば体力・機能さえも問題にならないのかもしれないですね。
身体の機能制限さえ乗馬の障害にはならないかもしれない、と述べたが実際の乗馬ではやはりいろいろと制限は存在します。
まずは体重の問題です。馬にとって、乗り手は荷物であり重りなのです。自動車にも安全を守るために乗員定数や荷重制限がありますね。体重400キロ近い馬でも、背中に乗せられる重量には限度があり、それが人間の場合、体重80キロ程度であれば問題ないそうです。しかし、それを超えるようだと、どの馬でも大丈夫とはいかないんです。乗り手の体重に見合う体格の馬でないと耐えられなくなるので。
次は身長の問題です。高い踏み台を用意すれば、背の低い人が背の高い馬にのることも可能になります。しかし、馬に乗る時には腿を開いて(股関節を横に開いて)「馬に跨る」姿勢ができないと非常に困るんです。
鞍に座るためには、鞍にまたがる必要があります。左足を鎧に掛けた状態で馬の後方へ右足を回し、(回し蹴りみたいに)馬の右側へ持っていく必要があるんです。したがってある程度の開脚ができる程度には柔軟性は必須になります。
(英国の貴族女性の鞍に跨らずに横坐りの様な姿勢で乗る乗馬スタイルは存在しますが、例外的な乗馬スタイルですね)
身長と体重がわかれば、乗馬クラブ側は適切な馬を用意することができます。(あるいは身体的な制限でお断りされる場合もある)
体重などの問題で不安があれば、事前にクラブ側へ相談することをお勧めします。
柔軟性がないくて難渋した男の話
以下は、人伝に聞いた話だから真偽を確かめることはできないのですが、股関節の可動性がいかに大切かという話をします。(聞いた話を勝手に脚色したので、フィクションだと思って欲しいです)
🏇🏇🏇
高齢になって初めて乗馬にトライしようとした男性がいた。
知人である女性に勧められ、カッコいい自分を見せたいと思い(男は何歳になっても「ええかっこしい」なのだ)体験乗馬に参加したのだった。
当日、乗馬クラブでいろいろと注意点や説明を受けて、事前の準備は完了。
いざ実践!
の段階で事件が起きた。
事件について説明する前に、乗り手が馬の鞍に跨るときの一連の動作を思い出して欲しい。馬に跨るのは、ママチャリではないロードレーサータイプの自転車に跨る時と同じ動作だ。自転車ではペダルだが、乗馬では鎧に足を乗せ、乗せたのと反対の足をサドルよりも高く持ち上げて座る。乗馬でも似たような動作になる。
実際の乗馬では、踏み台などに乗って、馬の左側から左足を鎧に入れてしっかりと踏み、鎧の上に片足で立つ。(西部劇では、台を使わないが、あれはアメリカ人が足が長く、馬種もクォーターホースで背が低いからできる)
つぎに立て髪や鞍を掴みながら、右脚を鞍よりも高く持ち上げて鞍の上を超えて馬の右側まで足を持っていく。この時、上体を馬の背に沿うように前に倒しながら右足を引き上げると足が上がりやすい。
右脚が鞍を超えたタイミングで、上半身を起こしながら、右足を馬の右側へ下ろしていく。
右足をゆっくり降ろして鞍に座る。
これで、馬に跨った姿勢になる。
あとは、右足を右の鎧にかけて、乗馬の姿勢が、完成する。
筆者の表現が下手で、文章では分かりにくいかも知れないが、要はママチャリでない自転車に乗るのと同じである。
件の高齢男性は、股関節の可動性に問題があり(病的ではなかったが、高齢化に伴い体がかなり硬かった)最初のトライで右足が鞍の上まで上がらなかったのでやり直しになった。
上体をタイミングよく前傾できていなかったのもいけなかったかも知れないが、
更に勢いをつけて二度目のチャレンジ。
右足を思い切り振り上げるが、鞍に届かず戻した。
ここで補助者が左の鎧長を短く調整してあげれたら良かったのだが、タイミングを失した。鎧のベルトはかなり短くできるので、かなり背の低い(あるいは短足の)人でも使えるようになっている。
高齢男性はチャレンジャーだった!
鎧の調整をせずに、自力で鞍の上に乗るべく、よっこらしょ、よっこらしょと同じ動作を繰り返した。
しかし、足は高く上がるどころか、むしろだんだん上がらなくなってくる。💦
男性の顔色は、アドレナリンの作用と屈辱感から真っ赤になった。
何度目かのトライアルの後、彼は無言で右足を台の上に戻して台の上に立ち、左足もゆっくりと鎧から抜いた。
そしてゆっくりと踏み台から降りると、静かにその場を離れ、クラブハウスの中に消えて行った。
その後、その乗馬クラブで彼を見かけた者は居なかったそうだ。
(誤解のないように言うと、この男性は筆者ではございません)
この話を聞いた感想
①準備運動で股関節を開き、十分開脚してから臨んでいれば結果は違ったかも。
②1度目のトライでダメだった時に、左の鎧長を短く調整したら、なんとかなったかも。
③右足を上げる際にタイミングを合わせて、上体を馬の背に沿って水平に寝かすことができれば、脚の開きが小さくても右足があげられたかも。
④男性がプライドを捨てて右足をあげる際に補助してもらっていれば、何とかなったかも?
いずれにしても、「乗馬を始めるにあたっては、身体の柔軟性があったほうが有利だし、難渋しないで済むかも」と言う話。
小生はたまたま股関節の柔軟性があり、お相撲さんの股割りができるし、年齢の割には開脚もできるほうだと思っている。
乗馬を始めてからも、特別な運動はしていないが、日常的に股関節の可動性を高める(というより低下させない)体操はしているし、乗馬前にもこの準備運動をするようにしている。
大切なのは、情熱?
この話が教えてくれたことは、身体柔軟性の大切さだけでなく、もう一つある。
馬に乗ろう、乗馬をしようと思う情熱の大切さである。
件の男性も「何がなんでも乗ってやる!」という気持ちがあったら、きっとその日に馬に跨ることができたのではなかっただろうか。
自分の事を振り返ってみても、ウエスタンのレッスンでインストラクターから指示された通りに出来なかった日には『自分には才能がなったのかな』と思って落ち込んだものだった。
しかし、いつかインストラクターのようにカッコよく乗りたい!
もっと馬の事を理解して、スムーズに乗りたい!
どんな馬でも気持ちを通じることができたらいいな!
人馬一体という境地を経験してみたいな!
そのような情熱が維持できたから、諦めずに辞めずに乗馬を続けてこれたのだと思う。
乗馬を始めて、継続しつづけるために一番必要な要素は、実は「乗馬や馬が好きだから!」という情熱なのかもしれない。
おしまい
🏇🏇🏇
いつもにんじん🥕(スキ❤️)を頂戴いたしまして、感謝です!
フォローして下さる方も徐々に増えていて、
やる気全開です。
これからもよろしくお願い申し上げます。
いいなと思ったら応援しよう!