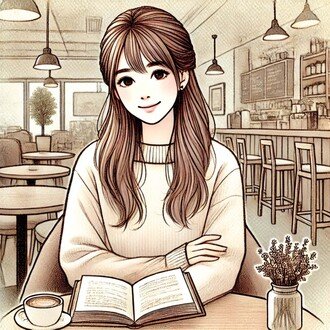「子どもが主体」が大切なワケ【モンテッソーリ教育】
本日もモンテッソーリ教育は
どんな教育なのか、
特徴についてまとめてみたいと思います。
前回
自立 → 自分のことが自分でできる
自律 → 自分をコントロールできる
これに向かって子どもは発達していく、
そして大人はそれを助けていくのが目標。
とお伝えしました。
今回は、
モンテッソーリ教育の
もうひとつの特徴をお話したいと思います。
もうひとつの特徴は
「子どもが主体」ということです。
では現在の教育は、
というと一斉教育が主流です。
保育園や幼稚園では
一斉に集団の中で教育を行うのが
スタンダードですよね。
でも
「子どもが主体」と
「一斉教育」って
まったく違うんです。
では、一般的な一斉教育(保育園、幼稚園)
は、誰が主体か、、、
というと先生ですよね。
保育園、幼稚園で一番目立っているのは先生です。
・ 先生の話を聞く。
・ 先生の用意した活動をする。
先生は子どもの発達段階に
よって行事、学期の案、月の案、週の案、
その日の案を作り込んで
実践してくださっています。
今日は何をするのか、
行事や発達段階によって
今は何をやらなければならないのか。
母の日が近いなら母の日の制作。
運動会が近づいてきたら、
毎日何をやっていくのか、
何をやらなければならないのか。
そうして毎日の保育はすすんでいきます。
それではその時、
子どもの気持ちはどうでしょう。
カリキュラム通りに進めていくことが
前提のため、子どもがやりたいかどうかは
後付けになってしまうんです。
「はい、今日はこれをします」
と、用意されているものを、
言われるままに行う。
やり方を聞いて、その通りに行う。
ある程度の幅はあれど、
同じ行動をし、同じものを
同じ時間内に作っていくのが
一斉教育です。
その活動がやりたくなくても、
子どもに選択肢はありません。
「今はそうゆう気分じゃありません」
「興味ありません」
とは言えないですよね。
「やらなければならない」が
ここで発生します。
この教育は誰が主体なんでしょうか?
主体が大人になってしまっていませんか。
子どもが大人に合わせている、
という現実がここにあります。
ある程度用意された枠組みの中に
子どもがはまっていくのが
一般的な教育となっています。
それでは、
モンテッソーリ教育は、というと、
子どもが主体になります。
現在スタンダードな一斉教育と
大きく違うのが次の点です
・ 子どもが自分のやりたいを叶えられる
・ 自分のやりたいものを自ら選んでいく
・ 自己選択の自由が保障されている
・ 時間にしばられない
モンテッソーリ教育には
ひとつひとつの能力を高めるために、
教具というものがあります。
でも、それを使うとしても、
子どもが「やりたい!」と
思ってるということが前提になります。
もしこれが、
「あなたにはそろそろこれが必要だから
これをやってね」 とか、
もう飽きているのに
「最後まで集中してやりなさい」
だったら、
もうそれは、やらせているということ。
その瞬間、
子どもが主体ではなくなってしまいます。
モンテッソーリ教育で
大切にされているものでは、
なくなってしまうんですね。
・ 子供が自分のやりたいを叶えられる。
・ やりたいと思ったものを子どもが自ら選んでいく
・ 自己選択の自由が保障されている
・ 時間に縛られない
これがモンテッソーリ教育なんですね。
「今日はこれをやりましょう」
とも決められてない。
時間も決められていない。
「はい片付け〜」と時間で切られない。
満足するまでできる自由に活動ができる。
これってとても素敵なことだと思いませんか。
内側から湧く
「やりたい!」「興味がある!」
というパワー。
それを内発的動機と言います。
この内から湧き上がる欲求、
意欲は0〜6歳の時期には特に大切です。
「これをやりなさい」
「絶対やった方がいい」は、
子どもの体と心が不一致を起こします。
体はイヤイヤ動かしたとしても、
心はそこにないんです。
大人でも、行きたくない仕事に行かされると、
心と体のバランス崩れますよね。
ギリギリまで行かないようにしたり、
足取りが重かったり。
心が伴わないと、
子どもバランスを崩します。
0〜6歳は人間としての精神を育んでいる
大切な時期です。
だからこそ「やりたい」という
内発的動機で、
物事に取り組むのが本当に大切なんですね。
だから、モンテッソーリ教育では、
一斉に何かをやらせたり、
大人の用意したものに、
子どもを当てはめたりしません。
子どもがやりたいと思ったものに
大人が合わせる、スタイルなんです。
内発的動機が大切だからこそ、
そういう方法を実践しているんですね。
子育ては子どもが中心。
子どもがあっての大人の関わり、環境です。
3歳だからこれ、5
歳だからこれをやるべき、とか、
行事があるからこれをしないといけない、
という環境の中に
子どもが当てはまっていく。
それでは子どもが
後付けになってしまいます。
それでは子どもの意欲は何処へやら、、、?
誰のためのなんの教育?
この環境は誰のためのものなのか。
子どもの発達に、
子どもの心の栄養に
どんなプラスがあるのかを考えると、
疑問が湧きます。
教師でも親でも、
当たり前になっていると環境とは怖いもので、
毎日やっていることとなると、
何感じなくなってきてしまいます。
一度立ち止まって、
これって本当にやらねばならぬことなのか?
毎年行われているこの行事、
目の前のすべての子ども達の発達に、
心の栄養にプラスになっているのかな?
と考えてみたいですね。
そう考えると、モンテッソーリ教育は
現在のスタンダードな一斉教育からは
だいぶかけ離れています。
なので、それを見直したり、
周りと違うことをするのは
とても勇気がいることだと思います。
大多数と外れるということですからね。
でも、大多数だからいいものだとは
必ずしも限らない。
立ち止まって考えて見直すことが
大切だなと思いました。
モンテッソーリ教育とは
自立 → 自分のことが自分でできる
自律 → 自分のことをコントロールできる
・ 子どもはここに向かって発達している
・ 子育てとはこの発達を助けていくこと
・ 子どもが自分のやりたいを叶えられる
・ 自分のやりたいものを自ら選んでいく
・ 自己選択の自由が保障されている
・ 時間にしばられない
これらを大切に
これからもモンテッソーリ教育を
いっしょに学んでいきましょう!
この記事は
モンテッソーリ教師あきえさんの
Voicyを参考につくっています。
【関連記事】
いいなと思ったら応援しよう!