
【掌編小説】鳴き声のする風景
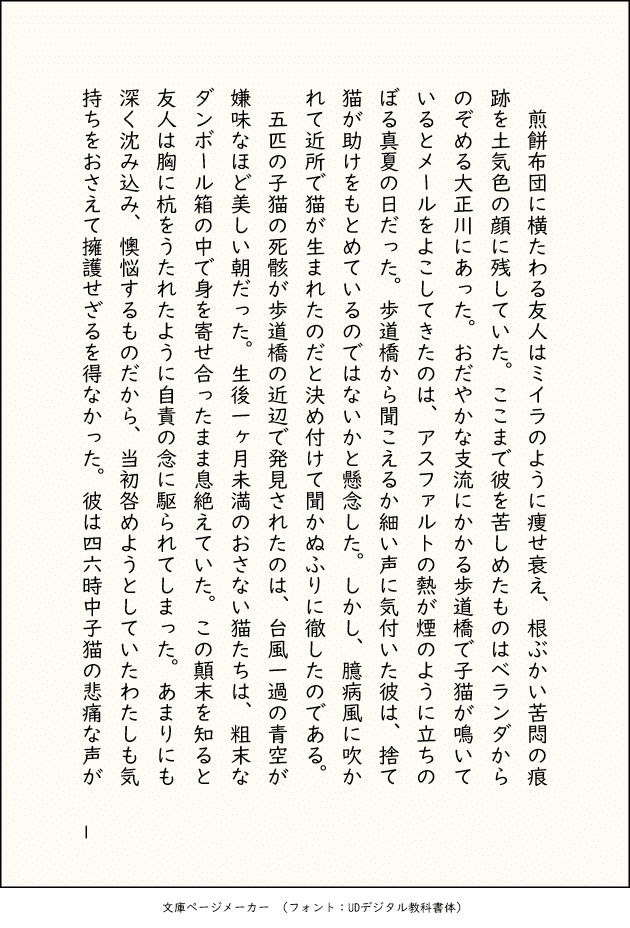

煎餅布団に横たわる友人はミイラのように痩せ衰え、根ぶかい苦悶の痕跡を土気色の顔に残していた。ここまで彼を苦しめたものはベランダからのぞめる大正川にあった。おだやかな支流にかかる歩道橋で子猫が鳴いているとメールをよこしてきたのは、アスファルトの熱が煙のように立ちのぼる真夏の日だった。歩道橋から聞こえるか細い声に気付いた彼は、捨て猫が助けをもとめているのではないかと懸念した。しかし、臆病風に吹かれて近所で猫が生まれたのだと決め付けて聞かぬふりに徹したのである。
五匹の子猫の死骸が歩道橋の近辺で発見されたのは、台風一過の青空が嫌味なほど美しい朝だった。生後一ヶ月未満のおさない猫たちは、粗末なダンボール箱の中で身を寄せ合ったまま息絶えていた。この顛末を知ると友人は胸に杭をうたれたように自責の念に駆られてしまった。あまりにも深く沈み込み、懊悩するものだから、当初咎めようとしていたわたしも気持ちをおさえて擁護せざるを得なかった。彼は四六時中子猫の悲痛な声が耳の奥に響くから仕事にならないとしきりに嘆いた。そうして悶え続ける内、ついに彼は執拗な幻聴に悩まされはじめた。
友人の日常が崩壊するまで大して時間を要さなかった。わたしにできることは、なにもかもわすれて心の養生につとめようという月並みな助言をあたえるくらいしかなかった。
晩秋の頃に友人は入院することになった。父親の運転する軽自動車に乗せられる姿に生気はなく、痛々しさを感じさせた。住み慣れた共同住宅を後にし、街角に消えていく車を見送ると秋風がいやに身に染みた。わたしは適当に時間をつぶしてから駅を目指して川沿いに歩きだした。歩道橋をとおりすぎるところでふと子猫の鳴き声を耳にする。ふりかえると茜色に染まる舗道には動物どころか人影もなく、あるものは夕景を撫でる川のせせらぎと風の残響だけであった。
※2016年脱稿・2017年改稿
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。
