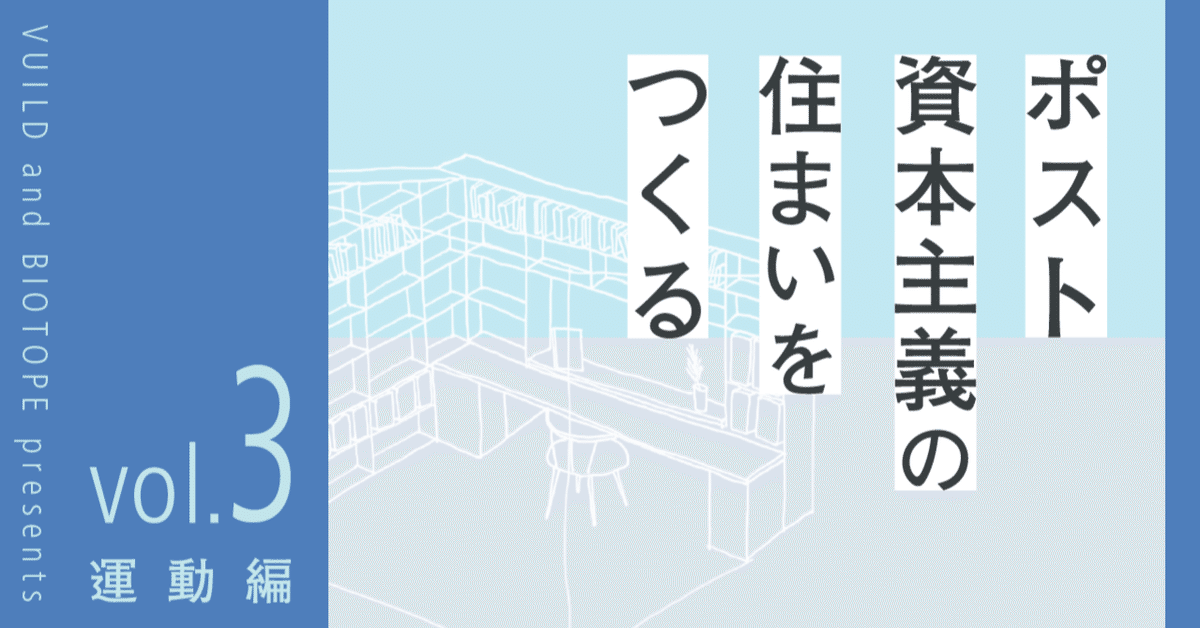
パンデミックの内省から始まった住まいの運動体
この連載は、「ポスト資本主義の住まいをつくる」と題し、BIOTOPE佐宗邦威とVUILD秋吉浩気がオブニバス連載の形で全6回で綴り、問いかけていくものです。
各回の内容は、以下の通りです。
第1回:内省編(佐宗)、第2回:経済編(佐宗)、第3回:運動編(秋吉)、第4回:実践編(秋吉)、第5回:教育編(佐宗)、第6回:提案編(秋吉)
今回はその3回目「運動編」。VUILD秋吉浩気が執筆します。
1. 無責任な展望より、希望的な実践を
コロナ以降、都市や建築の在り方はどうなるか。誰もが興味をもつこのような問いに対し、具体的行動を伴わない展望を述べたり、どうせ社会は変わらないと冷めた姿勢を貫くことは誰にでもできる。
だがもっとも重要なのは、どうなるかではなく「どうしたいか」、変わらないではなく「どう変えたいのか」を、先ず自分に問うことではないだろうか。無責任な展望を投げる口だけの人ではなく、こうしたいという希望を提示し、その実践を口火に社会変革を行ってきた先人達にこそ学ぶべきだ。
2. モダンデザインの祖モリスと、近代都市計画の祖ハワード
このような観点で僕が真っ先に頭に思い浮かべたのが、アーツ・アンド・クラフツ運動を巻き起こしたモダンデザインの祖ウィリアム・モリス(1834-1896)と、田園都市運動を巻き起こした近代都市計画の祖エベネザー・ハワード(1850-1928)だ。
モリスやハワードが生きたヴィクトリア時代(1837-1901年)の社会背景は、現代の状況と幾つかの共通点がある。彼らの具体的な活動内容は後述するとして、まずは当時の時代背景をみていこう。
3. 19世紀ロンドンとコレラ
第一回万国博覧会が開催された1851年頃のロンドンは、工場・鉄道・汽船などの第一次産業革命の波が押し寄せていた時期で、それに付随して①グローバルな貿易と②都市への人口集中が進行していた。
そんな折、1854年にロンドン中心部で大流行した感染症がコレラだ。スティーブン・ジョンソンの『感染地図 歴史を変えた未知の病原体』によると、当時のロンドンは下水道などの公衆衛生の都市インフラが十分に整備されていない不潔な都市環境であり、それに加えて、労働環境を求めて農村から流入した人口によって街が過密になっていた。*1
そこにアジアから伝播した飲料水媒介型の疫病であるコレラが蔓延し、1万5千人近くのロンドン市民が死んだという。つまり、先述した①グローバルな貿易網と②人口過密がコレラ禍を引き起こしたと、スティーブン・ジョンソンは指摘する
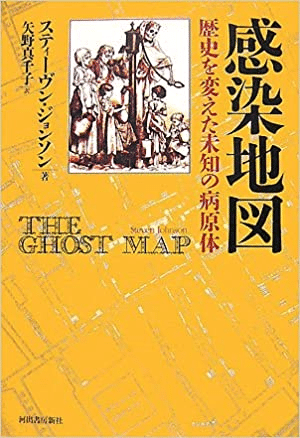
スティーブン・ジョンソン『感染地図 歴史を変えた未知の病原体』
きっと、当時のロンドン市民は、コロナ時代を生きる僕たちのように過密都市の限界を悟る大きな契機となったことだろう。我慢してまで都市の歯車として生きる必要はあるのか、あるいは、そもそも都市に依存せずに生きるにはどうしたらいいのか、と。
このようなパンデミックが与えた内省を契機に、都市一極集中化やその元凶である機械化の反動として生まれた動きが、アーツ・アンド・クラフツ運動と田園都市運動であると、僕は考えている。
4. 反分業化-理想の生活は自分たちでつくることができる
モリスらが巻き起こしたアーツ・アンド・クラフツ運動は、中世の手仕事を再評価し、分業化せず質の高いものを生み出すことで、生活に芸術性を獲得しようとしたものだ。
美術史家のニコラス・ペヴスナーによると、ルネサンス以降の芸術家は一部の金持ちに対して作品を制作する「高僧」だった。これに対しモリスは「民衆によって民衆のために作られるもの」こそが芸術であるとして、芸術(非日常の美しいもの)と工芸(日常を取り巻くもの)との一体化を図ったという。*2
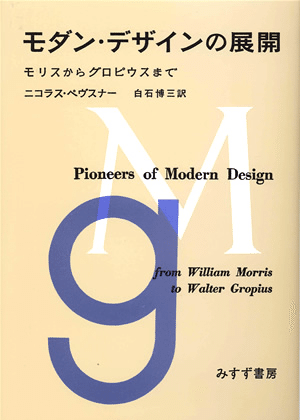
ニコラス ペヴスナー『モダン・デザインの展開―モリスからグロピウスまで』
これは、建築家が一部の金持ちのために建築作品を設計する存在として矮小化して理解されている状況によく似ており、「民衆によって民衆のために作られる建築の実現」こそが建築家が担うべき役割ではないかという洞察を与えてくれる。
そしてその実現のためのヒントは、工場労働的な分業を解体し、頭で考えたものごとを自らの手で実現するための全体性を獲得することであると。
5. 反都市化-理想の都市は自分たちでつくることができる
一方、ハワードの描いた田園都市は、田舎と都市それぞれの良い点を混ぜ合わせた職住近接型の都市を郊外に建設するというものであった。そこには、高賃金の仕事と低家賃の住居がありつつも、美しい自然と楽しい娯楽に囲まれるといった理想郷が提示されている。
ハワードの著書『新訳 明日の田園都市』訳者の山形浩生氏が指摘するように、ここで注意すべきは、ハワードが提示したものが単なる物理的な都市のデザインではなく、その背景にある経済システムや社会システムだということである。*3
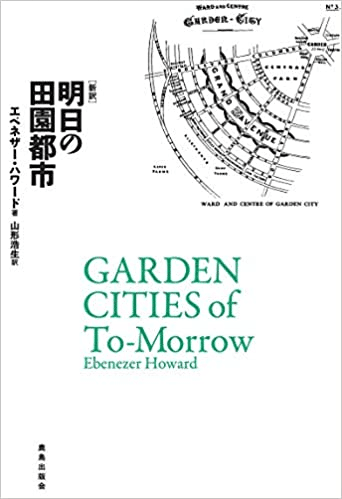
エベネザー・ハワード『新訳 明日の田園都市』
具体的には、田園都市が公社によって形作られている点が挙げられる。ハワードは、住人が都市の株式を持って自ら運営するという方式で、田園都市構想の実現方法まで提示している。したがって、戦後日本の郊外に誕生したニュータウンとは似て非なるものであり、都市に従属する労働者のためのベットタウンではなく、自治を目的とする完結した都市像だったのだ。
本書を読むとわかる通り、本書はほぼ投資家向けの事業計画書の体裁をとっている。このビジョンを元に資金調達を行い、1903年にロンドン北部のレッチワースに実際に田園都市を作ってしまった。つまり、マニフェストを掲げるだけでなく、自らの手で実践を行ったのである。
6. 20世紀モダニズムと結核
さて、これまで19世紀の状況について言及してきたが、20世紀における感染症と建築都市との関係性はどうだったのだろうか。建築史家のビアトリス・コロミーナは、20世紀のモダニズム建築と結核との関係を指摘している。1882年のロベルト・コッホによる結核菌の発見以降、1943年に抗生物質であるストレプトマイシンが発見されるまでの間、20世紀初頭の建築は結核にまつわる当時の迷信に基づいて、健康をテーマに発展を遂げてきたという。
20世紀を代表する建築家ル・コルビュジエ(1887-1965)の「近代建築五原則」でも、当時結核の原因とされていた「湿った台地」から建物を切り離すためにピロティによって建築を持ち上げたり、日光浴や新鮮な空気が結核対策に有効であるという説を元に大きな窓やテラスを設けたりする方法が示されているが、コロミーナはこれを、結核時代の建築理論だと指摘する。
つまり、コルビジェの「近代建築五原則」に代表される20世紀モダニズム建築は、彼の「住宅は住むための機械である」という言葉から連想されるような機能的な機械の美学の追求から生まれたのではなく、病院や療養所から生まれたのだ。このような病院の美学によって、モリスらが追及した「ざらざら」とした装飾は、掃除や消毒のしやすさから、金属やガラスによる「つるつる」とした表面にとって代わられたのである。

ビアトリス・コロミーナ『我々は 人間 なのか? - デザインと人間をめぐる考古学的覚書き』
7.人間の自律性と都市の自律性
話を19世紀コレラの時代に戻そう。20世紀のモダニズムの都市や建築がパンデミックから直接的な影響を受けたように、コレラ禍においてもジョルジュ・オスマンのパリ改造(1853-1870年)やフレデリック・ロー・オルムステッドによるニューヨークのセントラル・パーク(1873年)など、公衆衛生上の観点から直接的な都市のアップデートが試みられてきた。
今回のコロナ禍においても、あらゆる疫学・医学的観点から都市計画家や建築家の手によって都市はアップデートされるだろうし、既存の大都市が消滅することはないだろう。しかしながら、経済成長が頭打ちになり、かつ人口減少が進むこれからのポスト資本主義の社会において、都市の必然性や都市の在り方を考え直す必要があるのではないだろうか。
都市計画家の饗庭伸によると、都市とは「暮らしや仕事を成り立たせるための手段の集合であり、それを調達する空間である」という。*5

南條史生 他『人は明日どう生きるのか ――未来像の更新』
裏を返せば、生活を豊かにする手段を自らの手で生産できるようになれば、大資本でなくとも誰もが自分の理想都市をつくることができるということだ。そうなれば、既存の過密空間から解放され、どこにいても自由に暮らし、働くことができるかもしれない。モリスとハワードは、そんな「人間の自律性」と「都市の自律性」の意義を問うことによって、中央集約型の社会から分散型社会に転換するための補助線を引いてくれているのだ。
次回の第4回では僕らの実践を通して、住まいにどのような変化をおこしたいのかを紹介したいと思う。
*1 スティーブン・ジョンソン『感染地図 歴史を変えた未知の病原体』
*2 ニコラス ペヴスナー『モダン・デザインの展開―モリスからグロピウスまで』
*3 エベネザー・ハワード『新訳 明日の田園都市』
*4 ビアトリス・コロミーナ『我々は 人間 なのか? - デザインと人間をめぐる考古学的覚書き』
*5 南條史生 他『人は明日どう生きるのか ――未来像の更新』
