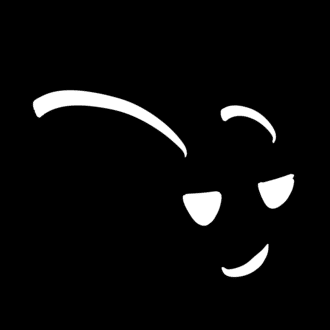『なぜ』そうするのかを考える
結果だけを見聞きして、そのままそれを鵜呑みにする人って結構いるんじゃないかなと思っている。
「プロがそうしているから、言っていたからそうする」というのを見かけたけど、「プロがやっている」という結果よりも「なぜプロがそれをやっているのか」という過程を見たり、考えることが重要だと思う。
そうしないと「あのプロとあのプロは違うことを言っている、どちらが正しいんだ」と思ったりもする。ほんとうはどちらも「正しい」ことが多い。
もっと言うと「正しいor間違っている」ではなくて、「何を選択したかどうか」なのだ。
例えば、プロの中でもピッチ修正をする人としない人、する場面としない場面がある。
僕自身も、歌そのものを気持ちよく聴かせたい、とか、スピード感を出したいとか、声が耳につかないようにバックグラウンドに馴染ませたい、そういう場合にはピッチはきっちり直す。
CMで街の人が歌っていたりとか、リズムをダラっとさせたい、とか、歌そのものじゃなくて、楽しい雰囲気などを伝えたいときとかはピッチをいじらないことがある。
過程で結果が違ってくるし、なぜそうするのか、という動機がハッキリしている。
「あのプロはピッチを直さないと言ったから直さないようにする」のように表面だけをとらえると、何が正しいんだ、となる。
「作曲がうまくなるには何百曲作れ」みたいなやつも同じ。
音楽家へのインタビューも、使用機材や制作手法を語る音楽雑誌のインタビューよりも、想いを語る、ファン向けの一般紙のインタビューのほうがヒントが多いと思っている。
どういう考え方をしてそのアウトプットになっているのか。それを読み解くと、逆に自分が作品を作るときにも生きてくる。
あと、インタビューをされる機会があったときに「他の人がそうやっているから」って答えたらかっこわるいじゃん。
なぜそうしたのか、というのを掘り下げておくと人に聞かれた時にもカッコがつく。
例えみんながやっていることであっても、自分の中で咀嚼して、なぜそれをやっているのかを自分の考えとして説明できる、ということは必要。
このツイート、近い感じがする。
勉強がわりとできる子の反応
— 篠田くらげ (@samayoikurage) July 18, 2019
生徒「これがわかりません」
私「んー?最初は何をする?」
生徒「分配法則でカッコを外します」
私「いいんじゃない?それから?」
生徒「そうするとこうなりますよね。でもここで行き詰って」
私「これ、因数分解できるんじゃない?」
生徒「あっ、本当ですね」
勉強が苦手な子の反応
— 篠田くらげ (@samayoikurage) July 18, 2019
生徒「これがわかりません」
私「最初に何をするの?」
生徒「3」
私「何をしたのか日本語で説明することはできる?」
生徒「普通に計算して……」
私「普通って何?」
生徒「3じゃないんですか」
私「ちがうな」
生徒「あっ、5ですか?」
私「まず最初にすることは?」
我々はフォン・ノイマンではないのですから、言語化せずに結論をぱっと出すことは不可能です。でも勉強が苦手な子は思考過程を言語化することができない。結論だけを言おうとするんです。
— 篠田くらげ (@samayoikurage) July 18, 2019
いいなと思ったら応援しよう!