
第2回 古本屋の時間
ちょっと変わった本を手にしています。『野呂邦暢 古本屋写真集』(岡崎武志&古本屋ツアー・イン・ジャパン編、ちくま文庫)——。

まさか、この本までが文庫になるとは! 親本は万の値のつく古書になっていましたので、勇んで買いに走りました。シブいけれども、おもしろい!
野呂邦暢(くにのぶ)さんは、1980年に42歳の若さで急逝した作家です。いまだに、熱烈なファンが少なくありません。
1973年下半期に、自らの自衛隊体験をふまえた「草のつるぎ」で芥川賞を受賞。36歳でした。同時受賞が「月山」の森敦さんで、2013年に黒田夏子さんが73歳で芥川賞を受けるまで、ながらく最高齢受賞記録となった62歳の“新人”でした。

授賞式の写真をいま見ると、リラックスしてにこやかにスピーチしている「貫禄十分」の森さんに対し、野呂さんは明らかに緊張した面持ちで、堅苦しい(?)挨拶をしている様子です。
1937年、長崎市に生まれ、終戦の年の春、父の応召にともない、一家は母方の実家のある諫早市へ疎開。そこで長崎への原爆投下の強烈な閃光を目撃します。地元、諫早高校を卒業後は、人生の荒波に揉まれます。
<高校を出た年、父が経営していた事業に失敗した。父は破産宣告をうけると同時に大病にかかって入院した。わたしは次男で弟妹が四人いた。上の妹はまだ中学生であった。わたしは働かなければならなかった。上京して仕事を探した。日がな毎日、新聞の求人欄をひろげては、これはと思う所に足を運んだ。しかし、自動車の運転も出来ず、熔接や塗装という特別な技能も持たない田舎者にロクな仕事はなかった。東京には身元保証人になってくれる知人もいなかった。>

台東区にあるガソリンスタンドなどの職につきますが、1年足らずで諫早に帰郷。「なべ底景気」といわれる不況のさなかで職はなく、佐世保の陸上自衛隊に入隊します。この時の体験が、後の芥川賞受賞作「草のつるぎ」に結実します。
自衛隊を1年で辞め、ふたたび諫早に戻った野呂さんは、家庭教師の仕事などで糊口(ここう)をしのぎながら、いよいよ作家の道をめざします。諫早の地に定住し、終生離れることはありませんでした。
「ものを書いて暮らしをたてるには東京がいいに決まっている」。けれども「小説という厄介なしろものはその土地に数年間、根をおろして、土地の精霊のごときものと合体し、その加護によって生み出される」と考えたからです(「鳥・干潟・河口」、前掲書所収)。
といって野呂さんは、いわゆる郷土作家とも違います。詩情ゆたかで端正な文体を持ち、諫早の“土地の精霊”に愛でられながら、これからどのような作品に挑んでゆくのか、それが楽しみな書き手でした。あまりに早い死が惜しまれてならない所以(ゆえん)です。
さて、その野呂さんの『古本屋写真集』です。もとよりプロの写真家ではなく、腕はお世辞にも、よろしくない! ピンぼけあり、ブレありで、はっきり言って素人くさい写真です。いまふうにスマホでパシャパシャなんでも気軽に撮れる時代とはちがい、遠慮がちにカメラを構え、隠し撮りのように慌ててシャッターを切る様子が偲ばれます。
発表する気もさらさらなく、個人的なひそやかな愉しみとして撮り続けていた古本屋写真。1970年代後半に撮影した東京・神保町のカットが29枚、早稲田が14枚、渋谷6枚、池袋2枚、荻窪1枚、そして広島が3枚という内訳です。
これらの写真が第1部を構成し、第2部が古本屋をめぐる野呂さんのエッセイ9篇。第3部が本書の成り立ちを語る編者ふたり(書評家の岡崎武志さんと古本屋ツアー・イン・ジャパンの小山力也さん)の対談です。
<岡崎 <古本好き><古本屋好き>というのはいるけど、<古本屋の写真を撮る>というのはなかなかいないよね。ぼくと小山君くらいしかいないんじゃないの(笑)。
小山 今はデジタルですけど、当時はフイルムカメラですからね。
岡崎 お兄さんが遺品を整理していて、出てきたこれらを、ぼくが諫早に行ったことをきっかけにいただいてしまった。>
保存状態も芳(かんば)しくなく、カラーの褪色も進んでいましたが、「発見されたときの驚き」をそのままに、デジタル補正をしないまま、2015年の春、盛林堂書房から『野呂邦暢 古本屋写真集』が刊行されます。刷部数500部、定価2500円。発売するや、ほぼ即完売。あっという間に古書価がついて、万の単位で販売されるようになりました。それが今回、再編集・増補を加え、めでたく文庫化されました。
人によって、楽しみ方はさまざまだと思います。4、50年前の古本屋を知る人には、たまらない懐かしさがあるはずです。神保町の田村書店、一誠堂書店、八木書店・・・店頭の光景はほとんど変わっていないものの、そこはかとない時代の変遷が感じられます。
野呂邦暢は、ほんとうに古本屋めぐりが好きでした。
<古本あさりは趣味といえるだろうか。
読み書きを業としている者が、趣味は古本屋がよいです、というのは気がひける。
漁師にとって釣りが趣味でないのは自明の理である。しかし、私の場合、仕事以外のことでくつろぐことが出来るのは古本屋の棚を眺めることしかない。>
岡崎、小山両氏が推測しています。野呂さんは上京した際に必ず古本屋に立ち寄って、写真を撮っては諫早の家に持ち帰り、時々取り出しては、「また行きたいな」と思って眺めていたのではないか――。
店の前にいる人物を意識的に撮っているのも印象的です。本棚を眺めたり、店頭の「均一本」台を物色する人たち。女子学生の姿が多いところも、野呂さんの“物語”を感じさせます。
昨年文庫化され版を重ねている『愛についてのデッサン――野呂邦暢作品集』(ちくま文庫)の表題作「愛についてのデッサン」は、まさに古本屋を舞台に、25歳の2代目店主を主人公にした6篇からなる連作長編です。タイトルからも明らかなように、男女の恋愛がテーマですが、古本屋稼業に寄せる若い店主の情熱に、作者の好みや思いがにじみます。
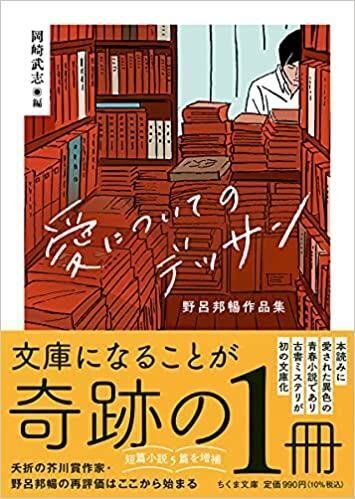
野呂さんの古本屋とのただならぬ関係を、最初に教えてくれたのは「ぼくも散歩と古本が好き」という沢木耕太郎さんのエッセイでした(『バーボン・ストリート』所収、新潮文庫)

高校を卒業して、東京に働きに出た野呂さんが、頻繁に通った東京・大森の古本屋。山王書房という店で、“幻の名著”といわれた随筆集『昔日の客』(現在、夏葉社から復刊)を遺し、59歳で逝った関口良雄さんが店主でした。「家が近かった」沢木さん自身も、しばしば出入りしました。

「見るからに頑固そうな」店主の思い出は、野呂さんが幾度かエッセイに書いています。「愛をめぐるデッサン」に登場する古書店のたたずまいには、「山王書房」の姿が重なります。
<つとめの行き帰りに立ち寄る小さな古本屋があった。S書房というそこは間口が二間あまり、奥行きもそれくらいの小さな店であった。三十歳あまりの主人とその奥さんが、かわるがわる店番をしていた。
歩いて一分とかからない近所であったから、日に一度はのぞくのがきまりだった。土間の隅には水瓶がすえてあって、季節の花が欠かさず活けてあった。日に褪せた古本と、色鮮やかな花のとりあわせが目に快く映った。ガソリンスタンドで油臭い仕事をした後で、S書房に寄り、水瓶の花や古本を見るのは私のささやかな愉しみだった。
給料は食べてゆくのがやっとだったので、私がそこで古本を買うのは月に二、三回もなかったと思う。それも三十円内外の文庫本ばかりである。>
やがて東京生活を切り上げ、九州に帰ることを決めた野呂さんは、意を決して山王書房に立ち寄ります。店頭にどうしてもほしい写真集が飾られていたからです。『ブルーデル彫刻写真集』という豪華本。懐には、わずかながらの退職金がありました。
<私は郷里に帰ることを主人に告げた。彼は黙って値段を三分の二にまけてくれた。餞別だというのである。私は固辞したけれどもいい出したらきかない相手だった。>
それから16年後のある夜、山王書房に「野呂邦暢」と名乗る人物から、突然電話がかかってきます。「野呂さんというと、今度、芥川賞を受賞された方ですね」と関口さんが応じると、「懐かしく思ったもので」と、かつての思い出が語られ始めます。

野呂さんは、芥川賞授賞式に関口夫妻を招待します。そして授賞式から2、3日後、野呂さんが店に現れます。「いつか一緒に上京するようなことがあったら、その本屋さんへ是非連れて行ってほしい」と望んだ夫人を伴って――。
かつて野呂さんが通っていた頃に、母親に抱っこされていた山王書房の娘さんは22歳になって、この日は婚礼を前に、関口夫妻が嫁入り道具を運び出しているところでした。
以下は、関口さんの文章です。
<野呂さんは、手伝いましょうと言うと、素早く上衣を脱ぎ、次々と荷物を運んで下さった。
小さい車は、すぐいっぱいになった。
なんのもてなしも出来なかったけれど、野呂さんとそれからそれへと話が続いた。
野呂さんの奥さんは、美しい静かな人だった。私達の話のやりとりを終始にこやかに聞いていられた。
話の途中で野呂さんは、何かお土産をと思ったけれど、僕は小説家になったから、僕の小説をまず関口さんに贈りたいと言って、作品集「海辺の広い庭」を下さった。
その本の見返しには、達筆な墨書きで次のように書いてあった。
「昔日の客より感謝をもって」野呂邦暢>
何度でも読み返したくなるエピソードです。実際、時々無性に恋しくなって、野呂さんの随筆を、関口さんの「昔日の客」を、沢木さんのエッセイを、どれほど繰り返し読んだことか、わかりません。
読むと、ささくれだった気分が落ち着いてきます。「水瓶に季節の花を活けた古本屋」の一隅に、自分も客として立っているような気がしてきて、いつも心がやわらぎました。
近年、野呂邦暢を再評価する気運が高まっています。「昭和、平成、令和とあわただしく世の中は更新され、スマホ依存で本離れが進み、文学の力そのものが弱められていくと感じられる中、快挙といっていい出来事である」と岡崎武志さんが力説するように(『愛についてのデッサン――野呂邦暢作品集』編者解説)、熱烈な野呂ファンの努力の賜物で、『野呂邦暢小説集成』(全9巻、文遊社)が刊行されるに至っています。

願わくは、文庫化の流れが、このままもう少し進んでくれたらと思います。向田邦子さんが絶賛し(*1)、21歳の佐藤正午さんが「一夜で読みあげ、強い感銘を受け、眠れぬまま作家に手紙を書いた」(*2)という『諫早菖蒲日記』、あるいは『鳥たちの河口』、『草のつるぎ』などが、読みやすい文庫で復刊される日が来ることを楽しみに待ちたいと思うのです。
*1、野呂邦暢の担当編集者として「現場で処女作・デビュー作・ヒット作・代表作・話題作」のすべてに接したという元文藝春秋・豊田健次氏の『それぞれの芥川賞 直木賞』(文春新書)で紹介されているエピソード。『諫早菖蒲日記』を読んで感動した向田さんは、自らの手でドラマ化したいと言い出し、テレビ局を相手に“大車輪、獅子奮迅”の交渉を繰り広げます。そして1980年5月の大型連休前、上京した野呂さんを豊田氏が向田さんに引き合わせます。会食の座は大いに盛り上がり2次会に及んだというのですが、その直後の5月7日、野呂さんは42歳の若さで急逝します。

*2、「私事——野呂邦暢『愛についてのデッサン――佐古啓介の旅』」(佐藤正午『小説家の四季』所収、岩波書店)。このエッセイがまた感動的です。野呂さんから返信をもらったという佐藤さんが、その後、郷里の佐世保に居を定め、孤塁を守りながら独自の作品世界を紡ぎ上げる、その「覚悟」を垣間見るような気もします。
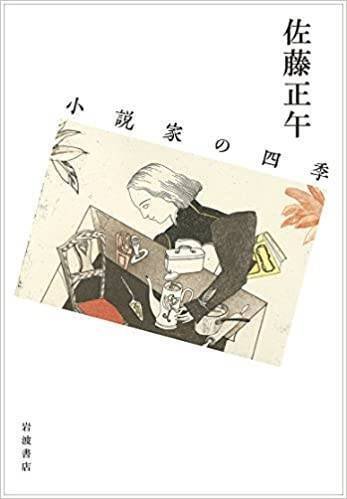
★関口良雄さんの『昔日の客』(夏葉社)については、「こんな古本屋があった」という一文を、以前に書いたことがあります(拙著『言葉はこうして生き残った』所収、ミシマ社)。夏葉社からこの本が復刊された時、どんなに嬉しかったことか。
