
第1回「男おひとりさま」朋友とともに山を下る
「人生100年時代」と、なにげなく言われるようになりました。
私が社会人になった頃、というのは1970年代の半ば過ぎ、多くの企業は55歳が定年でした。それが次第に、60歳定年制に移行します。当時の日本人の平均寿命は、女78.33歳、男72.97歳(1978年内閣府)でした。
ところが、昨夏の厚生労働省の発表によると、2020年の平均寿命は、女87.74歳、男81.64歳となり、過去最高を更新しています。いずれ100歳を超えても元気な老人が、当たり前のように、まわりに増えていくのでしょう。
とはいえ、人生のゴール地点がどんどん先へ逃げていくようで、何やら落ち着かない気分です。
そんな時に出会ったのが、『百歳以前』(徳岡孝夫・土井荘平、文春新書)という1冊です。90歳を超えた男やもめが2人、それぞれに綴った身辺雑記と思い出の記。往復書簡でも、交換日記でもありません。各自のスタイルで綴られた文章が、ほぼ交互に並んでいて、その好対照ぶりがおもしろい!
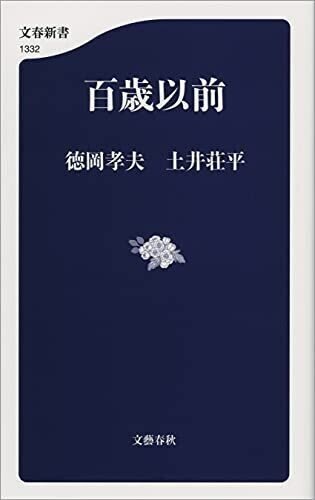
共通しているのは、二人が大阪の旧制北野中学校の同級生であること。在学当時は顔を見知っている程度の仲ですが、ときは戦争末期の非常時です。学業そっちのけで勤労動員に駆り出され、敵機の空襲に逃げまどう極限下の体験を共有します。
戦後の人生行路はまちまちですが、60代でリタイア後、著述に手を染めた土井さんが、すでに何冊もの著書、翻訳書を世に送り出していた徳岡さんに本を送ると、すぐに連絡が入ります。こうして元同級生の「老いての交友」が始まります。
以来、20数年。子どもたちは独立し、ともに愛妻に先立たれたひとり暮らし。90歳を超えた「男おひとりさま」の境遇が、二人をいっそう近づけます。
徳岡孝夫さんはジャーナリスト。毎日新聞社時代は名記者としてならし、『五衰の人——三島由紀夫私記』(新潮学芸賞受賞)、『横浜・山手の出来事』(日本推理作家協会賞受賞)などの著作、またドナルド・キーン、エドウィン・ライシャワー、アルビン・トフラー、リー・アイアコッカ、リチャード・ニクソンなどの翻訳書を手がけ、1986年には「気鋭のジャーナリストとしての文筆活動のかたわら、時代の書の翻訳紹介にすぐれた業績をあげている」として、第34回菊池寛賞を受賞します。

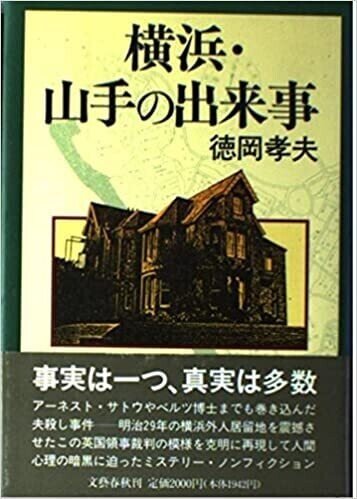
かたや土井荘平さん。商社勤務、自営業の仕事に区切りをつけ、大阪から神奈川に移住したところでエッセイや小説を書き始めます。初めての著作を徳岡さんに送ったところ、すぐ電話が来たのは、先述の通り。以後、同人誌に載ったものはすべて徳岡さんに送りますが、忙しい締切に追われているにもかかわらず、必ず感想を「一筆書いてきてくれた」というのです。
書くものが「ほとんど大阪を舞台にした大阪弁をしゃべる同世代人」の話だから、懐かしさや戦時下の共通体験が、老いての友情を深めたのではないか、と土井さんは述べます。
かくして生まれたのが『夕陽ヶ丘——昭和の残光』という共著です。一昨年の秋に刊行され、幸い好評を博します。その励ましに勢いを得て、次に取り組んだのが、今回の本です。
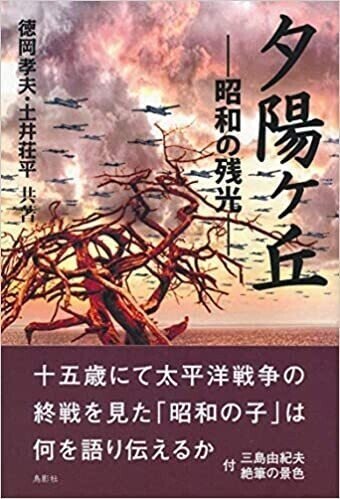
「長寿になったといっても、百歳になったらもう何をする能力もなくなる。百歳以前をどう生きるかだよ、これからの課題は。それを書こうと思う」という徳岡さんの呼びかけに応じ、土井さんは90歳を超えたいまの日常や心境を、徳岡さんは新聞記者時代のさまざまな思い出を綴ります。
執筆の背景としては、もう一つ特記すべき事情があります。数年前、徳岡さんはほぼ視力を失います。土井さんが口述筆記を担当しています。
徳岡さんは56歳の時、脳下垂体腫瘍のため右眼失明、左眼も薄明の状態になります。それでも、旺盛な執筆活動を続けていましたが、その後も眼疾は徐々に進み、いまや口述を吹き込もうにも、カセット・レコーダーの機器の操作ができません。電話のダイヤル操作も厳しいので、自分から電話をかけることはできません。
新型コロナウイルス禍と高齢のため、徳岡さんの家に出向くこともままならず、土井さんが電話をして徳岡さんの口述内容を録音し、それを文章に起こします。さらにそれを読みあげて確認してもらう、という煩瑣なやりとりを繰り返します。
<……年月日や固有名詞など、彼は記憶以外には調べることができない。そこで間違ってはいけない人名、地名、年月日などのウラを取るのも私の分担で、ネットで調べたり、年表で確認したりして彼の文章に入れている。毎日二、三回電話でやり取りしながら進めている。>
その合間を縫って、土井さんは自分のチャプターを執筆します。
「書こう!」と持ちかけたのは徳岡さんですが、これを励まし、サポートしているのは土井さんです。たいへんな労作、共同作業のたまものです。胸が熱くなりました。
「それなりの充実感」があり、「生きている目標」でもあり、「お互いのストレス解消にもなっている」といいますが、60代で再会した元同級生が、こうした関係をはぐくんでいることに、ほのぼのとした救いを感じます。

友情、という言葉は、たいていは「友情、努力、勝利」(『少年ジャンプ』の標語)のように、坂の上の雲に向かって、人生の上り坂を一緒に歩んでゆくイメージとともに語られます。90歳を超えた老人がふたり、支えあいながら山を下ってゆく友情を、こうして「本」というかたちで確認するのは、きわめて稀有な事例です。
夫婦でもなく、親子でもなく、仕事仲間でもない元同級生が、ものを書く、読むという行為でつながって、一緒に「本」を作るという目的に向かって歩を進めるプロセスに、生きることへの「熱」や「意思」をいっそう強く感じます。
著名なジャーナリストであった徳岡さんのもっとも有名なエピソードは、作家の三島由紀夫が1970年11月25日、自衛隊の市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を遂げた時、直前にすぐ近くの指定の場所で遺書を託され、すぐさま現場に駆けつけて三島由紀夫最後の演説を、自衛隊員にまじって聞いていたという事実です。
本書に綴られているのは、そうした「三島由紀夫のこと」もあれば、死と隣合せだったベトナム戦争取材時の「真の英国紳士」のエピソード、新人記者時代の「打ちのめされた」失敗談など、鮮烈な思い出を振り返りながら、「何が起こるかわからない人生をどう生きるか。後から来る人たちの参考になれば」という11編です。
土井さんのほうは、コロナ禍で外出もままならない「ひとり正月」の心中、お世話になっているヘルパーさんたちとのやりとり、不思議な夢や、物忘れ、「眼鏡が見つからない」話など、「まもなく100歳」の男の心情を、リアルに等身大で描いた、同じく11編の随想です。
内容にこれ以上立ち入ることはしませんので、興味のある方は、ぜひ本を読んでいただきたいと思います。
ただ、ひとつ後日談を報告します。というのも、あるローカル・ラジオ番組(RSKラジオ「おかやまニュースの時間」)で、この本の紹介をしたのです。
すると、放送からひと月ほどたったある日、局のスタッフからメールが届きます。「河野さん、嬉しい話です」と。
<以前番組で紹介した『百歳以前』の土井さん、徳岡さんから御礼の手紙が届きました。
是非、河野さんに御礼がしたいので転送してほしいという命も受けていますので、いただいた手紙をスキャンしてデータでお送りします。>
送られてきた土井さんのお手紙を拝見しました。
<過日、知人の教示によりスマホにて10月29日の放送の録音を聴くことができました。早速電話にて徳岡にも聴かせました。
(略)深く読み込んでいただいてのご紹介、著者として大変ありがたく、徳岡ともども嬉しく聴かせていただきました。
徳岡も感銘を受けたと申し、同時に昔を懐かしんでおりまして、小生よりお礼を申し上げてくれとのことで本状差し上げる次第です。
徳岡は現在読み書き不能で、電話のダイヤルも操作不可能な状態なので、直接のご挨拶もできず失礼するとの伝言ご連絡させていただきます。なお電話の受信は可能なので、お気が向けばお電話してやってくだされば喜ぶと存じます。>
実は、駆け出しの編集者時代から、徳岡さんにはさんざんお世話になった経緯があります。さっそくお電話したことは言うまでもありません。
以前と変わらない、じつに懐かしい声が聞こえてきました。しばらく思い出話を交わしました。ながいご無沙汰でしたが、この間も、『五衰の人——三島由紀夫私記』が文庫化された際に再読の感想を記したり(「四半世紀を経て書かれた歴史」、拙著『言葉はこうして生き残った』所収、ミシマ社)、イラクで非業の死を遂げた日本人外交官たちの葬儀に寄せた徳岡さんの感動的なコラムを紹介したり(「ほぼ日の学校長だより」No.137)、ブランクを「言葉」がつないでくれました。時の隔たりを、不思議なくらいに感じません。
ちょうど私自身、昨年11月からフリーの身の上になって、まさに「峠の茶屋」に腰かけて、来し方、行く末をぼんやり考えていた時です。思いもかけないめぐり合わせが、よけい心に沁みました。
それまで書き続けていたメールマガジン(「ほぼ日の學校長だより」)に終止符を打ったばかりです。「あの続編をどこかでまた」とリクエストしてくださる方もありました。
そんな声に励まされて、頭をよぎるよしなしごとを、これから書いてみようと思います。どのような道がひらけてくるか、皆目見当がつきません。地図も持たず、ナビにも頼らず、行き当たりばったりで、気ままに進んでみたいと思います。「百歳以前」には、まだまだ遠いと思いながら。
河野通和
