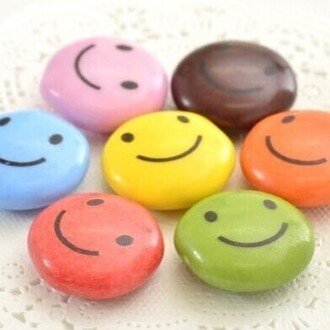clusterからクリエイターが流出するホラーシナリオ
2024年8月に、YouTuberのスタンミさんが自身のチャンネルでVRChatについての話題を投稿し始めてから、バーチャル空間でのコミュニケーションやイベントがさらに広く認知されるようになりました。
VRChatだけでなく、日本発のVRSNS「cluster」も、2024年8月29日に開催されたCluster Conference 2024のプレスリリースで「イベント累計動員数3,500万人」と発表し、その実績を示しています(アクティブユーザー数は非公開のため不明です)。
VRChatの盛り上がりと一緒にclusterもお客さんが増える?と期待したい一方で「クリエイターの流出」という課題が深刻化する可能性も予期しています。
本稿では、なぜそのような状況になるのかを、新規ユーザーや既存ユーザーの行動傾向、コミュニティの構造的な問題点から考察し、さらにプラットフォーマーとしてのcluster運営が取るべき方策について提案していきます。
新規ユーザーは増えているようで定着していない?
冒頭でも触れた通り、clusterでは一見新規参入者が増加しているように見えますが、実際にはアクティブユーザー数の成長ではなく、累計イベント参加者数という積み上げの数字に留まっている点が懸念です。
また、現在のデイリーのアクティブユーザー総数は、メインページの「ONLINE 人気のスペース・イベント」から推測できます。ただし、プライベートルームでの交流は表に見えないのですが、それを考慮しても、曜日や時間帯によってユーザーの波動はあるものの、リストされているオンラインのスペースの中に見えるユーザーアイコンの個数(必ずしもアイコンの数=人数ではないですが、目安にはなります)を足し合わせた数値が目に見える賑わいだとすると、アクティブユーザー数の純増はまだ外部にアピールできるほどではないと考えられます。
色々なメタバースの作り方や特色の出し方があると思うけど、clusterは
— Naoto Kato ∞ 加藤直人 (@c_c_kato) February 7, 2022
「いちばん敷居の低いメタバース」
であることに固執している
clusterの強みはクロスプラットフォームで、スマホでもアクセスできることです。これは仮説ですが、敷居が低いことによって、新規アカウント作成者数は多くても、体験価値が満足に得られず、一定期間を過ぎるとログイン頻度が減少し、最終的にアクティブユーザーとして定着しないケースが目立つのではないでしょうか。
スマホユーザーはハイスペックなパソコンやVRデバイスほどコンテンツを深く体験できないかもしれません。ですが、それを抜きにしても、遊びはじめてから早いうちに成功体験を提供し、より深く遊べるVR環境へステップアップしてもらうことや、どんなイベントに参加すべきか迷っているユーザーをサポートすることで、まだ成長の余地が十分にあると感じます。(注1
残ったユーザーが「観る」から「行う」に移行する
一方で、定着したユーザーはイベントを単に「観る」立場に留まらず、自らが「行う」立場へと積極的に移行する傾向があります。
お気に入りのイベントに参加し続ける中でファンとなり、そこでいつも顔を合わせる方々とのつながりが強固になると、やがて出演者になったり、単独でイベントを企画したり、ワールドを制作・公開したりと、創作や主催の側に回るユーザーが増加するのは、VRSNSのポジティブな特徴の一つです。
このような姿勢を後押しする環境は、非常に整っていると感じます。例えば、ワールド作成のテンプレート提供や、clusterのSDKの利用方法に加え、UnityやBlenderの使い方を含むノウハウの提供は初学者にとって大変有益です。また、疑問が生じた際にはDiscordの公式コミュニティで質問できるサポート体制も整っています。
さらに、イベントの開催ハードルも低く、思い立ったら既存のワールドを借りて歌を披露したり、楽器を演奏したり、トーク会や交流会をすぐに開催できる手軽さも魅力です。
こうしたサポートや環境が後押しとなり、実感としては、数か月間観客としてリピートするユーザーの多くが、やがて演者や主催者へとコンバートする可能性が高いと考えています。
一つのイベントあたりにくるユーザーが減り、やがて取り合いに
コミュニティ(=仕様では存在しないので概念的なものです)の細分化とイベント数の増加とともに、現在、1つのイベントあたりの参加者数が減少する傾向にあると感じています。
一部のアクティブユーザーは頻繁にイベントに参加していますが、イベントの開催数が増えると、これらのユーザーが複数のイベントシリーズやコミュニティを掛け持ちするようになります。
また、特定の人気イベントにユーザーが集中する一方で、それ以外のイベントは総じて人がまばらで、入場制限人数が同じ、公式のロビーを超えている客入りのイベントはせいぜい1つあるかないかです。
これは最初の仮説にもあったアクティブユーザーの総数が大きく伸びていない結果として「おなじみのメンバーの取り合い」が発生しているのではないかと思っています。実際、イベント主催者から見た参加者数や盛り上がりは、過去の開催時よりも減少しているという声を複数の主催者から聞くことがありました。注2)
このような状況では、ベテランユーザーはもちろん、新人クリエイターが安定してファンを獲得するのも容易ではありません。注3)
クリエーターはフィードバックが薄いとやる気をなくす
創作活動の目的は人それぞれ異なります。収益化を目指す人、有名になりたい人、褒められることを喜ぶ人など、目的の大小にかかわらず様々です。しかし、ユーザーの来訪数とエンゲージメント率は、どの目的においても基礎となる要素だと思います。(エンゲージメントの中身は、イベントに足を運ぶこと、ぴゅーいすること、コメントすること、イベント写真を挙げてくださることの総体を想定しています)
クリエイターがワールドを作成したり、イベントを準備したりする際に手間をかけても、参加者が少ないとフィードバックが少なくなりがちです。これが「せっかく作ったのに見てもらえない」や「反応が得られない」といった不満につながり、イベント終了後も継続して活動しようという意欲を失わせる要因となります。
言い換えると、X、BlueSky、Thread、mixi2というソーシャルメディアで、なにかつぶやいたときに「いいね」が付くことで心が満たされる経験ってありませんか? それに近からずも遠からじとおもってます。
さらに、今は頑張り続けても将来的に状況が変わらなければ、「このまま続けても成果が出ないのでは?」と感じるかもしれません。特にVRChatと併用しているクリエイターがVRChatで成功体験を得てしまうと、VRChatへの出張が「片道切符」になってしまう可能性も考えられます。
クリエイターにとってフィードバックは燃料のようなものですので、継続して創作活動に取り組んでいただくには重要な問題です。
プラットフォーマーのクリエイターに対する還元とは
クリエイターに対する還元の形は多岐にわたります。クラフトアイテムやアクセサリー、オリジナルアバターの販売収益、Vアイテムのレベニューシェアといった金銭的な報酬のほか、Creator Awardやお題企画の受賞による名誉なども含まれます。
こうした多様な還元の仕組みがすでにあることを承知しつつ、現段階のclusterにおけるクリエイターへの還元は、これまでの議論を踏まえて、
「新規ユーザーにたくさん定着していただくこと」
だと考えています。
具体的には、新規ユーザーがclusterを訪れ、スムーズにコミュニティに参加し、“観る”から“行う”へとステップアップしていくプロセスが機能しつつ、それよりも多いプラットフォーム全体の人口を増やすことです。つまり、立ち入ってくれたユーザーに早い段階で成功体験を味わっていただき「また明日も、もっと先も、遊びに行きたい!」と思ってもらえるような仕掛け作りがあって、安定的にイベントに足を運んでいただけるような流れがあることです。
継続率を高めることは、プラットフォームの人口増加につながりますし、結果としてクリエイターが制作したコンテンツやイベントをより多くのユーザーに見てもらいやすくなる土壌を育むことになります。これにより、見てくれる人が増える、あるいは、その時は見てもらえなくても、場全体でお客さんが増えていることを実感して、次はがんばってみよう、など、クリエイター自身もモチベーションを維持しやすくなり、再チャレンジの意欲を高めることができるのではないでしょうか。
プラットフォームの中の分断されたコミュニティをつなげる機会を創出する
新規ユーザーの継続的な利用促進だけでなく、並行して取り組む価値があることが他にもあります。
プラットフォーム内には多数のコミュニティが存在し、VRSNSの魅力である人的な交流は、コミュニティの外ではどうなっているか分からないのが実情です。注4)
すなわち、平均的なVRChatユーザーは仮想世界の99.4%とつながっていない)
コミュニティ内で多くのイベントが開催されると、参加者が取り合いになることもあります。そうした場合、異なるコミュニティをプラットフォーマー側がつなげて、例えば、ユニークな企画で皆さんがご存じのイベンターさんと、長く週一でDJイベントを開催している皆さんおなじみの方との共催など、clusterをリードするクリエイターやイベンター同士がコラボすることで、異なるファン層同士に新たな交流や体験を提供できるのではないでしょうか。注5)
こうした動きは、同じコミュニティ内ではイベンター・クリエイター同士が連携が取りやすいものの、コミュニティを跨いで行う場合は、プラットフォーマーから両者への企画提案がないと実現しにくいと想像します。
ジャンルやコミュニティが異なるクリエイター同士を集めて交流の場を創出することだけでも、自発的なコラボレーションが生まれるかもしれません。また、公式がコラボイベントを仕切ってもいいと思いますし、人気イベントを巡回する形式の企画など、同じプラットフォームの中でも、まだ知らなかった世界に誘導できる余地があります。
コミュニティを横断した取り組みは、一つのイベントへの集客力を高めるだけでなく、既存ユーザーのアクティブ率を向上させるメリットもあると思います。
提案
観客を増やすための活動
創作活動の受け手(=フィードバックしてくれるお客様)となる新規ユーザーが離脱しないシナリオを磨く
リピートの要因(=仮説ですが、スマホではハードウェアの制約のため、コンテンツの体験より、気の合うフレンドの有無が要因だと思います)をさぐり、そこに早期にたどり着きやすくなるようにする。
フレンドづくり以外の手として、コミュニティを可視化し、そこに帰属意識を持てる仕組みを用意する。注6)
既存の活発なイベントに自然に参加できる導線を強化する。
異なるコミュニティ同士をつなげる動きを作る
コミュニティ間の交流を深めるきっかけを作る。プラットフォーマーによる老舗イベンター・クリエイターの交流会でコラボの土台を作る、など。注7)
コラボイベントの仲介を行い、双方のコミュニティのファンに楽しんでいただく。と同時に一つのイベントに対してのフィードバックを増やす。
まとめ
clusterにおいてクリエイターが流出する要因として最近気になるものは、新規ユーザーの定着率不足やコミュニティの断片化による“観客の取り合い”、それに伴うイベントあたりの参加者数の減少、そしてイベンターやクリエイターへのフィードバック不足にあると考えています。
イベント参加者数、フィードバック減少の課題は、あくまで既存アクティブユーザーからの反応が主になるCreator Awardなど、現在のクリエイター支援の枠組みでは十分にカバーできておらず、どのようにユーザーのすそ野を広げるか、といったプラットフォームの運営方針や仕組みのデザインにも深く関わる根本的な問題です。
しかし、新規ユーザーがプラットフォームに長く留まり、多様なコミュニティが交流してそこから新しい機会が生まれる、というのは、プラットフォーム自体の成長ビジョンと大きく外れてはいないはずです。
新規ユーザーがフレンドを作ったり、コミュニティに参加したり、異なるコミュニティに属するユーザー同士の接点を増やすには、時には運営主導の取り組み(おせっかい)があってもよいと考えます。また、イベントを開催したりコンテンツを制作しているクリエイターが、現在の取り組みがプラットフォームの成長とともに大きな成果へと繋がるという期待を持てるようなビジョン提示も重要だと思います。
これらの施策を通じて、クリエイターがやりがいを持って活動を続けられる環境を整えることが、cluster全体の活性化と持続的な成長に繋がると信じてます。
注釈について
注1:現在は運営スタッフさんが、ロビーでユーザーに向けて、ワールド巡りのお誘いを時間帯で定期的に呼びかけています。これだけでも心のこもったサポートなのですが、欲をいうと、そこからフレンドさんを作る仕掛けがあるとさらにいいと思っています。
注2:複数のイベンター・パフォーマー・クリエイターから直接聞いた話、伝聞、ソーシャルの書き込みが根拠になっています。
注3:イベントの内容や、質や、主催者のメンタル、が要因という考え方もあります。一方で、tiktokは、新規ユーザーは反応が得やすいように投稿の表示優先順位が一時的に高くなるように設定されている噂があったり、メルカリは新規出品されたものが上位に表示されるアルゴリズムで注目を集めやすい、というのもあるので、仕組みによる効果の出し方もあると考えています。
注4:ここで言うコミュニティとは、cluster内では定義されておらず、特定のイベントジャンル(例えば音楽系イベント)にリピートして参加している人々を指しています。
注5:VRChatの音楽イベントでも「その場の全員がDJ」というのはときどき笑い話で言及されることがありますが、海外の音楽イベントのオーガナイザーさんから聞いた話で「クラブイベントの数が増えすぎて、オーディエンスの取り合いになったことが、コラボイベントを作るきっかけになった」と聞いております。事例として。
注6:イメージに近い仕様として、VRChatのグループ機能があります。それかDiscordとの連携を取りやすくするというのも手だと思います。
注7:GameJam、などのチーム制エントリーにもそういった意図があると推察しています。ですが、もっと偶発的なコネクションづくりが必要で、勉強会やライトニングトークからの小さ目のグループワークで初見の方同士を組ませるといったおせっかいも有効かと考えます。
いいなと思ったら応援しよう!