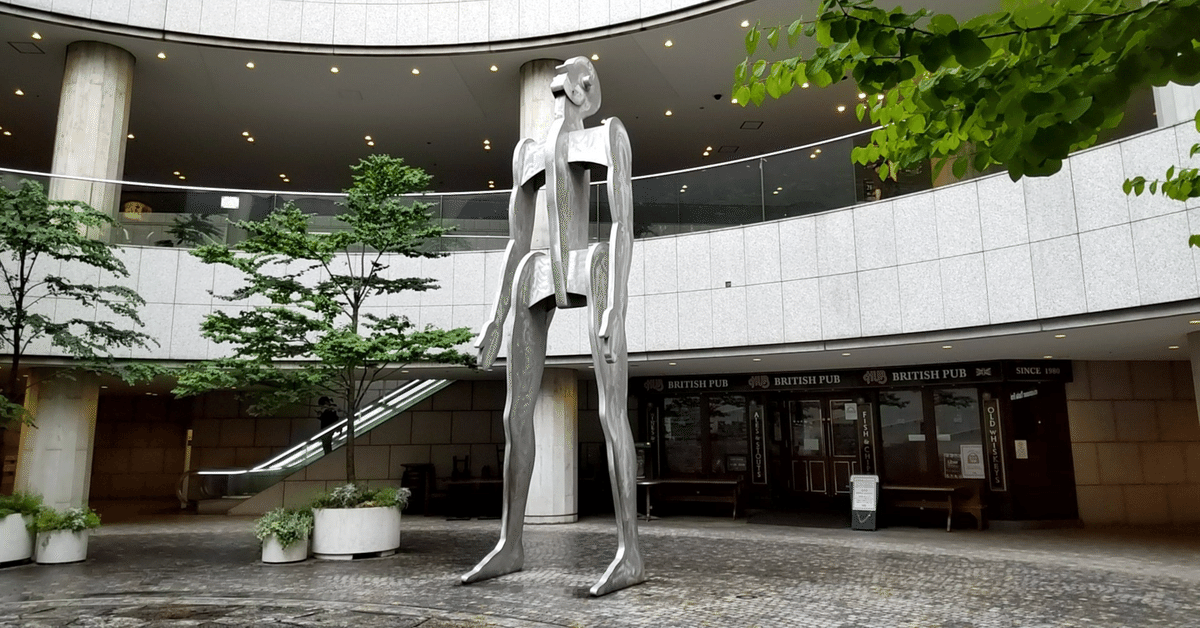
ミケル・バルセロ展 /東京オペラシティ アートギャラリー
ミケル・バルセロは、現役のスペイン人アーティスト。
その画業の全貌を紹介する展覧会に行ってきた。
チケットを手渡される際、「作品との距離をとってください」という珍妙な注意事項を伝えられた。展示室のなかで指摘されるならまだしも……であるし、むしろこのご時世、「人との距離」の言い違いかなと思ったくらいだ。
展示室の入り口の注意書きが、これまた珍妙。
本展は撮影可能です。ただし撮影のための後ずさり禁止
なんでも「作品との接触の危険」を防ぐためだとか。
これら珍妙にして厳重な注意喚起のわけは、実物に接してみて、よく理解できた。
巨大な画面に、ほとんど暴力的といっていいくらいの力をこめて絵の具を叩きつけ、ときに削り、傷をつけ、引き剥がす。
こういった作品であるから、どこを切り取っても違う表情があって、全図では伝わりづらい部分が大きい。つまるところ、じつに「接写したくなる」マチエールをしているのだ。


さらにこの画家は、キャンバスを破くことにさえ躊躇がなく、逆に画面を極端に盛り、木の棒などの異物を貼付までする――多くの作品がこういった特徴をもっていて、途中からはプラマイ2~3センチ程度の凹凸ならばすっかり見馴れてしまった。

平面のキャンバスを基本としながら、そこから大きく隆起・陥没している。
そのために、撮影に夢中になっているとつい、前後・遠近の感覚がつかめなくなる。
結果として、被写体としている作品や自分の背後にある作品に接触してしまう危険が高まってしまうのである。
だから再三、「作品との接触」への注意が喚起されたのだ。
そんなバルセロの作品の多くは、モチーフが具象的な形を留めてはいるけれど、ほんとうに具象画でいいのか、さらには平面といってよいものか、そもそも絵画なのか……疑問符が浮かんでは消えていく。
ある種の戸惑いをいだきながら最後の部屋へ行き着くと、そこでは、制作時のパフォーマンスの映像が投影されていた。
スーツを着た男性(バルセロ)が泥まみれになって、絵の具を分厚く盛りつけたキャンバスを拳で殴りつけたり、バットで叩いたり、自分の頭を突っ込んだりしている……
映像には、その場に居合わせた観客が洩らした「苦笑」も、しっかり捉えられていた。その笑い声を聞いたとき、「ああ、笑っていいんだな!」と、はっと気づかされるものがあった。なにも、身構えなくていいのだ。
そして、こういったものはやはり、制作のプロセスもまた作品の一部に違いない。これまでの展示室で観てきたものは、どんなパフォーマンスによって、どんなプロセスを経て「完成」とみなされたものなのだろうか――そんな想像をめぐらせながら、会場をあとにするわたしであった。
