
石原千秋の『反転する漱石』をどう読むか④ そんなに大人しくはない
読んだ本の感想をnoteに書いてみませんか?
記事を書く前に何時も読まされる文章だが、そんな恐ろしいことはないなと私の記事を読むと思ってしまう人もいるのだろうか。
具体的にあらすじを書いてしまうと必ず間違いを指摘されてしまう。自分ならこんなに恥ずかしいことはないと思うのだが、どうなのだろう。
それでも本当に石原千秋は良く読めている部類だと思う。これまで見てきた通り、ほとんどの人は石原千秋のところに届いていない。ぼやーっと読んでしまっている。つくづく漱石は凄いなと思う次第である。
ところで石原千秋はまず『三四郎』は完成度が高い、という話から始めた。私はそれをレベルが上がっているという解釈に置き換えて引き取ってきた。そしてその上でご覧の通り、石原千秋でさえ読み間違えているので、石原千秋は『三四郎』のレベルに追いついていない、それだけ凄いという理屈になる。そうなると改めて何故こんなものが書けてしまったのか、ということが不思議になる。
前回漱石には男女間の微妙で曖昧な関係を捉える目が『坊っちゃん』の時点ですでにあったことを確認した。しかし一場面を捉えるのと物語に展開するのは全く次元の違う話である。

だからこの問題は全然解決していない。その前提で先に進もう。
生物学=進化論は動物に雄と雌の違いがあることを再認識させた。
一般常識として、この表現は雑すぎる。「生物学または進化論」であれば内容はともかく形式的には整うが、「生物学=進化論」だと社会進化論が無視されてしまう。とくにダーウィンの進化論に関しては社会進化論の概念が先行して存在する前提で成り立っており、「生物学=進化論」でないことは当たり前の話である。
ここは石原が、
・女は明治に発見された
という趣旨で述べられている話だが漱石論としてはまずい展開である。なぜなら「性」の問題に関しては漱石に独自理論があるからである。
石原は「両性問題」というものが盛んに論じられたとしているが、おそらく漱石は英文法から性の概念を捉えていて、三性という概念を持っていた人なのである。
従って「野だ」を「かげま」のように描いたわけだし、佐々木与次郎は盛んに男子学生を女給のいない淀見軒に誘う。
なんなら皆さん大好きな『こころ』の海水浴、あれで腐女子の皆さんをキャーキャー言わせようというのは、やはり漱石のたくらみの一つである。
ところが石原は三性の考えを容れない。
こうした時代的なパラダイムを、はからずも漱石は最大限に利用したのではなかったか。当時の女の礼法にのっとって、よけいな動きをせず、よけいなことも言わない女が知識人の解釈を誘い、それが女の内面にわかり得ない深みを与える。これが、漱石が生み出した方法だった。
ここで時代的なパラダイムと言われているのは「処女は謎である」という考え方のことである。石原は社会学者でもないのに時々こうした社会学的な事を言い出すわけだが、引用している資料が大正十三年、明治三十七年、明治三十四年、大正二年と少しばらけすぎている感がある。
まあそこはさておく。しかしこれが藤尾に欠けているところだとすればまあ解らない話ではないとして、これでは『三四郎』の凄さを説明できていない。美禰子は「よけいな動きをせず、よけいなことも言わない女」ではないからだ。むしろこう言われて思い出すのは「名古屋の女」である。「名古屋の女」があまりにも積極的なので三四郎にとっては女が謎になり、恐ろしくなるのである。三四郎が完全に「落ちた」のは「ストレイ・シープ」という言葉を美禰子から囁かれたときである。
そもそも何故石原は「よけいな動きをせず、よけいなことも言わない女」などと言い出したのであろうか?
そんな女は……小夜子くらいなものではなかろうか?
ここは何がしたかったのか本当にさっぱりわからない。少なくとも石原が三性という概念をつかめていないことだけは分かった。
もう少し頑張れ、石原千秋!
[余談]
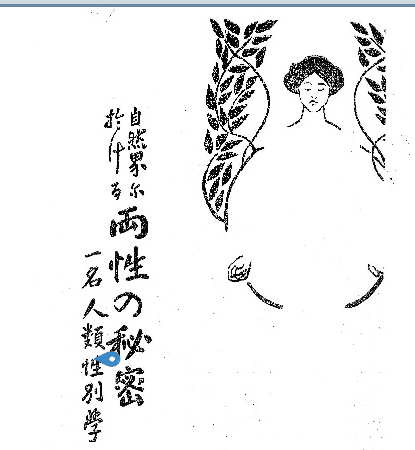
両性問題は生物学というより性別学ちがうかなあ。
