
飯島耕一氏の『漱石の〈明〉、漱石の〈暗〉』をどう読むか② 朔太郎と『行人』
本は知らないこと、知りたかったことを知るために読むものである。間違い探しのための読書など何の価値もない。飯島耕一氏の『漱石の〈明〉、漱石の〈暗〉』は、そういう意味では間違いなく読むべき本だ。
飯島はなかなか正確につかみきれない一郎の苦悩を、萩原朔太郎に重ねて捉えようとする。これは正直意外なことだ。
飯島が断っているとおり、萩原朔太郎は夏目漱石をまともには論じていない。ただ「孤独人」と書いているだけである。
芥川とのつながりにおいてみられるのも「くどい長編小説の読めない朔太郎」でしかなく、私は萩原朔太郎がまさか『行人』をまともに読んでいようとは思ってもいなかった。
飯島は「一郎の問題は、そのまま若い頃神経症に苦しんだ朔太郎の問題なのであった」として、高橋元吉あての手紙を引用する。
「……〈こうしては居られない、何かしなければならない、併し何をしてよいか分からない〉これです。この声が我々にとつていちばん恐ろしい声なのです。明からさまに云ふと我々は理想も目的も持たないのです。あなたも多分私と同じだらうと思ひます。時に私はかうした近代病の苦脳のために世の何人よりも烈しくやられて居るのです。私は中学を卒業するときから此の病気にかかつたのです。多くの友人たちが、希望にかがやいて未来を語り合つて居るときに私一人は教室の隅で黙つ陰気な顔をして居ました」(『萩原朔太郎全書簡集』)
この手紙は『行人』に触れながら書かれたものだという。朔太郎の父密蔵は医者であり朔太郎を医者にしたがっていた。朔太郎の友人たちは芸術家になることを勧めたようだが、朔太郎自身は「芸術は人間の目的ではなかった」としてさらに悩むことになる。
「その後他から強ひられていやいやながら高等学校に入りましたが私は全く学科を軽辱しました。何故かといふに私は特に文学を卑しんで居たからです。〈文学は道楽に過ぎない、それは恥づべき職業である〉当時に於ける私の考はかうでした」。
そりゃ大変すいませんねえ。
しかしね、「恥づべき職業」というのは文学でなくてね、だらしない文学ですよ。
しかしこの言い分は後の萩原朔太郎の活躍ぶりから考えれば、信じがたいものなのではなかろうか。
何の屈折もなく文学に入ってくるものなど信用に値しないが、少なくとも萩原朔太郎は左翼活動の挫折の吹き溜まりのような、そんな「恥づべき職業」としての文学者ではなかった。
しかし後に第六高等学校に進んだ飯島は、朔太郎の在籍を誇りとする生徒も教師も一人として存在しないことを発見する。
ちょっと待って。
日本近代詩の父って……。
バッハは?
音楽の父か。
凄いな。
夏目漱石が日本近代文学の父と言われることはない。
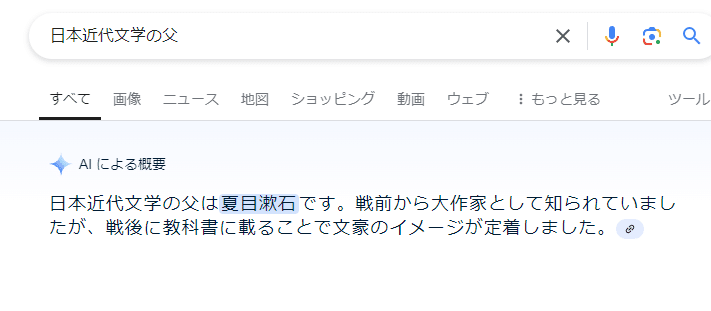
言うんかい。では紅葉露伴は日本近代文学の何?
と話が散らかるので先に進めると、どうも萩原朔太郎は文学志望ではなく、文学を軽蔑し、迷っていたらしい。
「そして今に至るまで私は何の理想も目的も見いだすことができません。しかも目的なしに生きてゐることがどんなに辛いことかといふことはあなたも御推察になることと思ひます。しかも、幸か不幸か、私は生活のために労働する必要がないのです。従つてその労働にまぎれて、さうした苦脳を忘れるといふ時間が私にはないのです、朝から晩まで私を悩み苦しめるものはただこの一つの思想です、
(何のために?)
〈何の目的で? お前は生きて居るのだ?〉
これです。」
確かに一郎同様無理にも狭いところに自分を追い詰め、高めようとは意思しながら、自ら苦悩を生み出している。
なんてね、アハハハ……という余裕がない。つまり照れもなく苦しむことができている。そういうことは普通出来ない。鏡を見ればあまりにも情けない顔に笑ってしまうだろう。しかしこの二人は同じ苦しみの中にいたのだ。
「自分のしている事が、自分の目的(エンド)になっていないほど苦しい事はない」と兄さんは云います。
私のnoteにも記事を読まないで新着記事に一つだけスキをつけていく馬鹿がいる。そんなもののために私は書いているわけではない。読んでほしい記事があるのかと読んでみるとあまりにも中身がないので驚きあきれる。おそらく彼らには何の苦悩もなかろう。金は欲しいのかもしれないが、それだけに羞恥心のかけらもない。ただただ醜悪だ。
私はそんなもののために悩まない。
それにしても飯島氏の慧眼は一郎の悩みのどうしようもなさを真正面からとらえているところにある。正直私は一郎の苦悩をユーモラスに捉えていた。なんというか心を病んでいる人の悩みというのは本質的で根源的であればあるほどどうでもいいものに思えるからだ。ここまでに引いた萩原朔太郎の手紙も「くどい」感じがする。なるほど本人は真剣なのではあろうが、他人からしてみるとどうでもいい。それこそ三島由紀夫ではないが体操で治るといいたくもなる。
なにしろそれは病なのだから。
この見立ては単に一郎を突き放しているだけで、いわば主人公を二郎として読む立場の特権である。多くの人が一郎を主人公として読み、なおかつ一郎の悩みに混乱してしまうところ、たまたまではあるが飯島氏は萩原朔太郎という同類を発見することにより、ああこういうことかと一郎の悩みを正面から捉えてしまった。ここは凄い。
私は天下にありとあらゆる芸術品、高山大河、もしくは美人、何でも構わないから、兄さんの心を悉皆奪い尽して、少しの研究的態度も萌し得ないほどなものを、兄さんに与えたいのです。
飯島氏はこんなHさんの言葉を引いてこう述べる。
こうした考え方はボードレールの散文詩にある「酔っていなくてはならない、何にでも」の思想態度とかなり類似したものとしていい。
正直このHさんの台詞も、そこまで意識していなかった。言われてみればいかにも適切な治療方法が示されている。
これはこういうことだと思う。みな初めてのものには戸惑う。大抵のものは初めて見る。ただ経験値によって、あれはこれの仲間かと判断できる。もう一つはやはり詩人らしい直観だ。ロゴやイメージキャラクターは言語やロジックを介さずにあれとこれとを直接結び付ける。イメージ力とはそういうものだ。
『行人』は大正元年(一九一二)十一月から、翌大正二年(一九一三)十一月まで朝日新聞に連載されたが、この時朔太郎は「夜汽車」など最初期の「愛憐詩篇」の詩を書き始めていた。また大正三年末からは、緊張にうち震えるような「浄罪詩篇」の形成期に入っていた。



日本近代詩の父は一郎から生まれたとまでは飯島氏は書いていない。ただ一郎の苦悩は朔太郎の苦悩に重なり、詩が生まれる。この話はもう少し続く。
[余談]
大学教授らしき一郎の悩みの出口の方向性もやはり漱石のように作家になることだったんじゃないかと思えてくる。教師が嫌で悩んでいた芥川も作家となって少しは救われた?
ともかく朔太郎が詩人になれてよかった。
