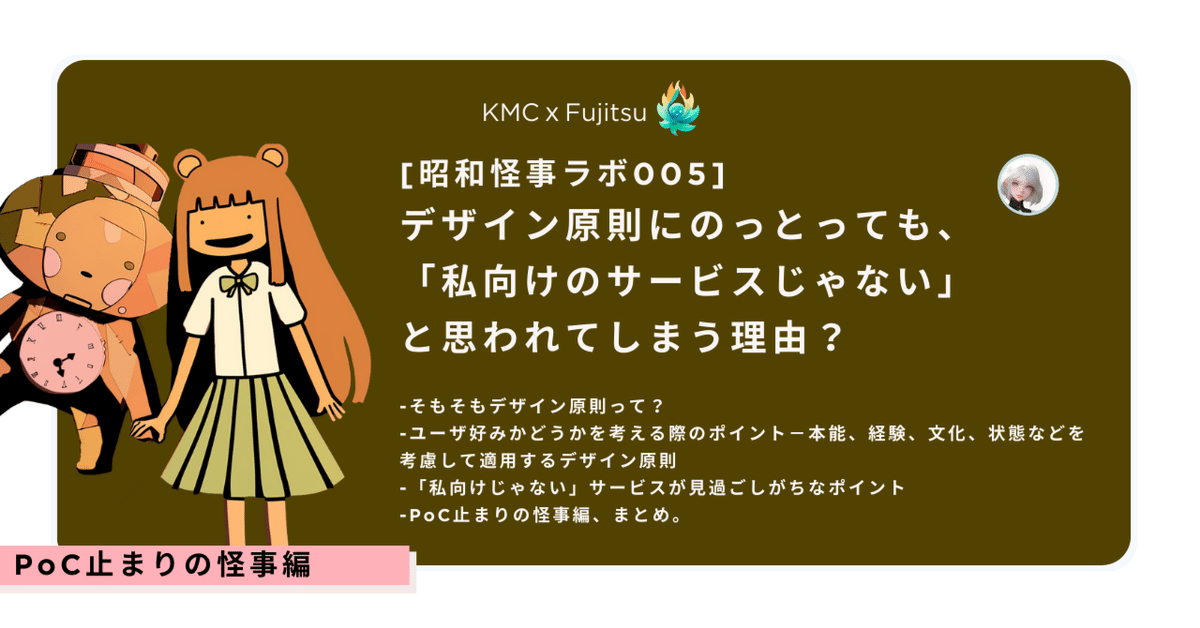
[昭和怪事ラボ005]デザイン原則にのっとっても、「私向けのサービスじゃない」と思われてしまう理由?
旅先で美味しい料理が食べたいなと思い、平均よりも少し価格設定が高めのレストランが立ち並ぶ高級店街へやってきました。いずれも格調の高さを示す建築や入り口に飾られた生花で、そのサービス品質の高さを示しています。1件目に覗いた店内はスーツやワンピースを品よく着こなした現地の人々であふれ、2件目では少しカジュアルで飛び交う言語も様々でした。
さて、あなたなら、どちらのレストランの方が、旅先の良い思い出が作れそうだと思うでしょうか?
人がサービスを選ぶ時、最も素敵だと思うものを選ぶのであれば、1件目のレストランの高級感は優れたものといえるかもしれませんが、サービスを使用するユーザのアイデンティティとフィットするかということを考える時、多くの外国からの訪問者にとっては現地の人々のみの空間は居心地の悪さにつながってしまうかもしれません。
このように、デザイン原則を適用する時、そのコンテンツの形や色などを考えるだけでなく、ユーザのエンゲージメントタイプやスキルやアイデンティティを考慮することで、よりユーザに向けたサービスを形成することが可能となるわけですが、後者は意外と忘れられがちです。そこで、今回はデザイン原則について、この後者を含めて見ていきたいと思います。
こんにちは。HCI (Human-Computer Interaction)という分野を専門に研究しているnacoです。
前回の[昭和怪事ラボ]PoC止まりの怪事編では、検討中のサービスがユーザーにとってどのようなサービスであるかを見極めることで、戦略的にサービスデザインを進める方法について考えました。今回の記事では、デザイン原則の中でも、「私向け」のサービスだ!とユーザに思って貰えるためには、検討が欠かせない部分を中心に見ていきます。
そもそもデザイン原則って?
新聞挟み込みのちらしやポストに投函されるDMを思い浮かべてみて下さい。安売りをアピールするもの(スーパーの特売など)と、高級商材(マンションなど)とで、使用している色や情報の混み合い方などに差があることに気付かれるのではないでしょうか?
人は、情報を処理する時、その中に含まれる色や形状やキャラクタや提示されるタイミングなどから何等かの印象を感じ取っています。黄色いや情報がびっしりと詰め込まれたレイアウントからは「安い」印象を、シンプルな色合いやムダの少ないレイアウトからは「高級な」印象を、一般的には感じ取ります。そういった原則的なルールがデザイン原則として整理されており、多くの書籍が出ています。
当然、これらは、本能的なものばかりではなく、文化や経験やコンテキスト(文脈)などによって異なって解釈されますし、絶対的なものでもありません。ただ、もし、デザイン原則を参考にせず、全てをイチから単独のデザイナーの感覚で決めていくとしたら、狙った効果を出せるデザインへ辿り着くまでには、果てしないユーザテストの時間が必要になると考えられます。
以下では、まず、デザイン原則を適用する際にユーザの選好を検討するポイントについて整理していきましょう。
ユーザ好みかどうかを考える際のポイント-本能、経験、文化、状態などを考慮して適用するデザイン原則

本能
本能、生理的に受け入れにくいもの、というのはありますよね。例えば、殆どの人は、犬や猫のフワフワな触感と、蜘蛛や爬虫類の少し湿った質感とでは、前者の方を好ましいと考えます。これを用いて、多くの人に好ましく受け入れられる必要があるキャラクタをデザインする時、あるデザイナは犬や猫をベースに検討を開始するかもしれません。
過去のやり取りや経験
一番初めに電話機を見た人は何が出来る機械なのか戸惑ったかもしれませんが、現在多くの人は、スマホの電話アプリの画面を見た時、数字ボタンを押すという動作によって、電話番号を入力することができるんだろうなと想像することができると思います。これはユーザの過去の経験から、「ボタン」という見た目と、「押す」という動作が紐づけることが容易だからだと思います。もし、ドアをデザインする人が、「引く」という動作をユーザに想起して欲しい場合には、「レバー」を候補に挙げるかもしれません。
文化や規定
そのデザインの受け手が、文化や規定の影響を受けていない状況は、ほぼないと思います。例えば、虹を描く時、使用される色数や色そのものにも、文化的影響があります。同様に、色から感じ取る印象も、文化圏によって異なります。例えば、明るい印象を作りたい時に、単純に明度の高い、いわば薄い色だけで構成されるコンテンツを作っても、意図した効果は得られず、「見えにくいだけ」と評されることも考えられます。
ユーザの状態やリソース
高速道路をハイスピードで走行している時と、休みの日にのんびり歩いている時とで、目に入る情報は違いますよね。その為、ユーザがおかれている状態やその時に使用可能なリソースを考慮して、高速道路に掲示する看板の文字のサイズやコントラストは、より明瞭に理解できるようデザインされます。動画ストリーミングサービスで、キャッチーなタイトルなど人目をひくサムネイル画像に多くの工夫がなされるのも、何気なく見てもらえる最初の数秒に力を入れてデザインされているのが見てとれますよね。
「私向けじゃない」サービスが見過ごしがちなポイント
「私向けじゃない」サービスだなぁ、と判定される時、上述までの基本的なデザイン原則については、キチンと考慮済である場合もあります。では、どのような考慮が不足していたのでしょうか?
何をもって、「私向けじゃない」と判定されるのかを考える時、とても使いやすいキーワードに、SAFE(State Authenticity as Fit to Environment)というものがあります。サービスがSAFEを担保しているかどうかは、ユーザがその環境において自分らしい状態でいられるかどうか、ともいえます。この記事の冒頭のレストランの例でいれば、1件目の高級レストランは外国人である自分にとっては自分らしい状態では居にくい環境の例でした。もし入り口で、アジア圏の言語で話しかけてもらえるようなレストランだと、大きく印象が変わるかもしれません。
SAFEを担保することで、ユーザに「私向け」のサービスと思ってもらう時、どのような考慮点があるか、ここでは、架空のユーザ、ボブを例に考えていきましょう。
アイデンティティ
ボブは、行きつけのレストランAへ、週に1回は訪れています。毎週訪れるので、やがて店員とは顔見知りになり、ちょっとした挨拶を行うなど、そこには和やかな雰囲気が漂っています。そうしてボブは、レストランAの良い雰囲気を保つコミュニティの一員として、立ち居振る舞いにも気を付けるようになったり、友人たちへレストランAの良い点を話すようになったりしています。
さて一方、レストランBでのボブの体験はヒドイものでした。注文したものと異なるものがきたので店員を問いただしても店員は自分の非を認めようとしませんし、会計の際には店員たちが自分たちの話で盛り上がっていて放置されました。ボブはこのヒドイ体験を近所に住んでいる友人たちにも共有しました。
つまり、ボブは、レストランAにおいてはコミュニティの一員というアイデンティティを持ち、レストランBにおいては歓迎されなかった客というアイデンティティを持ち、そのアイデンティティに沿った行動として友人たちへ良い点を広報したり、ヒドイ体験を共有したりしたわけです。
スキルレベル
ボブは日本的な料理を食べる機会が少なく、うどんと蕎麦の違いを知りません。日本の観光地で訪れたレストランのメニューの中に、うどんと蕎麦が大量に並んでいたのですが、彼にとっては、その2つの違いは分かりませんでした。それどころか、どのような料理なのか想像することも難しい状況でした。この場合、ボブが最初に知りたい事は、ここに大量に並んでいるのが、どのような種類の食べ物なのかということでした。
これと同様に、ボブはフランス語を話せません。試しにフランス語の発音を練習してみようと、適切なオンライン講師を選択しようとした時、発音スキルレベルが70点の講師と、100点の講師とが候補として挙げられました。いずれもネイティブなフランス人ではなく、70点の講師で十分なのであれば、自分のスケジュールにあわせてオンラインレッスンを受講することができそうです。しかしながら、この70点と100点の差というのは、ボブのような初学者にとっては、どのくらいの差なのかを理解することができません。こういったケースでは、もっとシンプルな尺度によって、「標準的」なレベル、「完璧」なレベル、と表現されている方が理解がしやすいケースもあります。
この2つの例から分かることは、ユーザのスキルレベルによって、解釈可能な内容が異なるということです。そのサービスにとって習熟/熟達レベルの低いユーザが多くいるような環境においては、このスキルレベルを考慮することで、「私向けじゃない」サービスだと判定される可能性を下げることができます。ただ、スキルレベルというのは変化していきますし、どのような尺度を用いてどのようなレベルを設定するのが良いかは、サービスによっては試行錯誤が必要になるかもしれません。
PoC止まりの怪事編、まとめ。
さて、今回の記事で、“PoC止まりの怪事編”は最終回です。シリーズを通して、一緒に考えて下さった方、おつかれさまでした。
今回の記事では、「私向け」のサービスだ!とユーザに思って貰えるために、検討が欠かせないデザイン原則について見てきました。デザイン原則自体はかなり広範で、キャラクターデザインなどを含めると、ストーリーテリングの手法などまで読むべき書籍が広がりますし、全体を網羅することは難しい為、ここでは、ユーザ分析を行う時にどのようなポイントを押さえて、デザイン原則を適用していく必要があるかという観点から整理してみました。これを参考にしてサービスデザインを行う方は、自分がデザインを行う対象が決まったら、その対象(テキスト、音、画像、ビデオ、キャラクター、VRアバタ、空間などなど)ごとに必要なデザイン原則を拡充的に学んでいくのが良いのではないかと思います。
[昭和怪事ラボ]全体では、イノベーションを起こす人たちにとって有用な沢山の身につけるべき知識・スキルのうち、そのいくつかでも整理しておくことで、昭和時代から連綿と正体不明のままになっている怪現象を乗り越えて、皆さんがイノベーションを起こしていく一助になればと思っています。
次回はその、シリーズ記事[昭和怪事ラボ]の全体像をまずは眺めてみて、その後に、PoC止まりの怪事編の、次の怪事編へと、皆さんと一緒に臨んでいけたらと思います。
【関連記事】
[昭和怪事ラボ000]昭和のままのスキルに気付いた時、私たちと、その組織は、成長し始める?
https://note.com/kmcxfujitsu/n/n63b22a0ef2a3
[昭和怪事ラボ001]システム中心のデザイン依存によって失われているもの?
https://note.com/kmcxfujitsu/n/n17a688a2744d
[昭和怪事ラボ002]ユーザがあなたのサービスを使わない理由?
https://note.com/kmcxfujitsu/n/n4ba15679c822
[昭和怪事ラボ003]ユーザの目的は実現しない、けど使い続けてもらえる不思議なサービス?
https://note.com/kmcxfujitsu/n/n0b8104c1140c
[昭和怪事ラボ004]会議室のツルが鳴かずにすむ戦略的な判断基準?
https://note.com/kmcxfujitsu/n/ned841df6d1e9
文責:naco
[昭和怪事ラボ]シリーズ全体は、昭和時代から連綿と正体不明のままになっている怪現象へ、取り組んでいきたいと思っています。“PoC止まりの怪事編”の次は、心理的安全性を担保するコミュニケーションスキルについてまとめようかなと考え中です。リクエストなどあれば、ぜひお願いします~
