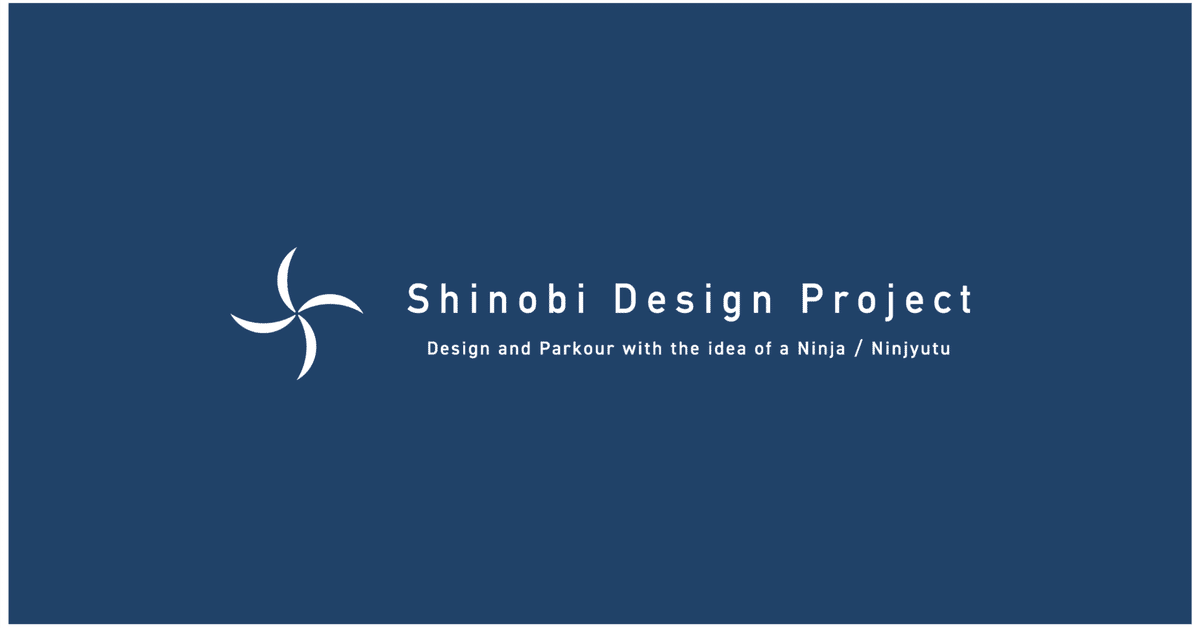
忍術の基礎「古法十忍の習い」を理解する【忍術書『正忍記』解説】
名取流(新楠流)の忍術書『正忍記』に記される「古法十忍の習い」これは古より基本とされる十種類の忍法の教えで、『正忍記』では全ての忍者の活動はこれを基礎とするといいます。
ここでは「古法十忍の習い」を解説し、忍術の基本的な考え方、基礎を学んでいきたいと思います。
(また、解説の下には原文と現代語訳も併せて記載します。)
「古法十忍の習い」
1、「音聲忍」
声・音に関する基本知識(基礎)
声・音で情報を得ることもできれば、敵に情報を与えることもあるので注意が必要です。また、謀る(情報・状況を書き換える)のにも使えます。
〈原文〉
一、音聲忍(音を利用する)
・音低きを用いる。
・枚木、奪口、裏聞き、音曲。
〈現代語訳〉
聞き取りやすい低音を使う。[陰忍]
枚(口木)を噛み声が出るのを防ぐ。[陰忍]
奪口(方言を使う)で土地に馴染む。[陽忍]
盗み聞きで情報を集める。[陰陽忍]
音楽で人心を謀る。[陽忍]
2、「順忍」
潜入、謀略、危機を脱す忍者の基本(基礎)
まずは警戒されないために敵に従います。
反感を買わないように話を合わせ、合言葉・合印を敵に合わせるなど、敵に順じます。
敵に警戒されては任務遂行に支障となり、終わりである。
〈原文〉
二、順忍(敵に順ずる)
・常に人に随う。
・事をやぶらず。
〈現代語訳〉
敵の言葉や作法に従い警戒心を下げる。[陽忍]
相手の話を論破せず仲良くなり付け入る。[陽忍]
3、「無生法忍・如幻忍・如影忍・如焔忍」
「無生法忍」大きな隙、状況(潜入)
「如幻忍」小さな隙、タイミング(潜入)
「如影忍」人や物を利用する(潜入)
「如焔忍」心の隙、油断、人(潜入)
状況・タイミング・人・心(天・地・人)で潜入のチャンスを探り得ます。
〈原文〉
三、無生法忍(混乱に乗じる):③大きな隙、状況
・乱れて利を取る。
・時にのぞんで利を取る。
〈現代語訳〉
混乱の隙を利用する。
チャンスがあれば利用する。
〈原文〉
四、如幻忍(些細な隙を利用する)
・少事にてすかさず利を取る。早きを元とす。
〈現代語訳〉
些細な隙があれば素早くつけ入り利用する。早さが大事。
〈原文〉
五、如影忍(人に着いて入る)
・人にはなれず。[陽忍]
・物をそいよる事。[陰忍]
〈現代語訳〉
人に付き添って警戒を掻い潜り潜入する。[陽忍]
物影に寄って隠れて警戒を掻い潜る。[陰忍]
〈原文〉
六、如焔忍(心の油断に付け入る)
・人の心の油断あれば入る。[陽忍]
・家も同じ時あり。[陰忍]
〈現代語訳〉
焔(ねたみ・怒り・恋情などの激しい感情)のような冷静さを失った心に付け入る。
家に潜入するときも、家人の心の油断に付け入る。
4、「如夢忍」
謀略・忍び込み、敵にアプローチして優位な状況に変える(攻撃)
敵に仕掛けて状況を変える。陽忍であれば言葉で謀略を行い、陰忍であれば夜込め・夜討ちを行う。敵の意識を現実から逸らすことが成功のカギです。
〈原文〉
七、如夢忍(夢物語りで謀る)
・人を計る。
・夜の事。
〈現代語訳〉
夢物語、夢心地にして人心を探り謀る。[陽忍]
夜闇、人が寝ているところに乗じて潜入する。[陰忍]
5、「如響忍」
土地・風俗を調査・利用(調査・準備)
任務を確実に成功させるために事前に情報収集。事前に危険箇所を確認し、利用できそうな事物を探ります。
〈原文〉
八、如響忍(郷に入っては郷に随う)
・その地を計る。
・その事に随う。
〈現代語訳〉
敵国の地形・風俗・文化などを調べ、利用して謀る。[陽忍]
敵国の地形・風俗・文化に従い警戒を掻い潜る。[陰陽忍]
6、「如化忍」
忍者の服装選び(準備)
敵に警戒されない服選びをします。陽忍なら変装、陰忍なら夜闇に紛れる色の服を選びます。
〈原文〉
九、如化忍(変装し騙す)
・常を用いるに人心を察す。
・己が形を作る。
〈現代語訳〉
変装して謀る。[陽忍]
人心を察し考え、怪しまれない姿を選ぶ。[陽忍]
変装する。または忍び装束で身を包む。[陰陽忍]
7、「如空忍」
謀略・潜入の痕跡を消す忍者の基本(基礎)
任務達成後も証拠を残さない。忍者の存在を警戒させないことで常に優位性を保ち続けます。
〈原文〉
十、如空忍(痕跡を残さない)
・人を計るに跡なし。人に事を覚えさせず。
〈現代語訳〉
謀略の痕跡を残さない。忍びの存在を覚えさせない。
「古法十忍の習い」を理解する
「古法十忍の習い」ということで、10種類の忍法が記されていますが、解説では理解しやすいように7項目にまとめました。
また、10種類の忍法をカテゴリーごとに分類すると、基礎が3法、潜入が4法、攻撃が1法、調査が1法、準備が1法(2法)となります。
忍者の任務は、①情報を探る(諜報活動)、②協力者を作る(謀略工作)、③撹乱する(破壊工作)、④奇襲(戦闘)の主に4つに大別され、いずれかが任務の“目標”となります。そして忍術(忍法)はこの目標を達成するための手段といえます。
忍者が任務を実行する流れは、①主君からの司令を受領する。②任務の目標を達成するための作戦立案に必要な情報を収集する。③目標達成のための作戦を立てる。④作戦を実行し目標を達成する。⑤任務達成を報告、評価するになります。
「古法十忍の習い」を任務の流れに対応させると次のようになります。
〈任務の流れ〉
①主君からの司令を受領する。
②任務の目標を達成するための作戦立案に必要な情報を収集する。
八、如響忍(調査)
③目標達成のための作戦を立てる。
九、如化忍(変装)
④作戦を実行し目標を達成する。
三、無生法忍(大きな隙に乗じる)
四、如幻忍(小さな隙に乗じる)
五、如影忍(人や物を便って入る)
六、如焔忍(心の隙に乗じる)
七、如夢忍(敵に仕掛ける)
⑤任務達成を報告、評価する。
十、如空忍(痕跡を消す)
ここに含まれないのが2法(一、音聲忍・二、順忍)ありますが、これは忍者の活動全体を通じて必要な基礎的な知識・素養と言えるものです。
⓪忍者の基礎的な知識・素養
一、音聲忍(音・声)
二、順忍(敵に従う)
(十、如空忍)
※⑤に分類した「十、如空忍」も基礎的な内容といえるので()で記載します。
忍術を習得するための、忍術の理解
このように、名取流の忍法を系統立てて分類すると10にはならないのですが、当時の忍びたちは忍術の学者ではなく、忍術を職能とした仕事人です。
忍術書は忍術を学ぶためのものなので、『正忍記』「古法十忍の習い」の目的とするところは技術の習得です。正確に分類すると大分類・小分類と枝分かれしますが、忍者にとっては大小関わらず全てが大事な基本事項です。忍術を技術として習得し、感覚的に使えるレベルに体得するために、名取流軍学において忍術の本質的原理と職能的必要性を考慮して考えられたのが「古法十忍の習い」だと思います。
↑参考 国立国会図書館デジタルコレクション『忍術伝書・正忍記』
いいなと思ったら応援しよう!

