
きわダイアローグ01 芹沢高志×向井知子 2/4
2.偶然と必然のダンス
ユラユラ揺れながら世界が形成されていく
///
向井:当時、P3という場所の体験については、映像的だと思うことが多かったんです。今も映像のことを考えるときに、よくP3のことを思い出すものですから。映像的ということは、ナラティブなストーリーとして見えてくるというより、レイヤーの反復のようなものに見えている。人が実際にはいなくても、それを見ている人の目みたいなものがレイヤーで重なっているような印象を受けたんです。「わたし」の目、それは誰の「わたし」かは分からないのですが、誰かの目を通して、多重に人の行為、経験みたいなものが立ち現れている。お話を伺うまで、芹沢さんは、紀行文のようなものについて、時間的な軸で動いているものを捉えていらっしゃるのかなとも思っていました。でも、そうではなく、レイヤーが重なっていくうちに、いつの間にか時間も重ねられてきたというか、イメージと体験の積み重ねが反復して出てくるような感じがしました。
芹沢:答えになっているかどうかはわからないですが、僕自身の物事の進め方として「動きながら進める」ということが多いんですね。象徴的に言えば、「歩きながら形が出てくる」というか。向井さんはレイヤーとおっしゃったけれど、迫っては消えてくるシーンの重ね合わせから、振り返ってみると、全体像としてこんなふうになっているのかと気づく。もちろんあてもなく歩き出すわけではないのですが、明確な最終目的地があるわけではない。細部については、歩きながらさまざまな偶然によってどんどん変化して、最初に思っていたのとはずいぶん違うようなところへ進んでいくのも嫌わず、それすらも含み込んで、できあがっていく。僕自身はそうやって、移動をしながら組み立てていくんですね。向井さんが映像的とおっしゃったように、ある意味、自分のなかでもメタファーとしてずいぶん使いますが、映画的な時間と空間のアプローチに、ものすごく興味があります。視点が動いていくことによって、いろんなランドスケープというか、いろんなシーン、状況と出会っていく。一見わからないような状況であっても構わないし、偶然が重なっていろんなことが起こっていく。それの積み重ねというか、集積体が出てきて、ある段階で振り返っていらない部分をそぎ落とすと、その時点の塊ができてくるというような。芸術のための空間を使わないタイプの、地方での芸術祭などを構築していく際には、映画を一番参考にしているかもしれません。例えば、別府の「混浴温泉世界」でも、さまざまな映画のさまざまなシーンが現実の空間に重なっていくなかで、それを手がかりにして再構築していくというようなことをしました。


2020年〈新装版〉、ABI+P3
そういう意味で、言語的なもので構成していくのではなく、シーンのつながりのようなもので考えていると言うと大げさですが、そういう映像的なアプローチをしているなとは思いますね。
向井:映像と言いましたが、映画の瞬間の場面、残像を観ているようだなというのは、よく感じていました。それから、ダイアローグで揺さぶっていくなかで、振り返ると、形が残っていたり、道が残っていたり……とおっしゃいましたけれど、その揺さぶりのなかで、おそらくどちらかに決めようと思う瞬間があると思うんです。だいぶ抽象的になってしまいますが、それはどういう体験なのでしょうか? 今回のプロジェクトで言うと、「きわ」みたいなものに見極めをする何かというか、こういう揺さぶりのなかでこういう形になっていくんだと見える瞬間があると思うんです。そういったことは、芹沢さんにとってどういう体験であったのか、どういったところから見極めて、際立たせていっているのでしょうか。
芹沢:かなり偶然の要素が多いと思いますが、今おっしゃっていることは、結構本質的で、大事なことのように、僕自身は思っています。
ちょっと話が飛ぶようですが、基本には生物のやり方というか、生命がどのように進化してきたかということがあるのではないでしょうか。生命進化のプロセスと、僕が思っているようなことが、実はすごく関係しているというか、一致していると思うんです。例えば、卵子に精子が入って、一個の均一な細胞が分裂を繰り返し、ある段階でそれぞれの細胞の役割が決まっていきますよね。その、細胞分裂している卵について、どの時期ならば切り取って、別の場所、例えば、本来はお尻になるはずだったものを頭のほうへ移植したときにどうなるのか。頭からお尻ができてしまうのか、それとも、細胞間でコミュケーションを行なって、ある段階までは融通を利かせて、きちんと頭になるのか。ここで二つに分かれて、また二つに分かれて、これとこれも二つに分かれて……と、バイファケーション *1 を繰り返して、シャワーみたいにワッと広がっていったとしても、あるところで、引き返し不可能、取り替え不可能になるときが出てくるわけです。生命的なプロセスでは、反応がずっと起こることで、さまざまな可能性が出てきます。その要所要所の分岐点に関しては、分岐の記録が残っているだろうと考えられています。英語で「宗教」は「religion」と言います。そのもとになったラテン語が「religio」。「religio」とは、「根源に戻りうる」ということ。つまり、道を引き返して、「origin」のところまで行き着くっていう言葉だということを、ある本で読んで、すごく納得しました。これは、個別の宗教の話をしているのではなく、ある一つの「origin」というか、元のものへ連なっていく記憶のようなものが、我々のなかには残っている。海のなかで発生したものの、現在では陸上化した我々みたいなものでも、胎児の段階ではえら呼吸をしています。それが消滅して、肺呼吸の器官ができてから生まれてくる。合理的に考えれば、人間は、陸上で酸素環境のなか生きていくわけなので、昔の記憶というか、今は使わない機能をわざわざ一度発生させて、何回もそれを繰り返さなくてもいいのではないかとなります。でも、進化の最前線でいつも使いながら展開しているようなことに関しては、合理的ではないから今までのデザインをご破算にして0から設計し直す、なんてことはできず、ここまで来ている。筋肉疲労もそうですよね。今も自分の体のなかで働いている小さな細胞たちの、酸素燃焼が追いつかなくなってしまったとする。そうすると、ある段階で発酵の過程が働き出し、乳酸がつくられてしまい、筋肉疲労が出てきてしまう。酸素燃焼が手いっぱいになってしまったとき、酸素燃焼以前に獲得していたプロセスが発動してしまうわけです。だから、メモのように、おぼろげな記憶というものが自分たちの体のなかに内蔵されているというか、蓄積されているんだろうと思っています。それは、我々の頭で理解することは、たぶんできないのではないか。我々の体の中では、さまざまな小さい微生物や化学物質が共生しています。ウイルスと言えば、今はみんなが恐れていますが、我々の進化では必要不可欠な働きをしてきたらしい。すべてが関係し合い、相互に影響し合っている。そういう世界の見方をしてみると、自分のなかにある「origin」のようなものにフラッシュバックしていく。細かく全プロセスを覚えているということではなく、要所要所で痕跡が残っている。生命的な記憶の形というものはあるんじゃないか。文字列で書けるような話ではないですが、化学的な記憶が、自分の体のなかに何らかの形で残っているんじゃないか。デジタル的な考え方が好きな人は、言語的な意味での記憶が残っているんだと思うだろうけれど、それもある意味合ってはいると思います。ゲノムの解析が進んでいったときに、いつかはそういうことが突き止められるのかもしれないですが、でもそれは、非常に限られた遺伝情報的な基本設計図でしょう。僕自身、最初に数学の勉強をしていたこともあって自然科学に大きな影響を受けているのですが、文化人類学者のグレゴリー・ベイトソン *2 や、発生生物学者のコンラッド・ウォディントン *3 、それから天体物理学者のエリッヒ・ヤンツ *4 や化学者のイリヤ・プリゴジン *5 などの考えに大きな影響を受けています。
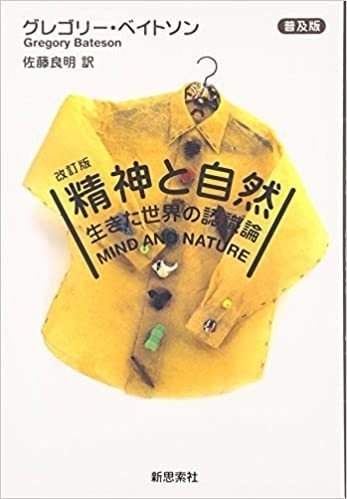
2006年、新思索社

1986年、工作舎

1980年、工作舎

1984年、みすず書房
ウォディントンは「エピジェネティクス」*6 、つまり、遺伝子は機械の設計図ではなく、あるきっかけであとから遺伝子の働きが発現していくような過程について述べました。それを説明するために「エピジェネティック・ランドスケープ」という概念も考えました。山の上のほうに球があり、それがコロコロと坂を落ちていく。性別を例に出せば、山の上にある球があっちに落ちるか、こっちに落ちるかで、男性になるか女性になるかが決まっていく。形態形成場です。そこでは、球が、あるところを越えると引き返しがつかなくなり、形が決まってしまう地点がある。その分岐点ではすごく偶然の要素が入ってくるのですが、それがすぐにも必然となり、偶然と必然がダンスをしていくというか、手に手を取って、ユラユラユラユラと世界が形成されていく。この考えにすごく共感したことを、今、思い出していました。僕には機械論的な世界ではなくて、生物や生命的な世界観というものに対する共感や考え方が染み付いているんです。この引き返しのつかないあるポイントについては、川の流れも想起できます。川幅が広くてほとんど流れもないようなところもあれば、滝のようにドオッっと落ちるところもある。流れが遅いところではいろいろな方向に進めますが、川が狭まってくると選択の幅もなくなってくる。急流ではなすすべもなく流れ落ちていく。つまり、あまたある可能性から何かを選んだ瞬間です。そういうイメージの仕方は、僕が映像的と言われる所以かもしれないですね。
我々はいつも、生成の現場にいるわけです。わたしが環境に働きかける、そうやって未来を切り拓くのだと言う。しかし、そもそも「わたし」とは何なのか? 「わたし」と周囲の環境は、そんなに明確に分かれているものなのか? 周りの環境というけれど、そこには他の生き物たちがごまんと生きている。そのごまんといる「わたし」が、それぞれの自分の環境に働きかける。しかも、人間の「わたし」について言っても、実は、ものすごくたくさんの生命の集合体ですよね。今ここにいる「わたし」も「あなた」も、微小な生命たちの集合体です。だから私たちは、気が遠くなるほどの数の生命体や生命現象の渦のなかにいる。さっきウイルスの話が出ましたが、ウイルスは生命かどうか、いまだに議論されています。一体どこからどこまでが生命なのか、そんなことを言い出したら、すべてが切れ目なしにつながっていますよね。確固とした個体というより、生命現象と見た方がわかりやすい。ある程度主体を持って出来上がっている、人間や猫のような、ある一つの個体的なものが「じゃあ俺はこういうふうにしよう」と何かをしようとしても、他にもいろんな生物個体がいて、それらがそれぞれに「俺はこうしよう」と思っているわけです。邪魔するやつも、一緒に組んで何かしようと言うやつも出てくる。そうすると、「環境」と言われているすべてが、ユラユラユラユラ揺れ動く。そしてとてつもない偶然も加わりながら、ユラユラと未来が生成されていく、そんな未来観を僕は持っています。
僕は建築を出たあと、日本でアセスメントというものが導入される頃に環境計画のほうへ進みました。ある一つの行為が環境にどのような影響を及ぼすかということ(環境アセスメント)について、考える現場にいたんです。その頃の流行りとして、予測とか未来予測という言葉がすごく身近にありました。職場での問題意識もありましたので、未来や予測、予兆といったことに関して、いろいろと考えていました。これは蛇足になりますが、60年代で都市計画について考える際、時々「エディプス効果」ということが言われていました。これは、オイディプスの神話が元になった言葉で、「不吉な予言を避けようとした結果、そこに行き着いてしまう」ことを指します。未来を見るのは難しいなあと思ったことを思い出します。
///
*1 バイファケーション
“Bifurcation” 二つに分かれること、分岐点などの意。
*2 グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson、1904年~1980年)
イギリス系アメリカ人の文化人類学・社会科学・精神医学等の研究者。統合失調症患者らの原因と症状の説明のため「ダブルバインド理論」を提唱したことで知られる。
*3 コンラッド・ウォディントン(Conrad Waddington、1905年~1975年)
イギリス出身の発生生物学者。システム生物学や進化発生生物学の基礎を築いたとされる。
*4 エリッヒ・ヤンツ(Erich Jantsch、1929年~1980年)
オーストリア系アメリカ人の宇宙物理学者。70年代のヨーロッパの社会システム設計運動などで知られる。
*5 イリヤ・プリゴジン(Ilya Prigogine、1917年~2003年)
1917年生まれ、ロシア系のベルギー人の化学者・物理学者。非平衡の熱力学システムの研究である「散逸構造論」で、1977年にノーベル化学賞を受賞している。
*6 エピジェネティクス
1942年にウォディントンによって提唱された「DNA配列の変化を伴わない、細胞分裂後も継承される遺伝子発現あるいは細胞表現型の継承的変化を追究する学問領域」の呼称。
///
