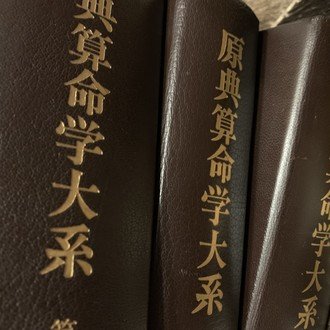5/23 「6種類・ 6通りの害」の構造と理解① 立体五行をベースに害を捉える
位相法条件ごとの「前進」について説明したついでに、本日は、「害」について改めてここで整理しておきます。
「害」というのは、「気と体」が不自然に融合する…という現象を引き起こす位相法条件で、その「気と体」が不自然に融合することによって「害」が成立する「十二支の組み合わせ」は全部で6種類ありますが、
同じ、「気と体」が不自然に融合する組み合わせでも、
その「気と体」が不自然に融合する組み合わせによってどんな現象が引き起こされるのか?というのは一律ではありません。
もちろん、昨日ご説明したとおり、「害」というのは、どの組み合わせであっても、
〇思いどおりにならない出来事が起こる
〇想定どおりに前進できない
〇その結果としてストレスフルになる(ストレスフルな現象が起こる)
…であるには違いないのですが、実は、その、
「思いどおりにならない」というその対象は、害を構成する地支の組み合わせによって異なりますし、
「ストレスフルな現象」というそのストレスの原因も、害を構成する地支の組み合わせによって異なります。
つまり、害には「6種類・ 6通りの害」があり、それぞれに異なることについて、
〇思いどおりにならない
〇想定どおりに前進できない
〇その結果としてストレスフルになる
…ということが起こるものであり、
本日は、その「6種類・ 6通りの害」についてご説明いたします。
さて、以下、「6種類・ 6通りの害」についてご説明するのですが、
その前に、この害の構造を理解するために、一つ大事なことを書いておきます。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?