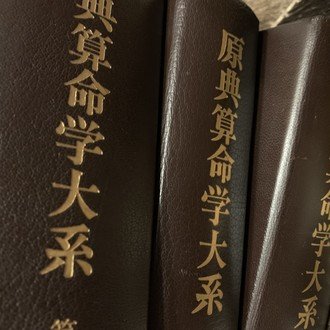6/29「福運・貧運」の事例② 守護神帝王+天将星、福の神を持つ福運の命式
「福運」と「貧運」の続きです。
引き続き、事例をとおしての説明です。
概念をもって理解する、
構造をもって理解する、
…ということはとても重要なのですが、
概念や構造を頭の中で理解しただけである場合、
「壮大な勘違い」につながることもあるので、事例をとおして説明しています。
昨日の後半では、
「日干が剋す」場合の日干(自分)の側の苦しさについて踏み込んだ説明をしましたが、
例えばその「日干が剋す」ということの意味を、構造だけで理解しようとすると、
自分が経験したことのある構造でしか理解することが出来ないので、
「圧倒的に強い立場」というものを体験したことがない人は、
ときに、「日干が剋す」という現象を、頭の中で想像して、
「日干がやりたいほうだいに出来る」=思い通りの性質発揮が出来る
…と解釈する方が少なからずおられるのですが、
「日干が剋す」、つまり「相手をやりこめる」というのが本質的にどういう意味かが分かると、
それは、「身動きが取れなくなる」ことを意味するのだということが理解できる、
つまり、構造的な理解だけだと、
自分の経験や想像の範囲を超えられないこともあるのですが、
事例によれば、その「自分の経験や想像の範囲」超えることができるので、
事例による説明が必要なのだということです。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?