
月経卒業!その後もイキイキ生きるヒント
こんにちは!
性教育認定講師/産業保健師の🦒です。
前回は『ピルと黄体ホルモン療法』
について、超長々書きまして、
お付き合い頂いた方には....
もう感謝しかございません😭!
さて、今回はその続編!
『月経卒業前後の身体の不調をコントロールする方法』
です。
俗に言う、【更年期症状】
辛い月経の煩わしい日々から
いざ!サラバ!👋✨
と思っていたら....
実は次の不調でとても辛い想いをされる方も
いらっしゃいます。
今日は、その不調と上手に付き合うため
元婦人科看護師🦒からお話をしたいと思います。
では、参りましょう~
1.そもそも【更年期】っていつですか?
最近、生理の周期が乱れてきて....
そろそろ閉経が近いのかしら?🤔
疲れが取れなくてイライラもするし…
これって「更年期」の症状?😱?
と思われている方!
可能性があるかもしれません🦒....
【そもそも更年期の定義とは?】
⇒「女性の加齢過程における生殖期から非生殖器への移行期で、加齢に伴い卵巣機能が衰退し始め、やがて低下安定するまでの期間」
(日本産婦人科学会)
⇒閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた10年間を「更年期」という
(日本産婦人科学会)
⇒英語では 「menopause」 の他に「climacterium」「climacteric」 という単語で表され、
『重要な転換期』という意味もあるそうです。
『生殖機能がその役目を終える前後』
というのが一番しっくりくるかもしれません。
新たなステージへの『転換期』と捉えると非常に前向きな表現で素敵だなと思いませんか?
ただ、冒頭でもお話した通り、その時期特有の不調があります。
更年期に現れるさまざまな症状の中で
・他の病気に伴わないものを「更年期症状」
・症状が重く日常生活に支障を来す状態を「更年期障害」
と言います。
では、またまた今回もホルモンに目を向けながら体の変化について
一緒に学びを深めて行きましょう!🦒
※ちなみに、閉経の定義ですが、
「連続して12か月以上の無月経」
と定義されています。
閉経間際は、
急に月経周期が早まったり、
逆に3-6ヵ月飛び飛びになったり、
色々な変化を経て
丸1年月経がなくなると『閉経したんだ』と後から気付くことが殆どです。
ですので、
明確に「いつ閉経したのか」
をハッキリ覚えている人って実は、なかなかいないのですよね~🦒
2.お世話になりました!ありがとう!エストラジオール!いよいよ閉経です....
閉経の前後がどうやら「更年期」という事は、
皆さんもすでに十分ご存知かと思いますので、
ここでは、ホルモンの動きがどのように変化し、その結果、どのような心身の変化があるかを見ていきます!
サクッと次に参りましょう🦒!
更年期障害の主な原因は女性ホルモン(エストロゲン)が大きくゆらぎながら低下していくことです。
下記の図で、更年期前後のホルモンバランス(エストロゲンの動き)のイメージを見てみましょう!
(下記の図は、第一三共様のHPよりお借りしています)

今までのnoteでもお話していますが、
卵巣に眠っている卵子が目覚め、排卵に向けて成長する時に
エストロゲン(今回はエストラジオール:E2と表現します)というホルモンを放出します。
ただ、卵子は産まれてから増えことなく減り続け、
小児期には約200万個あった物が閉経の頃には1000個程度になってしまうのです。
そうすると、毎月排卵を繰り返し、エストラジオール(E2)を大量に放出し続けて来た身体から、
エストラジオール(E2)の量は減り、閉経後は、ごく少量のエストロゲン(主にアンドロゲンから産生されるエストロン:E1)で生きて行かなければならなくなります。
(勿論、E2も僅かにはありますが、中心はE1に置き換わって行きます)
※急にE2とかE1とか出てきてごめんなさい!
ホルモンのnoteでも少しお話をしましたが、エストロゲンは3種類あり、それぞれに名前があります、
E2は卵巣の卵胞から、E1は副腎皮質から産生されるアンドロゲンから産生されます。エストリオール(E3)は、その2つを肝臓で変換して作られます。
⇒ここに関してはサラッとそうなんだな~で良いかなと思います!
この後の、治療に関するところでまた出てくるのですが、何となくでOKです!
話を戻して、エストロゲンの働きに関して少し復習を入れていくと、
【エストロゲンの心身への良い働き】
・女性らしいからだ作り
(肌のツヤを保つ、丸みを帯びた体形になる)
・妊娠のための準備をする
・自律神経を安定させる
・骨を丈夫にする 等
です。
更年期に差し掛かると、これらのエストロゲンの働きが低下(欠乏)し、
様々な不調をきたしていくのです。(下記図も第一三共様より)

更年期障害は、その上に
・加齢などの身体的因子
・成育歴や性格などの心理的因子
・職場や家庭における人間関係などの社会的因子
が複合的に関与することで発症すると考えられています。
勿論、ここまで読まれた方はもうご存知かと思いますが、
閉経に近しい状態になれば出る症状なので、
他の方より、卵巣機能が早く役目を終えてしまう「早発閉経」の方や
がん等の治療によってエストロゲンを押さえている方も
同じような症状が出ます。
今回は一般的な、年齢に伴う変化について、その対策を紹介していきます🦒
3.これって「更年期症状」?
さて、で前項を踏まえ「更年期症状」の中身に入って行きます!
【更年期症状】
⇒更年期に自覚される症状のうち器質的疾患の裏づけに乏しい不定愁訴を主体と症候群(日本産科婦人科学会の定義)
🤔!ん?
ですよね🦒!
更年期障害は人によって症状がさまざまです。
下記に主な症状を書きます!
※更年期障害とよく似た、まぎらわしい症状もあります。
中には、重篤な病気に発展する恐れのある症状もあります。
セルフケアは診断が出てから!
まずは病院で正しい診断をしてもらうことが大切です。
では、見て行きましょう!

『うわっ!キツイ!』
『そうそう、聞いたことある!』
という方多いですよね。
それを聞いて、不安になる方も沢山いらっしゃるかもしれません。
実際に、エストロゲンさんという強力な味方が激減すると、
それはそれは、身体にきそうですよね。
そして、更年期に差し掛かった年齢では、家庭でも職場でも、様々な変化や立場の重みがある時期でもあるのではないか?
ここを元気に過ごす方法では「婦人科」の助けを借りることも大切です!
4.婦人科で行われる『更年期』の検査
🤔『治療と言ってもどのタイミングで受診したら良いのか。…』
という方!沢山おられるかと思います!
元婦人科看護師としては。
🦒『辛かったら、タイミングなど気にせず気軽に相談にきて欲しいですね』
と言いたい所ですが....
一般的には、
「その症状が日常生活に支障をきたす」
かどうかがKEYになってきます。
ですので、勿論ある程度自分で対応出来るもの(生活習慣の改善などで)は、ご自身でセルフケアをして頂ければ良いと思いますし、
『そろそろセルフケアも限界だわ』
という時にご相談されても良いかと思います。
(※できれば、不調が2週間~1か月続いたら受診して頂くのが良いとは思います。別の病気の可能性もあるので変にインターネットでサプリメントを購入するなら受診されることをお勧めします。)
前置きが長くなりました💦
では実際婦人科では、どんな検査をして、どんな治療をするのでしょう?
【初診時に行う主な検査】
(私の勤めていたレディースクリニックの場合)
・問診(ここで、簡略更年期指数〚SMI〛もチェックします)
〚SMI〛は更年期の症状をチェックするリストです
(下記の図がそのリストです)
この他にも、「日本人女性の更年期症状評価表」等もあります。
他に問診では、
⇒困っている症状や、どんな時に強くなるのか、いつからなのか、月経周期(基礎体温が数ヶ月あるととってもありがたい!),お仕事やご家庭の状況等伺っています。

・エコー検査(採血の前にする場合が多い)
⇒子宮や卵巣の状況を確認
・採血
ここでは、主に
・FSH:卵胞刺激ホルモン
・E2:エストラジオール
・P4:プロゲステロン
(・LH:黄体形成ホルモン)
・甲状腺機能を測定
・貧血状態の確認
(・全身状態の確認の為に、血液一般を測定する場合も)
その他医師が必要と考えた項目
上記の検査を行い、総合的な判断を医師がします。
繰り返しになりますが、
『更年期症状?』と思っていても、
実は…下記のような病気の場合もあります。
ですので、是非症状は自己判断せず、まずは産婦人科で相談してください。
【更年期障害に似た症状を持つ病気の例】
のぼせ、ほてり→バセドウ病、高血圧、心臓病
頭痛、めまい→高血圧や脳の病気
動悸、息切れ→心臓病
めまい、耳鳴り→耳鼻科系の病気、メニエール病
また、重い「うつ症状を伴う更年期障害」と更年期に発症または顕在化した「うつ病」とを鑑別することは難しく、時には精神科医師との連携が必要になってくる場合もあります!
必要時は、それぞれの専門医が連携して治療を行います!
5.婦人科で行われる『更年期』の治療
では、産婦人科医師が『更年期症状』緩和の為に、
実際どのような治療をしているのでしょうか?
これを知ることで、
🤔「そうか、これは婦人科で相談しても良い物なのね」
🤔「こんな方法があるのね、婦人科行こう!」
とハードルが1mmでも下がることを🦒は期待しております。
では、治療の実際を見て行きましょう!
『更年期症状』の治療にも、ホルモンが使われます!
先日のnoteでは、ピルと黄体ホルモン療法についてお話しました。
そう....今回の『更年期症状』の治療にもホルモンを使う事があります。
では、早速治療のスタートです!
『更年期障害』は生活習慣の改善以外に
主に3つの方法があります。
①ホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy)
➁漢方薬による治療
③抗うつ薬や抗不安薬による治療(精神科で行う場合も多い)
①『更年期障害』のホルモン治療
:ホルモン補充療法(HRT呼ばれることも!)
これは、もうnoteを読んでいただいているので、大体想像がつくかと思います。
そう。失われた、エストロゲン(ここの場合はE2)を補うという方法です!
(※エストロゲン単独で使用すると子宮体がんのリスクを上げてしまうので、黄体ホルモンと併用します。)
もちろん、自然の摂理に反して大量に補ってしまうと、逆効果なので、
高い効果を得ながらリスクを最低限に抑える「最少有効量」
そうそう、必要最低量の薬を用いることが推奨されています。
この治療は、子宮の有無によって方法が異なりますが、細かい部分はさておき、ピル以外のどんな治療薬(ホルモン)を使うのか少し見てみましょう!
ごく一般的に、方法は2タイプの薬の使用方法があります。
①周期的投与法…
エストロゲン製剤と一緒に、ある一定期間だけ黄体ホルモン製剤を使用する方法です。
(イメージとしては、ピルですが、含有されているE2の量が全然違います!)
➁持続的投与法…
エストロゲン製剤と黄体ホルモン製剤、もしくはエストロゲン製剤を毎日使用する方法です。
(下記の図はバイエル様からお借りしております)

ここで使用される、エストロゲン製剤が特徴的で面白いので見て行きましょう!
【ジェルタイプのエストロゲン製剤】
ル・エストロジェル 0.06%(資生堂) 写真はPMDA様よりお借りしました。
そうそう!なんと『資生堂様』の製品です!
これ、医師が必要と認めた場合は、保険が効きます。


上記のように、医師から指示のあった量を腕などに塗って経皮吸収させます!
因みに、㈱ポーラが作っている【ディビゲル】なんていうのもあります!
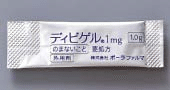
2つとも化粧品を作っている会社様ですので、
ちょっとホルモン療法が身近になったら良いなと思います🦒♪
また、夏はジェルが冷たくて心地よいのですが、
冬はちょっと。。。。という方向けに、
「エストラーナテープ」や「メノエイドコンビパッチ」があります。
これはシールタイプの、ホルモン剤でホルモンを経皮吸収させます。
※「メノエイドコンビパッチ」は黄体ホルモンも入っているので、
1枚2役です🦒!
そして、この2つは『久光製薬』様が作っています!
張り薬王道の会社様ですね~(下記パッケージです)


通常は、こういったエストロゲン製剤に経口で黄体ホルモンを使用したり、先日お話したミレーナを併用したり、色々な方法で「最少有効量」のホルモンを、医師の管理下で使用します。
4.ホルモンを補う事で生じる副作用
もちろん、お薬を使うので副作用もあります!
医師の管理下で使用すると同時に、確認しておきましょう。
【HRTの副作用】
・不正性器出血
・乳房痛
・片頭痛
もし副作用がでた場合は、投与方法や投与量で調整ができます。
【HRTの影響で上昇する可能性がある「がん」】
・乳がん / 子宮体がん / 卵巣がん があります。
ホルモンを足す治療ですので、それにかかわるがんが増える可能性があることは、十分に予想できますよね。
ですが、乳がんに関しては、米国の研究で下記のような結果が出ています。
(非常に有名な研究で、下記の図は分かりやすさから『久光製薬』様のHPよりおかりしました)

乳がんになりやすい要因として、HRTよりも
・乳腺の病気にかかったことがある
・乳がんになった家族がいる
・最初の出産が35歳以上
・出産経験がない
といったことのほうが、乳がん発症の危険性が高いことが読み取れます。
また、日本では、2004~2005年秋に厚生労働省研究班による調査が行われ
・過去10年間以内に乳がんの手術を受けた45~69歳の女性と
・同世代のがん検診受診者の中で乳がんではなかった女性
に対し、HRTの経験など21項目のアンケート調査を行ったところ、
・前者でのHRT経験者は5%、
・後者では11%
であり、乳がんではないグループの方に約2倍のHRT経験者が多いという結果が出ました。
(下記の図)

しかし、冒頭でもお話したように、ホルモンを使用するリスクは全くないわけではなく、HRTのリスクやデメリットについては、現在も世界と日本で再解析が行われています。
使用にあたっては、十分に医師と相談し、心配を残さないように使って行きましょう。
もちろん、ホルモンを使うので、ピル同様使用できない方もいらっしゃいます。
次は、そういった方と、そういった方々が、他の方法として使用する
【漢方療法】について見てい行きましょう!
5.HRTができない場合
ホルモン治療により悪化する可能性がある病気をもった人には、
原則的にホルモン補充療法は行えません。
例えば
・乳がんの方
・子宮体部がんの方
・血栓症の治療薬を処方されている方
・肝障害のある方
・原因不明の不正出血のある方
・脳卒中やその他の動脈硬化病変の既往が有る方 等
また、次の疾患に関しては医師の判断の下で慎重投与となります
・子宮筋腫/子宮内膜症/子宮腺筋症の既往、
・肥満や糖尿病、高血圧の有る方 等
上記にあてはまる方は、ご自身でのセルフケアなども慎重に、
なるべくかかりつけ医を持ち、定期的に相談をしながら
『更年期』とお付き合い頂く事が良いと思います🦒
では、皆さん気になる【漢方療法】に参りましょう!
6.『更年期症状』や『更年期障害』で使用する漢方療法
『漢方薬』という言葉の方が、『ホルモン剤』というモノよりもマイルドに感じられる方も多いかもしれません。
実際に、婦人科のみならず日本では多くの診療科で『漢方薬』が保険適応で処方されています。
漢方薬の中でも『更年期』に適応のモノ、
と婦人に見られる更年期特有の生理現象を含んだ概念の『血の道症』
というモノの適応で処方される薬があります。
日本産科婦人科学会のガイドラインでは
『更年期障害』『血の道症』の適応を持つ漢方
として下記のモノが挙げられています。
え?もう、呪文みたいですって?
私も漢字が全く読めないので、ツムラ様のHPで検索しました🦒!
カタカナつけても読めないです(笑)
さすが中国〇千年の歴史!
では、詳細を並べましたので....
※( )内がツムラ様の漢方番号です。ツムラ様のHPで数字で検索可能です。
・(11)柴胡桂枝乾姜湯(サイコケイシカンキョウトウ)
・(23)当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)
・(24)加味逍遙散(カミショウヨウサン)
・(25)桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)
・(57)温清飲(ウンセイイン)
・(63)五積散(ゴシャクサン)
・(67)女神散(ニョシンサン)
・(71)四物湯(シモツトウ)
・(105)通導散(ツウドウサン)
・(106)温経湯(ウンケイトウ)
・(113)三黄瀉心湯(サンオウシャシントウ)
・(124)川芎茶調散(センキュウチャチョウサン)
・(125)桂枝茯苓丸加薏苡仁(ケイシブクリョウガンカヨクイニン)
日本産科婦人科学会のガイドラインでも、こんなに沢山の漢方が紹介されています。
あの手この手で戦えそうですね!
太字の3つ
・(23)当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)
・(24)加味逍遙散(カミショウヨウサン)
・(25)桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)
は『女性の3大処方』と言われています。

その他、日本漢方生薬製剤協会様のHPには上記の図がありました!
漢方....奥深いですね。
7.まとめ
また、今回も横道にそれながら『更年期』に関するお話をしてまいりました。
『更年期』に差し掛かった方、私を含めこれから『更年期』と向き合っていく世代の方々、
【辛い】のイメージがホルモン療法や漢方療法で対処出来る!という安心につながって頂くと嬉しいです。
また、どのnoteでも必ず書いていますが、サプリメントも含めできる限り自己判断ではなく、【かかりつけ産婦人科医】と相談して一番安心安全な方法でご自身の健康を保って頂きたいと思います🦒
漢方はサラッと触れましたが、
次回以降で『女性医療と漢方』については深めに触れてみようと考えています。
(なんせ、歴史も長いですし奥も深いですしまだまだ勉強が足りないので…。)
また、精神症状に関する件は、やはり難しいケースなので、今回は飛ばしております。
餅屋は餅屋へ....医師同士も連携しております!
いつも、最後までお付き合い頂き感謝感激です!
引き続き、よろしくお願いいたします🦒
※そろそろ『男性不妊』を書こうと思っています!
お楽しみに🦒!
参考文献
産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2020 (日本産科婦人科学会)
はじめての婦人科看護 MCメディカ出版
婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック 第2版 学研
ファルマシア くすりの科学
2020年3月 特集「Common Diseaseの漢方療法の現状」
