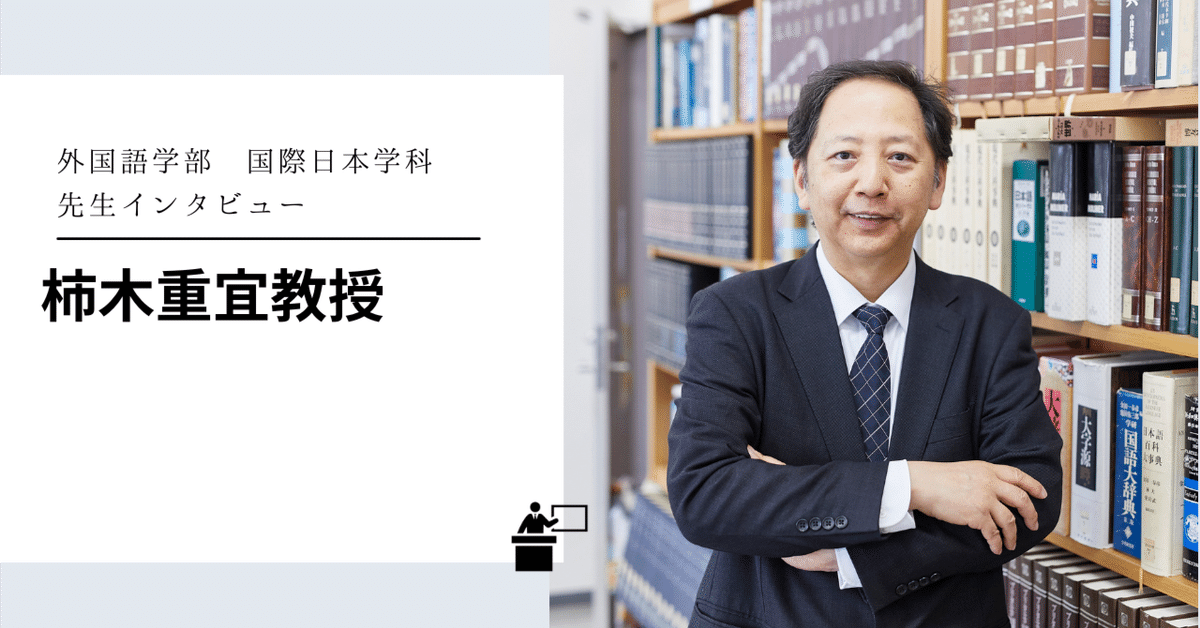
人との出会いを大切に研究活動を推進。日本語の起源を求めて
2024年4月に開設する国際日本学科に所属する(予定)教員にお話を伺う「先生インタビュー」。研究の内容はもちろん、先生の学生時代や趣味の話まで、幅広いお話を伺います。
第4回は言語学、日本語学がご専門で、国際日本学科の学科長に就任予定の柿木重宜教授です。
柿木重宜教授プロフィール

柿木 重宜(Kakigi Shigetaka)教授
大阪外国語大学(現・大阪大学)モンゴル語専攻卒業。同大学大学院修士課程 外国語学研究科 東アジア語学専攻修了。一橋大学大学院博士後期課程 社会学研究科(社会言語学)単位取得退学。博士(言語文化学)。滋賀短期大学教授、同大図書館長などを経て、2016年より、関西外国語大学外国語学部教授、関西外国語大学大学院外国語学研究科言語文化専攻教授(兼任)。2024年4月より、外国語学部国際日本学科学科長に就任予定。
日本語の起源を求めて
柿木先生が研究分野である言語学、日本語学の世界に興味をもったの高校生のとき。
教科書に掲載されていた大野晋(1919-2008)の「日本語の起源」という文章を読んだのがきっかけだった。
大野 晋(おおの すすむ)
言語学者・国語学者。東京の生まれ。橋本進吉に師事し、上代仮名遣いの研究をすすめる。また、日本語の起源や変遷についての考察、本居宣長の研究などでもすぐれた業績をあげた。著「日本語練習帳」「日本語の起源」「日本語以前」「日本語とタミル語」など。

柿木:朝鮮語やタミル語などが日本語の起源だと考えられるといったようなことが書かれていたのですが、「そんなに簡単にわかることなのだろうか」と疑問を抱いたんです。
――書かれてあることに感銘を受けたとかではなく、批判的な目で読まれたんですね。
柿木先生:面白い!と思う一方で、本当なのかな?と純粋な疑問をもった感じで。教科書には他にも有坂秀世、池上禎造、橋本進吉といった言語学者、日本語学者の文章も載っていて、「こんな世界があるんだ」と興味をもちました。
大阪外国語大学(現・大阪大学)モンゴル語専攻へ

言語学、日本語学に興味をもった柿木先生は、比較的日本語と近い言語といわれているモンゴル語の古語について研究すれば、日本語の起源についてわかるのではないかと考え、高校卒業後、大阪外国語大学(現・大阪大学)モンゴル語専攻に進む。
また同専攻を選んだのには、もう一つ別の理由があった。OBに柿木先生が大好きだった作家の司馬遼太郎がいたのだ。
――司馬遼太郎の作品は昔から読まれていたのですか。
柿木先生:兄が司馬先生の本をよく読んでいて、兄の本棚にあったのを中学生のときに手に取ったのが最初です。歴史好きだったこともあってすぐにハマり、高校生になる頃には既刊の司馬先生の小説はあらかた読了していました。
――憧れの司馬先生も通われていた大学というのも大きなファクターになった。
柿木先生:司馬先生が出身であったことも大きかったです。司馬先生自身も日本の起源に関する本も書いていますしね。
日本語の起源を解き明かすのは不可能!?

日本語の起源についてはタミール語説やアルタイ語説など諸説あるが、日本語だけを研究しても真相はわからない。その謎を解き明かすためのヒントとして、大学ではモンゴル、満州、ツングースなどアルタイ語系の言語の研究に取り組んだ。
日本語がどのように形成されていったのかを追究するのは魅力的で、楽しい作業だったが、一方で文献などを頼りにした既存の研究法では限界があると感じた。
柿木先生:まず古い文献がありません。ヒッタイト語の粘土板文書をはじめ、インド・ヨーロッパ語族の言語には紀元前1000年以上前の資料が比較的たくさん残っています。一方、日本語は『古事記』『日本書紀』が伝存する最も古い史書の1つですが、成立したのは700年代です。それより古いものでは、銘文が刻まれている稲荷山古墳出土鉄剣がありますが、年代は471年が定説とされています。ちなみに、モンゴル語の一番古い資料は1225年です。
――言語学的な観点から見たら、紀元後のものはまだまだ新しい。
柿木先生:弥生時代までくらいまでは起源を辿れると思いますが、それより先は、より古い文献か文字が刻まれた出土品が出ないと難しいでしょうね。ですので、日本語の起源を詳らかにするには、言語学だけでは難しいと感じています。
――学際的なアプローチが必要だと。
柿木先生:はい。人類学、血液学、遺伝学など他分野の方々とチームを組んで、多角的にアプローチしていく必要があると感じています。例えば、モンゴル系言語のブリヤート語の人たちと、日本人の血液を血液学の見地から分析したら非常に似た構造になっていたといったような、言語学とは別の観点からの科学的な分析が今後は重要になってくるでしょう。
――言語学的な側面からだけではダメだということがわかったときはショックでした?
柿木先生:逆に面白い!と思いました。大変ではあるけれども、学際的に研究すれば解き明かせると思ったので。学外の医学部などとの連携が必要なので、共同研究の体制を整えるのは簡単ではありませんが、いま手がけている仕事が一段落すれば、ぜひ取り組んでみたいと考えています。
日本語の国際性という観点からローマ字を追究
ローマ字を国字化しようとした言語学者・藤岡勝二

東京帝国大学文科大学言語学科の教授を務めた国語学の泰斗、上田萬年(1867-1937)。上田から同大の教授職を継承したのが藤岡勝二(1872‐1935)で、京都帝国大学教授の新村出(1876-1967)とともに、当時の言語学界の精神的支柱というべき存在であった。
日本語とウラル・アルタイ語族が似ていることを最初に指摘したのも藤岡の業績だが、『広辞苑』の編者としても有名な新村に比べ、藤岡の知名度は高くなかった。そんな彼の数々の功績に光を当てたのが柿木先生の研究だ。
実際にこれまで、
アルタイ諸語
国語、国語教育
母音調和
満州語の歴史
ローマ字表記
など、藤岡勝二が深くかかわった研究や事象について、数多くの論文を執筆してきた。
柿木先生:例えば、ローマ字の国字化に関する研究も断続的に行っていますが、ここにも藤岡勝二が深くかかわっています。1905年にローマ字団体を大同団結した「ローマ字ひろめ会」が結成され、藤岡はその創立以来の参加者であるとともに、彼の著書『羅馬字手引』はバイブルのような存在でした。
――西洋列強と伍していくために、漢字仮名交じり文に比べ世界により浸透しやすいローマ字を国字とするということでしょうか。
柿木先生:その視点を先鋭化させたのが、初代文部大臣の森有礼(1847-1889)が推進しようとした英語の国語化ですが、当時「漢字を止める」ことは統一の見解として認識されていました。例えば、1902年に国語調査委員会ができ、その資料に記された一つ目の項目が「漢字廃止」なんです。漢字の廃止は前提として、その上でひらがなとローマ字のどちらを採用するのがいいのかを調査するというのが最初に書かれています。

――その流れで、ローマ字の国字化も盛り上がっていた?
柿木先生:上述したローマ字団体の会員は最盛期で数十万人おり、大きな盛り上がりを見せていたようです。例えば、啓蒙活動の一環として発刊された『ROMAJI』という雑誌が、当時は産婦人科などにも置かれていました。今でいう週刊誌やファッション誌と同じような扱いで読まれていたということです。
――それだけ一般にも浸透していたローマ字が、結果的に広まらなかったのは?
柿木先生:運動が下火になったのは中心的存在だった藤岡の死去(1935年)が大きかったと考えられます。ちなみに、ローマ字は日本式とヘボン式があり、藤岡は後者を押していましたが、1937年に内閣訓示で日本式ローマ字が採用されたことで、完全に運動が縮小化していきます。
「ローマ字の国字化」の可能性について考察

日本語を母語としない日本語学習者にとって大きなハードルとなるのが、文字の問題だ。日本語には、「漢字・ひらがな・カタカナ」という3種類の文字があり、1つの文章で使い分けされているわけだが、一言語で複数の文字を使っているのは世界的に見ても異例といえる。
それが日本語が世界に浸透しない原因のひとつと考えられ、明治維新後の日本政府も「日本語の国際化」をめざしてローマ字の国字化をめざした。
ただ、この事象は100年以上も前の出来事ということだけではなく、今日的な問題もはらんでいる。
柿木先生:日本で働く外国人材が増えてきています。どの現場でも日本語能力が問われるのはもちろんですが、「ある程度話せるけど文字は書けない」という外国の方が少なくありません。彼らの立場になると、日本語がローマ字で書かれてあると学びやすいし、現場にもよりスムーズに入っていけます。
――一方で、「文化」という側面から見るとデメリットも考えられます。
柿木先生:藤岡の時代にも反対する人はいました。「漢字」は世界に誇れる日本の文化ですし、ローマ字を国字化していれば漢字文化は廃れていったでしょうから、その意味では「漢字仮名交じり文」を残したメリットはあります。一方で、世界に開かれた言語にするという観点からは3つの文字の併用はデメリットであるわけです。実際、学術論文も日本語で書かれたものが世界で読まれることはまずありません。
――日本でも英語を公用語にしようとする動きが折々で見られますが、そこまで行かなくとも、「読み」が担保されるローマ字にすることで、日本語の国際性を高めるということですね。
柿木先生:少なくとも海外の日本語学習者の数は増えるでしょう。ただし、ローマ字を国字化すると「日本の文化」という側面からはマイナスなので、そのメリット、デメリットのバランスをどう考えるかですね。
ちなみに、「日本語を広く世界に広めるにはどうすればいいのか」について研究しようと調べ始め、その課題に最初に取り組んだうちの一人が藤岡勝二だったわけですが、当時の国民がなぜこれほど熱狂的に日本語のローマ字化を受け入れたのか、またどこまで本気で「日本語の国際化」を考えていたのかといったことを、研究活動を通じて解き明かしていければと考えています。
――国際日本学科では「英語で日本の文化を発信する」ことを一つの柱としていますが、「日本語をいかに世界に発信するか」という視点も面白いですね。余談ですが、石川啄木の『ローマ字日記』を読むのに苦労した記憶があるのですが、ローマ字だと読みにくさの問題はないのしょうか?
柿木先生:慣れが大きいので、習慣化すればスラスラ読めるようになります。ただ、仰るように一般の人々がどのような反応をしたのかを考える上でも、藤岡勝二の時代のローマ字運動を研究する意味があるのではないかと考えています。
司馬遼太郎に後押しされ、教員から研究者の道へ

柿木先生は、大阪大学(旧大阪外国語大学)大学院を修了した後、高校の国語の先生になろうと考えていた。
進路変更し、研究者をめざして一橋大学大学院博士後期課程に進むきっかけとなったのが、ご自身が敬愛されていた司馬遼太郎先生の存在だ。
――司馬先生とは、どちらで面識を得られたのですか。
柿木先生:私が大学院に在籍していたときに、モンゴル語専攻の同窓会があって、司馬先生が参加してくださったんですよ。会の後、司馬さんを含む数人で喫茶店に入りました。お会計の際、司馬さんから支払い役を命じられて1万円渡され、釣り銭の中から「お小遣い」と5,000円をいただきました。もったいなくて使えず、今も大事に実家に置いています。
――その後もやりとりが続いたのですか?
書面でのやりとりが何度かあり、「モンゴル仏典における古代ウイグル語の影響について」研究した修士論文が書き上がった際にもお送りしました。すぐに返信があり、お褒めの言葉をいただいて、その後、直接お会いしたときに「研究を続けてくださいね」と声をかけていただいて。


――尊敬する大作家の方からそんなことを言われると舞い上がってしまいますよね。
柿木先生:急きょ進路変更をして、博士課程に進むことにしました。実は教員採用試験も受かってたんですけどね。一橋大学を選んだのは、社会言語学がご専門でモンゴルについても研究されていた田中克彦博士というすごい先生がいらっしゃったから。今もつながりのある私の恩師の一人です。
――折々で出会われた恩師の存在が現在の研究活動につながっている。
柿木先生:本当に一期一会で、人との出会いに恵まれたと感謝しています。司馬先生、田中克彦先生以外に、私が言語学の道に進むきっかけとなった大野晋先生とも、後に『日本語の語源を学ぶ人のために』(2006年、世界思想社)という本の共著者に名を連ねることになります。高校時代にその著書に出会った研究者と本を書くことになるとは驚きでした。「出会い」の大切さを感じています。
高校生のみなさんも、人はもちろん、本でも音楽でもなんでもいいので「出会い」を大切に、そこから多くのことを学び、自身の成長の糧としていっててほしいですね。
《著書のご紹介》
これまでに日本語学の初学者向けの本を複数出版されており(一部研究書含む)、興味のある方は図書館などで手に取ってみてください。
さいごに

研究の話が中心になりましたが、柿木先生の趣味についてお話を伺うと、「中学、高校ではバレーボールに熱中し、前任校ではバレーボール部顧問を務めました。クラシックギターは13歳から始め、大学4年間取り組みました。高校時代の親友が能楽師をしており、能楽鑑賞も好きです」とのこと。
――能楽などは、国際日本学科の学びともつながりそうですね。
柿木先生:能楽師の友人には水面下で講師に来てもらえないかと相談していますが、何かの機会に講義をしてもらえたりするといいですね。私自身、今は時間がなくて観能できていませんが、30代の頃はよく京都の観世会館に足を運んでいました。
――それでは最後に、国際日本学科の学科長としてコメントいただけますでしょうか。
柿木先生:国際日本学科では、日本学、日本語教育学、日本語学、英語学といった学問領域を専門的に学ぶことができ、これだけのものが一つの学科として体系的に学べるのはなかなかありません。英語、日本語、さらには日本の文化、社会について勉強したい、興味がある、という方には最良の環境で学びが深められると思います。
――おっしゃるように、高度な英語スキルを身につけるとともに、その上で日本語や日本の文化、社会を幅広く学べるカリキュラムとなっています。
柿木先生:語学をはじめとする専門的な学問を学修するだけではなく、主体的に日本語や日本の文化を世界に向かって発信する方法について考えるのも国際日本学科の特色です。
幅広い学びができる本学科で、伝統文化から現代のマンガ、ファッションなどのポップカルチャーまで、自身の興味のある分野を追究し、得られたものをぜひ世界に向かって発信していっていただければと思います。一期一会の出会いを大切に、共に学んでいきましょう。
【国際日本学科・特設サイト】

