
北川眞也さん(三重大学人文学部准教授)前編・1 働かないですべてが欲しいーイタリア、反労働という叙事詩
オペライズモとは何か
杉本 北川さんが翻訳されたビフォ(フランコ・ベラルディ)さんによる本書のタイトルは『ノー・フューチャー─イタリア・アウトノミア運動史』(廣瀬純氏と共訳、洛北出版、2010)。文字通りセックス・ピストルズの曲からのものですね。
北川 パンクですね。まさに。
杉本 そのピストルズの曲のタイトルは『ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン』ですが、歌のキモは「ノー・フューチャー」という節。
北川 それを日本語タイトルにしました。廣瀬さんの案だったかな。
杉本 本も冒頭のほうで1977年はパンクが出現した年、ピストルズの時代、と紹介されますね。これは私の10代の気分そのものじゃないですか、という。
北川 あ、そうなんですか。
杉本 丁度パンクが日本に輸入されたときに聞き始め、ハマっちゃった人間なので。
北川 ほお。それは。
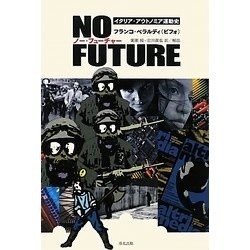
杉本 リアルタイムですね。いやでも、実際にこの本はかなり面白い。ですからこの本の作者である*ビフォ(フランコ・ベラルディ)という人への関心がぼくは先に生まれたんですね。で、このビフォという人は北川さんの専門の地理学では……。
北川 違いますね。ビフォは大学時代、哲学が専門です。
杉本 ちょうどその1977年にイタリアで運動が最高揚して、弾圧され、その77年でいちおう終結したアウトノミア運動の活動家であって。おそらくこの人ぐらいですよね?イタリアの「アウトノミア運動」というのがどういうものだったかということを系統的、継続的に語っている人は。
北川 イタリアではいろんな党派や立場の人がいます。本もいろいろありますね。
杉本 日本語になっているものでは…。
北川 確かにそうですね。まとまった日本語としては。
杉本 アウトノミア運動といっても、ほとんどの人はイタリアのこの運動は知られていないと思います。ぼくもこの本で初めて知りました。 実は原口剛さんに話を伺った際、テント村での活動を振り返った話をされて。そのなかで今後考えなくてはいけないと思うのは、テント村の住人というのは元々身体を張って労働をしてきた釜ヶ崎などの労働者の人たちが中心ですから、やはり労働者としてのプライドが非常に高い人たちであると。ただし、今後は労働者として生きていくことが難しい世代の人が増えてくるだろうし、そのことについて自分はまだ答えが出てないんだけれども、可能性としてはヨーロッパでスクウォッテング(空き家占拠)の運動などがありますと伺ったんですよね。私としてその延長でしばらく考えていたら。偶然この本の中でスクウォッテングのみならず日本のひきこもりにも言及している(「世界じゅうのひきこもりたちよ団結せよー日本の読者へ」)。
北川 書いてますね。
杉本 勘違いされている部分もたぶんあるかもしれませんけど、でも面白い。おそらくビフォさんの考え方と照らし合わせても、ちょっと類似的なものとしてひきこもりもあるんじゃないか。展望としてあるんじゃないかと思ったんですね。やや前置きが長くなりましたけれど、このビフォさんという人は非常に先駆的な運動にずっとかかわってきた人なんだと思うんです。1960年代から、しかも10代の頃から政治活動をしているわけですね。
北川 そうですね。14歳くらいでしたかね。
杉本 そのあたりの政治文化も興味深く、日本では到底考えられないような雰囲気ですけど。いまのイタリアはどうか分からないですが。まず彼もかかわった、「オペライズモ」の活動の話などからしていただけませんか。ビフォさんの思想の核としてもあるだろう、イタリアの戦後政治思想みたいなところから話していただければと思うのですけれども。
北川 わかりました。そうですね。ぼくの関心というのはイタリアにあって、いろいろな興味があるんですけど。主に関心のあることのひとつが、イタリアの議会外左翼の活動や思想、なかでもオペライズモ、さらにはアウトノミアという言葉で呼ばれるものです。大学生の頃にはまだ知りませんでしたが、大学院に入ってから勉強していく中で知ったんです。たぶん*アントニオ・ネグリらが*『〈帝国〉』という本を出したのを皮切りに日本でとても有名になったあたりから『〈帝国〉』だけではない、その背後にあるイタリアの思想的なものとか、政治的実践の歴史とかに興味が出てきたのかもしれません。
オペライズモは「労働者主義」と訳されますが、そのオペライズモからお話しますと、端的に云えば、イタリア共産党が掲げてきた、あるいはソ連が掲げてきたような、マルクス主義の歴史とか、労働者の闘争や革命の歴史とは異なる発想に立っていたということがあるんです。それをどう説明するか。いろんな説明の仕方があるんですけど、例えばさっきの原口さんの話をふまえて図式的に言うと、共産党などのアイデンティティとして労働者や労働倫理。働くことで世の中は発展し、豊かになり、私たちも豊かになる。こうした発想は、働くことが基本的に前提であり、それが労働者としてのアイデンティティを根本的に支えるものとしてある。先ほどの釜ヶ崎の労働者も同様ですが、自分が働いて、働かされて、搾取されて作ったもの。富。例えばビルが目の前にある。それが労働者。オペライスタたち、「オペライスタ」というのはオペライズモの知識人、あるいはミリタント。革命家のことですが、彼らはマルクス、特に『資本論』の機械や大工場の箇所を再読しながら、労働者の調査と分析を滅茶苦茶するんです。労働者たちがどんな欲望を秘めていて、どんな文化を持っていて、どんな行動をしているのか。彼らが注目したのは当時1950年代後半、60年代のイタリアの工場です。トリノやミラノあたりに先進技術をもったテイラー主義の流れ作業の工場、大規模な工場ができていき、そこで多くの労働者が働くわけです。なぜこの労働者たちが大事だったか。オペライスタが言うには、彼らが自分の労働者としてのアイデンティティとか、労働者としてのプライドとか、働くことが大事だよという倫理とかを全く持っていないからなんです。働くことで豊かになる?それ、意味分かりませんと。それこそイタリア南部の大量の移民たちが職人的技術も専門的技術も持たず、見たこともない機械に包摂されてそこで単純作業を繰り返すにすぎない存在として北部の工場で使われていく。あるいはドイツとかスイスとか、ヨーロッパのほかの国に行っても同様でした。でも彼らの感覚としては、いきなり工場という異世界に包摂されて、1日8時間とか、あるいはもっと働いてくださいって、何それ?という感じ。まったくついていけない。ビフォもこんなことを書いてたと思います。だからもう無理、逃げ出します。そういう感覚。
でもね。面白いのは、彼ら、豊かな生活はしたいというんですよ。戦後しばらくして、イタリアの南部の都市部でも、ショーウインドウの中に若者向けのたくさんの商品が出てくる。「こんな服を着たいな」「こんなお洒落なジーンズを履きたいな」と。そんなことを書いた小説があるんですけど。そういう欲求はムチャクチャ強いし、それをいっさい否定することもない。当然資本主義ですのでプロレタリア化してますから、食うために働き、カネを得ないとそれは手に入らないんですけど。でも働くことに関しては何のモチベーションもない。もう、ちょっとしたことでも、辞めたい。でもカネは欲しい。オペライスタが言うには、この南部から北部に移住してトリノなどで働いている労働者がなぜ大事かというと、彼らは労働者のアイデンティティがどうとかじゃなくて、労働ということ自体を拒否しようとしている。拒否して、極力働こうとしない。何なら労働を憎んでいると。彼らの「拒否したい」という欲望は、何かはっきりと「私たちは労働を拒否します」と政治的に公然と表現されるもっと手前の、個人のミクロなレベルの「サボり」とか怠けるとか、そういう話です。「ずる休み」とかね。イタリアでは“欠勤主義”って言います。だから労働者としての自分のアイデンティティ。労働者としての自分のあかしのみたいなものはいらないし、そもそもそうした考え自体がない。それが今までの労働運動の価値観との絶対的な違いです。労働者としてのアイデンティティ前提の運動ではないということです。
もちろん、彼らは労働者です。資本-労働関係の中で使われているし、彼らもより政治化、集団化すれば、世界の富は自分たちがつくったともはっきり言います。ただ重要なことは、資本主義という客観的な条件のなかで労働者という位置にいるわけですが、その自分たちの条件から離脱しようとしていることにある。もちろん、釜ヶ崎の日雇い労働者の中にもこうしたふるまいはさまざまにありました。ぼくが言うのも気が引けますが、労働現場などから逃げ出すことを表す「トンコ」という言葉がありますし、原口さんが序文を書いていますが、船本洲治という革命家の再版された本にもそのようなことが書かれています(『黙って野たれ死ぬな』共和国、2018)。だから、オペライズモが「労働者性」というときの労働者性とは、真面目に働くとかではなく、こういう拒否やサボりを含んでのことなんです。結局、労働の拒否が政治的に大事なのは、資本主義に包摂されて労働しなくてはいけない世の中なら、労働することで価値が生まれる世の中では、こうした拒否のいろいろなふるまいこそが、資本に莫大なダメージを与えるのではないか、ということです。そしてそれが連なれば。だからオペライズモではこのようなふるまい、主体性こそが大事だという話になった。そこがいちばんの特徴なんです。
杉本 結局それはごく素朴な常識からいうと、どっちかしか選択できないじゃないかという話になりますよね。それはもう、日本の工場労働の人たちも嫌ですよね。日本に来ている外国の労働者の人だっておそらくそう。拘束されて8時間も10時間も夜勤も含めて嫌だけど、家族に仕送りもしたい、自分もいい生活、日本に来たら少しいい生活ができると思って。でも豊かになるためには働かなくてはならない。それはどこかで最終的には自分の中で労働倫理みたいなものを内面化していくしかないと一般的には思う。友だち同士では「働きたくないよね」と言い合っているかもしれないけど、でもやっぱり働きに行きますよね。
北川 そうですね。実際、ほとんどそうなってしまいますよね。
杉本 おそらくイギリスの労働者階級の人たちはずっと産業革命の時代から階級分離しちゃってるから、今度は労働者同士が組織を組んで資本家に要求を突きつけるという組合主義の運動になっていくと思うんです。労働者の仲間。そこでのつながり。共同体意識みたいなのが生まれると思うんですけど、「働かないで豊かになりたい」。*『働かないで、たらふく食べたい』という本がありましたが(笑)。それとまさにおなじような要求を掲げて果たして通りますかね?という風に、おそらくね。ぼくなんかはアウトノミアの運動に「うんうん」と頷くわけですけど、当然、「それってどうなんだ?」っていう一般社会側の理屈。イタリア人のひともそういう風にはならないのでしょうかね(笑)。
北川 (笑)
杉本 ははは(笑)。ここはぼく、イタリアの面白いところだなと思うんですよ。だからちょっと日本が、どうなのかなあ?って。イギリスの話は少し脱線だけど、ヨーロッパと日本、違う所なのか。
北川 うん、なるほど。もちろん世の中の大勢はそう思っているでしょうね。イタリアだってそうでしょう。もちろん働く感覚とか、歴史的、政治的なこと、労働運動のあり方や成果に由来する違いはあると思うんです。これ、雑談ですけど。ぼくはスーパーやコンビニのレジって、すごく象徴的な場所だなと思うんです。日本のレジってすごく丁寧じゃないですか? もちろん職場でマニュアルなどがあって、そうせざるを得ないんだと思います。お釣りの受け渡しなんかもすごく丁寧じゃないですか。ちょっと列が並んで待ち時間があったりすると「大変お待たせいたしました~」と対応してくれる。コンビニとかなら棚の整理をしていても、お客さんがいたらレジまで走ってきてくれる。本当にエライことで。こういうのはたぶん日本以外では、ヨーロッパといってもぼくはイタリアばっかりしか知らないですけど、あり得ないでしょう。
杉本 そうでしょうねえ。
北川 もう全然。レジで店員はしゃべってますし。レジとレジをまたいでね。
杉本 (笑)
北川 商品ポンポンほおって「はい」って感じ。そんな、日本みたいに「お待ちのお客様、お待たせしましたー」とか、あり得ないです。
杉本 お客様は神様ではない。
北川 初めてイタリア行ったときに驚いたと同時に、いいなと思ったわけですよ。列がかなり並んでても別に急ぐようにはみえませんし、働いている人は列が並んでいようが普通に喋りながらやります。日本で客の列が並んでいようものなら店員がすごいプレッシャー感じてしまうわけですよね。もう早くせな、と。で、案の定ときに舌打ちする奴とかが出てきてしまうわけです。「はよしろや!」みたいな感じで。この速さや対応に慣れると、こうなってしまうのもわからなくもないですが、待てない。イライラする。これって電車ひとつ、メールひとつ待てなかったり、スムーズな流れや心地よさが乱されるとすぐにキレてしまう今の社会の感覚とつながるんですけどね。何かそんな違いとかは、なおもありますかねえ。
なので働くことに対するそういう価値観の違いというのは確かにあるとは思うんですけど、でもこの資本主義の世の中では、何であろうが働くこと、カネを得るために働くことが前提であり、普通にそれで生活するのが当たり前とされてるのは当然、同じことです。なので、当時50年代後半、60年代にオペライズモを通して出てきたような、あるいはのちの70年代のアウトノミアへつながるような、「働かずにたらふく食べよう」みたいな発想は、社会一般になかなか共有されてはいないと思います。でもそういうことをときどき思ったり、実際にそういう風に生きようと考える人、そうしてみる人が一部でもなお居るのも事実であって、それが大切なんだと思います。結局オペライズモの当時のインテリたちもそんな人々や現実を見つけて、さらに広げたかったのでしょうし。
彼らは、1956年のハンガリーの民衆反乱に対するソ連軍の介入で党に幻滅した人たちです。ソ連、イタリア共産党、その関係の労働組合とかとは距離を置き50年代、60年代に労働者の状況、政治的展望を考えようとした人々なんです。あと、イタリア共産党はマルクスを忘れているとも言っていました。つまり、時代や状況のなかで欲求や闘争の形、やり方を変化させる労働者の視点がない。はっきり言えば、生きた労働者の闘争の視点がない、と。やはり資本主義社会を基本的にはひっくり返したい。根本は同じだと思うんです。こう言うとでかい話に思えてしまいますが。
ただね、忘れてはいけないのは、1960年代の前、50年代当時は、労働運動はもう「死んでしまった」とか言われていたんですよ。闘争はないと。
杉本 ほう~。そうなんですか?
輩(ヤカラ)への着目
北川 戦後の1950年代とか、大きな労働争議とか運動はなくて、ましてやイタリア共産党は南部の田舎、農村から来た人々、工場とかで働いている彼ら若い男性について、自分たちがイメージする労働者じゃない、と言ったりしていたらしいんです。
杉本 やはり怠惰な労働者たち、という印象なんですか?
北川 それはあったと思います。党の言うことなんかまったく聞きませんし、デモとか、ストライキとか、党や労働組合が組織しても参加しないとか、「無駄だ」と言っている。「そんなことやっても全然無駄だ」「興味ないわ」と。いわゆる当時の左派の政治的言語や政治的闘争を語る側からすると、彼らはそれに全然あてはまんないわけですよ。むしろそれを拒否して敵の組合なんかに投票したりもする。何かとんでもないふざけた連中で、こんな奴らは単なる不逞の「輩(ヤカラ)」、「ごろつき」だと。
杉本 ルンペン・プロレタリアートみたいな言われ方ですね。
北川 そうです、そうです。実際これは1962年のことですが、工場から外に出てきた労働者たちが、広場で警察と衝突するんです。ちょうどトリノ一帯で大規模なストライキがようやく展開されていたときなんですけど、外に出てきた労働者が3日間にわたってトリノの街中の広場で衝突したんです。でも共産党とか既存の労組はもう引き上げろ、と。でもいっさいそういうことを聞かずにずっと警察と闘い続けて、投石しながらバリケードを築いている労働者がいっぱいいたんです。どんどん増えていきました。5~6,000、7,000人ぐらいだったかな。わかりませんが。この広場にいた労働者の半分ぐらいは南部から来た労働者。こういうのは共産党からすればただの「ヤカラ」。扇動者だ、何ならファシストだ、背後で彼らに対してお金を出している奴がいるに違いない。工場の中で正しいストをしていた本物の労働者とは違うにせ物だ、とか。まあそんな感じの労働者たちだったので、いわゆる当時の左派が政治を考えるときの言語、ふるまい、価値観。オペライスタは「主体性」というんですけど、もうそれが全然違う。髪が長い、ロン毛とか(笑)。そういう部分も含めて。その意味ではさきほど杉本さんがおっしゃったように「働かない」「すぐサボる」とかそういう態度や欲望は、すでに当時の世の中の大半からやはり「良く分からない奴ら」と言われたと思います。仕事は遅刻したりサボったりしてて、出てきたと思ったら、中でも仕事せず、外に出ていって勝手に暴れはじめる。そこに誰も革命性があると思ってませんし、大事だとも思われていなかったのですが、オペライスタたちはそこに「何かあるに違いない」と考えて、注目したわけですね。
杉本 けっこうな数の人たちが来てたんですか?南部地方のほうから。
北川 そうですね。50年代60年代には南部の貧しい地域から北部の工業地帯にかなり数の移民が向います。数百万規模でしたかね。大戦後、南部は仕事がないし、改革がなされたとはいえ相変わらず大土地所有制度が残っていたり。キリスト教民主党という自民党みたいな万年与党の票田のためとも言われましたが。とはいえ、農業に機械化が導入されたりで、仕事もなくなったり不安定で。自分自身のこともそうですが、家族を食わせるということもあったでしょう。主に男性の移民ですけどね。家族がのちのち合流したこともあったでしょう。もちろん帰る人もたくさんいました。トリノやミラノなど移住先にずっと住み続ける人もたくさんいました。トリノは南部の一都市だとさえ言う人もいたわけです。
*ナンニ・バレストリーニという人が書いた小説があるんです。さきほどお話した小説です。バレストリーニは、南部から北部にやってきた移民労働者たち、若い男性に工場のことや生活、家族、住まい、仕事や闘争の経験、これまでのことなど、いろんな話をたくさん聞く。工場の中には簡単に入れないので、オペライスタ同様、労働者がローテーションで入れ替わるときの工場の門で、早朝とか夕方につかまえて、話を聞いて信頼関係を築くということをしていたんです。そしてバレストリーニは、労働者から話をいっぱい聞いて小説を書いたんです。それが『ぼくたちはすべてがほしい(Vogliamo tutto)』(1971)という本です。ちなみに、ぼくは愛読してます(笑)。Vogliamo tutto。これは今も運動の中で繰り返される言葉なんですが、まさに今ずっとオペライズモの話をしているときの労働者のイメージにふさわしい言葉なんですね。オペライズモとは、端的に言って、この小説なんです。主人公には実際のモデルがいたようですが。この小説の最初のシーンがイタリア南部の集会。共産党が組織した集会で、戦後やはりこれから発展、進歩していかなくてはならない。そのためにわれわれが働くことが大事なんだ、それで豊かになれるんだということを言っているわけです。だけど、主人公はそれを違和感を持って見ているんですね。働くことで豊かになる?これから富を作る? 発展? 進歩? はぁ? リアリティなし。話がでかいし、労働はしんどい。楽をしたい。ほしいのはカネだけ。いますぐほしいわ、てな感じです。イタリア南部で最初工場の仕事をしますが、北部に移動します。最終的にはトリノのフィアット・ミラフィオーリ工場に行き、そこで戦闘性を爆発させるアツい小説なんです。主人公は、最初「偉大なる」フィアット社は天国やで、と聞かされてやってきたんですけど、やっぱり最悪の労働で、労働はやっぱ最悪だと。何がすごいかというと、かなりメチャクチャな人物なんですよ、主人公が。いまだったらただの「ヤカラ」にしか見えないかも。
杉本 パンクかな(笑)
北川 あ、パンクですね。何か働く時間とかそういう感覚ももう、規律化されてなくて。
杉本 なるほどねえ。
北川 嫌な言い方ですが、ある種「まだ」資本主義に生活の隅々までが今ほど包摂されてない、実質的に包摂されてなかったといえばそうなんですけれど。普通にマンガを読んでて仕事に遅れていくとか、酔っ払って仕事行くとか。もう「お前は働く態度悪いからクビだ」と言われたら意地でも契約分のカネだけもらおうと必死になって、そこだけ闘う(笑)。あと同じ南部出身者の友人の妻といい関係になってしまったから、友人への借金がたまってきたから、ミラノからトリノへ移動するとか。流動的ですね。で、そういう個人レベルで「ヤカラ」のようなやつが最終的にはトリノの工場で搾取され、他の人たちと協業する中で、同様の境遇を生きる労働者たちと出会い、そこで集団化していく。学生たちと出会ったりする中で語る言葉もちょっと洗練されていくといいますか。最後は工場の外に飛び出して、警察との激しい闘いを展開します。そこで大衆的な地区の住民たちと出会い、彼らの一部も主人公たち労働者の側で闘いに加わるという。ちょうど1969年7月に実際にあったトライアーノ大通りの反乱を参考にしていると思います。工場の外っていうのは、70年代にまた重要となってくるわけですが。とにかく工場の中でも外でも、自力の、いわば自律的なストや闘争に従事していくというストーリー。
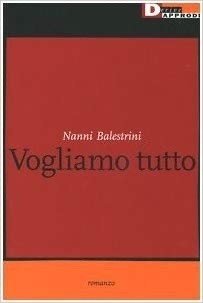
「働く」という世の中の仕組みがわからない
杉本 (笑)なるほど、なるほど。いやでも、本当そうですよね。個人でそれやったら簡単にクビ切られそうですもんね。「お前はダメだ」と。
北川 そうですね。
杉本 規律守れないからクビって言われたら、じゃあ心入れ替えますって。入れ替えたくないけど、入れ替えたフリして働かざるを得ない(笑)。そこでまあ、同じメンタリティの人たちが今度は徒党を組んで経営者と闘うわけでしょう。
北川 まあそうですね。
杉本 闘うというか、まあそれが闘う理屈になるのかどうなのか、分からないですけど。
北川 ははははは(笑)いや、そこはたぶんそうなんです。一見、闘うまっすぐな理屈というか、闘いの動機づけがつかみにくいでしょう。
杉本 そうですねえ。これはどう評価したらいいんでしょうね?やはり資本家の人たちがだいたい不当な要求をしてそこで喧嘩になる。ストライキとかになるんでしょうけど。どう考えても働く側のほうが働く気ないのに(笑)会社にやって来るということ。それを強引に、ここは俺の場所だからって。そう言うとしたらひとりではちょっと勝てないですよね。
北川 そうですね。ひとりだとまさにクビを切られていくことでね。ただ実は、まさに今おっしゃった不当な要求が向こうにあるかないかではないんですよね。そもそも「働く」という世の中の仕組み自体が耐えられないし、おかしいと思っているので。
杉本 そうかあ。ああ~。それはいいなあ(笑)
北川 そうなんです。
杉本 究極的にはそうですね。何で働かなくちゃいかんのか、って。まるで当たり前のように思われてきて、成人になったら働くのは当然で、と思っている。「働かざる者、食うべからず」でね、まさに。
北川 まさにねえ。
杉本 これは我々日本人にはもう骨がらみに沁みついているじゃないですか?「働かざる者、食うべからずだ」。働かないでも食いたい。どうしても栗原さんの本のタイトルを思い出すなあ(笑)。
北川 いや。でもまさにあれはそのことだと思います。
杉本 ではありますが……。
北川 そうですね。だからいいんじゃないですか(笑)
杉本 まあまあ、何というんですか。「不届きな」という声が。すぐ飛んできますけど。
北川 飛んでくるかな。どこからか、「俺はこんなに頑張ってるのに、あいつはなんや」みたいなのが出ちゃいますよね。職場で誰かひとりサボったり、あるいは心の病とかでも休んだりしたら、そのしわ寄せが同僚にいって「大丈夫?」じゃなくて「あいつのせいで仕事が増えた」となってしまう。ノルマとかもありますからね。こうして労働を通して、人は冷たい人間になってしまうと。
杉本 やっぱり嫌なんでしょう、本当は。みんな働かされて……。
北川 それはね。でも今だと働くことに自己アイデンティティを見いだしていく、みたいな話もよくありますよね。そうでもしないとやってられないのかもしれませんが。
杉本 そうそう、ありますよね。皆が見出せるわけじゃないんだけど。そういう意味でいうと、これはいろんなものを先取りしてるというか。ヒッピーとか、日本でいえば「フーテン」とか言われた人が生息してた時代。なんとなくそんなプータローみたいな、のらくらしている人たちがいたというか。でも、そういった人たちもいずれ包摂されてサラリーマンとして、まだ多少呑気だった時代はこうやって喫茶店で時間を潰すセールスマンやってたかもしれないけど。まあ、クビにならない程度にはちゃんとやるぞ、みたいになったと思うので、そういう意味では極めて早いというね。イタリアのそういう動きは。それをまた正当化するインテリの人たちが出てきたと。
北川 そうですね。
杉本 革命の種子になるかもしれないぞ、と。
*ビフォ(フランコ・ベラルディ) 1949年、イタリアのボローニャで生まれる。雑誌『ア/トラヴェルソ』の創刊、自由ラジオ「ラディオ・アリーチェ」を開局するなど、70年代のイタリア・アウトノミア運動の中心で活動する。77年の政治的弾圧によりフランスへ逃れ、その後ニューヨークにわたりサイバーパンクの潮流にかかわる。85年にイタリアに帰国後、インターネットをはじめとする新たなメディアを使ったネットワークの構築にとりくみ、メディア・アクティヴィストとして活動の領域を広げていく。邦訳書籍として『プレカリアートの詩:記号資本主義の精神病理学』(2009年)『ノー・フューチャー』(2010年)『フューチャービリティ』(2019)など。(Amazon参照)
*アントニオ・ネグリ (Antonio “Toni” Negri、1933年 - )イタリアの哲学者、政治活動家。パドヴァ大学、パリ第8大学などで教鞭を執る。オートノミズムの指導者として知られていたが、1979年4月7日、赤い旅団によるアルド・モーロ元首相誘拐暗殺を含む多くのテロを主導した嫌疑で逮捕・起訴された。その後、事件への直接の関与や旅団との関係は無かったことが明らかになるも、1960年代から逮捕に至るまでの言論活動や過激な政治運動への影響力の責任を問われる形で有罪とされた。
裁判中の1983年、イタリア議会選挙に獄中立候補し当選。議員の不逮捕特権により釈放されるも数か月後に特権を剥奪され、直後にフランスに逃亡・亡命した。フランスで活発な研究・執筆活動を続けていたが、1997年7月1日、刑期を消化するために自主的に帰国し、監獄に収監された。その後、数年をかけて処遇が緩和され、6年後の2003年4月25日に釈放となった。著書多数。
*『〈帝国〉』 ネグリによるアメリカの哲学者、マイケル・ハートとの共著。2003年。
*『働かないで、たらふく食べたい』 政治学者、栗原康による著作。2015年
*ナンニ・バレストリーニ (1935―)イタリアの詩人,小説家。新前衛派の代表的作家の一人。 1961年詩選集『最新人』に前衛実験詩を発表。『クィンディチ』誌に拠って評論活動を展開。左翼急進主義を唱え,政治的事件を素材に前衛的手法で文学活動を行う。主著,詩集『いかに行動するか』 Come si agisce (1963) ,小説『トリスタン』 Tristano (66) ,『すべてを欲して』 Vogliamo tutto (71) ,『彩られた暴力』 La violenza illustrata (76) 。(コトバログより)
いいなと思ったら応援しよう!

