
【StartPass社の事例から学ぶ】急成長スタートアップのための人事制度設計とOKR導入のポイント
【急成長スタートアップのための人事制度設計とOKR導入のポイント】の資料が欲しい方はこちら↓
はじめに:なぜスタートアップに人事制度が必要なのか
スタートアップはスピード感が命だと言われます。
新しいアイデアや技術をもとに、市場の隙間や顧客の潜在ニーズを見つけて急成長を目指す企業では、往々にして“プロダクト開発”や“資金調達”が最優先事項とされがちです。
しかし、急拡大するうえで見落とされがちな重要要素の一つが「組織づくり」であり特に「人事制度設計」です。
人事制度が不十分だと、次のような課題が生じるリスクがあります。

こうした問題を回避し、組織拡大と社員のスキルアップを両立させるうえでも、人事制度や目標管理(OKR等)の導入は必須です。
今回はスタートアップ支援のプロであるStartPass社の事例を中心に、その重要性と具体的な導入方法を解説します。
1. StartPass社について

まずは、本記事の事例企業であるStartPass社のご紹介です。
StartPass社は、スタートアップが必要とする多彩なリソースを集約し、ワンストップで利用できるサービスを展開しています。
※以下、StartPass社のご支援内容例

同社自身がスタートアップであり、かつ多数のスタートアップを支援するなかで「人事制度の重要性」も実感し、そこで社員数10名に満たない段階ながら、人事制度づくりに本腰を入れられました。
2. StartPass社が語る「人事制度設計」の大切さ
2-1. 早期導入のメリットがある
スタートアップにおける人事制度整備のタイミングは千差万別で、「社員数30名を超えたら」「売上◯億円を突破したら」と判断基準は企業ごとに異なりますが、StartPass社は社員数が10名以下のうちから制度整備をスタートしました。
早期導入によって得られるメリットは主に以下3点です。

2-2. 「コアメンバーが少ないうちに作る」意義がある
スタートアップは必ずしも“最初から大きく稼働”するわけではありません。最初は社長含めて数名、というケースがほとんどです。
しかしその段階で会社を支えるコアメンバー同士が納得感のある人事制度を作るか否かで、あとからジョインしてくるメンバーの働きやすさ・制度の運用効率が大きく変わります。

2-3. 採用活動への寄与
昨今、スタートアップでも採用難は深刻化しています。
一昔前は「大企業 vs ベンチャー」という構図で、ベンチャーは“やりがい重視”の人材を獲得できればOK、という雰囲気もありました。
しかし近年は、大手企業でもジョブ型雇用に舵を切るところが増え、ベンチャーほど自由度の高い環境を提供している例も珍しくありません。
こうした状況下でスタートアップが優秀人材を採るためには、「うちの会社ならこんな評価制度があって、能力や実績を正当に認める仕組みがある」という明確さを打ち出す必要があります。
これは特に経験豊富な方を採るときに効いてきます。
給与テーブルや評価項目などの“見える化”が採用成功の鍵となるのです。
3. 人事制度設計の基本フローとスケジュール
3-1. 8つの基本ステップ
一般的に人事制度を策定するときは、下記8ステップで進めることが多いです。

3-2. 設計期間の目安(スタートアップの場合)
大企業の場合、人事制度をゼロから全面刷新となると1年以上かけるケースも珍しくありません。
一方スタートアップでは、3~6ヶ月程度で「いったん骨格を固め、早めに運用へ」というパターンが多いです。
StartPass社の場合、3ヶ月で基本設計を終え、すぐに運用開始。
実際に回すことで浮き彫りになる課題を迅速に修正し、「アジャイル開発」的に制度をブラッシュアップしていくスタイルが功を奏しています。
4. StartPass社の事例:どのように制度を作ったのか
4-1. 人事制度のコンセプトと全体像
StartPass社がハイマネージャー社とタッグを組んで導入した制度の概要は、大きく分けて以下の3要素で構成されています。

まず会社として「何を評価軸にしたいか」を丁寧に議論し、「これからまだまだ新規事業やサービス展開を増やしていくから、流動的な『役割ベース』よりは個人の『能力成長ベース』にしたほうが合っている」という結論に至りました。
4-2. 職能等級制度を選んだ理由
人事制度の等級設計には大きく3種類あるといわれます。

最近のスタートアップでは「役割等級制度」が流行していますが、StartPass社は以下の理由で「職能資格制度」を採用しました。
新規事業が多く、役割が流動的
まだPMF(プロダクトマーケットフィット)を常に模索するフェーズ。
明確なジョブ定義やポジションが変わる可能性が高いなら、まずは“個人の能力”に着目するほうが運用しやすい。
社員の“伸びしろ”を評価・育成したい
スタートアップにとって人材の成長=組織の成長。
個々が足りないスキルを可視化し、そこを伸ばす仕組みを作ることが今後の拡大に直結すると考えた。
具体的には6段階のグレードを設定し、グレード4以上をマネジメント/スペシャリスト というように役割コースも分岐し、本人の希望や実際のスキル適性に応じてどちらを目指すか選びやすい仕組みにしていま
す。
4-3. 評価制度(OKR×能力評価)の仕組み
StartPass社では「能力評価」と「成果評価」を切り分けて、次のように運用しています。

4-4. なぜOKRを評価に組み込むのか
OKRはもともと「評価とは切り離し、あくまでもチャレンジングな目標管理に使うのが望ましい」と言われることが多いです。
理由は「評価に結びつくと、達成率を高めるために目標を低く設定してしまいがち」という懸念があるからです。
しかし、StartPass社では二重管理(OKRとMBOを併用し別々に運用する)にならないよう、あえて評価制度に組み込む道を選びました。
達成率を低く抑えようとするリスクは、最終的にCOO(早川さん)がしっかり“目標レベル感”をチェックしてコントロールすることで解消しています。

4-5. 報酬レンジの設定と昇降給の考え方
スタートアップでは、先々のキャッシュフローが読みにくいケースも多いですよね。
そのため、評価ランクごとに「固定的に◯%昇給」と決めるやり方はリスクがあるとスタートパス社は考えています。
そこで、従業員側に「今回はこれだけしか昇給できなかったが、こういう資金状況であるため」「今回の調達ラウンドでこう変わるから、次回はさらにこうなる余地がある」というふうに丁寧に説明し、納得してもらうアプローチをとっています。
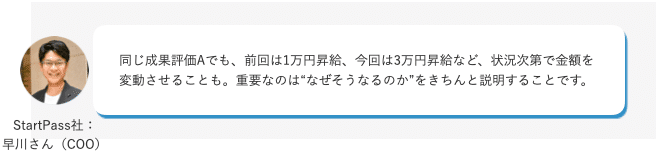
5. OKR導入のポイント:なぜ今OKRなのか
5-1. MBOとの違いと注意点
OKR(Objectives and Key Results)は、Googleなどが導入していることで有名になった目標管理手法です。
一方で、従来のMBO(Management By Objectives)も多くの企業で使われてきました。

ただし、OKRを評価に用いる場合、「目標未達が多発しても大丈夫なのか?」という疑問が出がちです。
StartPass社のように四半期ごとに実際の数値進捗を追って評価に反映する場合でも、あくまで「チャレンジ指標」である旨を理解させ、評価者がレベル設定をコントロールする」ことがポイントだといえます。
5-2. 目標設定時のコツ

5-3. チェックインとウィンセッションの運用
OKRは「設定したら終わり」ではなく、定期的な進捗確認(チェックイン)と振り返り(ウィンセッション)が大切です。
StartPass社では次のように運用しています。

「どうしてもチェックインが進捗報告だけに終わりがちでマンネリ化する」という課題もよく聞かれます。
そこを乗り越えるには、ディスカッションを重視した仕組みにするのがおすすめ。報告だけでなく、「なぜ遅れているのか?」「どうすれば巻き返せるか?」など相互支援を引き出す問いを意識的に設計します。
5-4. 実際の“あるある”課題と対処法

6. 評価・フィードバックにおけるAI活用の可能性
6-1. 職能・コンピテンシー定義への応用
近年、ChatGPTやNotion AI、Claudeといった生成AIが注目を集めています。人事制度の設計でもこのようなAIを活用することで、大きな効率化が期待できます。
たとえばコンピテンシー定義や等級別要件づくりは、従来コンサルタントや担当者が一つひとつ言語化していた作業です。これを「自社が重視する能力要素」「求める行動例」をAIに入力し、草案を生成してもらう」ことで、短時間で“使えるひな型”を得られます。
もちろん最後は人間が社風や戦略との整合性を確認し、微調整する必要がありますが、ゼロから作るよりも圧倒的にスピードアップが図れるのです。
6-2. Slackやドキュメントをエビデンス化
評価をする際、上長や人事担当者が「日常業務での具体的成果・行動」を思い出すのは手間がかかりがちです。
そこでSlackやGoogleドライブ、Notion等のログをAIが自動的に解析し、「この人はこういう発言や行動をしていた」というエビデンスを抽出するような仕組みを導入すれば、評価者の負担も大幅に減らせます。
6-3. 生成AIによる評価の効率化
StartPass社でもすでに「Notion AI」を活用し、テキストや会話ログをもとにスキル評価の草案を作成→最終調整するといった運用を開始しています。

一方で「AIでの評価は偏りや誤りを生む可能性もある」という声もあります。
最終的な判断はやはり上長が下すことが前提ですが、AIのサポート機能を上手に取り入れることで、より公平かつ効率的な人事評価を実現できるでしょう。
7. 導入後の成果と今後の課題
7-1. アライメント向上とチャレンジング文化の醸成
StartPass社が人事制度とOKRを同時導入して最も実感した効果として、早川さんは「組織のアライメントが一気に高まった」と語ります。

さらに、OKRの特性である「ムーンショット(高い目標)を掲げる」文化が根づき、「メンバーがより積極的に高い成果を追求しはじめた」ことも大きなメリットだといいます。
7-2. チェックインのマンネリ化防止策
一方、毎週のチェックインでは「つい進捗報告だけで終わってしまう」「ネガティブな情報共有がしづらい空気になると、早期支援が間に合わない」次などの課題が浮上しました。
これを防ぐため、StartPass社では「報告のみ」→「議論・合意形成もセット」という運営ルールを強化。
例えば「○○さんが今週抱えている課題は何か。それに対して××さんが何か手伝えることはないか?」など、相互協力の提案を促す工夫を行っています。
7-3. 評価・報酬における柔軟性と説明責任
報酬面については「評価に応じて自動的に昇給額が決まる形にはしていない」ため、どうしても個別説明が欠かせません。
スタートアップではキャッシュ状況に応じて出せる昇給幅が変化しやすいため、「今回A評価だけど昇給額は△△円、その理由は資金状況がこうだから…」という透明性ある説明が不可欠です。

まとめ:アジャイルに制度を作り、アップデートする大切さ
本記事では、スタートパス社の事例をもとに、スタートアップにおける人事制度設計とOKR導入のポイントを解説しました。
改めて鍵となるポイントを振り返ると、次のようにまとめられます。

スタートアップが急成長を目指す上では、製品開発やマーケティングだけでなく「人材と組織」をいかにスケールさせるかも決定的に重要です。
人事制度とOKRを適切に導入・運用することで、組織全体のベクトルを一致させ、個人の成長と会社の成長をシンクロさせることが可能になります。
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。
HiManagerに無料お問い合わせしたい方はこちら⇩



