
Designship2023公募セッション「対称な医療をデザインする」後編
Designship2023で登壇したプレゼンテーションを公開しています。前編はこちら。
「情報の非対称性」をどう超えていくか?
前編では新しい情報テクノロジーを用いて医療コミュニケーションを進化させる方法について、事例と可能性を紹介しました。
しかし、技術的に可能であればすぐに実現できるものでしょうか?
ここからは現実の話をしましょう。私は今の仕事を通じ、医療現場に新しい技術を実装することの難しさを身をもって痛感しています。どうやら、新しければ使われる、魅力的なデザインであれば使われる、という世界ではありません。
医療に新しい技術を実装するには多くのハードルが存在しますが、今回は大きく二つ紹介します。ひとつは信頼性の問題、もうひとつは医療におけるメンタルモデルの問題です。

信頼性とメンタルモデル
信頼性の方は単純です。AIやインターネットの言うことを鵜呑みにしてはならない。これについては現在のAIも消極的で、特に健康に関する情報は個人で判断しないよう常に忠告しており、誤りがあったときに誰も責任が取れないのが現実です。
続いて、医療のメンタルモデルとはなんでしょう?これは「医療の体験とはこういうもの」という確立されたイメージのことです。医療は患者と医師という2種類のユーザーの相互作用で成立しており、メンタルモデルが共有されることで、スムーズな医療体験が実現できています。

たとえばある患者さんに「新しい情報ツールが介入することで医師とより深いコミュニケーションができますよ」と勧めたとしましょう。
予測される大半の回答は「いや、今でも先生は話を聞いてくれるし困ってもないから別にいらない」です。
同じ質問を医師にしてみても「いや、自分の知識でまかなえているし、自分だけでやる方がだんぜん早い」という回答が予測されます。

ここから見えてくるのは、医療のメンタルモデルが情報の非対称性にかなり依存しているということです。医師は知っている、患者は知らないというモデルを両者が前提として持つことで、複雑な医療コミュニケーションを短時間で的確に行うことができています。

こうした状況から、ただ目新しさや便利さだけを売りにメンタルモデルを中途半端に変更するツールは医師・患者双方にとって必要ないことがわかります。困りました。

ではどうすればいいか?
どうすればいいでしょう?
先ほどの話でこのアイデアの直接的なニーズは得られなさそうでしたが、間接的なニーズを考えてみましょう。医師と患者、両方に共通のペインポイントとはなんでしょうか?

たとえば大きな問題として、業務の効率化と医療品質の担保があります。
患者にとって待ち時間が長いことは大きな問題であり、病院に行くことそのものも重い負担です。業務の効率化で待ち時間が減り、受診する機会が減ることは大きなメリットがあります。

またこの問題は医師にとってより切実で、多くの現場で医師は働きすぎを何とかしたいと考えています。
そして、負担を減らす代わりに医療の品質を下げることは誰も受け入れたくありません。待ち時間が減り、医師の業務負担が減った代わりに医療サービスの質が下がり、亡くなる方が増えました、はあまりにも本末転倒だからです。

実際に2024年から大規模な医師の働き方改革が予定されており、就労時間管理の規制が強化されます。これには医療を支えられなくなることを危惧する医療側からの不安が常に叫ばれています。
この問題には、医療コミュニケーションに情報テクノロジーが介入する強いインセンティブになるはずです。
たとえば診察→検査→結果説明で2回かかっていたコミュニケーションコストを、AIによる詳細な問診と医師に向けた検査の提案により、1回に減らすことができるかもしれません。

また、病気と診断された後に、病気に関する教育や治療目的の行動変容をうながすプログラムを介入させることで回復を早め、長期的な負担を減らすことができると考えられます。

もうひとつのアイデアは、既存モデルの延長としてのデザインです。「AIで解析した結果がこちらです!」と新しいツールとして仰々しく導入させるのではなく、心電図の自動解析のように電子カルテの機能の一部としてしれっと登場させることで、医師の認知的な抵抗感が減り、メンタルモデルの変化もスムーズに成功できる可能性があります。
デザインが医療に介入できるポイント
こうした業務効率を上げ、体験の質を下げないこと、既存モデルの延長として認知させることはtoBのデザインとしてはとても基本的な観点です。しかし、とかく患者の治療と安全を最優先する医療の世界でこうした視点は抜けがちとなり、これからデザインが医療に介入する上での大事なポイントになります。
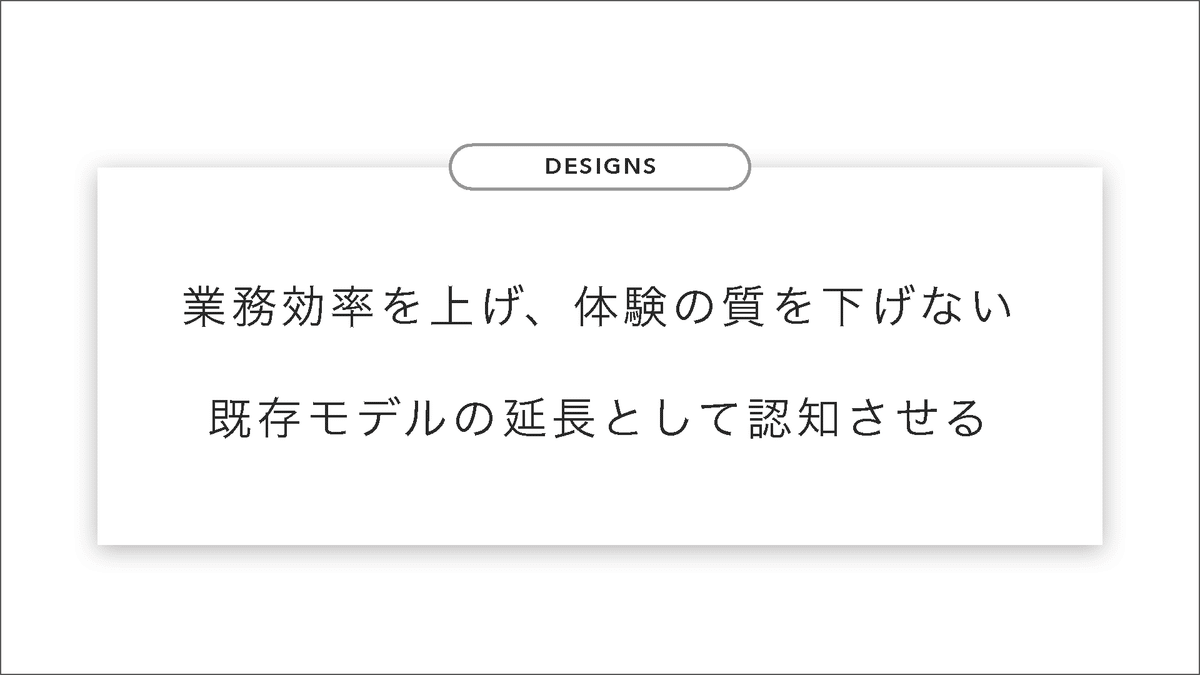
さらに基本的なことを言うと、医療に携わるデザイナーは、医療者と患者についてもっと深く知る必要があると考えています。医療のプロセスにどのようなパターンがあり、どのポイントでどのような介入をすればどのようなメリットが得られるか?を徹底的に分析することで、適切なデザインは生まれます。
たとえプロジェクトが医療側から発信されたものであっても、医療の人間がここまで深くユーザーを洞察することは難しく、デザインが真価を発揮する領域です。

CureAppのデザインはこうしたユーザーの理解に重きを置いており、さまざまなバックグラウンドを持つユニークなプレイヤーが垣根を超えて医療を観察し、議論を重ね、デザインを多角的にブラッシュアップし続けています。
日々発見の連続の、非常にエネルギッシュな現場です。
デザインと医療をつなげることはCureAppだけの仕事ではなく、もちろん私だけでやる仕事でもありません。より広いデザイナー、そして医療者に関心を持ってもらい、多くの専門家によって前に進めていきたい、それが私のビジョンです。

登壇を終えて
Designship2023ではこのプレゼンテーションを通じ、多くの方から質問や相談をいただき、改めて自分のデザイン観を見直すきっかけにもなりました。
エビデンス重視のアカデミックなプレゼンテーションとは大きく異なり、自分の思考や想いの熱さを観客にぶつける体験はとてもエモーショナルで刺激的でした。
他のプレゼンターの話も素晴らしく、現代のデザインにおける課題や希望が多角的かつ高密度にパッケージされていました。
ぜひアーカイブも堪能してください!
そしてCureAppの仕事に興味を持たれた方はぜひこちらもどうぞ!
