
節分に豆まきは1300年の歴史。昔の儀式では真夜中に撒く⁉
執筆者
#Ishikawa・Hironao
節分になると豆をまく行事がありますよね。
「有名人が神社で豆をまいてるから」
「学校のイベントでやったから」
という理由で豆まき経験をしたという人も多いかと思います。
飛鳥時代に中国から日本に伝わった「追儺(ついな)」と呼ばれる儀式が起源だと言われているそうです。中国では病気・災害・飢饉などの起きる理由は鬼のせいだと言われていたため、その儀式をしていたそうです。
日本で初めて行われることになったのは、疫病が発生した慶雲3年(西暦706年)の大晦日だったので、約1300年前です。
どうして、豆を撒くのか?
日本では穀物に邪気を払う力があると考えられており、特に豆や米・麦などは魔除けとなる力があるとされており、お祓いなどの行事の際にはよく使われていたそうです。
この時代から穀物を大事されていたのですね。
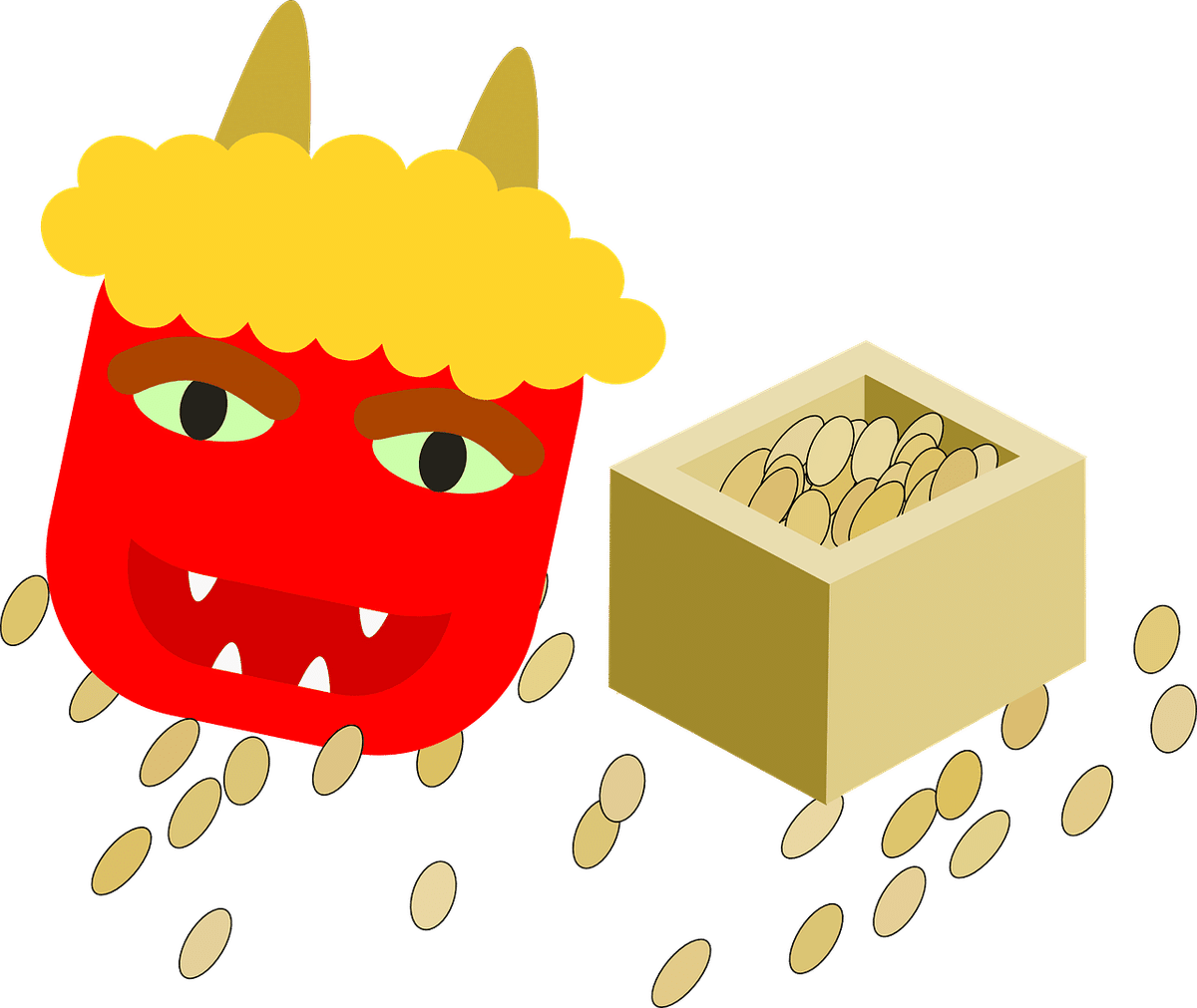
本来は豆まきは夜に行うもの。
夜になったら玄関、窓をすべて開放して
「鬼は外、福は内」と声を掛けながら鬼に向かって豆をまいて鬼(=邪気)を追い出すのが本当の節分みたいです。夜になってやるのもなかなか面白そうですね。
地域や時代によって変化している
本来の豆まきでは、家長である父親、年男・年女がいる場合は、その人が豆をまくということになっているそうです。地域の差によって時代ややり方は違うみたいで、特にルールはありませんが古くからの豆まき方法をやってみるのも面白いかもしれません。
当事業所も豆まきをしましたが、コロナも早く外にいってほしいものです。大変な時代になっている昨今、こういった豆まきという行事が意外に良いのかもしれませんね。
いいなと思ったら応援しよう!

