
こんばんは。グラフィックデザイナー、カラリストの藤田です。
今日は色彩学的な「色彩の調和」について。
自然な調和、不自然な調和
色には、先日お話したように視覚的に重さがあります。
基本的に同一トーンでは、黄色が一番明るく、青系が暗くなります。

同一トーンの色相は、こんな感じの曲線を描きます
黄寄りの色が明るく、青寄りの色が暗い配色は、目になじむ「自然な色彩調和=ナチュラルハーモニー」と言います。
逆に黄寄りの色が暗く、青寄りの色が明るい配色は、自然界にはない「不自然な色彩調和=コンプレックスハーモニー」と言います。
ナチュラルハーモニー
草は光が当たるところは明るい黄緑に、影は暗い緑になります。
明るい部分が黄色に寄って、暗い部分は緑に寄ってますね。
自然に目に入ってくる色合いで、落ち着いた印象になります。

コンプレックスハーモニー
同じ色相で、黄寄りの色を暗く、青寄りの色を明るくしてみましょう。
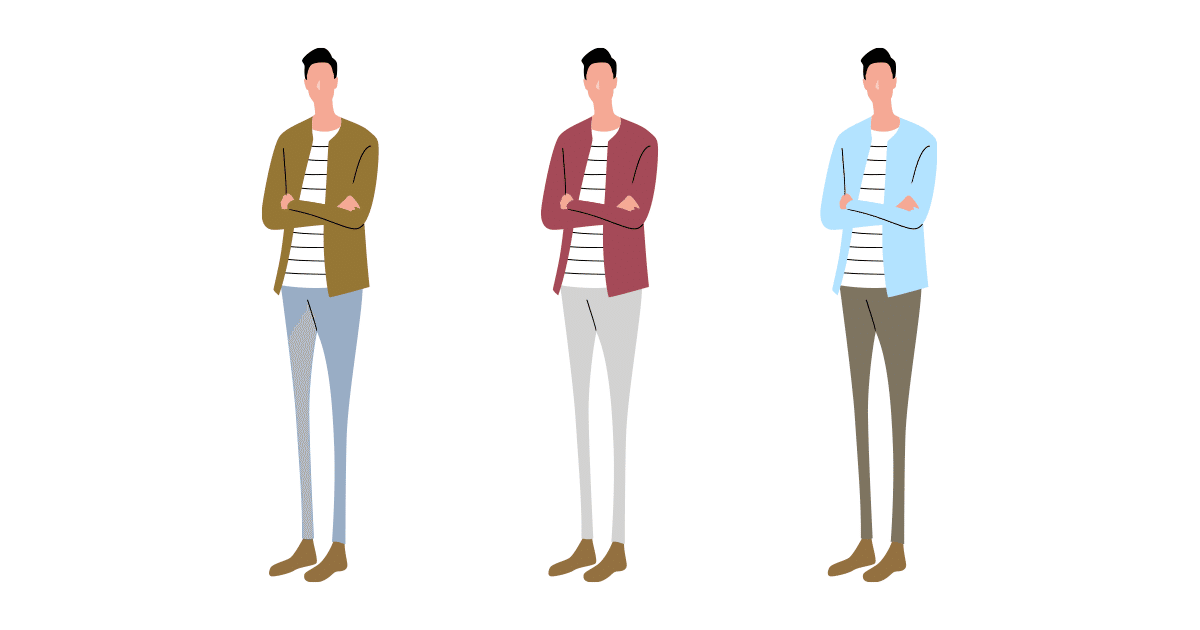
すると、少し不安定さが出る印象になります。
黄色寄りの色のトーンを、青系より落とす感じですね。
不安定さはアクティブさ
色相だけでなく、配置する場所も影響します。
ふつうは重いものが下に来るので、
上が明るく、下が暗い配色は安定感があります。
逆転させると頭でっかちな不安定さが出てきます。
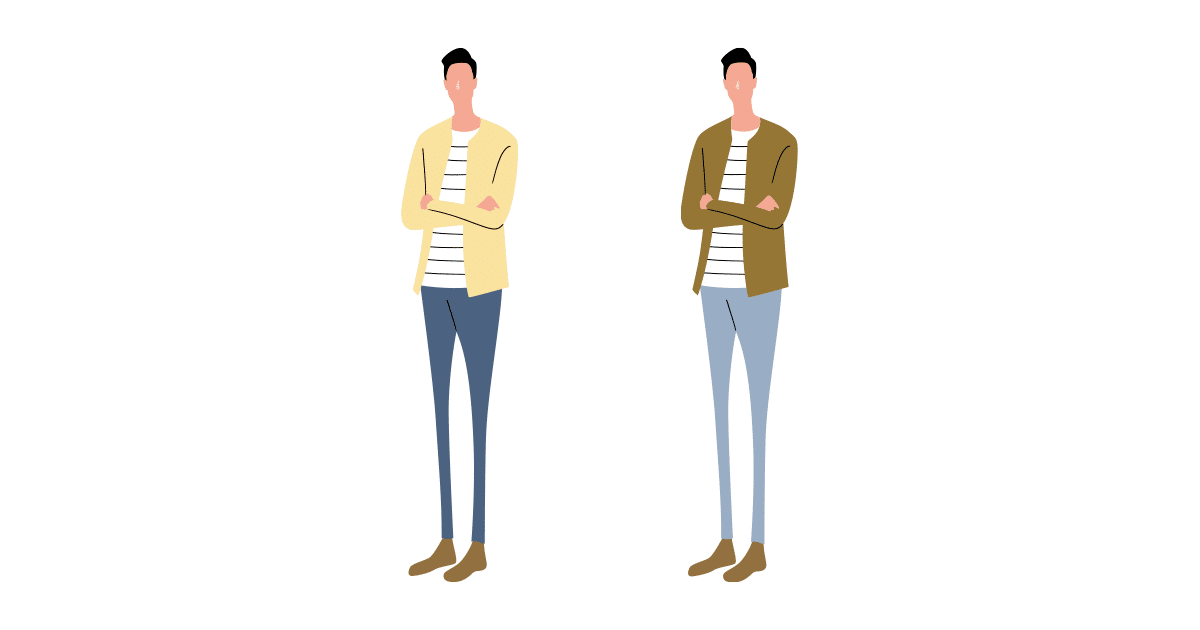
左の方が、下に重心があって安定感がありますね。
コンプレックスハーモニーや、上部を濃くする方法は、
不安定さを逆手に取って、動きのある(アクティブな)イメージに転換することができます。
それぞれの良さを活かして
コンプレックスハーモニーの話を厚めにしましたが、どちらが良いとかではなくて、それぞれに良さがあります。
ナチュラルハーモニーの強みは、その見慣れた安心感。
リラックスしたい空間や、落ち着いた気分になりたい時に効果を発揮します。
コンプレックスハーモニーの強みは、見慣れない新鮮さ(あるいは違和感)。
楽しく過ごしたい空間や、明るい気分になりたい時に効果を発揮します。
お互いの強みが、それぞれの弱みでもあるので、
環境や状態、気分などを考慮して、使い分けに挑戦してみてください。
明暗を逆転させるだけで、つまらないと思ったものが楽しくなったり、刺激が強すぎると思うものがマイルドになったり、変化が起こると思います。
いいなと思ったら応援しよう!

