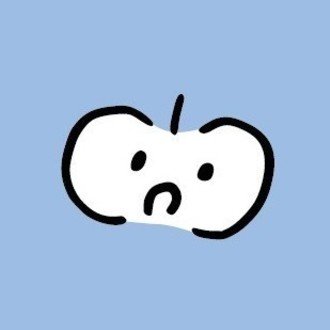評者:押谷仁【『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』書評】
この note では、2025年1月発売:
佐々木周作・大竹文雄・齋藤智也
『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』
の書評を公開しています!
評者は、新型コロナ・パンデミックでは政府の複数の有識者会議等にも参加された、ウイルス学・感染症疫学等がご専門の 押谷仁 先生(東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授)です。
ワクチンをめぐる専門家間の「健全な対立」と
社会実装に向けた「試行錯誤」を描く
押谷 仁
Oshitani Hitoshi
東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授
1987年東北大学医学部卒業。国立仙台病院(現・国立病院機構仙台医療センター)を経て、1991年よりJICA専門家(ザンビア)。1995年東北大学医学博士、1997年テキサス大学公衆衛生修士。新潟大学医学部公衆衛生学講師、WHO西太平洋地域事務局・感染症地域アドバイザー等を経て、2005年より現職。
新型コロナ・パンデミックでは、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード、基本的対処方針分科会等の構成員を務めた。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対しては、従来では考えられなかったようなスピードでワクチンが開発され、短期間に多くの人に接種が行われた。世界中でさまざまなワクチンが開発されたが、日本で使用されたワクチンのほとんどがメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであった。このワクチンは新しい技術を用いたものであったため、当初は有効性や安全性に対する不確実性もあった。にもかかわらず、日本では他の先進国と比べても高い接種率が達成された。本書は、ワクチンに多くの不確実性が存在する中で、行動経済学の手法を用いて自発的なワクチン接種を促すことを目的とした研究者の記録である。
1 論文執筆で終わらず、問題解決にこだわる
本書を主に執筆したのは行動経済学を専門とする大阪大学の佐々木周作さんであり、行動経済学分野の第一人者である大阪大学の大竹文雄先生、感染症危機管理を専門とする国立感染症研究所の齋藤智也先生との共著となっている。佐々木さんは私が研究総括を務める、JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)の「さきがけ」の「パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤の構築」という領域に研究者として参画している。「さきがけ」は主に若手研究者を支援するプログラムであるが、この領域ではウイルス学や公衆衛生学といった従来からパンデミックの問題に取り組んでいる分野の研究者だけではなく、佐々木さんのような経済学・政治学・歴史学など人文・社会系の研究者を含め、幅広い分野の研究者が参画していることが大きな特徴である。これはCOVID-19のパンデミックは社会・経済全般に大きな影響を及ぼしており、医学だけでは解決できない問題となっていたという問題意識に基づくものである。
ワクチンがその効果を発揮するためには、ワクチンが開発・製造され、接種が可能になるだけでは不十分で、人々にワクチン接種を受けるという行動を起こしてもらう必要がある。多くの国で、COVID-19に対するワクチン接種は義務化されていた。しかし、歴史的経緯もあり、日本ではワクチン接種は努力義務とされ、強制力を持ってワクチン接種を進めることはできなかった。すなわち、ワクチン接種は人々の自発的行動に依存していたことになる。
このような自発的な行動変容をいかにして促すかということは、行動経済学が取り組んできたテーマである。本書に記載されている佐々木さんたちの研究は、行動経済学の分野で有効性が示されてきたナッジという手法を、ワクチン接種に応用したものである。ナッジは、強制することなく、経済的インセンティブを大きく変えることなく、行動変容を促す手法とされている。この研究の結果、ナッジがワクチン接種意向の強化につながることが科学的に証明され、その成果は国際学術雑誌にも掲載されている。さらに、年齢などの個人属性によるナッジの効果の違いだけでなく、ナッジを閲覧した人の精神的負担への影響も示され、ナッジを有効に活用するためにはきめ細かい対応が必要であることが明らかにされている。ナッジは近年保健医療の分野でも応用が始まっている手法であるが、この研究結果はパンデミック下の保健医療でも応用可能であることを示唆している。さらに、行動経済学やナッジについてだけでなく、ワクチンについても基本的なことが専門外の人にもわかりやすくかつ詳細に記述されており、これらの内容について知りたい人にとって格好の入門書となっている。
この研究では、ナッジの効果を検証するだけはなく、インターネット調査を複数回実施し人々の接種意向を丹念に調べて、どのようなナッジが有効である可能性が高いかについても検討している。COVID-19以前には危機的状況下のワクチン接種にナッジを応用した実績がなかった中で、研究を進めるうえで必要なプロセスだったと考えられる。そのうえで、自治体と協力してワクチン接種行動に対するナッジの有効性についても検証している。しかし、COVID-19のワクチン接種を進めるにあたっての大きな課題は、ワクチンに関する知見が、時間とともに大きく変わっていったということがある。当初、mRNAワクチンは発症阻止効果も重症化阻止効果も非常に高いとするデータが示されていたが、その後の調査でワクチンの効果は時間とともに減弱していくことが明らかになった。さらに変異株の出現によって、ワクチンの効果、特に感染や発症を防ぐ効果は大きく低下していることも示された。この研究では、そのような状況の変化に応じて接種意向やナッジの効果がどのように変化しているかについても解析している。さらに追跡調査によって、実際にどのくらいの人が接種を受けていたのかというところまで調べ、接種意向と行動の不一致の原因なども解析している。
これら一連の調査・研究の根底にある理念は、単に調査をして論文を書いて終わりということではなく、これまで行動経済学で培われてきた知見を活かして、どうしたら実際にワクチン接種という行動につなげることができるのかという問題解決を目指した研究であるといえる。

『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』
日本評論社、四六判、378ページ
2 経済学者と疫学・公衆衛生学者の「健全な対立」
大竹先生とは専門家会議・分科会でもご一緒する機会が多く、分科会会長であった尾身茂先生が主宰していた「勉強会」でも、毎週のようにCOVID-19をめぐるさまざまな課題について議論をしていた。本書の中で、大竹先生が「大竹文雄の目」として書かれているパートで詳細に述べられているが、大竹先生と私の意見は対立する場面も多かった。これは、大竹先生は主に経済学の立場から社会・経済活動をできるだけ早く元の状態に戻したいと考えられていたのに対し、私は疫学・公衆衛生学の立場からできるだけ被害を最小限に抑えることを考えたことによるものと整理することができる。
たとえば、2021年9月3日に行われた分科会で、私が「ワクチン・検査パッケージ」の導入に反対したことが書かれている。大竹先生の意見は、行動制限を緩和するために「ワクチン・検査パッケージ」というツールを積極的に活用すべきということであった。しかし、ワクチン接種歴もしくは検査の陰性証明を活用するだけは流行を防げないことも、その時点で明らかになっていた。その根拠はいくつかある。たとえば、アメリカのマサチューセッツ州でワクチン接種率の高いコミュニティーで大規模な流行が起きたことが2021年8月初旬に報告されていた。当時流行していたデルタ株は、それまでの株に比べ病原性が高いことに加え、ワクチンの効果も低下していることが示されていた。そのためにワクチン接種率の高いコミュニティーでも流行が防げなかったことになる。私の意見はそのような疫学的知見に基づくものである。
本来分科会は、さまざまな立場の専門家がそれぞれの意見を提示する場であるべきである。異なる意見が存在する場合には、専門家の意見を参考として政治家が最終判断をすべきものである。上記の「ワクチン・検査パッケージ」の事例でも、このようなツールを使っても大規模な流行は起こりうるが、社会・経済活動を優先することも必要なので一定のリスクは許容したうえで導入の判断をするということはありうる。しかし、その判断をするのは専門家ではなく、選挙で選ばれた政治家であるべきである。しかし、日本では政治家が「専門家の意見を聞いて判断」したと説明している場合が多く、施策に伴うリスクの説明を回避してきていた。大竹先生の文章を読んでいろいろな解釈をされる方がいるかもしれないが、私自身は大竹先生と私の間にあったのは「健全な対立」であったと考えている。欧米などではワクチン接種をめぐって深刻な社会の分断が生じてしまっていた。日本でもワクチンに反対する人たちの意見がSNSなどで拡散しているという現状があり、より「不健全な対立」が生まれやすい状況になっているように思われる。さまざまな誤情報がSNSで急速に拡散されるような社会の中で、ナッジなどを使ってワクチン接種を促していくにはさらなる工夫が必要だと考えられる。
3 将来のパンデミックに備えるために
本書の最後の第5部では、将来のパンデミックに向けた政策研究の提案がなされている。将来のパンデミックはCOVID-19と大きく異なるものである可能性がある。特に、本書に書かれているように、子どもが重症化し死亡するようなパンデミックでは、ワクチン接種をどう進めていくかはより難しい課題がある。冒頭で述べた私が研究総括を務める「さきがけ」の領域では、異なる研究分野の若手研究者がCOVID-19とは違うパンデミックに対応するためにはどうしたらいいかということも議論してきている。なによりも専門分野の異なる専門家が平時から顔の見える関係を構築しておくことは重要である。地球の人口が80億人を超え、グローバル化が進んだ現代社会でのパンデミックのリスクは、かつてないほどに高まってしまっている。一方で世界の分断が進み、世界が協力してパンデミックという人類共通の課題に取り組んでいく体制を構築していくことはより困難になっている。将来パンデミックが起きた際には、立場の違いによる対立を超えて異なる分野の専門家が結集して、困難な状況でも最適解をみつけていくことが必要である。佐々木さんのようなさまざまな分野の若手研究者がパンデミックの問題に真剣に取り組んでくれていることに、希望の光を感じている。
(『経済セミナー』2025年2・3月号掲載の同名記事より転載)
『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』関連情報
■ 本書の「プロローグ」も公開中!
本書の「プロローグ」と詳細目次は、【 コチラ 】で公開中です!
(クリックいただくと、PDFが開きます)
■ 主な目次
プロローグ(佐々木周作)
第1部 「未知のワクチン」にどう向き合うか?
第1章 「未知のワクチン」に向き合うための基本道具
[大竹文雄の目] ワクチン導入をめぐる政策議論
第2部 「未知のワクチン」の接種開始前夜
第2章 「接種を受けるつもり」を測定する意義〜たかが意向、されど意向〜
第3章 自律性を阻害せずに接種意向を高めるナッジ・メッセージの探究
[佐々木・大竹・齋藤の「当時を振り返る」] エビデンスのつくり方と使われ方
[大竹文雄の目] 接種勧奨と出口戦略をめぐる政策議論
第3部 「未知のワクチン」の接種はじまる
第4章 接種意向は水物か?〜実際の行動とのギャップ〜
第5章 ナッジは実際の行動も促すのか?〜フィールド実験による挑戦〜
第6章 ワクチン接種の意外な効果
[佐々木・大竹・齋藤の「当時を振り返る」] パンデミック下の研究開発と社会実装
[大竹文雄の目] ワクチン効果の変化と行動制限の必要性をめぐる政策議論
第4部 ワクチン普及後の世界〜「未知」から「既知」へ〜
第7章 ブースター接種にナッジは必要か?
第8章 ワクチン接種者と非接種者の分断と共生
[佐々木・大竹・齋藤の「当時を振り返る」] ナッジの意味とは
第5部 ネクスト・パンデミックのために「行動経済学+感染症学」ができること
第9章 将来のパンデミックに向けた10の政策研究アジェンダ
第10章 政策研究アジェンダの「実現可能性」を議論する
あとがき(大竹文雄、齋藤智也)
■ 本書の著者紹介
佐々木 周作(ささき・しゅうさく)
大阪大学・感染症総合教育研究拠点・特任准教授
1984年生まれ。大阪大学にて博士号(経済学)を取得。専門は、行動経済学、実験経済学。
行動経済学会の副会長とともに、中央府省庁や地方自治体のナッジ・ユニット等で有識者委員やアドバイザーを務める。三菱東京 UFJ 銀行(現・三菱 UFJ 銀行)行員、京都大学大学院経済学研究科特定講師、東北学院大学経済学部准教授等を経て、2022年より現職。
大竹 文雄(おおたけ・ふみお)
大阪大学・感染症総合教育研究拠点・特任教授
1961年生まれ。大阪大学にて博士号(経済学)を取得。専門は、行動経済学、労働経済学。
新型コロナ・パンデミックでは、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会、基本的対処方針分科会等に参加した。著書『日本の不平等』(日本経済新聞社、2005年)ではサントリー学芸賞、日経・経済図書文化賞、エコノミスト賞を受賞。2006年に日本経済学会石川賞、2008年に日本学士院賞を受賞。大阪大学社会経済研究所教授、同大学大学院経済学研究科教授等を経て、2021年より現職。
齋藤 智也(さいとう・ともや)
国立感染症研究所・感染症危機管理研究センター・センター長
1975年生まれ。公衆衛生学修士(ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大学院)、医学博士(慶應義塾大学大学院医学研究科)。医師。専門は、公衆衛生危機管理、バイオセキュリティ。
新型コロナ・パンデミックでは、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード、東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議等に参加した。厚生労働省厚生科学課健康危機管理対策室で東日本大震災への対応等公衆衛生危機管理、結核感染症課で新型インフルエンザ対策等に従事。2021年より現職。2023年より、新型インフルエンザ等対策推進会議委員も務める。
いいなと思ったら応援しよう!