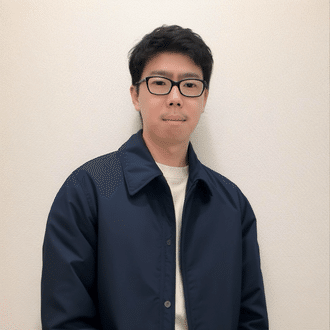難しい経済理論を10分で理解:初心者向け経済学「ミルトン・フリードマン」
経済に関するニュースや話題を目にしない日はありません。
私たちは身近でありながらも解決策を見出せない難しい課題を日々、突きつけられています。
こうした現代のリアルな課題に対して、半世紀以上前の経済理論が新たな洞察をもたらすかもしれません。
その理論を打ち出したのが、20世紀屈指の経済学者、ミルトン・フリードマンです。
フリードマンが提唱した「貨幣数量説」は、私たちの日常生活に潜むインフレやデフレのメカニズムを解き明かし、中央銀行の政策判断に強い影響を与えています。
また、彼の大胆な政策提言「公営住宅の廃止」や「最低賃金制度の撤廃」は、効率性と公平性という2つの視点から社会の仕組みを再検討するヒントを与えてくれます。
本記事では、フリードマンの理論を分かりやすく解説し、現代への応用について探っていきます。
貨幣数量説について
フリードマンの理論で、まず押さえたいのが「貨幣数量説」です。
これは、「お金の総量(マネーサプライ)と、そのお金が経済を循環する速度(流通速度)が、物価と経済成長を左右する」という考え方です。
フリードマンは政府や中央銀行による貨幣供給量のコントロールが、物価安定と経済成長のカギになると指摘しました。
数式で見る貨幣数量説(簡略版)
MV = PY
• M:貨幣供給量
• V:貨幣流通速度
• P:物価水準
• Y:実質経済成長(生産量)
フリードマンの主張は「貨幣供給量( M )が増加すれば、物価水準( P )は上昇する」すなわちインフレが発生するといった考えに基づいています。
この理論により、彼は「インフレは常に貨幣的な現象である」と断言しました。
もし貨幣供給量が経済成長以上に増えれば、その差分は物価上昇(インフレ)を招く可能性が高まります。
こちらの記事も参考にしてみてください。
現代への応用
日本銀行の量的緩和政策は、デフレ脱却を目指した「貨幣供給量」の増加策です。
その背後には、貨幣数量説が理論的な裏付けとして存在します。
また、欧米諸国の中央銀行も金融緩和や引き締めを検討する際、フリードマンの理論を参考にしています。
公営住宅は廃止
フリードマンは公営住宅制度に疑問を呈しています。
その理由は、次の3点に集約できます。
1. 選択の自由の制限
公営住宅は、特定の場所に受給者が縛られるため、多様なライフスタイルや働き方を固定化し、生活水準は向上しません。
2. 効率性の低下
公営住宅を維持・管理するには膨大な税金が必要です。しかし、そのコストに見合うほど住環境の改善や居住者の満足度向上は実現できません。
3. 民間企業への影響
必要な住宅には限度があり、公営住宅が増えれば、民間住宅市場が縮小し、価格競争や質の向上といった市場原理が働きにくくなります。
代替策:住宅補助金の提案
フリードマンは、公営住宅の代わりに、低所得層に「住宅補助金」を付与する考え方を示しました。
受給者は民間市場で自分のニーズに合った住居を選び、結果的に市場は競争力を増し、住宅の質やコストが改善される可能性があります。
日本の老朽化した公営住宅の問題に対して、この補助金制度は必要かもしれません。
最低賃金制度は撤廃すべき
最低賃金制度は労働者を守るための仕組みに思えますが、フリードマンはその「副作用」に注目しました。
1. 労働者の雇用抑制
法定で定める最低賃金が高くなりすぎると、企業はコスト削減のため雇用を控える傾向が強まる可能性があります。
2. 市場メカニズムを歪める
賃金を強制的に底上げすれば、需要と供給による自然な雇用調整が難しくなり、結果的に雇用が生まれにくくなります。
3. 失業率の上昇
最低賃金が払えない企業は倒産するか、既存の従業員を解雇して最低賃金をクリアしようと動くかもしれません。そのため失業率が高まり、貧困対策どころか問題を拡大してしまう恐れがあります。
代替策:負の所得税
最低賃金制度に代わる解決策として、フリードマンは「負の所得税」を提案しました。
この制度は、一定の所得以下の人々に対して税金を還付し、最低限の生活を保障するものです。
これにより、以下のメリットが期待できるとしています。
• 雇用の自由化:企業が労働力を柔軟に活用できる。
• 効率的な福祉:直接的な現金給付で、低所得者を的確に支援。
いま議論されている「103万円の壁」を撤廃する動きも類似した考えです。
所得のセーフティネットを確立できれば、雇用機会を奪わずに経済全体の効率性と公平性を両立させられます。
日本で議論が続くベーシックインカムや労働市場改革を考えるうえで、この視点は示唆に富んでいると考えます。
また、日本では最低賃金の引き上げが議論されている一方で、中小企業への負担増加が問題視されています。
フリードマンの提案する「負の所得税」は、こうした現代の課題に対する新しい視点を提供する可能性があります。
免許・認可制度は不要
フリードマンは医師免許や弁護士資格、タクシー業の許可などは、業界内への新規参入を制限し、競争をなくすとして、不要だとしています。
免許制度の主な問題点として以下を挙げています。
1. 参入障壁の高さ
新規プレーヤーが市場に入るには、高額な取得費用や長期の研修、難解な資格試験が必要。結果として、競争が限定され、業界内の革新が滞る。
2. 消費者の選択を狭める
制度によって限られた事業者だけが正規参入を許されるため、消費者は「より安く、より質の高い」サービスを享受できる機会を逃す可能性がある。
3. 既得権益の保護
既存の免許保有者は、新たな参入者からの競合を阻止し、自らの市場シェアを半永久的に維持できるため、価格やサービスなど品質改善のインセンティブを損なう。
医療免許のケーススタディ
フリードマンは医療分野を例に挙げ「医師免許制度が医療提供者の数を事実上制限し、結果的に医療費高騰を生む」と指摘しました。
本来、医療サービスの質は市場で自然淘汰され、患者からの評判や、第三者認証機関がその役割を果たせば十分だと考えたのです。
「免許がないと、玉石混交にならないか?」と懸念する声もありますが、フリードマンはむしろ、多くの参入者がいることで競争原理が働き、悪質な事業者は自然に淘汰されると説きました。
「患者や専門業界団体などの評価を参考に信頼できるサービスが選ばれ、市場は需給原理に従って最適化へ向かうはずだ」というのが彼の主張です。
ただ、いくら市場の自由が効率化を生むとはいえ、個人的には医療分野では免許は必要では無いかと思っています。
私の考えと同様、この提言には多くの批判がありました。
自由と効率、そして公平性
フリードマンの理論は、必ずしも全員にとって「心地よい」ものではありません。
しかし、彼が着目したのは「自由な市場」と「効率的な政策運営」のバランスです。
それは低成長に悩む現代社会でも有効な問いかけではないでしょうか。
貨幣数量説が示す「お金と物価」の関係は、あなたがニュースで目にする金融政策を分かりやすく捉えるためのサポートになると思います。
また、公営住宅や最低賃金制度といった社会保障制度として「当たり前」だと思われている仕組みを見直す方が、経済合理性があるという視点は非常に面白い理論だと感じます。
経済学の面白さについて
彼の政策提言は、他にも多くありますが、私は全てに賛同しているわけではありません。
むしろ、「何を言っているんだ?」と思うことの方が多いかもしれません。
ただ、経済学が本当に面白いと感じる瞬間は、正解が一つに定まらない点ではないでしょうか。
異なる価値観や立場からの議論が繰り広げられるところに魅力があるのだと思います。
あなたが、何を重視するかによって、「最善策」や「最適解」は大きく変わってしまう、だからこそ、時に「何を言っているんだ?」と思うような極端な意見に触れることすら、私たちの思考の幅を広げてくれます。
フリードマンのように自由市場を徹底的に信奉する学者もいれば、国家主導の経済運営こそが安定をもたらすと主張する人もいます。
片方の見解だけを聞いていると、「それこそが唯一の真理だ」と思い込んでしまうかもしれません。
しかし、全く異なる視点を知れば、私たちは「そもそも経済とは何なのか」「どのような条件で、この政策は有効か」といった問いを改めて考え直すことができます。
経済学は、歴史や文化、そして人々の行動心理などが複雑に絡み合った「社会の縮図」です。
そのため、学者や専門家でさえ、先行きを正確に予測するのは困難です。
その「不確実性」と「多様性」こそ、経済学を単なる暗記や数式のパズルではなく、魅力的な学問へと変えているように感じます。
まとめ
以上、フリードマンの経済理論のトピックをまとめました。
彼の理論をさらに深く理解したい方には、『資本主義と自由』がおすすめです。
自由市場が個人の選択肢を最大化し、結果的に社会全体の厚生を向上させるという強い信念が凝縮されています。
経済理論に「完全な正解」は存在しないと思います。
しかし、新たな視点を得ることで、未来を変えていくヒントを見つけられると私は思います。
フリードマンの思想は、その「ヒント」を与えてくれるのではないでしょうか。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
※「note」を利用する筆者のブログについて
当ブログは、 Amazon.co.jp のリンクによってサイトが紹介料を獲得できる「Amazonアソシエイト・プログラム」に参加しております。
いいなと思ったら応援しよう!