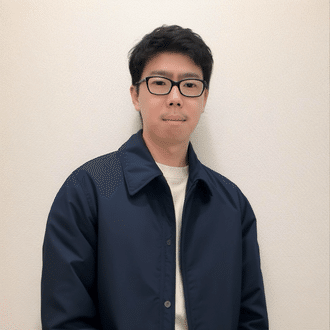具体と抽象:「なんか〜」を多用する曖昧な人
私の周囲には会話の中に「なんか〜」を差し込み、多用する人が結構います。
正直、私はこの「なんか〜」が苦手です。
この「なんか〜」には意味があるのでしょうか。
これは、具体と抽象の概念で考えると、抽象表現です。
本記事では、この抽象表現を多用する人について考察します。
「なんか〜」とは
あなたの周りにも「なんか〜」を頻繁に使う人がいるかもしれません。
この表現は、会話の中で「抽象的なフィラー」として使用されます。
フィラー(filler)とは、会話において、言葉を選んでいる間に時間を稼ぐために用いられる言葉やフレーズです。
例えば、「えー」「あのー」などがこれにあたります。
「抽象的なフィラー」とは、会話において具体的な意味を持たない、あるいは非常に曖昧な意味しか持たない言葉やフレーズを指します。
「なんか〜」は抽象的なフィラーの1つで、他には「〜みたいな」「〜とか」などが該当します。
これらは、会話の流れを自然に保つ役割を果たすケースもありますが、過度に使うと内容が不明確になってしまいます。
「なんか〜」の問題
なぜ、このような曖昧な表現を人は使うのでしょうか。
言語学的には、自信がないときや、自分の考えを整理しているとき、頻繁に用いると考えられています。
また、聞き手に対して具体的な情報を提供せず、時間稼ぎに使われることもあります。
「なんか〜」は抽象性が高く、聞き手にとっては理解しにくい要素となる可能性があります。
ここで考えたいのは、この言葉の選択がコミュニケーションの質にどれほど影響するかという点です。
抽象的表現の影響
言葉は私たちの考えや感情を伝える手段ですが、抽象的な表現を多用すると、コミュニケーションを困難にしてしまいます。
例えば、夏休みの思い出について答える際に「なんか楽しかった」という表現では、具体的な内容が相手に伝わりません。
「海岸で家族と砂の城を作った」と具体的に述べる方が、聞き手にはっきりとしたイメージを提供できます。
もちろん「楽しかった」ということが伝わりさえすれば良い、と考えているならば抽象的な表現でも問題はありません。
しかし、抽象的な言葉の多用は「話し手が自身の感情を整理できていないのではないか」と聞き手に誤解を与えてしまいます。
このようなコミュニケーションスタイルは、聞き手にフラストレーションを感じさせる原因となるため、抽象表現の多用は控えた方がよいと考えます。
5W3Hの意識
コミュニケーションにおいて、具体的な表現は聞き手に明確な情報を提供します。
対照的に、抽象的な表現は話の背景や文脈によって解釈が変わるため、誤解を招くことがあります。
効果的なコミュニケーションを目指すなら、場面に応じて具体性と抽象性のバランスを取るのはとても重要です。
例えば、ビジネスのミーティングでプロジェクトの進捗を報告する際には、具体的なデータや成果を提示することが求められると思います。
「プロジェクトは順調に進んでいます」と抽象的に述べるよりも、
「目標の70%を達成し、次のフェーズに移行する準備が整っています」
と具体的に報告する方が、聞き手に安心感を与え、次のアクションに繋がりやすくなります。
私が「なんか〜」を多用する人を苦手なのは、抽象的な報告や連絡をするからです。
まだ、部下からの報告・連絡・相談ならば、なんとか理解しようと思いますが、上司などからの指示が抽象的な場合は、非常に困ります。
相手に伝わらない指示や命令は、時間を無駄に費やすだけだと思うので、私は出来る限り以下の「5W3H」を意識して伝えるように心がけています。
「5W3H」
When(いつ:時間)
Where(どこで:場所)
Who(誰が:人物)
What(何を:課題)
Why(なぜ:理由)
How(どのように:方法)
How Many(どれくらい:量)
How Much(いくら:価格)
できれば、上位職の人は「5W3H」を意識してコミュニケーションを取ってあげましょう。
仕事や作業の効率が上がるはずです。
言語の選択が与える印象
言葉の選択は、話し手の知性や信頼性の印象にも大きく影響します。
具体的な表現を用いれば「話し手は知識が豊富」という好印象を与えます。
一方で、抽象的な言葉を多用すると、その人の専門性や誠実さが疑われることもあります。
また、聞き手にとって具体的な情報は理解しやすく、記憶に残りやすくなります。
そのため、教育や指導の場面では、具体的な事例を交えながら説明する方が理解を深め、学習効果を高めると言われています。
具体的な表現を増やすトレーニング
「なんか〜」を減らし、具体的な言葉を増やすためには、何をすれば治るでしょうか。
私が考えるに、抽象表現を多用する人は、自分が抽象表現を使っているかどうか分かっていないのではないかと思います。
普段、自分が抽象的な表現を使用しているか意識していないから分からないという人は、まずは自分の言葉に耳を傾け、どのように表現しているかを意識することから始めてみてはいかがでしょうか。
また、情報を事前に整理し、話す前にメモを取る習慣をつけると、自然と言葉が具体的になります。
読書や文章を書くことで、様々な表現を学ぶのも効果的だと思います。
私の場合、noteを毎日投稿していますが、この習慣が具体的なコミュニケーションの訓練になっていると実感しています。
また、気になるフォロワーさんの記事などを読むことで、自分の表現を修正するケースもあります。
このように、具体的な取り組みを継続することで、人は抽象的な表現の多用を克服していくのではないでしょうか。
あと、前文で使いましたが、「このように」と具体例を加える習慣を身につけると、より明確なコミュニケーションへと繋がるので、ぜひ真似してみてください。
まとめ
毎日の言葉選びに少し注意を払うだけで、相手に対する自分の印象を大きく変えられます。
皆さんも、具体と抽象のバランスを意識してみてください。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
いいなと思ったら応援しよう!