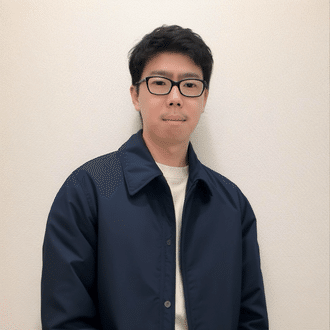M&Aに興味がある初心者向けファイナンス講座 第一回
M&Aに興味を持つ方に向けて、体系的に学べる初心者向けのファイナンス講座を連載でお届けします。
この連載講座ではファイナンスに関する基礎的な知識をわかりやすく解説します。
MBAでの学びを参考に、現場での経験を活かし、財務モデリングの重要性やM&Aにおける手法なども連載の中で紹介します。
初心者でも安心して理解できる内容を目指していますので、ぜひ最後までお読みいただき、ビジネススキルの向上にお役立てください。
ファイナンスの基礎知識
ファイナンスとは、資金をどのように調達・管理・運用するかを体系的に学ぶ学問として確立されています。
企業におけるファイナンスは、投資判断や資本コストの管理、財務リスクのコントロールなどが該当します。
M&A(合併・買収)もファイナンスの一環として扱われることが多く、企業が成長戦略の一環として他社買収や、合併によってシナジー効果を得ようとします。
初心者にとって、まず押さえておくべきはファイナンスとM&Aの基本的な関係性です。
M&Aは大規模な資金調達や投資回収、将来の事業計画を伴います。
そのため、ファイナンスの知識がなければM&Aの実行は困難です。
例えば、企業が他社を買収する際には、現金や株式交換を通じて取引を完了させますが、その買収資金はどこから捻出するか、どうやって調達するか等を考えるのもファイナンスの一つです。
ファイナンスの基本概念とM&Aの関係性
ファイナンスを学ぶ際に重要なのは「資本コスト」です。
多くの人がファイナンスの「運用」、つまり「どれくらい儲かるか?」に焦点を当てる傾向にありますが、そもそも運用するためには、資金調達と管理が必要です。
資本コストとは、資金調達するために支払うコストのことです。
企業がM&Aを実施する際には、自己資本や負債を利用して資金調達しますが、その際にどのような資本(負債)を使うか、どのように資金調達を実施するかによって、取引の成否が左右されます。
自己資本を使う場合は、株主への配当が求められる一方、負債を使う場合は利息の支払いが発生します。
要は、資金調達のコスト(利息や配当)よりも高いリターン(利益)を生まないのであれば、そもそもM&Aを実施する必要はありません。
例えば3%の利息を払って、1%の利益が期待できる事業に、あなたは投資するでしょうか?それは銀行に儲けさせるだけですよね。
そのため、資本コストの概念は、M&Aにおいて重要です。
また、M&Aの場合、「シナジー効果」の検討も不可欠な要素です。
シナジー効果とは、合併などによって、個別の会社で事業活動するよりも、統合することによって効率的に利益を生み出すことを指します。
例えば、本部機能は統一すれば少ない人員で済むかもしれませんし、事業領域の拡大によりスケールメリットによる効果が期待できるかもしれません。
このように、資本コストやシナジー効果を予測するためには「財務モデリング」を学ぶ必要があります。
具体的には次回の講座から詳しく説明しますが、財務モデリングの概要だけは理解しておいたほうがよいです。
財務モデリング
財務モデリングとは、企業の将来の財務状況をシミュレーションするための計算モデル構築のプロセスです。
財務モデリングは、投資判断をサポートする非常に重要なツールです。
特にM&Aの場面では、企業買収によるシナジー効果や財務リスクを事前に評価するために財務モデリングが使われます。
M&Aにおけるシミュレーションでは、買収後のキャッシュフローの予測や、コスト削減効果、収益の増加などの要素を計算します。
これにより、買収が企業にとって成長や収益力向上に繋がるかを事前に判断できるようになります。また、上場企業の場合は株価への影響なども考慮しなければなりません。
財務モデリングがなければ、企業はリスクを過小評価する危険性があり、重大な意思決定ミスを犯しかねません。
財務モデルの構築について
財務モデリングを使ったシミュレーションは、M&Aの成功を左右する重要なプロセスの一つです。
財務モデルを構築する際には、まず買収先企業の財務諸表を分析し、買収によって予想される影響を数値化します。
このプロセスでは、財務三表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)の各項目がどのように変動するかを予測します。
たとえば、ある企業が競合他社を買収するとします。
この際、買収にかかるコストが企業の負債にどのように影響するか、または収益がどの程度増加するかなどをシミュレーションすることが必要になります。
取引後の収益性やキャッシュフローの変化を予測し、企業の将来の財務健全性を評価するのが財務モデリングの役割です。
財務予測と財務モデリング
ここで簡単に財務予測と財務モデリングの違いについて解説しておきます。
財務予測は、過去の実績データや市場の動向、会社の戦略を基に、売上、経費、利益などの主要な財務項目を予測します。
予測の範囲は短期、中期、長期で、資金繰りなどの意思決定に使用されます。
予測は一般的に簡素なもので、変動要因の分析よりも大まかな見通しに重点を置きます。
一方で、財務モデリングは、詳細な数値モデルを作成し、異なるシナリオを検証するために使われます。
複雑なスプレッドシートや計算を通じて、企業の財務状況やその将来のパフォーマンスを分析します。
例えば、M&Aのシミュレーションや新しいプロジェクトの投資判断などに使われ、複数の変数を考慮し、様々な仮定に基づいて結果を試算します。
詳しくは以下のサイトが参考になります。
財務モデリングの基本プロセス
財務モデリングを成功させるためには、いくつかの基本的なプロセスを理解する必要があります。
まず、企業の過去の財務データを分析し、それに基づいて将来の予測を行います。
財務モデリングには主に3つのステップがあります。
財務諸表の作成:企業の過去の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書をもとに、将来の財務状況を予測します。
シナリオ分析:さまざまなシナリオ(たとえば、売上が増加する場合や減少する場合)を設定し、それが財務状況に与える影響を計算します。
キャッシュフローの予測:企業の将来のキャッシュフローを予測し、投資の採算性を評価します。
主要な財務三表の連動性の理解
財務モデリングにおいては、財務諸表の連動性を理解するのが重要です。
財務三表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)は互いに密接に関連しており、一つの変動が他の表にどのような影響を与えるかを理解すれば、より正確なモデルを作成できます。
例えば、損益計算書上で利益が増加すれば、それは貸借対照表の純資産の増加につながります。キャッシュフロー計算書では、営業キャッシュフローとして計上されることになります。
これらの関係性を理解していないと、正確な財務モデルを作ることは困難です。
そのため、ファイナンスについて学習したい方は、並行して財務三表についての基礎知識を学ぶ必要があるかもしれません。
ただ、細かい仕訳や決算処理などを覚える必要はありません。
お金の流れが、ある程度理解できれば、それほど問題ではありません。
分かりやすい初心者向けの書籍で十分だと思います。
初心者向け財務モデルの作成手順
初心者でも財務モデリングを始めることは可能です。
まずはExcelなどのツールを使って、シンプルな財務モデルを作成することから始めましょう。基本的なモデルの作成手順は以下の通りです。
過去データの収集:企業の過去3〜5年分の財務諸表を収集し、これをモデルの基礎データとして使用します。
将来の予測値を設定:売上高や利益率などの重要な指標について、現実的な予測値を設定します。
シナリオ分析を実施:複数のシナリオを設定し、それぞれに対する財務的な影響を計算します。
モデルの検証:作成したモデルを使って、企業の将来のキャッシュフローや収益性を予測し、実際のデータと比較して正確さを検証します。
上記のステップを踏めば、初心者でも財務モデリングのスキルを習得していくことができると思います。
今回の内容では、ファイナンスやM&A、財務モデリングの基礎的な考え方を紹介しました。
次回以降の講座では、Excelのテンプレートを使用して、さらに具体的な財務モデルや、M&Aにおけるシミュレーションについて解説していきます。
ただいま、テンプレートを準備中です。
ぜひ次回の講座をお待ちください。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
いいなと思ったら応援しよう!