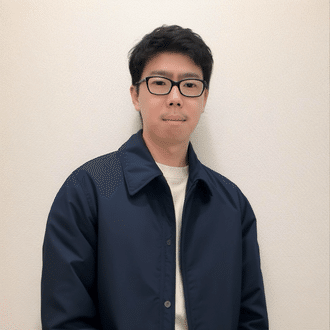貨幣価値と通貨の信用について
今回も、フォローしているnoterの「海尾守」様からの依頼に対する回答記事です。
今回は「貨幣価値が下がり続けると、いずれ円の信頼が無くなりジンバブエドルのようになる」について考察してみます。
これは「貨幣価値が下がり続けると、円への信頼が失われ、物価が急上昇して生活が不安定になるリスクがある」という意味で捉えました。
よって、今回は「貨幣価値と通貨の信用について」の記事となります。
なお、前回の記事はこちらです。
記事執筆の経緯
1.海尾さんの上記のブログ記事のコメント欄に、B様から以下のご質問。
「何世代にも渡って借金を残すのか」
「貨幣価値が下がり続けいずれ円の信頼が無くなりジンバブエドルのようになる」
「日本の借金は1300兆円で20年分の税収に相当する」
と反論されると思うのですが、どう論破すればいいと思いますか?
2.これに対してコメント欄で返信したかった海尾さんですが、noteの制約(コメント500字以内)により、別記事をアップ。
3.以前、海尾さんの記事を引用させて頂いたご縁があり、上記記事の内容の検証依頼がありました。
国債発行によるインフレの可能性
「貨幣価値が下がり続け、いずれ円の信頼が無くなりジンバブエドルのようになる」
こちらの説について、海尾さんは他国の状況や、通貨の信任の仕組みを踏まえて、日本円はジンバブエドルのようにはならないことを論じています。
私も同じ意見です。
ジンバブエドルのように「ハイパーインフレ」を引き起こす要因は、債務の金額の問題ではなく、統制不能な政策や信用喪失が重なった結果だと思います。
日本円の場合、特に国内外の需要が強固であり、経済の信頼性が維持されている限り、同様の状況に陥る可能性は非常に低いと考えます。
海尾さんが述べているとおり、アメリカや中国も多額の債務を抱えています。
それでも米ドルや中国元の信用が維持されているのは、経済の強靭さと国際的な需要があるためでしょう。
結論として「国債を発行し過ぎると、円の価値が下がってインフレになる可能性は若干あるかもしれないが、必ずしも因果関係があるわけではない」と考えます。
通貨の信用に関する理論
通貨の信用とインフレの関係については、フィッシャーの交換方程式を使うと分かりやすく説明できます。
この方程式は、経済における通貨の供給と需要が物価に与える影響を理論的に示しています。
フィッシャーの交換方程式
フィッシャーの交換方程式は以下のとおりです。
MV = PY
M: 貨幣供給量(市場に流通する通貨量)
V: 流通速度(通貨がどの頻度で取引に使用されるか)
P: 物価水準
Y: 実質GDP(経済の規模)
この式は、経済全体の取引価値( PY )は、貨幣供給量と流通速度の積 (MV) に等しいことを示しています。
流通速度とは
流通速度とは、通貨がどのくらいの頻度で取引に使われているかを示す指標です。
例えば、ある100円が1年間に何回も使われるなら、そのお金が経済全体に与える影響は大きくなるといえます。
以下に事例を示します。
• 流通速度が低い場合
もし、100円が1年間で1回だけ使われるとすると、その100円は1回分の価値しか生み出しません。例えば、ある人が100円でリンゴを1個買ったきりで、次の取引には使われないと考えてみてください。その100円は経済活動にはあまり貢献していない状態といえます。
• 流通速度が高い場合
一方で、同じ100円が1年間に10回使われた場合を考えてみましょう。例えば、100円が最初はリンゴの購入に使われ、その後も何度も使われ続け、最終的に10回取引されると、その100円は経済全体で10倍の価値を生み出したことになります。
このように、流通速度が高いと、少ない貨幣供給量でも多くの経済活動が行われます。
流通速度とインフレの関係
流通速度が高まると、同じ量の通貨でも取引回数が増え、物価水準(P)が上昇しやすくなる傾向があります。
人々が手元にあるお金をすぐに使おうとすると、お金が「不足」しているように感じられ、商品の価格が上がりやすくなるからです。
逆に、流通速度が低下すれば、取引に使われるお金が少ないため、物価も安定しやすくなります。
このように、流通速度は、経済活動や物価水準に大きく影響を与える要素の一つです。
通貨の需要が安定している場合のインフレリスク
「通貨の需要が安定している」とは、実質GDP(Y)の規模と貨幣の流通速度(V)が大きく変わらないことを意味します。
この場合、中央銀行が貨幣供給量(M)を適切にコントロールすれば、物価水準(P)も安定し、急激なインフレは発生しにくくなります。
数式に基づくと、物価水準(P)は以下のように表されます。
P = MV / Y
もし貨幣供給量(M)が安定し、流通速度(V)と GDP(Y)も一定ならば、物価水準(P)も安定した水準を維持します。
したがって、通貨の需要が変わらない日本において過度なインフレは発生しにくいといえます。
通貨の需要が急減した場合のインフレリスク
次に、通貨の需要が急減した場合(すなわち、流通速度が急上昇した場合)について考えます。
このような状況では、貨幣供給量(M)が変わらなくても、物価水準(P)が急上昇し、インフレが発生するリスクがあります。
通貨の需要が急減する理由としては、通貨に対する信用低下や不安から多くの人が急いで通貨を手放し、商品や他の資産に交換しようとするためです。
数式での説明
流通速度(V)が急増すると、物価水準(P)はどうなるでしょうか。
P = MV / Y
もし流通速度(V)が急増し、貨幣供給量(M)や実質GDP(Y)が一定ならば、物価水準(P)は増加します。
つまりハイパーインフレが発生するリスクが高まります。
分かりやすくするために、数字を入れて説明します。
貨幣供給量 M = 100
実質GDP Y = 200
流通速度 V = 1
上記の値を代入すると、物価水準 P は次のようになります。
P = (100 × 1) / 200 = 0.5
ここで、何らかの要因で通貨の流通速度(V)が急増し、V = 4 になったと仮定します。
この場合、物価水準(P)はどうなるでしょうか。
P = (100 × 4) / 200 = 2
初期の物価水準は P = 0.5 でしたが、流通速度が V = 1 から V = 4 に急増したことで、物価水準は 0.5 から 2 まで上昇しました。
つまり、物価水準は4倍に急上昇します。
このように、流通速度が急増すれば、物価水準は急激に上昇し、インフレが加速します。
通貨に対する信用が大幅に低下し、経済全体で通貨の流通速度がさらに上がる(金が手に入ったら、すぐに使うようになる)と、ハイパーインフレに陥るリスクが高まります。
しかし、預貯金好きの日本人の場合、この現象は起きにくいのではないでしょうか。
あるとすれば、「円よりゴールドだ」「仮想通貨で持っておこう」「不動産の方が安心だ」といった、別の資産への交換かもしれません。
通貨の信用に関する留意点
つまり、通貨の価値は供給量よりも、国の信用力と経済基盤に基づいているといえます。
日本には強固な経済基盤があるためハイパーインフレなどの心配は少ないと思います。
しかし、信用力の維持には「持続的な経済成長」と「安定的な財政運営」が必要であり、それが失われると円の信用も揺らぐ可能性はあります。
たとえば、人口減少や経済成長の停滞が続けば、円の信用が揺らぐ可能性もあるかもしれません。
結論
通貨の需要が安定している(V や Y が一定)場合、中央銀行が通貨供給量 M をコントロールすることで物価水準 P を管理でき、過度なインフレリスクは低くなります。
通貨の需要が急減(流通速度 V が急増)すると、通貨の信用が低下して物価水準 P が急上昇し、インフレやハイパーインフレのリスクが高まります。
このように、通貨需要の安定性がインフレリスクに大きく関与しているといえるでしょう。
よって、海尾さんの記事と私は同意見といえます。
長文をお読みいただき、ありがとうございます。
いいなと思ったら応援しよう!