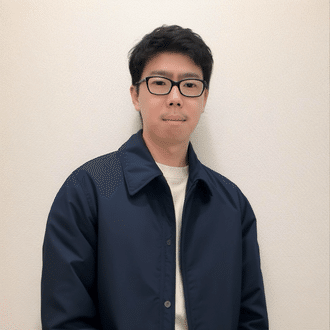銀行員の職位定年:意識を変えられるか?専門性があるか?
40代後半から50代の銀行員は、銀行生活の終わりを迎える準備が必要です。
多くの銀行では50代で職位定年を迎えます。
この現実に対し、どのような対策が取れるのでしょうか。
この記事では、銀行に留まるメリットとデメリット、新たなキャリアの模索、収入維持の方法を解説します。
職位定年後の人生設計を考える方に、必読の内容です。
職位定年後、銀行員の給料はどう変わるのか?
職位定年を迎えると、多くの銀行員が給料の減少という現実に直面します。
しかし、なぜそのような減額が行われるのか、具体的にどの程度の影響があるのかは、まだ多くの人が理解していないかもしれません。
ここでは、職位定年後の給料の変動について解説し、その背景にある銀行業界特有の事情についても触れていきます。
今後のキャリアを考える上で、ぜひ知っておきたい情報です。
職位定年後の給料の減少幅
職位定年後、多くの銀行員は給与が約20〜30%減少するとされています。
これは、銀行が組織の年齢構成を適正化するための措置です。
年功序列で昇進する銀行では、年齢とともに役職が自動的に上がり、人件費が増加するため、定年を迎えた社員の給与を調整し、若手行員へシフトさせる必要があります。
労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、61歳時点の給与は60歳直前の約73.5%まで減額されることが報告されています。
職位定年後の給与減額は業界全体で一般的な傾向といえます。
手当や福利厚生
職位定年後は基本給だけでなく、各種手当や福利厚生も見直されることが一般的です。
職位定年によって管理職としての責務が軽減されることに伴い、管理職手当や職務に関連する福利厚生が減額されるケースが多く見受けられます。
多くの銀行では職位定年後の福利厚生見直しを行っており、具体例として、住宅補助費や通勤費補助の削減などが一般的な対応のようです。
職位定年後の収入と支出のバランス
銀行の場合、40代に突入すれば、自身のポジションの限界も見えてきます。
職位定年後の収入減少を見越し、生活費の見直しや副収入の確保を検討することが重要でしょう。
支出を削減できなければ、生活費のバランスが崩れ、将来的な家計への影響が大きくなる可能性があります。
そのため、支出の見直しや、副業の検討が必要かもしれません。
職位定年後のキャリア形成
職位定年を迎えた後も、長年の経験と信頼関係を活かし、銀行に留まりたいと考える方は多いかもしれません。
ただ、職位定年後の銀行でのキャリアには、新たな役割や収入面での変化が伴います。
そんな中で、キャリアの新しい道も模索しつつ、銀行に残る場合にはどのようなスタンスが重要なのでしょうか。
職位定年後に銀行に留まる場合に意識すべきポイントについて考えてみます。
銀行に残るメリットとデメリット
職位定年後に銀行に留まるのは、安定した収入や信頼関係の維持といったメリットがある反面、キャリアの限界や収入減少というデメリットもあります。
職位定年後に銀行に残る大きなメリットは、信頼関係を活かした仕事の安定性でしょう。
長年勤めた組織のため、同僚や顧客との関係性が構築されており、職場での本人のストレスは軽減されると思います。
また、再就職先を探す時間や手間を省き、スムーズに業務を継続できる点もメリットといえるでしょう。
しかし、同時にデメリットも存在します。
前述のように、職位定年後の給与は減額されるのが一般的です。
また、昇進やキャリアアップの機会は限られてしまうことから、将来設計が制約される点はデメリットといえるでしょう。
したがって、留まるか否かの判断には、自身の優先順位と将来計画をしっかり見据えることが重要だと考えます。

銀行に留まる場合のキャリアと姿勢は?
銀行に残る場合、自身の役割を再定義し、新しい役割の模索が必要でしょう。
職位定年後、銀行での役職が変化しても、価値を提供できる場面は多く存在すると思います。
たとえば、これまでの経験を活かして若手の育成や知識の共有を行い、行員のスキル向上に貢献するなどが考えられます。
このような形で組織に対して新たな役割を果たす姿勢は、結果として銀行における存在意義をアピールできると思います。
しかし、勘違いしてはいけないのは、「職位定年後も同じ役割が期待されるわけではない」という点です。
銀行に留まることで、これまでと同様の責任や権限をもてるとは限りません。
役職や評価が変わる中で、従来の立場に固執せず、自ら変化に対応する柔軟な姿勢が求められます。
特に重要だと考えるのは、過去の実績やポジションに頼らず、現在のニーズに応えるための行動です。
たとえば、新しい業務やデジタルツールの導入に率先して参加し、自身の経験と最新の技術を融合させる取り組みなどが価値を生み出すのではないでしょうか。
もし「昔、俺が営業してた頃は…」とか「支店長時代に表彰を受けたときは…」といった武勇伝を伝えるために留まりたいと考えているなら、おそらく職場の邪魔な存在になるだけでしょう。
職位定年後のキャリアにおいては、過去の役職やポジションにこだわらず、今必要とされていることに全力を尽くす姿勢が、銀行内での存在意義を確かなものにすると考えます。
年功序列での評価体系が変わりつつある銀行業界では、スキルを基に評価される流れが強まっているため、個々の専門性が待遇に直接影響する可能性もあります。
昔の知識と経験だけで頑張ろうとするのはやめた方がいいと思います。
収入を維持するために必要なアプローチは?
職位定年後も収入をできるだけ維持するには、転職を検討してもよいかもしれません。
職位定年後の給与減額が受け入れられない場合、収入維持のために転職を視野に入れるのは賢明な選択肢の一つでしょう。
銀行で長年培った経験やスキルを活かせる業界や職種への転職を検討すれば、給与水準の維持や昇進のチャンスを得られるかもしれません。
ただ、転職を検討する際は、銀行でのキャリアを振り返り、どんなスキルや経験が他の業界でも活かせるのかをしっかりと見極めることが大切です。
あなたに、スキルも資格も何も無い場合、転職は難しいかもしれません。
これから先、長く働いてもらえない50代が採用してもらうためには、専門性が求められます。
事実、一般的な銀行員は、サラリーマンとしての総合力は高くても、専門性を持ち合わせていない人が多いため、転職先であまり重宝されません。
むしろ、「役に立たない人」扱いされる可能性さえあります。
そのような立場になる可能性を少しでも恐れている方には、転職はオススメしません。
出向という道も考えられますが、職位定年後の出向は給与水準が上がるわけではないので、収入を維持したいのであれば専門性を持った状態での転職がベストではないでしょうか。
まとめ
職位定年後も銀行に残りたいと考える場合、役割の再定義が有効です。
あまり目立たず、必要とされることを淡々とこなす方が、周囲から評価されると思います。
もし、収入を維持したいのであれば、早めに専門性を身につけるべきでしょう。
もう職位定年が近いのであれば、今から間に合うスキルや資格は誰でも取得できるものが多いので諦めた方がいいかもしれません。
それでも、働ける場所があるだけマシと思えれば、なんでもできるかもしれません。
自身の価値を再確認し、将来の一歩を踏み出してください。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
いいなと思ったら応援しよう!