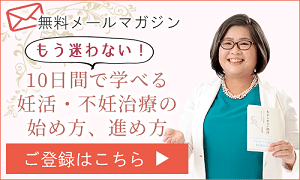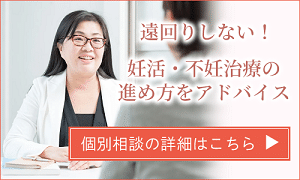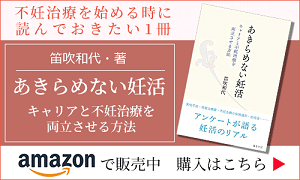【不妊治療と保険適用】 保険適用の年齢条件について
先日、不妊治療の保険適用に関する年齢と回数の条件が話題になりました。
来年4月に始まる不妊治療の公的医療保険の適用を巡り、厚生労働省が体外受精に関しては保険の対象となる年齢や回数を制限する方針を固めたことが7日、分かった。現在の国の助成制度でも治療の効果を勘案し、「妻の年齢が43歳未満」「最大6回まで」という上限がある。これと同じ条件とする案が有力で、年末までに決定する。回数や年齢を超えた場合も治療は受けられるが、全額自己負担となる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5c279c439b574d19c5391021cc0474c12b2fc92
不妊治療の保険適用の年齢や回数の条件に関しては、現行の助成金制度の条件がそのままスライドされる可能性が有力となってきているようです。
この記事では年齢条件について書いていきたいと思います。
(回数に関してはまた別記事で記事にしていきます)
なぜ43歳未満なのか? 年齢関係なく保険適用してほしいという声
SNSでこの話題に触れた際に、なぜ年齢で保険適用が制限されるのか?年齢関係なく保険適用してほしい。これでは助成金と大して変わりないのではないか?
そんな声も多く見受けられました。
ただ不妊治療は年齢とともに出産までたどり着く人は非常に少なくなります。
43歳以上の出産率(生産率)は以下の数値になります
*2018年日本産婦人科学会報告より
43歳 3.1% (28715周期中877症例)
44歳 1.7% (20212周期中350症例)
45歳 1.1% (13187周期中145症例)
46歳 0.7% (7480周期中54症例)
ちなみにこちらの数値は何歳の時に保存しておいた受精卵かは、この報告書からはわかりません。
この数値を少しでも可能性があるのであればと読むのか、それとも可能性は限りなく低いと読むのかは個々によって違ってきます。
周りに43歳や44歳で妊娠、出産に至った人がいれば、可能性があるかもしれないのに、なぜ43歳未満で区切るのか?という憤りを感じる人もいるでしょう。
どうしても40歳以上の場合、妊娠・出産に至った例ばかり取り上げられがちです。
でも、妊娠・出産までたどり着いた人がいる反面、ほとんどの人は妊娠・出産に至ることはなく不妊治療を終えていきます。
厳しいかもしれませんが、年齢とともに可能性が低くなる不妊治療に関しては、どこかで線を引かなければならないのです。

43歳以上の患者の治療を積極的に行っているという矛盾
なぜ保険適用年齢に関して制限がつくのか?という声があがる要因の一つに、各クリニックが43歳以上の患者の治療を普通に行っているということがあげられるのではないかと考えています。
こちらは都内のあるクリニックの患者の43歳以上の割合です。
(各都道府県が行ったクリニック調査の報告データから抜粋しています)
Aクリニック 29%(604人)
Bクリニック 14%(324人)
Cクリニック 25%(2603人)
Dクリニック 15%(544人)
Eクリニック 16%(286人)
Fクリニック 18%(274人)
Gクリニック 22%(291人)
Hクリニック 16%(204人)
Iクリニック 22%(322人)
Jクリニック 45%(132人)
どうでしょうか?
ここにあげた多くのクリニックは不妊治療でも有名なクリニックの為、どうしても43歳以上の患者が集まりやすいという点はありますが、患者全体の2割前後が43歳以上、クリニックによっては半数近くが43歳以上の患者が占めるところもあります。
・出産に至る可能性は5%以下であることを知って納得して治療を選択しているのか?
・それとも、体外受精を繰り返せば出産できるはずとクリニックを信じて治療を継続しているのか…
もし後者の割合の方が多いのであれば、不妊治療の保険適用年齢の制限に疑問があがっても仕方ないのかもしれません。
クリニック側からの治療終結の提案やサポートも必要になってくるのでは?
43歳以上でも繰り返し治療を続ける人がここまで多いのはなぜなのでしょうか?
・医療者側は、患者は出産に至る可能性が低いのを知ったうえで治療を選択している。
・患者側は、医師はある程度可能性があるから治療を提供してしている。やめ時は医療側から提案してもらるはず…と思っている
実はこんな行き違いが起こっているのではないか?と思う時があります。
特に気になるのが医療側の説明が十分ではないという点です。
以前、とあるクリニックのブログ記事が炎上した時にこのような事をツイートしたことがあります。
治療を繰り返すに従って、患者は治療の終わりを模索し始めている。このまま治療を続けようか、もう終わりにした方がいいのか…なかなか聞けないけど本当は医師からアドバイス欲しい人も多いのでは?
— 笛吹和代@「あきらめない妊活」キャリアと不妊治療を両立させる方法 2月12日発売 (@wlsskazuyo) August 10, 2021
患者が何も言わないからと言って、患者は治療継続を望んでいると思い、ただただ治療を繰り返すだけ
というのもどうなのか?と思う。
— 笛吹和代@「あきらめない妊活」キャリアと不妊治療を両立させる方法 2月12日発売 (@wlsskazuyo) August 10, 2021
治療回数ごとに区切りを決めて、治療の継続有無をカウンセラーやコーディネーターと話す機会をクリニック側がきちんと設けてほしい。特に難治性の患者が集まるクリニックは余計に。
医師にどのように質問したらいいのかわからない、短い診察時間であれこれとは聞けない、でも誰にも相談できない…と悩んでいる人は少なくありません。
クリニックには客観的に判断するデータがあります。
医師が時間を取って説明できないのであれば、カウンセラーやコーディネータが客観的なデータをもとに、今後は治療のやめ時のサポートもしていく必要があるのではないでしょうか?
特に保険診療と自由診療が切り替わる43歳のタイミングでは、きちんと説明し、納得したうえで自由診療の不妊治療をスタートさせる必要があると思います。
自由診療に変わった瞬間、効果が怪しげなオプションの追加等、患者のどうしてもという心理に付け込んだような治療が繰り返し提供されないことを願うばかりです。
不妊治療の保険適用は今まで不妊治療に多額のお金を費やしてきた多くの人の願いでした。
ようやく2022年4月から保険適用がスタートされます。
しかし、不妊治療の保険適用はここがゴールではありません。
まだまだたくさんの問題を抱えていますし、残念ながら保険適用43歳未満という制度をうまく利用としてくるクリニックも出てくるかもしれません。
今後どのように不妊治療の保険適用が運用されていくのかきちんと見守っていく必要があると思います。
回数制限に関してはまた別記事で書いていきたいと思います。
こちらのメルマガでもお伝えしていきます。
いいなと思ったら応援しよう!