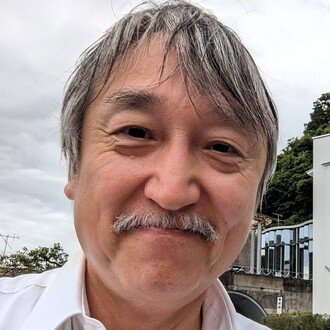MSDOS3.x - 新時代だ!
1984年はMacintoshが発売された年として記憶されていますが、IBMもこの年にPC-ATを発売しています。
IBM PC-AT - 互換機の代名詞となった新機種
CPUは80286となりましたが、売りとなる追加されたプロテクトモードを活用するOSはあまり使われず、基本的には高速な8086として使われていました。大きな変化としては標準でハードディスクが搭載されたようになったことで、これに合わせてMS-DOSもVer3になりました。
MS-DOSの進化と国際化対応 - Version 2.x
ハードディスクを搭載したことにより、アプリを使う度に起動フロッピーを入れて再起動して立ち上がるのを待っていたのに比べれば、あっという間にパソコンが立ち上がり、すぐにアプリを使える状態になります。アプリケーションのデータも「どこに仕舞ったっけ?」とフロッピーを探すこと無く、ハードディスク内のいつもの場所に置いたままで済むようになりました。これでせっかくVer2で追加された階層化ディレクトリも活用できます。
見た目ではわからないのですが、大容量(といっても数十MB)のハードディスクの領域を管理するのですから、フロッピー時代のFAT12と呼ばれる方法で使うと、ひとつのブロックが大きくなりすぎて、小さなファイルをたくさん作るとあっという間にディスクが溢れてしまいます。そこでハードディスクに対してはFAT16という、より細かな管理が出来る方法になりました。
File Allocation Table
そして3.1からは遂にネットワークがサポートされるようになりました。さあ「新時代」です!
【Ado】新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
この時点では、そもそもネットワークに接続して使うという使い方は限られていて、今までのように大型機の端末として使うのではなく、部屋のどこかに置かれたネットワーク・サーバと接続して使う形が想定されていました。そのためネットワーク・サーバ毎に異なるNOS(ネットワークOS)に対応する必要があり、代表的なものにはNetWareであるとかLANMANなどがありました(そしてTCP/IPもあります)。
ネットワークオペレーティングシステム
MS-DOS側では、これらのNOS毎に対応したデバイスをお馴染みのCONFIG.SYSで組み込んで、ファイルを共有したりすることが出来るようになるわけです。MS-DOSはシングルユーザ(そしてシングルタスク)なので、ネットワークに対してはPC毎に固有のユーザでログインして使うのが一般的でした。もっとも当時、ネットワークに接続して使うようなPCはオフィスくらいで、NOSを組み込むとそれなりのメモリを使うので、ゲームはもちろんアプリもメモリ不足を引き起こすことが多く使い勝手は良くなかったです。それもありEMSやXMSにデータを追い出すような使い方が増えていきました。
さてVer3.21になり、ようやくアジア圏に対して個別にカスタマイズしていた2バイト文字コードが正式に取り入れられることになりました。とはいえ「使える」だけで具体的な実装は相変わらずOEM毎ではあります。異なる2バイト文字圏(日本と中国)のファイルを混ぜて使えば文字化けで済めば御の字でアプリによってはPCがハングアップすることすらありました(良くベルが鳴りまくりとかしました)。
こうしてハードディスクと共にVer3.xは広く使われるようになったのですが、ここからが少しややこしいことになります。PC-9801向けのMS-DOSはVer.3を出すにあたり、Ver.3.21をベースに日本語処理などを追加したのですが、この時にバージョン番号を3.3としてしまったのです。これはあくまでNECな世界なので、ご本家の方ではこれを無視してPS/2が登場した時に3.3としたので、同じバージョン番号であっても機能が異なるという事態になってしまいました。マイクロソフトはOEM先の問題としてあまり気にしていなかったようで、これが次のVer.4の時代には混乱を招くことになりました。まあ、まだPC同士を接続することも無いですし(ネットワーク接続は使い方としては、あくまでサーバと接続するだけ)、バージョン番号なんて識別できれば良くてマーケの問題じゃない?くらいに思っていたのかもしれませんが。
フロッピーからハードディスクがメインの使い方になったので、異なる設定が必要なアプリを切り替えるのに苦労するようになり、これを管理するようなユーティリティなどが多く登場しました。NECもMS-DOSに付属させるメニューアプリを充実させるのに努力したようで、3.3Aから少しずつ改良を加えて3.3Dまでをリリースしましたが、比較的よく知られているのは3.3Cかもしれません。電源を入れメニューからアプリを選べばすぐに使えるという形になったので、あまりPCに詳しくなくても使えるようになり、実際に使う人がとても増えたのがこの時代です。
ユーティリティの中にはメモリの中に「常駐」し、他のアプリを使っているときにも呼び出せる機能が使えるということで、多くの「常駐ソフト」が流行りましたが、当然ですがアプリが使えるメモリを減らすので、いよいよ640Kまでフル実装しているPCでもメモリが足りなくなるようになりました。「便利な機能は欲しい、でもメモリが足りない!」ということで、メモリをやりくりするメモリ職人が多く現れた覚えがあります。ちょうどパソ通が流行り始めたこともあり、職人たちがセッセと情報交換している掲示板が大流行していました。
MS-DOS
ヘッダ画像は、以下のものを使わせていただきました。https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NEC_MS-DOS_3.3C.jpg
Darklanlan - 投稿者自身による著作物, CC 表示 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94047049による
#レトロPC #MSDOS #PCAT #NEC #PC9801 #NOS #日本語 #2バイトコード #ハードディスク
いいなと思ったら応援しよう!