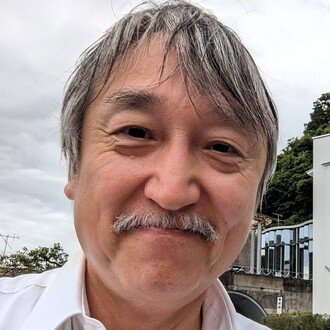マイコン博物館の展示物たち その15 - 変わり種ハードとソフトたち
さて長い事、マイコン博物館の展示物を紹介してきましたが、そろそろ終わりが見えてきました。今回はマイコンとは限らずちょっと変わったデバイスやソフトウェアたちを紹介します。
最初はヘッダ写真に使った「100ドルPC」、世界中の子どもたちにパソコンやネットワークを体験してもらうには今のPCは高機能すぎるし高すぎる。100ドルのPCがあれば、学校に寄付してひとりひとりに体験してもらえるだろうということで開発されたものです。
OLPC
子どもたちに「学びの機会を与える」ためのコンピューティング教育で、考えるべきこと――OLPCの開発者たちが語る
この取り組み自身は素晴らしいもので、開発されたハードウェアもなかなか良くできていたのですが、ハードウェアを与えるだけで解決できる問題には限りがあったようです。スマホ時代の今、デジタル体験がPCで良いのかというのが今の課題なのかもしれません。
さて、学習用といえば、懐かしいハードもありました。1978年にTIから発売されたスピークアンドスペルというものがありました。まだパソコンですら、ようやくその姿を表した時代に音声で話してくれるデバイスには夢がありました。音質はとにかく発音としては本格的で日本人にはちゃんと聞き取りにくい「正しい」英語を話してくれた記憶があります。
Speak & Spell (toy)

世界中のアーティストから愛されたSpeak & Spellの復刻版が発売
Speak & Spell (1978年にTIが発売した喋る知育玩具)です。
そして時代を彩ったソフトウェアたちも並んでいます。もちろんソフトなので並んでいるのはあくまでパッケージではありますが、ああ、あれも使った、これも使った。中には随分と泣かされた記憶が蘇ってきます。


棚の隙間にはそれこそ何でも並んでいる感じです。80年代のメディアと言えばカセットテープか5インチフロッピーで、身の回りにある磁石がどれも危険物に見えたものです。

時代が進むと光学メディアが普及して磁石が怖くなくなりました^^;

そして通信の時代が始まります。電話線にモデムを接続して「ピーヒャラヒャラ」とやっていました。

モデムを使う前は受話器に音響カップラを巻き付けていたんですよね。そんな時代の電話はまだ黒電話。

そんな昔、図書館に行けばお世話になったマイクロフィルムというものがありました。本棚に本を並べるには場所を取りすぎるので、各ページを写真に撮ってそれを閲覧する道具がありました。写真と同じ話なのですが、かなり小さなフィルムに焼き込むので資料的な分厚い本は、これを使って閲覧することも多かったです。といっても数回しか使ったことはありませんが。

最後に元祖マイコンともいうべき基板たち。技術少年出版から出ているマイコン学習キットともいうべき基板時代のマイコンの復刻版です。こんな時代のCPUをどこから手に入れているのかとは思うのですが、半導体は長持ちするのであるところには残っているようです。
技術少年出版


何とERIS6800を近く発売するそうで、TinyBASICも動くのだそうです。最近のプログラミングは巨人の肩に乗っているものばかりなので、1からコードを書く体験が貴重なのかもしれません。
X にあった告知 - 夢の図書館+マイコン博物館+模ラ博物館(公式)
コンピュータ・サイエンスの入門に適したトレーニング用マイコンERIS6800を2025年新春に発売します。
— 夢の図書館+マイコン博物館+模ラ博物館(公式) Microcomputer Museum Japan (@Dream_Library_) January 17, 2025
小学校高学年からアセンブラ言語を始めると、コンピュータの仕組みを理解出来、その後の上達が早く、腕利きの技術者になれます。
電子立国の復活を小中学生に託すのがERIS6800の目的です。… pic.twitter.com/KgovVMsnn3
さていよいよ次回が最終回かな。
#マイコン博物館 #OLPC #SPEAKandSPELL #SoftwarePackage #Modem #CDROM #電話機 #フロッピーディスク #マイクロフィルム #ERIS
いいなと思ったら応援しよう!