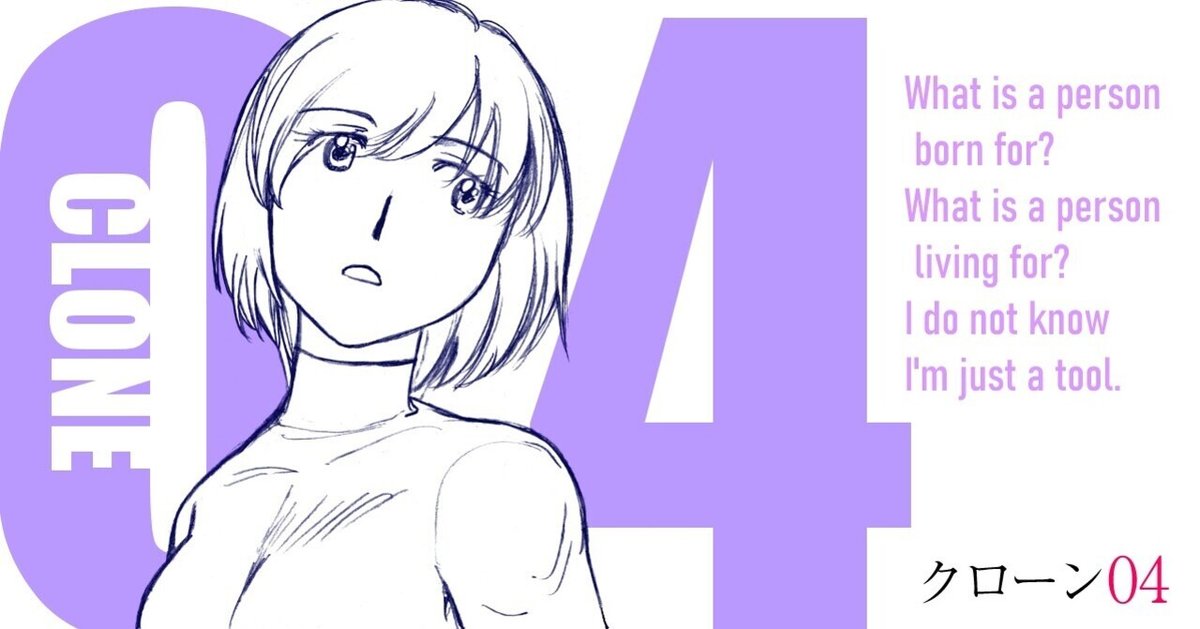
クローン04 第6話
六 彼女が私で、私は彼女
「リンスゥ、表の札、ひっくり返しといて」
「はい」
ヤーフェイの指示を受けて、リンスゥは大きく開いた店の正面、その両脇にたたまれた扉に向かう。そこには「営業中」の看板がかかっていた。
その板に手を伸ばし裏返す。すると表示は「準備中」になる。営業時間外だというお知らせだ。
この食堂は正面の壁を全部開けられるようになっていて、晴れた日には店の前にも席を用意している。今日は風もなく一日いい天気で、まさにそういう日和だった。とても貴重な一日だ。
人間の経済活動と天候の間には、昔から切っても切れない関係があった。食料生産はもちろん、衣料、レジャー、その他もろもろ。気候変動が進んだ現在では、その影響はますます大きくなっている。こんな小さな食堂では、なおさらだ。
突然のゲリラ豪雨で大急ぎで机を引っ込めることもざら。そもそも暑すぎて、外の席どころか、正面を開けない日もある。何日も続く暴風雨になれば客足も遠のく。海寄りのこの地域では水害も多く、店を閉めなければいけないこともある。売り上げの見通しも仕入れの計画も、まさに雲行き一つで大きくくるわされる。
だから今日のような晴れたおだやかな日は、本当に貴重なかせぎ時なのだった。朝から晩までリンスゥはいそがしく働いた。そしてようやく店じまいの時間となっていた。
店内のお客さんも、もうだいぶ少ない。
「やあ、すまないね、もう終わりかね」
「ああ、大丈夫ですよ。そのお品はゆっくり食べていただいて」
「ありがたいね。こいつをじっくり味わうのが、一日のしめのお楽しみなんだよねえ」
ヤーフェイが返事をしたのは、いつも最後までいる初老の男性。おつまみの皿と酒が注がれたグラスを前にして、いい気分で酔っている。長っ尻だが悪酔いしない、いいお客さんだ。
「そちらも、急がなくていいですからね」
先ほど営業時間終了すれすれに入ってきて、あわてて遅い夕食をかっこむ男性が、口にご飯をほおばったまま、うんうんとうなずいた。近くで働く独身男性。毎日この人が来るのを待って、ラストオーダーになる。
リンスゥもこの辺りの常連客と、ようやく顔なじみになってきたところだった。マリアほどの余裕はないが、少しずつ話したりもするようになっていた。
少しずつ慣れて、この店のことがわかってきた。
少しずつわかってきて、それが日常となってきた。
そう感じていたところだったので、このあと来た客と、それにより起きた事態にとまどったのだ。
一人の見知らぬ客が、戸口でじっと立ちすくんでいた。
何か思いつめたような、青ざめた顔の青年。
伏目がちに身じろぎもせず立つ姿は、細い体躯と、手入れされずぼさぼさの髪と相まって、まるで幽霊のようだった。気づいた店内のみんなが一様に、あ、という顔をする。だが、声には出さず、すぐ目をそらした。
リンスゥにとっては初対面だが、どうやら常連客の間ではよく知られている人のようだ。けれど、それにしてはみんなの反応がおかしい。
あの最初の日に会ったゴロツキのような危険人物なのかと一瞬考えたが、臨戦態勢を取るコンマ数秒の間に、それはちがうなと思い直す。
戦闘に必要ない感情を抑制され、自分の心の動きにはうといリンスゥだったが、逆に相手の気配や、そこから生まれる緊張感には敏感だ。それは戦いを生きぬくために必要なスキル。そしてその緊張感も数多く味わってきた。だが今店内を支配するこれは、見知ったものとは少しちがう。
目を合わさないのは暴力に対する恐怖からではない。目を合わせただけでもこわれてしまう、そういう恐れ。ふれてはいけないこわれ物をあつかうときのような、そんな緊張感がただよっていた。
自分はどう対応すべきか、みんなの様子だけでは情報が少なすぎて、リンスゥは決めかねていた。けれど青年が突っ立ったままピクリとも動かないので、とにかく声をかけようと一歩ふみ出した。扉の札を返したように、もうオーダーは止まっている。周りの様子からは、この青年が本当に客なのかも疑わしかったが、とにかくまずはそれを伝えなくては。
「あ、待ってリンスゥ」
その時、店の奥から声がした。
マリアだった。ちょっと席を外していたのだ。
マリアの登場は、店内を支配する緊張感を、ますます高めた。
それはリンスゥには意外なことだった。この店でのマリアの存在は、緊張よりも弛緩を呼ぶもの。みんなを和ませ、場を明るくする。いつもなら自然と人目を引くマリア。だが彼女からも、みんなは目をそらしている。不自然極まりない。そして、その不自然さを、当のマリアも受け入れているようで、辺りに目を配ることもない。これも意外なことだ。
次々と起こる予想外の状況にとまどうリンスゥ。戦闘モードであれば即断即決の彼女だが、経験のないこういった状況では、どうふるまえばいいのかわからない。
マリアは通りすがりに片目をつぶって、そんなリンスゥにささやいた。
「私のお客さんなんだ」
マリアはそのまま、優しい笑顔を浮かべながら青年に近づいていく。それに対して青年は、マリアを見つめる目線を切って、また目をふせた。その表情は対照的に苦しそうだ。
「ごめん、俺、また……」
「ううん、いいよ。もう少しでお仕事終わるから、待っててくれる?」
青年はうなずいた。
そしてマリアにうながされ、店の奥、階段そばのすみの席に座った。その身を固くして頭を下げ、目の前の一点をじっと見つめている。それだけではない。膝の上でにぎりしめられた手が小刻みにふるえているのにリンスゥは気がついた。本当に何か尋常ではない様子だ。
食べ終わり、席を立った客が、青年を見ながらポツリとつぶやいた。
「あいつ、まだだめなのか……かわいそうにな」
「マリア、片付けはいいよ」
ヤーフェイが厨房から声をかける。
「はい。ごめんねリンスゥ、任せちゃって」
「う……うん」
リンスゥはとまどいながらうなずいた。
みんながわかっている何かの事情があるようだ。それだけははっきりしている。そして、この場で自分一人がそれを知らない。
ただ、それが何かを聞くことはできない。みんなが気を使っている様子がまざまざと伝わってくる。ふれてはいけない何か。ふれたらとたんにくだけてしまう、危うい何か。そんな空気に、疑問を口にするのもはばかられたのだ。
「じゃあ、行こうか」
そばに来たマリアの小さくささやくような呼びかけに、青年はためらいがちにうなずいて、立ち上がる。その手をマリアがそっと取る。
マリアに導かれるように、二人は奥の階段を上がっていった。
その後ろ姿を見送って、いっせいに、みんなの口元からつめていた息がもれた。
だが緊張感が消え去り、店内の雰囲気が元にもどったわけではない。やはりふれてはいけない気まずさが、みんなの表情に残っている。リンスゥは事情を聞けないままだった。
その後、最後の客の食事も済んで、本当に店じまいとなった。リンスゥは扉を閉め、テーブルをふき、一日の仕事を終えた。
まだ少し洗い物が残っているヤーフェイに、先に上がっていいと言われ、三階の自室へと向かう。
その時。
マリアの声が聞こえた。
小さく、しとやかな、優しい声。
はげますような、なだめるような、やわらかい声色。
何か語りかけているようだ。一緒に階段を上って行ったのだから、相手はあの青年だということは容易に想像ついた。だが、何をしている?
マリアの寝室の扉がちゃんと閉まっておらず、少し開いていた。
ちらりと、中の様子が見えた。
リンスゥは息をのんだ。
胸元を開いたマリア。
ブラウスからのぞくなだらかな肩。
胸にすがりつく青年。
優しく頭をなでる手。
ほんのり上気した頬。
下半身をなでこする青年の手。
ゆっくり刷り上げられるスカート。
白くなまめかしい太腿。
「ふう」
悩ましい吐息を唇の間からもらす。
ふと、リンスゥと目が合う。
「ちょっと待って」
ベッドから降りて、マリアはこちらに向かってきた。
はだけた胸元。
かわいらしい下着。
着くずれている。
そこからこぼれるやわらかなふくらみ。
白い肌にはじんわりと赤味が差し、息をのむつやを見せる。
ちょっと上目づかいにリンスゥにほほえんで、マリアは扉をそっと閉めた。
リンスゥは自室に入った。後ろ手に扉を閉める。そのまま背を預け、ずるずると座り込む。
唖然としていた。
何が起きているのか、理解できなかった。
そんなリンスゥの意識を引きもどしたのも、マリアの声だった。
強化されたリンスゥの聴覚。向こうの部屋の声が聞こえてしまう。
短い押し殺すようなあえぎ声。
きしむベッドの音。
絶え間なく続く。
赤外線センサーにつながった視覚が、マリアの部屋の様子をあらわにしてしまう。
混乱しているリンスゥは、うまく視覚を切りかえることができない。一度意識下へ押し込めても、声に意識が行ったとたんに、またつながってしまう。
熱く火照った二つの身体が、白く浮かび上がる。からみ合う肢体。マリアのなめらかな曲線がうねる。
あのマリアが、今、男に組みしかれ、その身体を蹂躙されている。
赤外線画像は通常の視野とはちがっている。だが、その姿を想像するには十分すぎる。
同じ顔をしているだけに、まるで自分が犯されているような気分になった。思わず両腕で自分の身体を抱きしめる。
寒々とした空気を感じ、身ぶるいがした。
知識として、男女の行為についてはわかっている。
けれど、それを体験したことはなかったし、また戦闘型であるがゆえ、そんな事態が自分の身に起こることもあり得ないと思っていた。組織では高価な兵器としてあつかわれ、手出しをしてくる者などいなかった。ここへ来て、チェンにさわられたのが初めて、というぐらいに経験値がない。けれど。
マリアと自分を重ねて、今初めて、それが自分の身にも起き得ることなのだと実感したのだ。
リンスゥとマリアは同じシリーズのクローンだ。ちがう個体だけれど、同じ遺伝子を持っている。
他人だけれど、他人ではない。
彼女が私で、私は彼女だ。
その曖昧とした境界が、彼女の体験を、まるで自分の体験のように錯覚させる。
その生々しさは、リンスゥに激しい忌避感を生じさせた。
素早く着がえてベッドにもぐりこむ。枕をかぶって耳をふさぐ。
ふさいだ耳にまだ何か聞こえる。
また二人が交わる音かと思い、枕を強く引きつけた。
だが。
何だろう、これ。
ちがう音だと気づく。
歌声?
小さな、聞こえるか聞こえないかすれすれの音量で、歌声が聞こえる。
はっきりと歌詞を口ずさんでいるふうではない、ハミングのような。
不思議な声だった。
小さな小さな声なのに、なぜかはっきり聞こえる。
心の中にふんわりと積み重なっていく。
さっきまでの寒々とした空気が、その歌声で、暖かく満たされていった。
リンスゥはクローンだ。しかもいわば工業製品のように量産されたクローンだ。卵細胞に遺伝情報を挿入して分化させる、伝統的な手法は取られていない。一つの細胞から成長させるという手間は省かれている。でなければ生産に時間がかかりすぎるからだ。リンスゥは培養された細胞を3Dプリンターの要領で「積み重ねて」形成された。そのまましばらく培養槽につけて、各器官をなじませ、調整して出荷された。工程としては急速成長と名づけられているが、はたしてそれは成長と呼んでいいのかどうか。細胞という名の六十兆個の部品を組み立て作られた、とする方が、戦闘機械としてはしっくりくる。
だから。
そんなリンスゥには、子供時代はない。
そんなリンスゥは、子供時代を知らない。
けれど、なぜだろう。
リンスゥはこの歌声を、知っているような気がした。
慈愛に満ち、おだやかで、ゆったりとした安らぎを与えてくれる。聞いたはずはないのに、聞いたことがあるような気がする。
そう、これは、子守歌だ。
その歌声に包まれて、リンスゥは知らないうちに眠りについた。
「おはよう!」
朝起きて、着がえて扉を開けると、ちょうどマリアとはち合わせになった。いつも通り明るい、朝のあいさつが飛んでくる。
「お……おはよう」
それに対してリンスゥは、まともにマリアの顔を見ることができない。昨日の事を思い出して目をそらし、思わず頬を赤らめてしまう。
そんなリンスゥの様子に、マリアは苦笑い。
「そうだよね。昨日いきなりだもんね。おどろいたよね」
「え……えっと……」
マリアは階段をとととっと何歩か降りると、壁の向こうに顔をのぞかせ、もう朝の仕込みに入っていた厨房のヤーフェイに声をかけた。
「おばちゃーん、ちょっと遅れてもいい?」
「ン」
ヤーフェイは特に理由を聞くことなく、うなずく。マリアのちょっとした仕草で、もう事情をくんだようだ。
「まあまあ、座ってよ。ちゃんと説明するから」
二階の台所で、席をすすめられる。マリアは手早く朝ご飯も用意した。ヤーフェイが作っておいてくれた豆乳スープと揚げパン。それにコーヒー。二人ともミルクも砂糖もたっぷり。
けれど、リンスゥはそれに手をつける気分ではなかった。何を聞く事になるのだろうと緊張して、マリアを見つめる。
「えへへ」
リンスゥの緊張がうつったのか、照れたように笑ったマリア。ホットコーヒーの入ったマグカップを、両手の間でくるくると回しながら、しばし考え込む。
その無言の間に、リンスゥの緊張がさらに増す。
そうなると、マリアの方もますます切り出しづらくなり……。
その間がさらにリンスゥの……。
「ふう」
延々とめぐる悪循環を断ち切るべく、マリアが大きく息をはく。
そして落ち着いた声で語りだした。
「ええっとねえ。簡単に言っちゃうと、私はああいう仕事をするために作られたクローンなんだ。リンスゥが戦うために調整された個体なら、私は、男性の相手をするように調整された個体なの。高級娼館に卸されて、そこで仕事してたんだよ。そこには同じ顔した子がたくさんいたわ」
リンスゥは身を固くした。昨日のあの姿から、そうでないかとは思っていた。
SYRシリーズは見た目がいい。整った顔立ち、すらりと伸びた四肢。それでいてやわらかくふくらむ胸、丸みを帯びた腰つき。昨日のマリアのつややかな姿を思い出すと、同性どころか同型だというのに、リンスゥの頬が赤くなるほどだ。
リンスゥたち戦闘型のシリーズとは別に、そういう用途のバリエーションがあることは、情報としては知っていた。だが、マリアがそうだったとは……。
告白は続く。
「多分リンスゥも同じだったと思うけど、その生き方には別に疑問を持たなかった。だってそういうふうに作られたんだもの。毎日お客さんににっこりほほえんで、抱き合って、その欲望を受け止めるだけ。むしろ色んな人とお話できて、楽しかったぐらいよ。でも、ある日私についた客が……」
そこまで言って、マリアは、くっと息をのむ。
そのままだまりこんでしまった。
視線を落としたその表情に、葛藤が浮かぶ。
簡単に口にできないことなのだとわかる。
それを見たらリンスゥは、無理には問えない。ただ見つめて、次の言葉を待つ。
マリアはもう一度ふうと息をはき、悲しそうなほほえみを見せた。
「見て」
ブラウスのボタンを上から外していき、胸元をはだける。
昨日も見た、白い肌。やわらかい曲面。リンスゥは思わずまた赤くなってしまう。
マリアの手は止まらず、昨日は見えなかった所まであらわにして、ブラをずらす。
ふるりとこぼれる乳房。
「あ」
やわらかそうな丸い乳房の外側に、白い肌の中でいやがおうにも目立つ、赤くただれた傷あと。
「え、……それは……」
「ある日私についた客がね、本当に危ないやつだったのよ。確かにそこは、お金を積めば色々な事ができたわ。ちょっとしたお芝居をしてあげたりもしたし、しばられたりとかしばったりとか、たたいたりたたかれたり、さらにあまり言えないような事とか……。でも、何でもできると言っても、それは遊びの範囲内で、商品を傷物にしたら、後々差し障るわけじゃない? お店だって、そんなの許さないわ。でもそいつはふつうのSMじゃあきたらなかったの。大金を積んで、私を買い取って……」
マリアの手が少しふるえていた。
「私をしばり付けて、本物の劇薬で私を焼いたのよ。一滴、一滴、薬剤をたらされ、泣きさけびのた打ち回る私を、あいつは恍惚とした顔で見てたわ。暴れる私に自分自身を差し込んで、中で何度も果てた。満足するまで私を焼いたあと、あいつは私をまさにごみとして捨てた。本当に使いつぶした道具のように、捨てたのよ」
リンスゥの身体もふるえた。
自分と同じ顔のマリア。同じような仕事着姿のマリア。正面に座る彼女は鏡を見ているようだ。
リンスゥは彼女の痛みを自分のことのように感じた。
持ち主の都合で無茶な使い方をされ、使いつぶした道具のように捨てられるのは、自分の運命であったかもしれなかった。
「街外れの処分場で、私はそのまま息絶えるはずだった。娼館が引き取るわけない。きれいに直そうとしたら治療するだけ高くつくもの。新品だって安くはないけど、でもその方がまし。あまりの体験に、私は神経障害も起こしてたと思う。もう娼婦としては使い物にならなかったわ」
そこでマリアは一息ついた。
しばらくの沈黙。やがて言葉を継いだ。
「そんな私をね、シロさんが見つけて、助けてくれたの。私を助けて、ちゃんと治してくれた。腕のいいお医者さんの所に連れてってくれて、再生治療を受けさせてくれて。この街にあんなすご腕の人がいるなんておどろきだわ。身体はすっかり元通り。むしろきれいになっちゃったかもしれない。けど、ここだけ残してあるの。もうあの仕事にはもどりたくないから」
下着をもどし、ボタンをかけ直していくマリア。
最後にちらりと見えた赤い傷あと。
リンスゥはしぼり出すようにたずねた。
「……でも、それなら、どうして……」
昨日あの男と、寝ていたのか。
「うん」
マリアがほほえんだ。慈愛に満ちた笑みだった。
「あの人はかわいそうな人でね。事件に巻き込まれて、奥さんを目の前で亡くしてるの。ひどい死に方だったみたい。店にいたお客さんが、だれもふれようとしなかったでしょ? こんな街に住んでいる人でも、そう思うぐらいだったのよ。あの人はそれからずっと、その心の傷に苦しんでる。何度も何度も後を追おうとして死に切れなくて。私は別に今でも、男の人と肌を重ねるのに抵抗はないから、もし、どうしても一人がつらくなったら、なぐさめてあげるから来てねって言ってあるの。でも、自分がそんななのに、この傷あとを見たら、痛かったろうって、優しくしてくれたのよ。いい人なの」
服の上から、そっと傷あとの辺りにふれた。
「もう仕事としてやるのはいやだけど、だれかを助けてあげられるなら、うれしいの」
マリアの顔がほころぶ。
「それになんかね、私の歌声って特殊なんだって。人をいやす波形なんだってシロさんが言ってた。シリーズでも特別なバージョンみたい。した後に子守歌を歌ってあげるとね、ぐっすり眠れるんだって。いつもつらい夢を見るのに、見ないんだって」
リンスゥも昨日の歌声を思い出した。確かにあの声は心地よかった。全てを包む優しさに満ちていた。
「ただねえ、シロさんによると、エッチしにくるお客さんには眠くなるなんていらない機能で需要がなくて、私のロットだけですぐ仕様変更になっちゃったらしいんだけど」
重い話題を振りはらうように、マリアはぺろりと舌を出して落ちをつけた。
「でもね、そういうのも、本当は私はだれかを助けるために生まれてきたのかなって思えて、うれしい」
そして急に、いたずらを思いついた時の顔になった。
「そうだ、今度来たら、リンスゥといっしょにやってあげよっか! こんなかわいい子が二人でサービスなんて、お金はらったら高いのよ。きっと喜ぶわよー!」
「え……っ、ええ?」
動揺するリンスゥを見て、けらけらと笑う。いつもの明るいマリアにもどっていた。
夜、自室にもどって、リンスゥは今朝のことを考えていた。
同じクローンなのだから、何か目的があって作られているはず、とは思った。シリーズの用途のうちに性産業向けがあるのは知っていたから、マリアがそうだったことそれ自体は、おどろきはしたがありうることだ。
けれど、あんな過去があったなんて。
聞いているだけで、自分も身体がふるえてきた。
肉体的な痛みに恐怖したのではない。戦闘用クローンが痛みにおびえるようでは使い物にならない。だから、その感覚は抑制されている。薬剤で焼かれたことだけなら、戦闘用クローンも敵につかまり拷問を受ける可能性があり、それに対する恐怖は対応済みだ。
恐ろしいのは、まさに道具としてあつかわれたこと。結果としてこわれたのではなく、一度使用したらこわれることがわかっている消耗品として、使われたことだ。
確かに自分たちはクローン。道具として作られた。リンスゥも自分がそういう存在だということはわかっている。必要な能力を強化され、いらない感情は抑制され。任務を効率よくこなすための道具。
量産された道具だから、同じ顔が、こんなにいるのだ。
その時、窓に映る人影が目に入った。
もう外は暗い。窓ガラスには部屋の様子が映っていた。物の少ない味気ない部屋。手前に置かれたベッド。そこに座る人影。
あれは、自分。
あれは、マリア。
あれは、リンサン。
思わず首元をそっとなぞった。
自分を殺してしまったようなあの感覚。まだこの手に残っている。
人を殺す道具として作られた私は、自分を殺すことになった。
欲望を解消する道具として作られたマリアは、その欲望のために自分が殺されそうになった。
なのにマリアは何で、あんなに明るくいられるんだろう?
マリアの姿を思い浮かべる。いつも朗らかで、明るい笑顔。そんな陰はふだんの様子から感じることはない。
それとも見えないマリアの心の中では、陰が色濃く残っているのだろうか。
思いに沈み、どれだけ時間が過ぎたのだろう。とんとんとドアをノックする音に、リンスゥは意識を引きもどされた。
扉を開けるとマリアが、パジャマ姿で枕を抱えて立っていた。
「マリア?」
「えへへー。ねえリンスゥ、いっしょに寝てもいい?」
唐突な申し出に、リンスゥはおうむ返しに問い返した。
「え? いっしょに?」
「だめかな? リンスゥ、一人じゃないと寝られないタイプ?」
「ううん、別にいいよ」
急だったのでおどろいたけれど、特に断る話ではない。二人で寝るにはちょっとベッドがせまいようだが、もともとリンスゥはそんなことを気にするタイプでもない。必要とあればどこでだって寝られるし、そうしてきたのだから。なので特に考えず承諾した。
枕を二つならべ、二人ともベッドに上がる。
リンスゥが奥の自分の枕のところに移動しようとすると。
マリアの手が伸び、背後からぎゅっと抱きしめられた。
「マリア? 何?」
「うふふー。いつも私がされる方じゃない? だからたまには私がする方に回ってみたいなー、なんて思って……」
マリアがリンスゥの耳元に口を寄せ、ささやく。
「私の話聞いたんだから、させてくれるよね、リンスゥ……。ちなみに私、女の人の相手も得意なのよ。気持ちよくしたげる……」
耳朶にかかる吐息に、リンスゥは身を固くした。マリアはそんなリンスゥの身体をほぐそうとするようにさすり始めた。優しい手つき。胸をやわらかくつかまれる。
「ひゃ!」
あわててその手を振り解いて、マリアから距離を取りベッドのすみへ。
どうする?
どうしよう?
マリアがなぜ訪ねてきたのか、深く考えずに承諾したが、まさかそんな話だとは思わなかった。彼女は、人と肌を重ねるのには抵抗がないと言っていたが、そういう用途向けに作られたのだから、そう刷り込まれていて当然だ。むしろ、行為そのものは好きなはずだ。
それに対して、自分はどうか。本来であれば、どうとも思わない、というところが正解だ。戦闘用の固体は感情が抑え込まれている。基本的に高価だから、組織ではその目的には使わないようにお達しが出ていたが、もし命じられていれば気にせず受け入れていただろう。
ところは自分は不良品で、その抑制が外れてきてしまっている。そして、一度恥ずかしいという感情を学んでみると、自分がけっこうそっち方面に弱いということに気がついた。ついつい頬が赤くなってしまうのを止められないのだ。
要するに昨日あの青年としていたことを、二人でしようよというおさそいなのだが、そんな恥ずかしいこと、たえられそうにない。
拒絶するのは簡単だ。リンスゥが本気を出せば、戦闘用ではないマリアが無理強いするのは不可能だ。だが、本気を出していいのか、というところでリンスゥはとまどう。マリアを傷つけたくはない。突き飛ばして、けがとかさせたらどうしよう。
それに、マリアを拒絶すること自体、悪い気がする。彼女は行為はよくないことだと思っていないし、気持ちよくしてあげると言っていた。そこにはある種の善意があり、それを拒否するのも、ある意味彼女を傷つけるのではないか。
実際、胸をさわられてびっくりして距離を取ったけれど、その前のさわり方は優しかったし、気持ちいいか悪いかで言ったら、ちょっと気持ちよかっ……何を考えてるんだ、私は!
リンスゥの頭の中は、ぐるぐる、ぐるぐると大混乱。しかし、感情抑制の刷り込みの影響で表情にとぼしいため、そこには表れていない。ちょっと眉をひそめた程度で、真顔のまま、じっとマリアを見つめている。
では何も影響がないかというと、そうではなく。
じわじわ、じわじわと顔が赤くなってきて、もう耳の先までゆで上がっていた。
「あははー、うそうそ! ごめん、冗談だよー」
その姿を見て、マリアがけらけら笑う。
本気なのをごまかしているのではないかと、リンスゥはマリアの表情をうかがう。心の陰をその表に探す。
しかし、そんなものは微塵も見えない。リンスゥを見てくっくと笑うマリアは、本当にリンスゥをからかっているだけのようだ。
リンスゥは息をついて、力をぬいた。
「もうー」
もどって布団にもぐりこむ。
「でも人肌は好きなのよねー」
ぴた、とマリアが寄りそってくる。
「私がそう刷り込まれてるだけで、もしかしてリンスゥはそういうのいや? くっつくのだめ?」
「いいけど……」
あんなことされたあとだから、どうしても意識してしまう。やわらかく、暖かい身体。ちょっと照れくさい。
「ありがと」
きゅ、と抱きしめられた。ふわりといいにおい。
「じゃあお礼に、お姉ちゃんが子守歌を歌ってあげるね」
マリアがささやくような声で歌い始めた。
人をいやす波形だというマリアの歌声。
か細い声なのに、しっとりと、耳に残る。
じんわりと、心のすみまで染みわたっていく。
あ、これはあれと同じだと、リンスゥは気づいた。
おいしいものを食べた時の、染みわたっていく感覚。
身体中をほっこりと温めていく感覚。
それを幸せというのだと、リンスゥは学んだ。
そんな歌声に包まれ、守られるように、リンスゥは心地よい眠りについた。
ここから先は

銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE
2016年から活動しているセルパブSF雑誌『銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE』のnote版です。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
