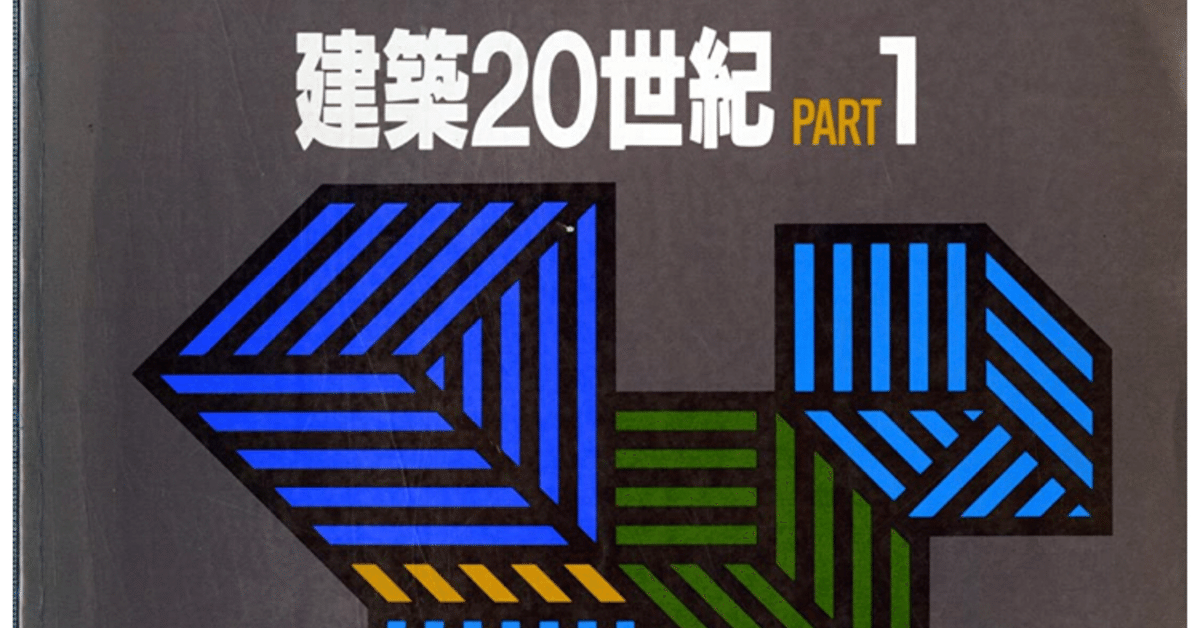
建築の20世紀 Part1,2 新建築別冊 1991年
ブックカバーチャレンジ。長野光明 から。
ねずみ算ネットワークビジネス方式!感染爆発を避けるには7人に回したらあかんね、的なこと言いながら回してくるのが、彼らしい笑 ので、気分のままに乗っかる。
#BookCoverChallenge
#7days #day1
#bookcovers
建築の20世紀 Part1,2 新建築別冊 1991年
850作品が掲載。
この本は、わたしの人生変えた。
20年前、大学に入学。
苦手な受験で浪人もして、必死に頑張って、入学成績は最下位だけど、ギリギリ入学できた。
そして迎えた、初めての造形演習授業。
そこでいきなり「すごい!こいつらに勝てない。圧倒的な造形力とセンス!」というのが何人かいた。振り返っても自作品の自己評価は70点、彼らは90点やなと。
志望だった建築のコースに入れて、
さあ頑張ろうと思った矢先、
ふたたび挫折。
別の内井昭蔵先生の授業で、
この中で建築家になれるのは1人いるかいないか、
といわれて。
どうしたらいい!?このままでは建築家にはなれない。それよりあと4年どうする!?と焦り、考えた。
また別の機会に、
松岡 拓公雄先生を何人かの学生で囲んでいた時に「君たちは建築家の名前を何人言えるの?」との問いに、5人くらいしか言えなかった。また挫折。
松岡先生は「建築家になろうと勉強してるのに、先人の作品や、どんな人が作ってるのか知らなくて、いい建築は作れない」という言葉を放った。
でも、ちょっと待て。わたしは5人だけど、その場にいた同級生は2人くらいしか言えなかったよな。
少しでも抜きん出られるものを探していたわたしは「もしかして、ここはイケる?」と思った。
そして、自分で造形を生み出す力がまだ弱いので、デザインの引き出しを増やすためにも、この本の建築家の名前と作品名と写真を全部覚えよう、と思った。
頑張った。
結果、ほぼ、全部覚えた。
その後、他の分野のデザインに携わるときも、とにかく大量にインプットして、引き出しに入れまくる。そして、アウトプットしながら、整理し、パターン化し、応用する、という、自分なりのやり方を、この時に身につけた。
アーキテクトタイタンの幅広いデザイン領域の原点の1つ。

※書庫から離れたところにいるので、Amazonのキャプチャでご容赦ください。
ーー長野くんのシェア時の引用
さて、いわゆるネズミ算方式で、ネットワークビジネスと同じ手法ですね。ちなみにこの7人を2人以下にすると、感染爆発起こさないって政府がいってる数字ですね。7人だと6世代で10万人やることになりますが、紹介のところにハードルがあって、外出自粛状態でしょうか。
で、人が1冊紹介してるのを見てもそこまで面白いわけではないですが、7冊そろって俯瞰すると滅茶苦茶面白い。7冊やりきった人を見てあげてください。その人の内面が見えるのでまあ面白い。
せっかく僕がはじめたものでないので、そこに甘えて気楽に楽しみます。
