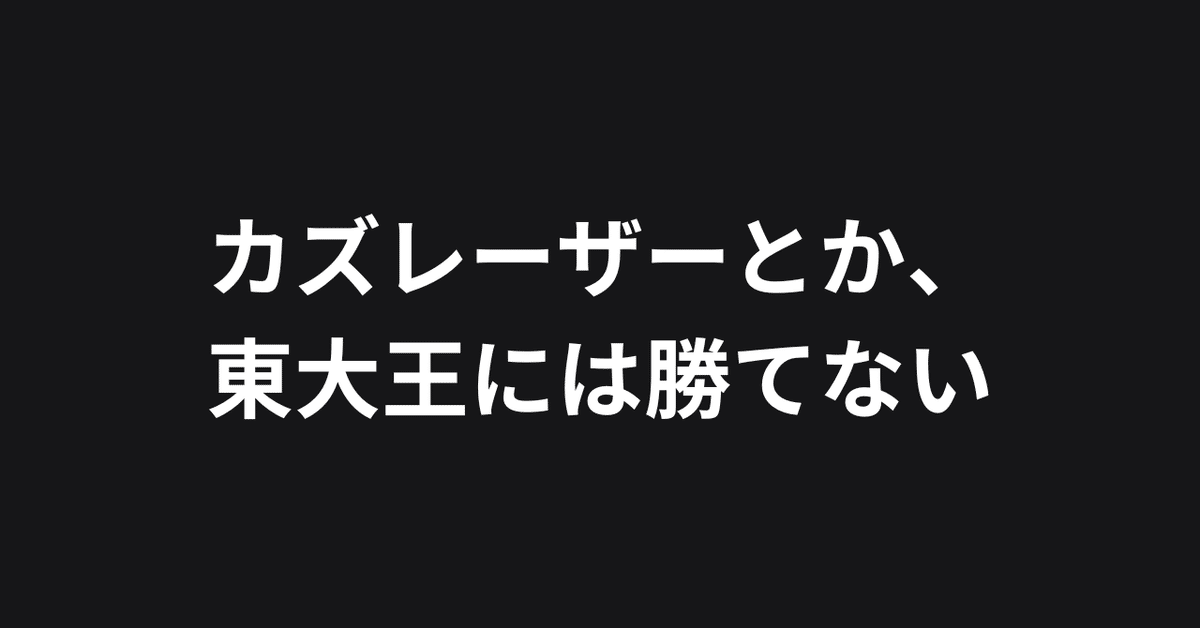
ものしりは生まれたときから失業していたんだよ説
そうです、私がものしりおじさんです
自分はいわゆる生き字引というやつで、正直なんでも知っている。
なんでも知っている人というのは二種類あって、ひとつはカール・ポパーの師匠の家具職人みたいに、なにか一つのことに通暁した結果、その経験の応用でなんでもそれっぽい答えを用意できる人である。
もうひとつは記憶力が多少優れていて、見聞きしたものをよく溜め込んでおけるから、なんとなくものを知っている感じがする人間で、私はこちらに該当する。
いにしえにはものしり職があった
なんで私みたいなのが生まれてくるかというと、たぶん人類がまだ文字を知らなかった時代に、知識溜め込み係みたいなのが必要だったためだと思う。
私が5万年前に生まれていたら、ものしり爺さんとして薄汚い洞窟の奥であぐらなどかき、人のもとめに応じて必要な知識(その人の先祖がどんな人だったかとか、いい感じの結婚式の行い方とか、食べられるきのこの判じ方とか)を歌って聞かせたかもしれない。
そう、私は歌もうまいのだ。
アレックス・ヘイリーの「ルーツ」でも、下記感動エピソードがあると聞いた。
奴隷としてアメリカに拉致されたヘイリーの爺様は文字がない村の出身だったから、ヘイリーが訪ねていっても爺様が行方不明になった記録はのこっていなかった。
なにしろ爺様が連れ去られたのは200年も前の話だから、覚えている人もない。
しかし長老が村の歴史をうたってくれるというので聴いたところ、「ある日狩りに行ったクンタ・キンテ(爺様)が帰ってこなかった~」という歌詞がちゃんと残っていて、ああ俺の爺様は本当にこの村の生まれなんだとわかったという。
やはり文字がない集団にはこういう歴史歌い係が必要なのである。
ものしり職消滅の経緯
またカエサルの「ガリア戦記」にも、文盲のガリア人部落には超絶記憶力をもった神官がいて、天地開闢以来の村の歴史を諳んじ、尊敬されているが、一度部落に文字が入ってくるとそういう人らの記憶はたちまちにして衰えてしまい、尊敬も消え、部落秩序が崩壊するみたいな話があった。
同様の話は中島敦の「文字禍」でも取り上げられている。
してみると我ら記憶の眷属は文字のせいで失業したのである。
なんと憎き文字であることか。
追伸
ここまで書いてみて気づいたが、この説はカート・ヴォネガットのパクリである。
彼のエッセーか、あるいは彼の小説のなかでキルゴア・トラウトが言っていた気がする。
曰く、世の中には、有名人になるほどではないけど、絵がうまかったり、歌が歌えたり、一芸を持っている人が存在する。
彼らは、ちいさなコミュニティーの中で一定の地位を確保し、その芸でもって隣人を楽しませていたのだ。
しかし、ラジオだのテレビだので世界の情報が人々にもたらされ、上には上がいることが分かってしまった。
隣人はテレビスターに夢中になり、身近な芸には見向きもしなくなる。
それで村の絵描き、村の歌うたいはすっかり凋落してしまったのである。
してみると私の記憶芸もそのたぐいで、そりゃ確かにタモリとか、カズレーザーには勝てんものな、仕方ないな、文字だけでなく、テレビにも負けてたんだなと思った次第。
