
刀を守った人と、日刀保設立の背景
敗戦で日本刀が投棄される危機に陥る中、それを救った人の話です。
そして日本美術刀剣保存協会(日刀保)設立もその活動の延長上にある事が分かりましたので、経緯をまとめました。
(内容は「薫山刀話」から一部内容を引用しています)

(画像転載元:https://www.touken.or.jp/)
①敗戦して刀は没収、投棄される可能性があった
進駐軍の総大将マッカーサーのいるフィリピンへ、陸軍から参謀次長の河辺虎次郎中将が行った際、向こうから受けた命令書の中の一項目に
「刀剣と武器は全部没収する」という事が書かれていたそうです。
そこで薫山氏は相当に驚き、一時は本当に途方に暮れたと記載があります。

②当時の総理大臣に直談判
それを何とか変えてもらうべく、昭和20年9月2日、当時の総理大臣と防空壕の中で何時間も話をしたそうです。
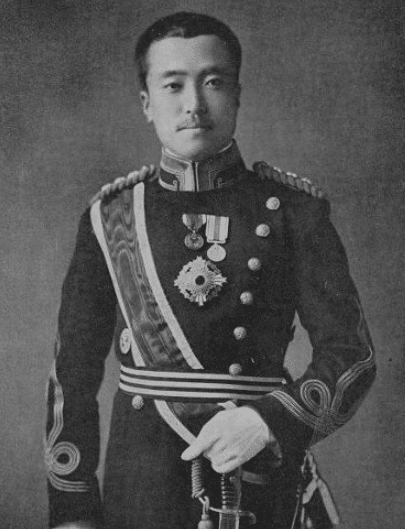
↓薫山氏の言い分
「刀は武器ではあるが、日本の愛刀家はそういう角度から刀を大事にしているものではない、その美しさを鑑賞し、あるいは先祖をしのぶという面から大切にしている。そのため全て取り上げられては困る、善処してほしい」
最初は理解の進まない総理大臣でしたが次第に納得されたそうです。
③ついにGHQへ直談判が受け入れられる

その後先方との刀談判が順調に進み、昭和20年9月14日、マッカーサー司令部、GHQより日本政府に以下の覚書が来ました。
「善意の日本人が所有する骨董的価値のある刀剣は、調査の上で日本人に保管を許可する」
④骨董的価値の証明に鑑定審査機関を設ける
美術的な刀と武器としての刀をどう区別するかと言う話になり、きちんとした審査機関を設けようという流れになったそうです。
⑤進駐軍は待ってくれない

しかしその間も美術刀剣といっても何の証明もない為、進駐軍は刀というだけでどんどん没収していったそうです。
その状況を危惧し、憲兵司令官のキャドウェル大佐が上野の国立博物館に刀を入れておけば没収されないよう守ってくれると約束を果たしました。
(大包平もそれで没収の手から免れた一振です)
これを機に薫山氏は刀の所持に関する色々な問題をキャドウェル大佐と率直に交渉が出来るようになりました。
そして、美術的な刀か、武器としての刀か、それを識別する審査権を日本の権威ある人々の審査に任せてもらいたいと申し出たところ、これを承諾。
昭和21年5月14日の事でした。
その当時は厳重に審査員を選定したらしく、始めは総理大臣が審査員の辞令を出したと言われるほどです。
その後昭和23年2月24日に文部大臣の認可が下りて日本美術刀剣保存協会が設立されました。
⑥終わりに
日本刀は現在約300万振り存在していると言われますが、終戦後の薫山氏の活動が無ければ大半の刀は投棄されていた事でしょう。
そうすれば今刀を手に取る事も見る事もかなり困難になっていたはずです。
また、美術刀剣の該当範囲ですが、向こうからは最初国宝や重要美術品、それに準ずるものや高度の記念品、それだけでよいのではという意見があったらしいです。
しかし、ここでも薫山氏は「日本の愛刀家が鑑賞しているのはそういうクラスのものだけではない、重要美術品以下のものでも大切にしてみんな鑑賞しているのだから、もう少し線を下げてもらいたい」と粘って言い続け、
最後には「専門家が見ていずれかの点にか美術的価値を認められるもの」という事で折り合いがついたようです。
それが今に繋がっています。
こういう方達が昔にした偉業を調べるのもとても面白いですね^^
今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き御刀ライフを~!

