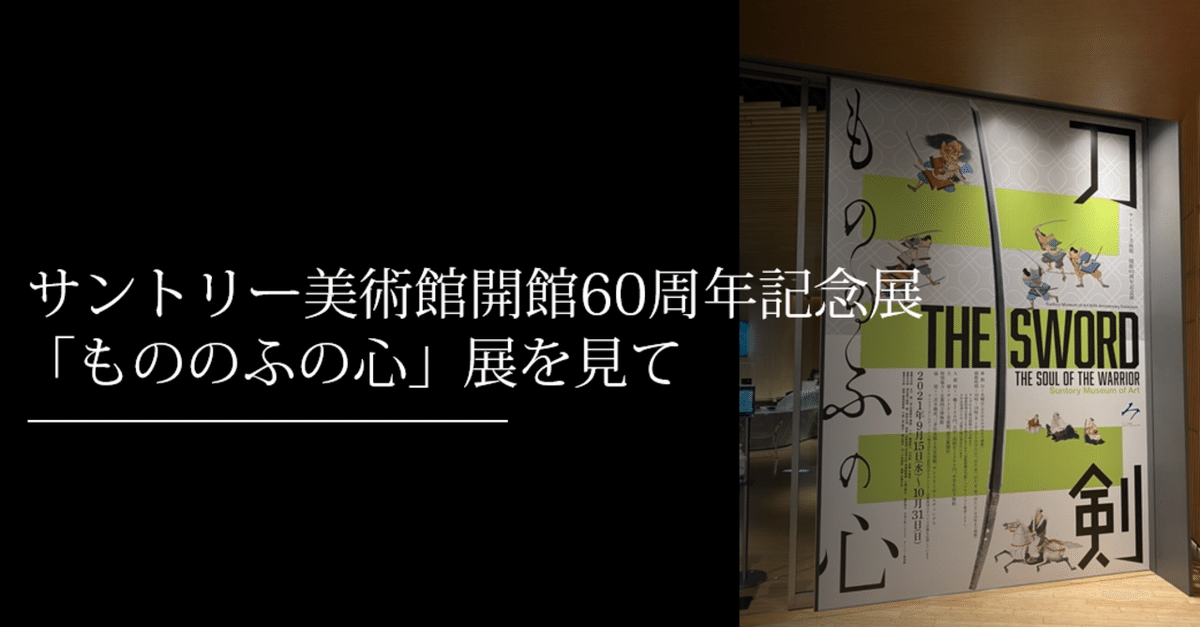
サントリー美術館開館60周年記念「もののふの心」展を見て
サントリー美術館開館60周年記念として開かれたのが今回9/15~10/31で開催されている「もののふの心」展。
という事で昨日見に行ってきました。
平日でしたがもの凄い人でゆっくり鑑賞できる雰囲気ではありませんでしたが、日本刀というものを多角的な視点から見つめる事の出来る素晴らしい展示でした。
因みに展示品の写真撮影は全てNGです。

①刀を多角的に見つめる事の出来る展示構成
今回刀剣の展示は名品ばかりが並んでいますが、その中でも有名な所と言えば、「膝丸(薄緑)」、「秋田藤四郎」、「義元左文字」、「骨喰藤四郎」でしょうか。
何といっても面白いのは刀だけではなく、様々な合戦絵巻や逸話をもとにした酒伝童子絵巻から刀の使われ方や、刀がどのようなものとして人から捉えられていたのか、
また、馬を調教している場面の絵巻だったり、研師や柄巻師など刀職達の暮らしぶりが描かれた絵巻などから、刀に関わる当時の人達の暮らしぶりにもフォーカスされている展示でした。
\狩野元信筆の名品/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 30, 2021
重文《酒伝童子絵巻》で源頼光と四天王らが酒伝童子を成敗する、まさに物語のハイライト。狩野派の巨匠・狩野元信が筆をふるい、また近年修復を終えて鮮やかな色彩が蘇った本作は、#刀剣展 必見の作品の一つ。https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/m7bfHP3I4u
\刀剣だけじゃない/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) September 8, 2021
「刀剣 もののふの心」展では、刀剣だけでなく武士の日常の暮らしを今に伝える貴重な絵画作品も展示し、武家の美意識に迫ります。 #刀剣展 #サントリー美術館https://t.co/ohyap2opQ7 pic.twitter.com/BS9Iw94UFU
②展示品について(刀剣)
・膝丸(薄緑)
茎に「〇忠」とあり、〇の部分が潰れて見えないのは、銘が消されたものと思っていましたが、図譜の解説を見るとどうやらそうではないらしく、昔付いていた刀身と同じ素材の鉄でハバキを作っていた事からそれが影響してボロボロになったと考えられるらしい。
作風からは古備前光忠の父である近忠や、同派の実忠、家忠が作者の候補に挙がるとのこと。
優美な腰反り姿に映りが鮮明に現れていました。
\名物膝丸・薄緑/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) September 22, 2021
数々の伝説に彩られ、源氏の重宝として名高い名刀「膝丸」。 #刀剣展 会期中は全期間展示します。 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/0Tc0qCi5Gr
\名物膝丸・薄緑 付属資料/#刀剣展 4階展示室には「名物膝丸・薄緑」の旧鞘・付属資料を展示中。かつてGHQに接収された際のラベルが残り、幾多の危機を乗り越えてきたその歴史を今に伝えます。図録未収録の特別展示を、どうぞお見逃しなく。 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/OsKaBfS34H
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 28, 2021
\頼光の土蜘蛛退治/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 14, 2021
浮世絵は展示替えを行い、昨日から新たな作品が続々登場。歌川国芳の《和漢準源氏 源賴光 薄雲》は頼光の土蜘蛛退治を取り上げたもの。その手には愛刀、膝丸が。 #刀剣展 #サントリー美術館https://t.co/ohyap2opQ7 pic.twitter.com/YO6j3K6fGG
・義元左文字
義元左文字は「京のかたな展」で拝見した以来でした。
今回は刀までの距離が近く、被災により金象嵌が溶けて茎に飛んだ金紛まで視認する事が出来ました。
再刃という事もあり、地鉄は白っぽく見えましたが流石の刃の明るさです。
\名物義元左文字/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) September 23, 2021
桶狭間の戦いで織田信長が今川義元から奪取したという逸話が残り、歴史ファンにもおなじみの名刀。#刀剣展 会期中は全期間展示します。 #サントリー美術館https://t.co/ohyap2opQ7 pic.twitter.com/z3rQBz3c79
・骨喰藤四郎
こちらも再刃という事でいわゆる粟田口の肌の質感とは違い肌は白っぽいですが、この360℃視認出来る展示ケースのお陰で刀身の両面の彫り物を見る事出来ます。
茎のとろけた様子も見る事ができ、刀身が火にさらされるとどういった茎になるのか、という点でとても良い勉強になりました。
茎が赤茶色になる、というのがよく分かります。
\名物骨喰藤四郎/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) September 24, 2021
足利将軍家を経て豊臣秀吉、そして徳川将軍家と、歴代の天下人が所持したことで知られる名刀。江戸期の大火を経て今に残る名品を、その目でぜひご覧あれ。 #刀剣展 会期中は全期間展示します。 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/hy0FCRTtOH
・秋田藤四郎
ちょっとライトがまぶしすぎて地鉄の色味がよく分からなかったのですが肌は立っているように感じました。
振袖茎に刀身が綺麗にまとまっており姿がとても美しい。
吉光の中では一番小振りだそうです。
\名物秋田藤四郎/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 8, 2021
10/6(水)より展示中の「秋田藤四郎」。全長32cmほどの小ぶりな姿とは思えない存在感を放っています。10/31(日)の会期終了まで展示。 #刀剣展 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/YHWiWQGhCe
\「折紙付き」の語源/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 20, 2021
名物秋田藤四郎とともに展示されているのは、刀剣の鑑定書である「折紙」。品質に定評があるという「折紙付き」という言葉の語源にもなっています。展示中の折紙は1697年の鑑定書。古くから刀剣の価値保障が行われていたことがわかります。 #刀剣展https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/tuyRikQTsD
・則宗(名物二ツ銘則宗) 足利尊氏佩刀
則宗といえば福岡一文字の祖。自分の中では幻の刀工位に思っているがこうして拝見出来て嬉しい。
今年は三井記念美術館でも在銘の則宗を拝見出来た。
今回の太刀は「宗」の字はよく分かりませんでしたが、「則」の細い鏨が肉眼でも捉える事が出来ました。
鎬筋を越えるほどに高く出た映りからは古さを感じられました。
\展示は本日まで/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 11, 2021
足利尊氏所用と伝わる《太刀 銘□□国則宗(名物二ツ銘則宗)》が収められていた拵(こしらえ)。中世太刀拵の最高峰とされ、金具に笹文が彫られていることから「笹丸」の名で呼ばれます。太刀は全期間展示ですが、拵のみ本日まで。お見逃しなく。 #刀剣展https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/xUfIGxZI5o
\足利尊氏佩用の太刀/#刀剣展 には多くの有名武将が登場しますが、本品は足利尊氏佩用と伝わるもの。歴代の室町将軍に受け継がれた足利将軍家の重宝は、その後豊臣秀吉に贈られ、秀吉から愛宕神社に奉納されたという歴史を持ちます。 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/dYiq3JksVg
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 26, 2021
・黒漆剣 坂上田村麻呂佩刀
見た目的にボロボロだったからかこの刀の前は全然人がおらず結構じっくり見れました。
直刀ですが、刀身の先が刃側に状さっているのが印象的。
また肌がとても立っており何となく古伯耆にも通じる所があると個人的には感じました。
\古代の刀剣/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 16, 2021
#刀剣展 で展示中の重文《黒漆剣》の歴史は本展で最古の9世紀・平安時代まで遡り、坂上田村麻呂所用と伝わるもの。経年の錆で刀身が侵食されていますが、その傷が千年以上の歴史の重みを感じさせます。 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/tPn6a4dk7r
・無銘剣(国宝)
普通剣と言えば短いものを想像していたのですが、これは2尺を越える長寸の剣。
美しさに圧倒されるものの、人が多すぎてあまりよく見えなかったのが残念。細直刃、切っ先は丸みを帯びているというよりは鋭い印象。
どちらかと言うと西洋の剣に似ている印象も受けた。
\神仏に捧げられた剣/#刀剣展 では「邪をはらう」存在としての刀剣に注目し、各地の寺社に奉納された刀剣を展示しています。金剛寺所蔵の本品は非常に珍しい長寸の両切刃造の剣。古代の刀剣らしい風情を漂わせ、重厚な存在感を放っています。https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/al6rpT9z8E
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 25, 2021
・祇園社御剣 出羽大掾藤原国路
八坂神社に奉納された三口のうちの一振。拵えもとても特徴的です。
この拵え実はとても面白い意味というか、国路ならではの新しい感性が現れているようです。
図譜の解説に記載あるので是非ご覧になってみてください。
\素戔嗚尊に捧げられた刀剣と拵/#刀剣展 でひときわ目を引く華やかな拵。八坂神社の三祭神に捧げられた三口揃いの刀剣と拵のうち、素戔嗚尊(すさのおのみこと)に相当するもの。男神に向けた外装として、あえて神宝の格付けを度外視し力強い印象の黒漆を用いています。https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/fCNMRz9Ju8
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 29, 2021
・長刀 和泉守藤原来金道
これは武器として使われたものでは無くて、祇園祭の際に担ぐ飾りのてっぺんに付けたとされる長刀です。
刃長だけでも約1.3mととてつもなく大きい。
錆びているので肌などは分かりませんが、これだけ大きいのに他の通常サイズの薙刀と遜色ないほどに形がとても綺麗に成形されていた。
高い位置にあり見えないから少しゆがんでいても大丈夫だろう、という手抜きが一切感じられなかったのが、来金道の仕事ぶりを感じる上でとても印象的でした。
\見上げる高さ!/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) September 29, 2021
吹き抜けに展示されているのは、祇園祭の山鉾巡行で先頭を巡行する「長刀鉾」の先端に据えられていた、江戸期の長刀。背後の山鉾のシルエットは実物より縮小しているので、実際には当館の天井高9mを遥かに超える高さなんです。 #刀剣展 https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/j82gxBAqGY
\描き変えられた長刀鉾/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 22, 2021
当館所蔵の《祇園祭礼図屛風》は元は襖絵で、切り分けられた他の場面は世界各国の美術館に所蔵されています。そのため当初本作には先頭を行くはずの長刀鉾は描かれておらず、後から描き変えられたものだそう。 #刀剣展 https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/QrGlepADGX
③終わりに
刀や絵巻の他にも鐔や甲冑なども展示されています。
\鐔いろいろ!/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 18, 2021
刀の柄と刀身の鎺(はばき)の間に挟む刀装具、鐔(つば)。それぞれに趣向を凝らした鐔の装飾からは、武士の美意識が感じられます。裏面も見えるアクリル板展示でお楽しみください! #刀剣展 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/haVnHC0hE9
\井伊の赤備え/#刀剣展 では刀剣以外にも甲冑武具や刀装具を展示中。井伊家所用と伝わる本品は、朱漆塗で全体を仕上げた「赤備え」。武田家や真田家の赤備えとともに「井伊の赤備え」として名高く、その風格の向こうに勇壮な戦国武将の姿が目に浮かぶようです。https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/kOaZZsnlpK
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 29, 2021
\秀吉愛児の遺品/
— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 15, 2021
4階展示室の出口付近に展示されているミニチュアサイズの武具は、幼くして亡くなった豊臣秀吉の長子・棄丸所用のもの。小さいながらに贅を尽くした品からは我が子を思う秀吉の愛情が伝わり、胸を打たれます。 #刀剣展 #サントリー美術館https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/iA9KU4tknH
\甲冑武具と刀装/#刀剣展 は「第1章:絵画に見るもののふの姿」「第2章:甲冑武具と刀装具 武家の装いと刀剣文化」「第3章:祈りを託された刀剣 古社寺伝来の名刀を中心に」の3章立て。2章では当館所蔵の《朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足 伝豊臣秀次所用》も堂々展示中!https://t.co/ohyap26Orx pic.twitter.com/i4xRjdJgsD
— サントリー美術館 (@sun_SMA) September 17, 2021
今回の展示会でも図譜が販売されているのですが、今回の図譜の良い所は、刀の写真というよりも、前九年合戦絵巻や後三年合戦絵巻など戦闘風景が拡大図でとても分かりやすく詰め込まれている所にある気が個人的にはしている。刀の先端に討ち取った首を刺して馬で駆けている様子であったり、太刀を腰に携えて戦っている様子など見れば見るほど新しい発見があり面白い。また図譜の最終ページの解説も充実しているので、家でゆっくりと「ああそういう事か」と眺める事が出来るのも有難い。
刀だけの図譜も面白いですが、刀を多角的な視野で見つめる事の出来る図譜というのもとても面白いです。
興味ある方は明日までの展示会ですが、是非会場で購入されてみて下さい。

今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き御刀ライフを~!

