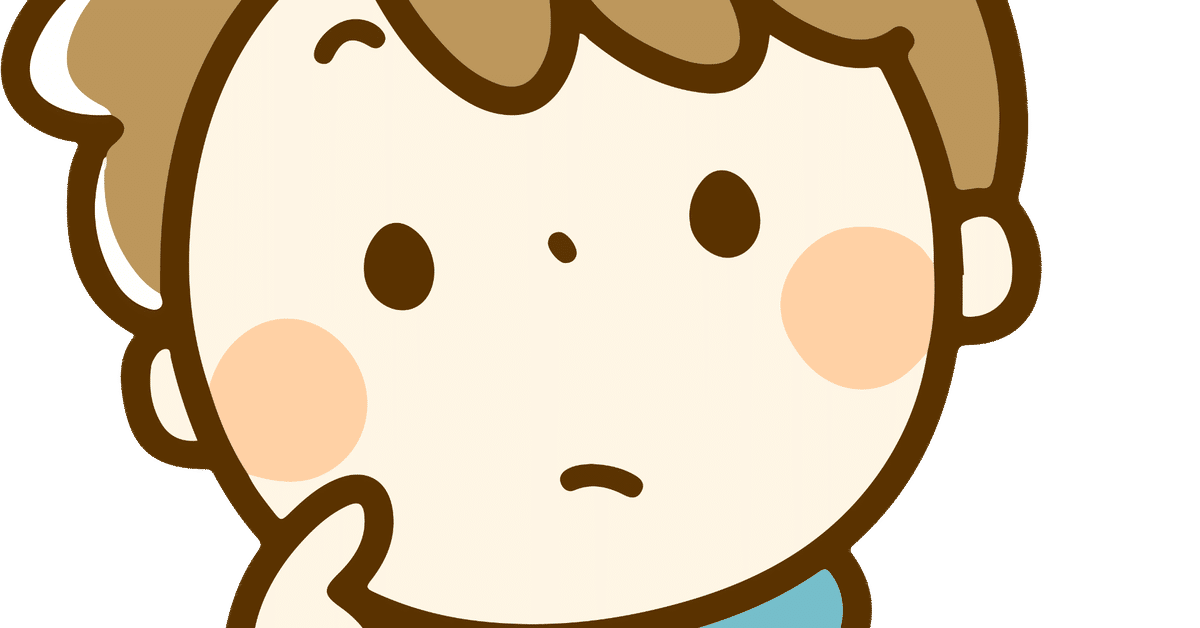
056「今年の節分が2月2日だった理由」から始まる恋
節分、今年はなぜか2月2日でした。
この理由を知ろうとすること、これ、めちゃめちゃ大事だと僕は信じています。
なぜなら、当たり前の「日常のズレ」のウラには「なにか」があるからです。
事実には理由がある。理由には原因がある。原因には事実がある。
中学受験に向けて勉強をしていた時に、塾の先生に教えてもらった言葉です。
国語の記述式問題。選択式の問題とは違って、自分で文章を組み立てる手ごわい問題です。
「問6 下線部③『ぼくは、地元の夕焼け空を特別綺麗だと思った。』より、このときの主人公の気持ちを60文字以内で説明してください」
当時の僕にとって60文字の長文記述は超難問です。
うずうずしていると、僕に向かって塾の先生が教えてくれました。

「事実には理由があります。理由には原因があります。原因には事実があります。」
例えば今回の「主人公が地元の夕焼け空を見て綺麗だと思った」ケース。
その時には、以下のように分析ができると示してくれました。
【事実】主人公は地元の夕焼け空を特別「綺麗だ」と思った。
↓
【理由】いつも見る夕焼け空に比べて美しく澄んでいたから。
↓
【原因】①排気ガスが少ない地域では、夕焼け空がより一層澄んで見える。②主人公はいつも都会に暮らしていて、地元を懐かしんでいる。
↓
【事実】①地元はクルマ通りが少なく、緑化も進んでいる。②都会と地元の夕焼け空を比較した結果、地元の夕焼けの方がきれいだと感じた。
「骨格を分析出来たらあとは肉付け。文章からそれらしき言葉を抜き出してにぎやかにして終わりだよ」
この考え方を教えてもらってからは、パズルのように国語の文章記述を組み立てられるようになりました。
(なおその先生の正体は塾講バイトの東大理系院生だったと後に知ることになりました。かしこい。)

つまり、「日常のズレ」を分析すれば「新しい事実」が見つかる。
目の前の事実を分析すれば、なにか新しい事実が姿を現します。
この先に絶対「なにか」がある。
編集者を目指す自分が持ち続けるマインドだと思っています。
ちなみに。節分が一日ずれた理由はこちらです。
■節分が一日前倒しになったのは節分は立春の一日前だから。(新事実)
■立春は二十四節気の一つである。(新事実「二十四節気」)
■二十四節気とは黄道を24等分した分割点に日付を割り当てたもの。いろいろあって日本の現実とは一致していない。なお、夏至、春分、大寒、も同じように決まっている。(新事実「黄道」「季節は24等分されている」「旧暦」)
■なお黄道とは一年間毎日、正午に太陽がいる点をプロットしていった軌跡のこと。一年間観測すると見かけ上、空の星座が約1°ずつずれていくので、太陽が天球上を1年で大体一周する。それが黄道。(新事実「天球」「ここまで調べるために使った中学受験用YouTuberの存在」「受験勉強してた時の心情」「見かけ上ってなんやねん」)
■このズレは、黄道のうるう年的な微調整によるもの。(新事実「うるう年」「うるう秒」「自転」「公転」「地軸の傾き」「年周運動」、、、)

頭がいそがしくなりました。
自分の「知ろうとする」気持ちをもっと加速したい
目の前の事実の理由を知ろうとすると、原因にたどり着き、新しい事実の発見につながります。
そして調べる過程で、紐づいている昔の思い出がフラッシュバックします。
これがめっっっっっちゃ大事。
このときめきを恋と呼ばずになんと呼びましょう。
身近な「なぜ」を拾い逃さないこと。そしてそれらを突き詰めること。
この感覚が、編集者としての力量・才覚につながるはずです。
僕が僕であるうちは、これを続けようと思っています。
よーーーし!
ちなみに、ぼくは毎日、天然で「ズレ」を分析し、気づきをメモにためています。詳細はこちら(↓)
では!
