
【奈良県】公立小中→(高校受験)→畝傍高校→浪人→神大工 教育ログ29人目
0.今回の教育答え合わせさん
→畝傍高校から神戸大学工学部に合格されたダンチさん。今改めてご自身の教育を振り返った結果はこちら!
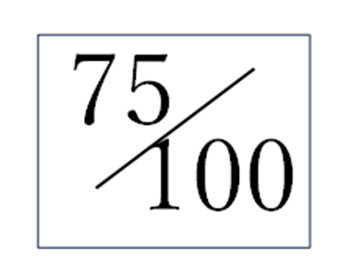
「私は、部活動にかなり全力投球をした部類の人間だ。
私の場合は、“教育”をテーマに振り返ると、受験勉強以上に、野球という部活を考える必要があった。小学校、中学校、高校、大学まで、体育会系の野球部に所属していた。なので、学習塾などにはほとんど行っていなかった。そんな私の教育振り返りである。
概要としては、75点の内、加点の要素として、両親からかなり信頼をしてもらっており、自由にできていた面がある。なので、勉強も自発的に取り組んできた。また、野球を通して自律性・ストレス耐性が身についたという面も加点に含めている。
一方で、特に高校では、野球をやり過ぎて勉強がおろそかになったことを、大きく減点要因としている。
(ただ、結論として、野球に情熱を注いだことへの後悔は1ミリもなく、寧ろ、今も大事な趣味となっており、人生を豊にしてくれたと思っている。)」
と語るダンチさんの教育答え合わせに迫ります。

1.回答者略歴
Q:お名前を教えて下さい。
→ダンチ
Q:年代を教えて下さい。
→40代
Q:ざっくりのご職業・業界を教えて下さい。
→会社経営
Q:ご自身の幼少期のキャラクターについて教えて下さい。
→「明朗活発」だったと思う(自分で書くのも照れくさいが)。クラスでも中心的存在で、スポーツも比較的よくできた。
Q:ご自身の性格について、以下の観点でお答えください。

Q:最終学歴を教えて下さい。
→神戸大学 工学部
Q:そこまでのルートを教えて下さい。
→公立小・中学校→(高校受験)→畝傍高校→一浪(大阪予備校)
Q:大学合格時点での学習能力の自己採点をお願いします。

① 自走力・自律性 :5P
→小学生の頃から厳し目の少年野球をやっており、「何かに取り組むときには、“妥協せず全力で”取り組む」ということが染み付いていた。受験勉強等にはプラスに作用した。私は勉強に対して、才能とかではなく、自律性のみで取り組んでいたとも言えるぐらいだ。
② 要領の良さ :1P
→要領は悪い方だと思う。生まれてくる時代がもう少し早かったら、英単語の辞書を1ページ目から暗記して、暗記したらそのページを食べていたタイプと自認している。
③ 持久力・耐久性 5P
→持久力・耐久性はある方だ。③と①だけが私の強みと言えると思っている。
④ ストレス耐性 5P
→勉強への抵抗はほぼなかった。野球部でのシゴキや練習での肉体的・精神的なストレスに比べれば、「勉強は座っているだけだから楽だ」と、よく思っていた。小中高と野球部では倒れそうになる練習を何度も経験してきた(チームメイトは何人も倒れていた)。こういったことを乗り越えてきたことは、特に勉強時間が必要だった大学受験では、精神的なタフさで乗り越えることが出来た。
⑤ 理解力 2P
→理解力は高くないと自認している。複雑なことを理解するまでの時間はかかる方だった。
⑥ 関心範囲の幅 4P
→理系でありながら、特に社会は好きだった。地理は、理系科目の勉強の息抜き(楽しみ)として勉強していた。
Q:ご自身の各学習能力に関してどう考えていますか?
→高校、大学の友人と比較して、強みになった要素は①自律性、③持久力だと思う。高校から進学校と言われる高校に入り、高校、大学では他の友人の頭の良さ、要領の良さには驚いた。一方で、受験勉強期には、他の誰よりも遊ばずに勉強していたとは思う。
Q:(あれば)ご自身の学習特性に気付いた時期、気づいた上での学習面の工夫などあれば教えて下さい。
→自分の学習特性としては、「長時間でも勉強ができる」という点と思う。
中学の頃から、定期テスト前の部活が休みになる1週間程度の期間については、長時間勉強することが出来ていた。なので、かなり力技で各科目勉強していた。
具体的には、全教科(副教科の音楽、美術、保健体育、技術・家庭も含めて)の教科書のテスト範囲のページは、全て毎日音読していた。どうやって、こんな昭和な勉強方法を自分が編み出したかは覚えていないが、ともかくこの力技の勉強をよくやっていた。例え1週間でも毎日音読すれば、自然と教科書の内容を暗記できていたので、その結果、副教科もとても試験の点数が良かった。よって、内申点が非常に良かった。
中学でも高校でも、受験期には、長時間の勉強で、睡眠時間を削って勉強していた。
工夫と言えるものではないが、長時間勉強することが出来ていたというのは、自分の学習特性と思う。
Q:教育の得点配分を教えて下さい。

Q:得点配分の意図を教えて下さい。
→振り返ると、以下の内容にまとめられると思う。
両親:基本的に放任だった(良く言えば、信頼されていた)。よって、影響をほぼ受けていないので、分母自体を小さくした。
小学校:野球に没頭しており、野球で培ったメンタリティーが、かなり受験勉強でいきた。今回振り返ると、野球を始めた小学生のころからさかのぼる必要があると気づき、小学校も、全く勉強していないにもかかわらず、高めの配分とした。
中学校:小学校と同様に野球部に所属。そこで、何かに全力で取り組むというメンタリティーが更に醸成された。一方で、「定期テストに真剣に取り組む」というマインドセットが出来た。そしてテストに向けて集中的に勉強するスタイルも自分なりに確立できた。
高校:ここでも野球部に所属。高校の野球部は、学歴に直結したかと言えば疑問だ。しかし、自分の学歴のゴールである神戸大学については、高3 及び浪人での受験勉強が学歴に直結していることは確実なので、高くした。
結果的に、小中高それぞれの配分は平等に30ずつとなった。
2.保護者の教育スタンス(配点10点)
Q:ご家族の最終学歴について教えて下さい。
→父(地方国立大学、理系)
母(短大)
兄(大阪大学、工学部)
姉(短大)
Q:保護者の教育方針はどのようなものでしたか?
→基本的には放任だった。いわゆる教育ママ、教育パパでは全くなかった印象だ。
野球に没頭していた私には、野球をよくサポートしてくれた。幼い頃の習い事(習字、ピアノ)だけは両親が決めた記憶があるが、それ以外には私が好きなことをしてきた。
思い出されるのは、中学の2年の時に一時期、学習塾に通ったが、すぐに辞めたことだ。これもあっさり承諾されたので、両親はやはり教育熱心なタイプではなかったと思う。
母は、自分自身よりもよく勉強をし、成績も良い私のことを素直に感心しているということをよく話してくれた。
父は、受験校選びの時には一言二言父なりの考えを言ってきたが、それも全く押しつけがましいものではなかったので、最終的には全て自分で選ぶことができた。
父母ともに、受験勉強中の私によく言ってきたのが、「たまには勉強せずに休めよ。」だった。
Q:その教育方針はご自身の学業にどう影響したと思いますか?
→とてもプラスに影響した。
大学や社会人になってから強く自覚した自分の性格として「他人からとやかく口出しされることを極端に嫌う」という面がある(なので、現在は自分で会社を立ち上げ、会社経営をしている)。
もし勉強について親から口出しをされていたら、かなり反発をしていたと思う。口出しをされなくて良かった。
Q:ご両親は学業に関してどんな接し方でしたか?
→特徴的だったのは、両親から一言も「勉強しなさい」と言われた記憶が無いことだ。
ただこれは、このnoteの随所で記載する通り、私の勉強の強みが「自律性」に集約されるからだとも思う。誰かに言われなくても、必要な時には自分で机に向かって、勉強をしていた。
なお、勉強嫌いの姉は、よく両親から「勉強しろ」と言われていた。なので、殊更両親が子供の勉強に口出ししないタイプだったという訳では無いと思う。
また、兄は中学受験をしていたので、両親共に多少学歴への意識は高い方だったと思う。(ただ、その兄の中学受験は不合格だったこともあってか、姉と私は中学受験を全く薦められたなかった。)
私は、良く言えば両親から信頼されていたと思うし、悪く言えば(三番目の末っ子ということもあり)甘やかされていた、もしくは、両親も三番目の子供なのでもう教育熱が冷めていたとも、振り返って思う。
Q:今振り返って学業につながった、家庭内の文化や習慣があれば教えて下さい。
→
1)兄の存在
1つ目は、兄が、地元の進学校である畝傍高校に入り、その後、阪大に現役で合格したことである。これによって、私は、高校も大学も難関と言われる学校を自然に目標にできた。
また、家庭内の習慣の一つ例を思い出した。夕食時に兄が母に教科書を渡して、「試験やから、教科書の何ページから何ページまでの間で、クイズを出して」とよく言っていた。母が出す教科書からのクイズに兄が答える、というやり取りを見ていたので、自分もそのやり方は踏襲した。これはあくまで一例だが、つまり、私は兄を見て、勉強の仕方をある程度イメージできていたのは、アドバンテージだった。
2)読書好きの家族
2つ目は、父、母、兄、姉は全員読書家だった。もちろんテレビもよく観ており、そういう団欒をしていたが、テレビを点けていても誰かはリビングで本を読んでいるという光景が記憶に多い。それによって、兄、姉の知識量は、同学年ではかなり高い方だったと思う。
残念ながら、私は読書習慣が子供の頃に身につかなかったが、賢い兄、姉に囲まれて育ったので、私の知的な成長にも繋がったと思う。
3)肯定的なスタンスの母
父は仕事が忙しく、平日にほとんど家にいなかった。そのため、育児はほぼ母によって行われていた。
その母の性格が、非常に大らかで、肯定的なスタンスの人柄だった。今思えば、これが非常に良かった。
幼心に、母から何か否定をされた記憶が極めて少ない。それによって、自分の社交的な性格が培われたと思うし、また好きなこと(野球)を徹底的に打ち込むことが出来たと思う。
4)専業主婦の母とのコミュニケーション
私が明確に記憶しているわけではないので、推測での考察になる。
今自分が育児をしており、本を読んで得た知識だが、「親との会話量が多い幼児は、学力が高くなる」という研究結果があるらしい。
私は、母が専業主婦であり、しかも母の地元を離れて、見知らぬ土地で育児をしていた。よって、今でも母は「知らない土地だったので友達もいなかった。なので、自分の子供が話せるようになると、話す相手が出来て嬉しかった」と回想している。
母との会話量が多かったことが、兄、姉、私の学力の根本を培ったと思う。
5)兄、姉とのコミュニケーション
3人兄妹の末っ子だった私は、当然ながら自分より物事をよく知る兄、姉に囲まれて育った。上述のとおり、母とよく会話していた兄、姉の知的な成長は早い方だったと思う。更にその兄、姉は幼い頃から読書家だった。
その兄、姉と常に会話して育ったことが、自分の知的な発達に大きく寄与したのではと考えている。
後述するが、私は小学校では入学するなり、成績は良い方だった。このことを振り返ると、未就学児での体験が私の学力の底力になっていたと思う。その源となったのは、4)、5)で挙げた、母、兄、姉との会話だろう。(母、兄、姉に感謝)
一方で、中学以降は、野球で培った自律性で勉強に取り組んだので、中学以降の学力は自力で開拓したものと思っている。
ここの1)で挙げたとおり、目標設定には兄の存在が大きかったのは間違いない。しかし、自分の学力の獲得という意味では、その土台を固めることができた小学校での体験(野球チーム)が大きかったと考えている。
Q:ご両親の教育スタンスについての小計を教えて下さい。

→そもそも、両親からは学業に関して、ほぼ何も言われていないし、何かサポートがあったり、有効なアドバイスをもらった記憶も少ないので、分母自体が小さい。
幼少期から振り返っても、よくある公文、そろばん、進研ゼミなどは、全く薦められなかった。
そして、それが私にとても合っていた。理由としては、「口出しされるというストレスが皆無だった」ということが大きい。なので、満点の10点とした。
3.~小学校時代※小学受験含む(配点30点)
Q:小学受験はしましたか?
→していない。全く考えていなかったと思う。
そもそも、奈良の片田舎の郡部で育った私は、通学圏内に私立や国立の小学校が無かった。また、幼稚園の友人でも、小学校受験をした友人は聞いたことがない。
両親が、多少でも子供に小学校受験を考えさせるのであれば、住むような町ではなかった。
Q:小学校の頃の学業成績について教えて下さい。(全6レベル)

→神童と言われたことはないが、常にトップクラスだったと思う。
そもそも、小学校の頃に勉強を難しいと思ったことがなく、教科書の内容を簡単だと思っていた記憶が多い。
また、通知表も、10段階でほとんど10だった。
なぜ、いきなり成績が良かったのか?という点については、Q.家庭内の文化や習慣で、述べた通りだ。
Q:小学生当時の勉強への意識はどのようなものでしたか?
→最低限の宿題はやる。それ以外はゼロ。
宿題を除いて、勉強をした記憶が無い。土日は少年野球に夢中だったし、平日は、友達とよく遊んだ。
Q:小学校の教育環境についてはどう考えていますか?
→典型的な田舎の小学校であり、のんびりしていた。学年で150人ぐらいいたが、受験して私立中学に進んだ生徒はゼロだったと思う。
当時としては新しい巨大な公団(団地)に隣接する小学校で、若い世帯が多く、活気はあった。それが、奈良の田舎という土地柄もあってか、勉強や受験熱に向かう地域では無かった。その分、スポーツや運動会などは非常に活気があった。
こういう環境だったので、私が勉強を熱心にしなかった面もあるし、ましてや受験を考えることは無かった。
Q:毎日どれくらい勉強していましたか?

宿題以外にやった記憶が無い。
Q:小学校まで習い事は何をやっていましたか?

Q:学習貢献度の高い習い事について、始めたきっかけを教えて下さい。
少年野球:少年野球は兄がやっており、また仲の良かった幼馴染が入部したので、私も始めた。親から薦められたのではなく、自発的に始めた。
習字:兄、姉がやっていたから、親の薦めで始めたと記憶している。
ピアノ:ピアノについては、完全に親から強制的に言われ、始めた。というのも、姉がピアノを始めたので、家にピアノを買った。すると、両親が「せっかくピアノを買ったのに、一人しか弾かないのは勿体ない」という恐ろしくくだらない理由を主張しだし、姉より年下の私が始める羽目になった。
Q:習い事の学業成績への影響面について教えて下さい。
野球:少年野球が最も貢献度が高いことは、説明が必要と思う。
自己分析をするに、私の学業はかなり自律性・ストレス耐性に支えられてきた。その自律性・ストレス耐性を培ったのが、野球だからだ。よって貢献度を高くした。
習字:習字は、勉強に貢献したことは皆無だと思う。優しい先生のところに、毎週火曜日の決まった時間に友達とお菓子を食べに行っていたぐらいの思い出だ。
ピアノ:ピアノは、貢献度は最低とせずに、一つだけプラスにした。
正直言って、ピアノは全く練習をしておらず、毎週水曜日に課題曲を弾けないままピアノ教室に行って、先生に呆れられていた。そんな記憶しかない。私も、やりたくて始めた訳ではないピアノが嫌でしょうがなかったし、先生も、なんでコイツ弾けへんのに毎週来るんやろうと思っていたと思う。
ピアノの経験(弾けなかった経験)で、楽器を奏でるのがどれだけの鍛錬が必要か、よくわかった。(それ以降、音楽家への尊敬を持つようになった。)
なお、ピアノを学習貢献度で最低とせずに、一つプラスとしたのは、楽譜が読めるようになったからだ。楽譜が読めるようになったので、中学の定期テストの音楽の筆記試験は、とても楽だった。
Q:今振り返ってやればよかったと思う習い事は?
→水泳
野球をやっており、体育は得意な私だったが、泳げなかった。そのせいで、中学の夏場だけ、通知表の体育の成績が悪くなるというのが、少し悔しかった。
Q:小学校までの読書について教えて下さい。
→ほぼ読んでいない。マンガばかり読んでいた。少年ジャンプに熱狂していた一般的な子供だった。
夏休みの宿題の読書感想文で必要な本を読むぐらいしか、読書はしていなかった。
上述した通り、家族全体は読書習慣があったが、私が読書に目覚めるのは大学に入ってからだった。
Q:当時熱中していたことは何ですか?それは学業にどう影響しましたか?→野球だ。
野球によって自律性やストレス耐性が培われた。野球が直接的に学業に影響した効果はゼロだと思う。しかし、間接的な影響は非常に大きかった。
私はとても強い少年野球チームに所属していたということもあり、監督、コーチも熱心だった。
体罰などは無かったが、強豪チームによくあるような「選手が自ら進んで練習する雰囲気」が、少年野球ながらに漂っているチームだった。なので、私も自然と、野球の練習を常に頑張るというマインドが染み付いた。例えば、少年野球の練習で坂道をひたすらダッシュするなどしんどい練習も多かったが、手を抜くということは考えたこともないぐらいだった。
また、当時の野球の練習では、「精神面の鍛錬」として、ひたすら走らされる、ひたすらうさぎ跳びをする、などが一般的であった。とても辛かったことを覚えている。そういった練習を小学生ながらに繰り返すうちに、良くも悪くも、やらなければならないことを(盲目的に)全力で取り組む、という典型的な体育会系気質が身についた。
整理すると、少年野球を通して以下の2つの重要なことが、私に残った。
・「何かを取り組む際には、全力で、妥協せずに取り組む」という真面目なマインド
・何か苦労があっても、「野球の練習に比べれば断然楽だ」という意識
これらは、後々の勉強にかなりプラスに作用した。
Q:小学校時に学習・進学などで記憶に残る言葉はありますか?
→特にない
Q:小学生時代の教育環境の小計を教えて下さい。

→小学校で勉強をしていないので、点数を入れることも躊躇った。
しかし、繰り返すが、少年野球を通して自律性・ストレス耐性が培われたことは間違い無く、これがその後中学での定期試験も真面目に取り組むことにつながった。よって、決して無視はできない。
そういった意味では満点の30にしても良かったのだが、今自分が育児をしていて思うに、「私は野球ばかりしすぎた」という点の、マイナス面も感じる。
私は小学2年から野球を始め、土日、祝日は絶対に練習や試合。小学生低学年からGWやお盆休みは無かった。なので、他の友人が「旅行に行った」「こんな映画を観た」「遊園地に行った」などを経験している中、私はそれらの経験が極端に少なかった。(それゆえ、小学校時代の文集の自分の作文が、どれも野球の試合内容ばかり書いており、スコアブックみたいで、全く面白くない)
幼児〜小学生の間に様々な経験をさせるプラスの効果が大きいと、今になって知ると、私の小学生時代は偏り過ぎていたと思う。その分を、マイナス10点した。
4.中学時代※中学受験含む(配点30点)
Q:私立の中学受験は考えましたか?
→全く考えなかった。
兄が、国立の中学を受験していたことは知っていた。しかし、私は興味を持たなかった。また、両親からもそういう話は一切なかった。
Q:中学行時代の学業成績について教えて下さい(全7レベル)

常に学年で1〜3位だったと思う。
150人の生徒がいる一般的な奈良の田舎の公立中学である。上述の通り、特段受験熱の高い地域でも無かったので、勉強をする人、しない人がはっきり分かれていたとも思う。
なお、親友の一人が勉強ができるタイプで、彼と常にトップ争いをしており、定期テストの点を言い合っていた。その親友は、高校は同じ畝傍高校で、早稲田(文系)に現役で合格した。
Q:中学生当時の勉強への意識はどのようなものでしたか?
→部活(野球部)が生活の中心ではあったものの、定期テストだけ、かなり真剣に勉強した。
中学に入り、「毎学期、中間テスト、期末テストという定期テストというものがある」ということを知り、「これは真面目に取り組むべき対象だ」と早々に認識した。
誰かに言われたわけではなく、定期テストに対して手を抜くという発想を全く持たなかった。中1の時点で、野球と同じくらい気合いを入れて取り組まなあかん、とマインドセットが出来た。
なので、部活動が完全に休みになる定期テスト前の1週間は、とてもよく勉強した。また、定期テストの日から逆算して、間に合いそうにない試験科目は、例えば2週間前から夜勉強を始めるなど、自発的に取り組んでいた。
なお、定期テストに関連すること以外では、宿題ぐらいしかしなかった。日々の予習、復習などを自ら勉強したことは皆無だった。
Q:中学校の教育環境についてはどう考えていますか?
→田舎の一般的な公立中学なので、まず受験熱が一切なかった。
成績が公開されることも無かったので、いわゆる「競争」のような意識は全く無かった。なので、特に隠している訳でも無く、友達同士でも、成績を言い合うことも無かった。結果的に、進学する高校がわかり始めた中3ぐらいのタイミングで、それぞれの学力がどの程度かわかるような雰囲気だった。
やはり、勉強をする人、しない人が明確に分かれていた町だったと思う。また、勉強をしない人を、ネガティブに考える風潮も無かった。(それよりも、スポーツで有力だと尊敬を集めていた)
Q:毎日どれくらい勉強していましたか?

中1、2、3と、定期テストは真面目に勉強をしていた。しかし、通常の日は宿題しかしていない。宿題もそんなに多かった記憶もなく、普段の日常では勉強をしていなかった。よって、「平均値」と言われると、0〜30分に落ち着くと思う。
受験期は、かなり勉強をした。中学の野球部を夏頃に引退し、その後、学習塾に通い始めた。確か、夏期講習を受けることが入り口だった記憶がある。
その時期から受験本番まで、休まずに夜中まで毎日勉強した。
平均値ということで、5〜6時間と書いたが、これは、中3の頃に、授業が終わり帰宅してから寝るまでの間の勉強時間のイメージだ。
Q:中学校時の習い事について何をやっていましたか?

Q:習い事について学習能力への影響を教えて下さい。
野球部:(小学校の欄と重複するが、)野球部の練習により、自律性・ストレス耐性がかなり培われた。物事に対して全力で取り組むというマインドができあがったので、その意味では、間接的ではあるものの、学習能力への影響は大きいと考える
学習塾:友達が楽しそうだったので、中2の1ヶ月程度だけ、学習塾に通ったことがある。その時に、塾での授業の内容が、単に中学の予習をしているだけだと知った。塾で学ぶと、肝心の中学校の授業がおもしろくなくなると痛感した。よって、時間の無駄使いと感じ、親にすぐに話して、塾は辞めた。
その後、中3の部活動引退後に、受験を意識して、学習塾に通い始めた。生徒数が多い学習塾で、10クラスぐらいあったが、入塾テストの点数で配属クラスを決定されたところ、すぐに一番上の最難関クラスに入った。これは、私の地頭の良さではなく、純粋に定期テストをかなり真面目に取り組んできていたので、基礎学力が高まっていたからだと思う。
正直言って、やはり塾で特別な学びはなく、単に分量が多いだけではあった。ただ、他中学の友人がおもしろく、最後まで通った。
学習塾は影響度としては大きくないと思うものの、プラスには作用したとは思うので、高い方の貢献度とした。
Q:中学時代に学習・進学などで記憶に残る言葉はありますか?
→大きな印象に残る言葉はないが、細かな点で、自信を獲得する毎日だった。
国語の作文では先生に褒められ学級内で発表され、数学の解法が良かったと先生に激しく褒められた。美術では、自分の書いた絵が学年代表で寄贈作品に選ばれたこともあった。書いていて嫌味だなと自分で感じるが、こういうことが日常茶飯事だった。(高校に入ると、一切無くなったが・・・。)
中学では何かと見本になるような扱いを受けることが多く、こういった経験は、間違い無く自分の自信を育み続けたと思う。
(一方で、力を入れていた野球では、同じ部活に自分より上手い選手が何人もいたので、そこまで天狗になることは無かった)
Q:中学校時代の教育を振り返ってどう評価しますか?

教育という面では、第一志望であった畝傍高校に入学できた。その時点で、満点である。具体的には、
・定期テストへの取り組みを通じて、自分なりの基礎的な勉強の仕方を習得できた
・第一志望の高校に合格できるだけの学力を培えた
ということに尽きる。
また、副教科も妥協せずに定期テストで高得点を取り続けたし、部活動の野球部ではレギュラーとして県大会で準優勝した。またクラスでは盛り上げ役でもあったし、学級委員も何度も担った。これらから、内申点はかなり高かったと思う。
5.高校時代※高校受験含む(配点30点)
Q:私立の高校受験は考えましたか?
→私立の高校を受験し、合格した。
ただ、私の地元では、大半が公立高校を第一志望にしており、私もそうだった。
また、私は高校野球を頑張り、甲子園に出たいとも思っていた。一方で、私立高校では一般受験の入学者は野球部の入部すら認められないケースが多く、その意味でも私立高校に積極的に進学する意思はなかった。
なお、滑り止めで智弁学園の特進コースを受験。また少しチャレンジの意味で、大阪の私学で清風高校の理数コースを受験し、両方とも合格した。
Q:高校時代の学業成績について教えて下さい(全7レベル)

まず驚いたことに、中学までは勉強で苦労したことが無かった私だったが、進学校の友人に圧倒された。友人は頭の良さが半端では無かった。また、最初は高校の授業が非常に難しく感じた。
更に、野球に没頭していた私は、甲子園に出たいという意思が強く、勉強に全く関心が向いていなかった。
それゆえ、高校での定期テストは、どこが分かっていないかも分かっていない状況で取り組み、結果は毎回惨憺たるものだった。私の必殺勉強法である「試験範囲の教科書を全部音読する」も全く通用せず、早々にこの勉強法は捨て去った。
勉強をほぼしていないので、当然定期テストや模試の成績は悪く、学年410人中、400番台がザラだった。きっと、進学校といえども勉強していない連中は一定数居て、380〜410番台は誰も勉強しておらず、彼らは生まれたままの能力で試験を受けていたと思う。
Q:高校の教育環境についてはどう考えていますか?
→私は有効活用できていなかったが、「とても良かった」と思う。
公立でありながら、進学校だけあって、進学を想定した内容が多かった。先生はユニークな先生が多く、面白、可笑しく教えてくれた。とてもレベルが高かった。
また、進路指導も充実しており、情報やサポートも豊富だった。
更に、何よりも環境の良さとして挙げるべきは、勉学のレベルの高いクラスメートの存在だろう。和気あいあいとしつつも、勉強の独自のやり方を皆で教えあったりして、支え合う雰囲気があった。
進学校でありながら、のんびりとした校風だったと思う。受験熱が高いわけでもなく、特に高1、2の間は、私が部活に没頭していたように、友人らもそれぞれの学生ライフを満喫していた。
一方で、受験シーズンになると皆図書館や教室に残って勉強するなど、メリハリがきいていた。
私は結果的に浪人したが、その時でも、同じように浪人した高校時代の友人と支え合うことが多かった。予備校内の新しい友人は、長く付き合うような友人はできなかった。
なお、また野球部の話になるが、当時の野球部は、実績として7、8割近くが浪人をしていた。先輩らは、そうやって高校野球に打ち込み、その後大学に進学していた。なので、私も自然と浪人することが十分にあり得るとは考えていた。
Q:毎日どれくらい勉強していましたか?(平均値で算出してください。高3は受験期を含む1年間、受験期はピーク時という意味)

高校1,2,3年と、野球部に没頭し、勉強はおろそかだった。友人らと遊ぶのも楽しく、友人らも受験までは全くガリガリ勉強する雰囲気ではなかった。高3になってようやく塾(予備校)に行く友人も増え始めましたが、私は現役時は最後まで塾には行かなかった。
受験期については、部活動を引退後、それまで野球に注いでいた情熱を、全て勉強に切り替えた。
睡眠時間は数時間ということもザラであり、夜中まで日夜勉強した。椅子に座って勉強すると寝てしまうので、立って勉強していた時期もあった。目の下にメンソレータムやタイガーバームを塗って、強制的に自分の目を開けるという昭和な勉強方法もしていた。
その甲斐あって、高3の5月に学年最下位だった成績も徐々に上向き、卒業時には学年で真ん中よりやや下ぐらいにはなった。
浪人の時期は、夜は12時までに寝て、朝は7時に起きるという生活リズムに切り替えた。現役時代にかなり深夜まで勉強することもあったが、浪人では落ち着いて勉強した。
10〜13時間というのは、高3の授業がない日、及び浪人時代の自分で行う勉強時間のイメージだ。
Q:習い事は何をされていましたか?

野球部:小学、中学までは野球を通して自律性・ストレス耐性を獲得したというプラスの効果を、ここまでで書いた。高校では、明らかに自律性・ストレス耐性は獲得し終えていたので、冷静に分析した。
振り返るに野球に没頭し過ぎていたことは否めない。それだけ高校野球と甲子園は自分にとって魅力的であり、そのことには一切の後悔はない。ただ、純粋に勉強という面で振り返ると、野球を言い訳にしていた面があるので、そのことはマイナスにしたい。
現に、野球部の同級生や先輩でも、部活と勉強を両立し、現役で京大、旧帝、早慶に合格した部員は数多いる。
一方で、大学選びにも野球が関連している。神戸大学を現役でも浪人でも私は第一志望にしていたが、理由は神戸大学の硬式野球部が強いからだ。
(最終的に私が大阪大学に入れる学力があったかどうかは、一旦置いとかせて頂いて)大阪大学や、学力的に近い大阪市立大学、大阪府立大学、その他地方の国立大学などよりも、神戸大学の方が硬式野球部が強かったので、神戸大学を第一志望としたのだ。
これにより、学年最下位で、当時は神戸大学なんて夢また夢だった私が、高い目標を設定できた。
大阪予備校:既に倒産した予備校なので、知っている人は少ないだろう。
私は、大手予備校も考えたが、親の出費を考え、特待生枠(学費が半額)で入れる大阪予備校を選んだ。
最初は真面目に通学していたが、どうも全体的に講義のレベルが低いことに気づき始めて、このままで神戸大学に落ちると感じ始めた。6、7月頃から、本当に有益な講座だけ出席し、それ以外は、地元の奈良の図書館に通う日々となった。宅浪のようなものだ。結果的にこれが非常に良かった。
宅浪状態になると、参考書選びが非常に重要になる。私は、各教科で良い参考書に出会い、それで格段に学力が伸びた。最終的には、模試の判定では神戸大の工学部は常にA判定となっていた。
大手予備校だと、私の性格上、授業や講師を盲信してしまい、最終的に自分の学力が神戸大レベルまで上がったかは、わからない。逆説的な結果論ではあるが、大阪予備校を選んだことも良かったのだろう。
Q:高校時に学習・進学などで記憶に残る言葉・事件はありますか?
多々あるが、3つに絞る。
①高校3年の5月の校内の模試で、学年最下位を取った。そのことに驚くと同時に「今更勉強してもしゃーない。野球を引退する7月末まで、勉強を封印して、野球のみしよう」という、体の良い?言い訳(開き直り)をした。つまり、それぐらい、学力が低かった。
②英語がわからなさ過ぎて、高3の8月に、「今からゼロから英語を勉強するよりも、センター試験はロシア語で受けた方が良いのではないか」と真面目に考えた。そんな判断もできないくらい、アホだった。ロシア語の問題集を買って数日で挫折し、結果的に英語で受験した。つまり、それぐらい、学力が低かった。
③クラスに天才がいた。数学で、非常に難しい問題集があり、先生が宿題で出すその問題集の問題が、いつもとても難しかった。一晩かけても解けない問題が多く、秀才揃いのクラスメートの皆が四苦八苦していた。そんな中、宿題はやってこず、当てられたらその場で考えながら、黒板にスラスラと正解を書いている生徒がいた。彼は現役で京大の理学部に合格した。上には上が居ると知り、京大はとんでも無い人が集まる場所と強く思った。
これらは、どれも余談に近いエピソードとなるが(申し訳御座いません。)、私の高校の勉強を振り返ると、自身を表した特徴的な話なので、書かせて頂いた。
Q:高校3年5月で学年最下位から、どのような学習をしたのか?結果、どれだけ伸びたのか?
①高校3年の夏までほぼ勉強していなかった私なので、名実共にまっさらな頭で受験勉強を始めた。
当初はどの教科の何もわからなかったので、高3の教科書を一からやり直した。すると、高2の内容をわかっていないことが、わかった。よって、高2の教科書に取り組み始めたが、その結果、高1のレベルもわかっていないことがわかった。なので、高1の教科書の最初のページから、全教科やり直した。
すると、今までチンプンカンプンだった高3の授業が徐々にわかるようになってきた。「教科書というのは、よくできているな」と妙なことに感心したことを、昨日のことのように覚えている。
振り返れば、中学時代から高校まで、教科書を中心とした学習をしてきた。それが自分に合っていたのか、勉強の地力が付いたように思う。
教科書というのは、非常にクオリティーの高い教材だと思う。高校時代の私は、「文部科学省も捨てたものではない」などと、学年最下位のくせに、偉そうに思ったものだ。
②教科書中心の勉強が身を結び、現役時のセンター試験間近になり、数学、物理が得意になってきた。一方で、地理も好きだった。しかし地理は二次試験の科目ではないので、そこまで勉強時間を作れなかった。気づけば、理系科目の休憩として、地理の勉強をするようになっていた。
そのことが浪人時代も続いて、結果的に数学、物理、地理が得意科目になった。浪人のセンター試験では、数ⅡB、物理は満点、地理は98点だった。
一方で、英語、国語は浪人しても伸びずに、最後まで足を引っ張る科目だった。
いずれにしても、高2、高3の校内模試で、数学も物理も0点を取ったことがあった私が、センターで満点を取れるようになったわけだ。これらが得意科目なるのだから、振り返っても不思議なものである。
Q:高校以降の教育を振り返ってどう評価しますか?

高校の学業の成績は悲惨だったので、0にしようかとも思った。
しかし、高3の秋、冬、浪人と、かなり追い込んで勉強をした。そこで、幼い頃からの野球で培った自律性・ストレス耐性がいきていると思う。
浪人時代は、奈良の田舎から、初めて大阪に通学した。浪人した中には、大阪での遊びを覚えて成績が下がる友人もいる中で、私は自分を律して勉強に取り組めた。しかも、ほぼ宅浪という自分しか監視している人がいない状況で、である。振り返っても、良くやったと思う。
それらを甘めに加味して、30点満点中の15点とした。
Q:ご兄弟(姉妹)との学歴または学力の差異があれば、その発生要因の分析をお願いします。
・兄(阪大 工学部、現役)
総じて、大学までは兄の方が私よりも若干学力が優っていたように思う。
仔細に見ていくことにより、その理由を考察してみる。
1)部活
まず、兄も私も運動部だったことは共通している。私は兄と同じ少年野球チーム、同じ中学の野球部に所属していた。兄も私も同じ高校で、兄は野球部でなかったが、高校でも運動部に所属しており、熱心に取り組んでいた。
2)塾・習いごと
兄は中学受験をしたこともあり、小学5、6年に学習塾に通っていた。また、中学は3年間塾に通っていたと記憶している。一方、私は小学校で塾に通っておらず、中学では中3の夏休みから、半年だけ塾に通った。
3)中学の成績
中学の通知表の成績は、(父曰く)私の方が兄より良かった。それは、上述のとおり私が副教科も徹底して手を抜かずテストに挑んでいたからだと思う。
一方で、兄の方が、私よりも5教科の学力は有ったようだ。理由は、地元の西大和学園高校に兄は合格していたが、私は教師のアドバイスにより受験すらしなかった(西大和は落ちるだろうと言われた)。
4)高校での成績
高校は兄と同じで、かつ兄も体育会系の部活動に入部していた。しかし、兄は高2の頃に骨折をし、部活動を長期間休んだ。その頃から兄は勉強を真面目に取り組むようになり、高校での成績も上がったと語っていた。結果、阪大 工学部に現役で合格したのである。
一方で私は、上述のとおり、兄よりも高校時代に勉強をしていなかったことは明らかで、それがそのまま神戸大 工学部に一浪との結果になった。
5)現在
兄は、誰もが知る大企業で技術部長に昇進している。一方、私も大企業に務めていたが、退職し、自分の情熱に基づいて、自分で会社を立ち上げた。今もその会社を経営している。
また、幼い時は兄を非常に賢い人間と思っていたが、社会人になったぐらいから、そこまでの差を感じなくなった。思うに、単純に兄弟間の年齢の差があり、知的な成熟度から兄を雲の上のように感じていただけだろう。今となっては、知的なレベルは同じ程度と感じている。
6)考察
上述のとおり、兄と私は似たような経歴を歩んできた。このように仔細に振り返れば、兄の方が私よりも子供時代から高校までの絶対的な勉強時間が多かったことは明らかである(兄は小学5〜中3まで塾に行っていた、兄は高2から勉強を真面目にし始めた、兄は子供の頃から読書家だった等)。それがそのまま、出身大学の差になったと考える。
・姉(短大)
姉と、私(及び兄)の比較も、重要と思う。
姉は、私(と兄)とは異なり、勉強を避けてきたタイプである。違う言い方をすれば、私(と兄)は真面目タイプであり、姉は不真面目なタイプであった。
会話をしていての論理構成力など、地頭の良さは、私よりも姉の方が良かった。両親も常に兄姉私の中で姉が一番頭が良いと言っている。
姉と、私(及び兄)の明確な違いは、小学生の頃におけるチームスポーツの経験の有無である。姉は、私が野球から培った自律性に関わるような素養を、子供時代に育む機会は少なかったと思う。姉が自律的に何かを頑張るというのは見たことがない。
もちろんこれだけではないと思うものの、その結果が、学歴差に現れたと思う。(そういうこともあって、私は我が子には小学生の頃から何らかのスポーツをして欲しいと願っている)
Q:ちなみに、お兄様やお姉様は音読されていたのでしょうか?
→兄、姉は音読はしていなかった。私は兄の勉強法はいくつか真似したが、そもそも兄、姉、私で勉強法で話し合ったことは一切なく、それぞれ独自に勉強していた。
5.答え合わせを終えて
最後まで書いてみて、改めて自分自身のことながら、以下のことに驚いた。
1)これほどまでに野球ばかりしていたのか
学生時代、頭の中は常に野球で占められていたように思う。野球は野球で最後まで全力でやりきり、その後、部活を引退したら徹底的に受験勉強をする、ということを繰り返してきた学生時代だった。
嫌味に聞こえるかもしれないが、中学、高校、大学と、ずっと塾に通い、やりたいことを封印して、大学に進学する友人を多くみてきた。それに比べれば、私はこれだけ野球などの好きなことを満足いくまでやって、その上で、難関と言われるような大学に合格できたのは、幸運だったと思う(勿論、私は私なりの苦労もあったのだが)。なんだか、美味しいとこ取りをしたみたいだなと、振り返って思う。
なお、これだけ情熱を注いだ野球だが、私は特段野球で優秀な成績を修めることができたわけではない。中学では県で準優勝したが、高校では県大会2回戦負け、甲子園には遠く及ばなかった。憧れて入った大学の野球部では補欠だった。一方で、同じ大学の野球部には、勉強もしてきたが甲子園に出場したり、後にプロ野球選手になったチームメイトがいた。上には上がいるものである。
2)自分の子供にどう接するか
そもそも、私がこの「私の教育答え合わせ」さんの企画に取り組ませて頂いたのは、自分が育児をしているからである。今、我が家には未就学の子供二人がいる。
その子供らの育児方針を考える上で、自分なりに自分の学歴を振り返ってみることは有効と考えたからだ。
そして、自分で答え合わせをやってみた結果、以下の2点を重視した方が良いだろうとの結論に至った。
・未就学の段階では、家族間の会話を多くする
→ これが、自分の経験(及び育児に関する研究)から、子供の知的発達に大きく寄与すると考える為
・小学校以降は、本人がやりたいことを尊重し、サポートする
→ 私が両親からそうしてもらったように、好きなことをやらせてあげられる環境を作る。否定的なスタンスを取らず、満足するまでやらせてあげる。
このように、子供に接してあげたい。
私が、今振り返って強く思うのは、親から「受験のために、野球部を辞めて、塾へ行け」などと言われてなくて、本当に良かったということだ。もしそんなことを言われていたらと思うと、ゾッとする。きっと大反発しただろうし、親子間に埋まらない亀裂が入っただろう。
口出ししない両親でラッキーだったと思うし、改めて両親に感謝したい。
6.採点後面談
どうも、#1のカラシカシです。
過去最大ボリュームでしたが、完成度(分析が多角的でなおかつ客観的)が屈指だったことこと、見たかった答え合せの方向性の一つだったこともあって、怒涛の勢いで読めました。
個人的には本当に色々参考になりましたが、主だった点は以下通り。
①勉強以外で勉強の努力方法を学ぶ
これですね。野球を通じてPDCAを学びそれを勉強に応用できた、ここが大きなポイントだなと。
②音読勉強法
面白いなと思いました。僕はどちらかというと「音読なんて何の意味があるんじゃ!」と馬鹿にしてた口ですが、文章を視覚に加えて聴覚でも捉えるのはやっぱり一定意味があるのかなと思い直した次第。(数学の難問で図を書くことで、文章→数式の脳内変換を視覚でサポートするのと同じような理屈なのかな??)
③悲壮感が感じられない
高校時代はそれなりに勉強で苦労されていたとのことですが、少なくとも書きぶりに悲壮感が感じられないのが羨ましいなと。生来の性格なのか、野球―勉強とのメリハリによるところが大きいのか、ここは他の同様の答え合わせを待ちたいですね。
ダンチさん、答え合わせお疲れ様でした!&ありがとうございました!
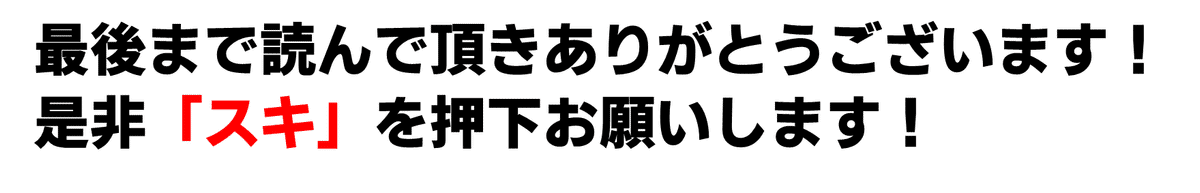
いいなと思ったら応援しよう!

